富士通グループ環境行動計画
事業環境と成長戦略
ビジネスモデル変革に伴って環境活動も変化
通信機器メーカーとして誕生した富士通は、ICTを活用したサービス・ソリューションを提供する「テクノロジーソリューション」、PC・携帯電話などの開発・製造を行う「ユビキタスソリューション」、半導体事業を展開する「デバイスソリューション」の3分野にわたる垂直統合型の事業を展開しながら、ICTグローバル企業へと成長を遂げてきました。2015年度以降は事業構造改革を進め、テクノロジーソリューションをコア事業として経営資源を集中させ、2019年度からは「デジタルトランスフォーメーション(DX)企業」を標榜し、デジタル技術を駆使して革新的なサービスやビジネスプロセスの創出を追求しています。さらに2021年には新たに「Fujitsu Uvance」を始動させました。お客様のSustainability Transformation(SX)や社会課題解決のために、先端AI技術と融合したビジネスを展開し、サステナブルな世界の実現を目指していきます。
こうしたビジネスモデルのシフトとともに、富士通グループの環境負荷のありようも変わってきました。たとえばエネルギー消費量は、以前はその大半が半導体や電子部品、PCなどの製造に伴うものでしたが、事業再編により現在それらは大幅に減少した一方で、クラウドコンピューティングやIoTの進展により、データセンターの消費電力量が大きなウエイトを占める様になりました。そこで、データセンターの省電力化や高効率化、再生可能エネルギー利用に取り組むなど、富士通グループは、社会の要請に応えながら、成長戦略とリンクした環境活動を推進しています。
責任あるグローバル企業として
国連における持続可能な開発目標(SDGs)の採択やCOP21のパリ協定発効など、地球規模の持続可能な社会への取り組みがより一層強く求められるようになりました。富士通グループも、持続可能な発展への貢献に向けた活動の実効性を高めていくため、グループ横断でマテリアリティ分析を実施し、環境をはじめ、人権・多様性、ウェルビーイング、サプライチェーンなど、6つの重要課題からなる「グローバルレスポンシブルビジネス(GRB)」を設定しました。GRBの活動を通じて非財務分野の取り組みを強化し、責任あるグローバル企業としての「サステナビリティ経営」を目指します。
環境行動計画のあゆみ
自社の環境配慮からお客様・社会の環境貢献へ
富士通グループは、1993年から環境行動計画を策定し、環境活動を継続的に拡大してきました。第1期から第5期(1993~2009年度)では、工場やオフィスにおける環境配慮を徹底し、CO2排出量や化学物質排出量、廃棄物発生量など、富士通グループ自らの事業活動に伴う環境負荷を大きく低減しました。第6期(2010~2012年度)は、自らの環境負荷低減の強化に加えて、お客様・社会全体への貢献、生物多様性保全という3本柱に取り組みました。そして第7期から第9期(2013~2020年度)では、ICTの利活用によって、お客様や社会の環境課題解決に貢献する姿勢を鮮明に打ち出しました。自らの環境負荷低減としては、お取引先などを含めたサプライチェーン全体へと対象を広げ活動を展開しました。第10期(2021~2022年度)では、CPPAなどを通じた自社事業所の再生可能エネルギー導入拡大やブロックチェーン技術など富士通グループならではの先端ICT技術を活用し、お客様・社会の再生可能エネルギーの普及・拡大にも努めました。
これからも富士通グループは時代の変化をとらえ、持続可能で豊かな社会の実現を目指して環境活動を深化・発展させていきます。
第11期 富士通グループ環境行動計画
Sustainability Transformation(SX)リーディング企業としての社会的責任
富士通グループは、サプライチェーンを含む自社グループの環境負荷低減の実現とともに、SXリーディング企業として、お客様・社会の課題解決にテクノロジーで貢献し、提供価値の拡大・向上を図っていきます。そして、サステナブルな未来をお客様やパートナーとともに実現していきます。
第11期富士通グループ環境行動計画の概要
環境・社会課題の解決に向け、「お客様・社会」および「自社・サプライチェーン」の2つの軸で、世界経済フォーラムのグローバルリスクである「気候変動」「資源循環」「自然共生」の3つにおいて8項目の目標を設定しました。お客様・社会へのデジタル技術貢献に向けた取り組みや、自社の再生可能エネルギー使用率拡大など、富士通グループの環境ビジョンの実現に向け足元を固めた取り組みを展開していきます。
- 目標期間:2023年度から2025年度までの3年間
お客様・社会
富士通のビジネスは、2030年にESG貢献およびSXを重点テーマとしたポートフォリオ、オファリングへの変革を目指します。特に、気候変動(カーボンニュートラル)、資源循環(サーキュラーエコノミー)、生物多様性の環境領域の課題解決に向け、企業と社会をつなぎお客様と社会のSXに貢献します。2023年度は、お客様にサービスを提供した際に環境への貢献を価値として訴求できるよう、その貢献量を測る指標を策定しました。2024年度以降、その貢献量を測定し公開していきます。さらに、誰ひとり取り残さない持続可能な社会の実現のために、グローバル規模で様々なお客様や社会の皆様からSXのリーダーとして信頼いただけるよう客観的評価の獲得を目標として、SXに資するソリューション開発や取り組みを推進していきます。
自社・サプライチェーン
気候変動
自社の事業活動における温室効果ガス排出量およびバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量をネットゼロ(注1)とするため、2025年度に向けて削減目標を設定しました。これらは、再生可能エネルギーの戦略的な導入と先進的なICTの活用による省エネの展開を行うと同時に、サプライヤーの環境負荷の把握や削減の推進、自社製品のさらなる省電力化などで実現していきます。
- (注1)温室効果ガス排出量ネットゼロ:温室効果ガス排出量を目標年度に基準年度の90%以上を削減し、10%以下となった残存排出量を大気中のCO2を直接回収する技術(DAC)の活用や、植林などによる吸収で除去すること。
資源循環
製品の省資源設計、資源循環率の向上を図り、資源制約から脱却したサーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの構築のため、2025年度に、その製品・サービスの開発を目指します。また水リスクについても、使用量の削減やサプライチェーンへの水資源保全意識の強化などを継続していきます。
自然共生
ネイチャーポジティブの達成に向け、昆明-モントリオール生物多様性枠組みの「2030年に向けたグローバルターゲット」(目標15)に対応する活動として、サプライチェーンを含む自社の企業活動の領域において、生物多様性への負の影響を低減し、正の影響を増加させる活動を実施します。
環境行動計画
| お客様・社会 | 自社・サプライチェーン | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネス領域 | 上流 | 自社領域 | 下流 | |
 |  | 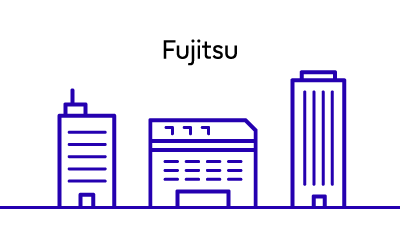 |  | |
| 気候変動 |
|
|
|
|
| 資源循環 |
|
|
| |
| 自然共生
(生物多様性の保全) |
| |||
環境行動計画目標
| 目標 | 基準年度 | 2025年度目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様・社会 |
| — | SXに資するソリューションの提供 | ||
| 自社・SC | 気候変動
(注2) | スコープ 1,2 |
| 2020年度 | 50% 以上削減 |
| スコープ 3
(カテゴリ 11) |
| 2020年度 | 12.5% 以上削減 | ||
| スコープ 3
(カテゴリ 1) |
| — | 目標設定完了 | ||
| 資源循環 |
| — | CEビジネス製品・サービスの開発 | ||
| — | 57,000m3 以上 | |||
| — | 依頼完了 | |||
| 自然共生 |
| 2020年度 | 12.5%以上低減 | ||
- (注2)気候変動:スコープ1,2,3が対象。事業買収と売却を調整した値。


