- ストレージトップ
- 製品ラインナップ
- ETERNUS関連情報
- お役立ち情報
-
ユニファイドストレージ徹底活用
お客様の選定・検討に有用な情報を集約
-
1分でマスター!オールフラッシュ
技術用語解説やフラッシュストレージの特長、展望などが1分程度で理解できる
-
ストレージ技術用語解説
ストレージ製品に関する技術用語を解説
-
用語集
ETERNUSにまつわる用語を解説
-
ユニファイドストレージ徹底活用
- コンセプト
シン・プロビジョニング(Thin Provisioning)とは
シン・プロビジョニング(Thin Provisioning)とは、ストレージリソースを仮想化して割り当てることで、ストレージの物理容量を削減できる技術。ストレージ容量アップに合わせて設備投資を急ぐことなく、コスト削減や運用負荷の軽減が可能になります。
概要
ストレージ業界で注目されている技術の1つが「シン・プロビジョニング」です。ご存知のようにビジネス現場での情報量は急増しています。それに合わせたストレージ容量の確保は、設備投資に大きな負担がかかります。さらに、数年先を見越して余裕のある容量にしている場合、使われずに無駄にしてしまうケースも出てくるのです。
概念
シン・プロビジョニングは、実際に登録されている物理容量にかかわらず、仮想的に利用可能な容量を設定できます。例えば、実際に50TBのディスクドライブを用意しなくても、50TBのボリュームを設定して運用することが可能です。OSやアプリケーションも50TBのボリュームとして認識されます。また、ボリュームに物理ディスクを割り当てるタイミングはストレージ製品によって異なりますが、あらかじめ余裕を見て割り当て量を確保するタイプ(図1)と、物理リソースの記憶領域を動的に割り当てるタイプ(図2)の大きく2つに大別できます。
シン・プロビジョニングのメリットを(図2)で説明すると、新システムの稼働時は、10TBで運用し、実データ量が増えてきたら物理ディスクを追加し対応していくため、キャパシティ・プランニング(容量設計)を不要とし、ストレージのリソースにおける利用効率の向上や最適化が図れます。
シン・プロビジョニングは、SANにおいてボリュームへのブロックアクセスレベルに関する仮想化技術です。一方で、NASではファイルシステムのアプリケーションレベルで仮想化を実現しています。ストレージプールの未使用容量を共用することで、容量増加の際にも物理ディスクドライブの追加を不要とし、必要な時に必要な容量を簡単に追加可能とします。
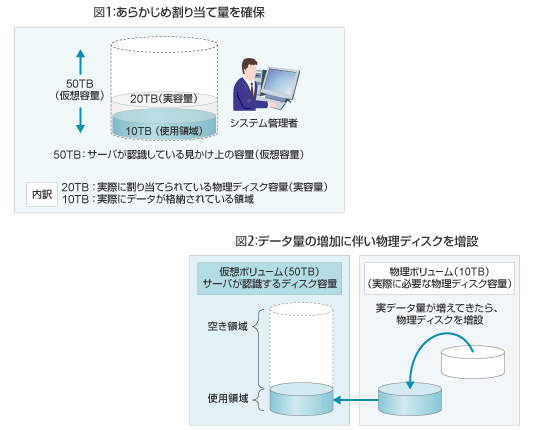
物理的な容量を減らせる
シン・プロビジョニングにより、物理的なストレージ容量を減らすことができ、スモールスタートが可能となります。特にデータセンターなど複数サーバからストレージ装置を共有するシステムでは、いっそうの効果が期待でき、CO2削減など環境問題にも貢献します。
運用の負荷を軽減
仮想化によりストレージを集約することで、物理的な装置を減らすことができるようになります。これにより、システム管理者の運用負荷を軽減できます。
また、従来システム管理者の負荷が大きかったキャパシティ・プランニングも不要になります。物理容量を見直していくだけで、個々のサーバへの割り当てを意識する必要がありません。
展望
従来、大型ストレージに組み込まれていた機能でしたが、エントリーモデルにも採用され、中堅・中小企業でも活発に利用や検討が進められています。特に規模の小さい企業では専任管理者でなくとも、容易に効率的なストレージ管理ができるようになります。
当社のオールフラッシュストレージおよびハイブリッドストレージは、シン・プロビジョニングをサポートしています。
更新日:2021年6月28日
掲載日:2009年5月7日
製品情報
関連情報を探す
ストレージシステム ETERNUS製品・サービスに関するお問い合わせ
-
入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
この製品に関するお問い合わせは、富士通株式会社のフォームを使用し、2024年4月1日よりエフサステクノロジーズ株式会社が対応いたします。

-202x49px_tcm102-7514827_tcm102-2750236-32.png)