今から備える!2026年度診療報酬改定と医療DX推進体制整備加算の改定ポイント
掲載日:2025年10月16日
2025年6月13日に、「経済財政運営と改革の基本方針2025(いわゆる骨太の方針)」が閣議決定され、政策の基本的方向性を示されました。また、同年5月22日より中医協より、2024年診療報酬改定の調査結果が入院・外来医療等の調査・評価分科会より示され、2026年改定の方向性が徐々に見えてきています。
1.2026年診療報酬改定の行方
1)改定の全体方針
まず、骨太の方針では、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額を行うことが示されたことより、2024年改定で新設されたベースアップ評価料の見直しや、賃上げを可能とするための基本診療料の見直しが行われていくでしょう。
入院・外来医療等の調査・評価分科会(6月13日)の資料では、2024年12月の新たな地域医療構想に関するとりまとめの一部が示され、これからの医療提供体制の現状と目指すべき方向性として、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制の構築を行っていくことが明示されました。
具体的には、「増加する高齢者救急への対応」を図るとして、①救急受け入れ体制の強化、②入院早期からのリハビリによるADL低下防止と早期の自宅復帰、③かかりつけ医機能の発揮、④医療DXの推進等による在宅医療機関と高齢者施設等との連携強化等が求められています。
2)方針に基づく、改定ポイント
- ①救急受入れ体制の強化
- 「高齢者救急・地域急性期機能」
高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリテーション等の提供を確保するとのこと。そこで、2024年に新設された地域包括医療病棟では、下線部分の退院後のリハビリテーションの提供に関する新たな基準が設けられる可能性があります。 - 「在宅医療等連携機能」
地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対応を行うとのこと。そのため、地域包括ケア病棟では介護施設の協力医療機関となり24時間体制の診療及び入院受入機能を有するだけではなく、その実績要件が設定されるかもしれません。 - 「急性期拠点機能」
手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行うこととし、但し、地方によっては「救急搬送受け入れ件数」だけで拠点機能を決めていくのは難しいことより、「地域の救急患者受け入れシェア」等も勘案していくことが示されています。
- 「高齢者救急・地域急性期機能」
- ②入院早期からのリハビリによるADL低下防止と早期の自宅復帰
- 専門等機能
集中的なリハビリテーション、中長期にわたる入院医療機能など一部の診療機能に特化して地域のニーズに対応することが示されています。
なお、回復期リハビリテーション病棟においては、平均リハビリテーション単位数とFIM利得の関係性について、廃用症候群リハビリテーションは運動器リハビリテーションと似たパターンであることが示されたことと、廃用症候群リハビリテーションの実施割合が比較的多い医療機関があったという点から、2024年改定の運動器リハビリテーションと同様の単位数制限が行われる可能性もあるでしょう。
慢性期入院料においては、在宅医療と介護施設、療養病床の一部については患者像が重複する場合があることより、慢性期の医療提供体制は療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくことが重要との記載もあることから、病院でなければ難しい治療のみに医療区分が見直され、医療区分2・3の該当割合を満たすことが難しいような仕組みになることも予測されます。
- 専門等機能
- ③かかりつけ医機能の抜本見直し
時間外の対応や在宅医療の提供、介護サービスへのつなぎなど、安心して地域で療養を継続できるような、かかりつけ医機能を評価した診療報酬が改定ごとに増え、施設基準も算定しやすい区分を設けていっているものの、届出及び算定する医療機関がほぼ増えていないという調査結果でした。そこで、多くの医療機関が「かかりつけ医機能を発揮」していただくような仕組みにするべく、2025年4月から開始する「かかりつけ医機能報告制度」の報告項目を踏まえて、かかりつけ医機能の体制構築を評価する「機能強化加算」や「地域包括診療料・地域包括診療加算」及び「時間外対応加算」の施設基準や算定要件を見直す流れがあります。
既に他医療機関と連携して時間外の対応や在宅医療を行うことは評価されているものの連携しづらいという意見も多いため、ICTを活用した患者情報の共有や他医の患者へのオンライン診療も組み合わせた診療の連携の形を新たに評価する可能性があるでしょう。 - ④医療DX・情報連携の加算評価の見直し
医療DXによる患者情報の可視化により、医療の質の向上及び患者自身の予防医療の意識向上、医療現場の業務の効率化等をすすめていくことを今後の医療制度改革の要としたいという厚労省の意図もあることより、電子カルテ情報共有も含めた医療DX・情報連携の加算の算定要件の強化が推し進められていくでしょう。
2.2026年改定の医療DX推進体制整備加算のゆくえ
2-1.電子カルテ情報共有サービスの進捗状況
医療DXの推進に関する工程表においては、2024年度中に全国医療情報プラットホームの基盤構築の後に、2025年度より診療情報提供書、退院時サマリの交換に関する運用を開始する予定でした。実際に2025年2月3日から、愛知県でモデル事業が開始され、その他全国9地域でモデル運用がすすんでいき、2025年度中に全国に拡大していく予定となっています。
まずは3文書6情報からとなるようですが、3文書とは、診療情報提供書、退院時サマリ、健診結果報告書であり、6情報とは、傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査(救急、生活習慣病)、処方となっています。
2-2.医療DX推進体制加算の施設基準(電子カルテ情報共有サービス)の見直し
医療DX推進体制加算の施設基準に、「電子カルテ情報共有サービスで取得される診療情報などを活用する体制の整備」が設定されていますが、2025年9月まで経過措置となっています。現段階ではモデル事業が運営されている状況でもあるため未導入の医療機関が多いこともあり、経過措置が延長になるのか、もしくは、電子処方箋を発行する体制と同様に、未整備の場合の区分が設けられ、評価点数に差がつけられていく可能性があるでしょう。
| No. | 医療DX推進体制加算の施設基準 | 加算1~6の基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 電子情報処理組織を活用した請求 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | オンライン資格確認を行う体制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | オンライン資格確認等システムを活用して患者さんの薬剤情報や特定健診情報などを診察室や手術室、処置室などで閲覧・活用できる体制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 5 | 電子カルテ情報共有サービスで取得される診療情報などを活用する体制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 医療DX推進の体制に関する事項と質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、医療機関の見やすい場所やウェブサイトなどに掲示 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
| 7 | マイナポータルの医療情報などに基づき、患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
2-3.マイナ保険証利用率の引き上げ
マイナ保険証利用率は、2024年6月、10月、12月と段々引き上げになってきており、2025年4月は下記のとおり、利用率が15%未満であれば医療DX推進体制加算が算定できない仕組みになりました。
| マイナ保険証利用率 2025年4月~ |
点数 | |
|---|---|---|
| 医療DX推進体制整備加算1 | 45%以上 | 12点 |
| 医療DX推進体制整備加算2 | 30%以上 | 11点 |
| 医療DX推進体制整備加算3 | 15%以上 | 10点 |
| 医療DX推進体制整備加算4 | 45%以上 | 10点 |
| 医療DX推進体制整備加算5 | 30%以上 | 9点 |
| 医療DX推進体制整備加算6 | 15%以上 | 8点 |
2025年4月時点での全国平均のマイナ保険証利用率は28.65%となっていること。医療機関別では、病院:約45%、歯科:約40%、診療所:約25~30%、薬局:約23%で推移しており、診療所の利用率は低いものの、病院は45%という高い比率となっています。
2025年8月以降、高齢者対応(顔認証がうまくいかない場合等の目視確認モードの運用)や救急対応の仕組み強化(救急隊員が傷病者のマイナ保険証にて情報を把握し、円滑な搬送先病院の選定が出来る仕組み)により利便性向上が見込まれることもあり、2025年10月~2026年3月にかけて報酬加算での利用率要件が「15%→30%→45%」と段階的に引き上げられる予定であり、2026年改定後の6月以降においては、さらに利用率要件の引き上げが進んでいくことでしょう。
補足.自院のマイナ保険証利用率を上げるためには
1)患者への声かけ・働きかけを強化する
- マイナ保険証をご利用いただくと、自己負担が軽減される可能性があります
- 限度額適用認定証の持参が不要になります
- マイナンバーカードを持参いただければ、保険証との紐付けは当院で行ないます。
などのメリットを説明。また、マイナンバーカードは持っているが保険証と紐付けできていないからと思っている患者さんもいるため、次のような声かけも必要です。
2)患者さんに分かりやすい掲示を行なう
外来のどこかの壁にポスターを貼るのではなく、患者さんに見えやすい受付近くに貼るか、もしくは受付窓口に「マイナンバーカードをご持参ください」との案内板を置くなどの工夫が必要です。患者さんは意外に院内の掲示物は見えていません。医療機関の中には、外来にポスターを貼りすぎて重要な内容が記載されているものが分かりづらい状況になっています。「当院にとって特に見ていただきたいもの」は受付近くに、それ以外のものは掲示物コーナーなどを設けてまとめて掲示するなどの工夫は必要です。
3)受付・職員教育の徹底
マイナ保険証利用率が下がると、医療DX推進体制加算の算定が出来なくなったり、加算点数が下がることにより医療機関の収入が減少してしまいます。「受付職員に「マイナ保険証利用率の低下=収入減」という意識が薄いと1)2)への取り組み強化につながらず、結果として、利用率向上につながらないという状況が多く見られます。実際に筆者も歯科に定期的に通院していますが、一度も口頭でマイナ保険証の提示を求められたことはなく、ポスターも患者に見えづらい場所に掲示されている状況です。
「マイナ利用促進=経営的な加算メリット」の意識共有を行なうために、マイナ保険証利用率の月ごとの目標を設定し、利用率を上げるための取り組みをKPI設定するなどの仕組み作りも重要です。
3.まとめ
医療DXは、厚労省だけの施策ではなく国の施策です。電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋が導入されていくことにより、情報の共有による投薬等の安全性の確保、AIやビッグデータの活用による診断・治療の精度向上が可能になること。マイナポータルからの情報により患者自身が健康管理に参加する患者中心の医療の実現や、情報共有の効率化による医療現場の業務効率化と事務負担軽減が図れることから、医療DXが進むための施策として2026年の診療報酬改定においても確実に評価に組み込んでいきます。
但し、評価する診療報酬項目が設定されても、現場の職員に経営的な視点が伴っていなければ、加算の算定につながらず、業務の効率化(保険証の確認業務、患者情報の見える化)にもつながらないため、加算を算定することによるメリット(収入増、どういう業務の効率化が可能になるのか)、デメリット(収入減、非効率な状況が続くこと)を現場スタッフ間で共有していくことが重要です。
筆者プロフィール

株式会社リンクアップラボ 代表取締役 酒井麻由美
急性期病院へ入職し、リハビリ部門、入院部門へ配属。
その後、医療・介護専門コンサルティング会社へ入社、副所長取締役に就任。
2018年、株式会社リンクアップラボを設立。
医業経営コンサルタントとして、年間100件以上の講演を開催。
主な執筆活動として、医学通信社「月刊保健診療」、医学書院「看護管理」、福祉医療機構「月刊WAM」、QOLサービス「デイの経営と運営」、医業経営コンサルタント協会「JAHMC」ほか多数。
免責事項
本稿の内容は執筆時点の情報に基づいて作成されています。情報の正確性・完全性については細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。情報の活用や運用に際しては、ご自身の判断と責任において行なってください。なお、無断での複製や転送は禁じさせていただきます。
関連コンテンツ
-
 【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -
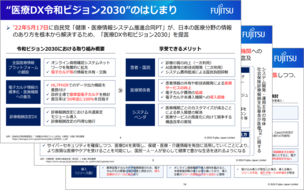 【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -
 【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -
 【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。
富士通のヘルスケアソリューション
富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。
ご不明な点やご要望などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。















