シームレスな医療・介護連携で患者の経験価値(PX)を高める
掲載日:2025年3月3日
1. はじめに
日本は現在、急速な超高齢化社会に突入しています。総人口に占める65歳以上の割合は年々増加し、高齢者が抱える健康課題や生活支援のニーズも多様化・複雑化しています。このような状況下で、医療と介護の連携はこれまで以上に重要な課題となっています。
従来、医療と介護はそれぞれ独立したサービスとして提供されがちでしたが、高齢者が安心して生活を続けるためには、医療と介護がシームレスに連携し、一貫したケアを提供することが求められます。医療による治療や健康管理だけでなく、介護による日常生活の支援やリハビリテーションが統合されることで、患者・利用者の生活の質(QOL)が大きく向上します。
2. PXという考え方
これまでの医療・介護サービスの評価指標としては、患者満足度(Patient Satisfaction:PS)が主に用いられてきました。しかし、これらの指標は抽象的であり、具体的な改善策の立案には限界があります。近年、患者経験価値(Patient Experience:PX)という新たな概念が注目を集めており、これらを活用することで、サービスの質を多面的かつ具体的に評価・改善することが可能となります。患者経験価値(PX)とは、患者が医療サービスを受ける際に経験する具体的な事象を指します。これは、医療スタッフとのコミュニケーション、診療やケアのプロセス、施設の環境など、多岐にわたります。
一方、PSは「期待が満たされたかどうか」を評価するものであり、その人の主観的な期待に大きく左右されます。そのため、具体的な改善点の特定が難しいという課題がありました。
従来の患者満足度調査の結果は『回答者の主観』に依存する傾向にありましたが、PXサーベイは『医療サービスの質』や『患者個々のニーズ』を客観的に測ることができます。このため、PSではなくPXでサービス評価をすることが求められています。また、介護分野ではまだ広く取り入れられていないものの、医療におけるこの分野の発達が介護分野でも将来的に求められてくる可能性があります。
表1. PXとPSの違い
| 患者満足度(PS) | 患者経験価値(PX) | |
|---|---|---|
| 評価対象 | 患者・利用者の期待と実際のサービスとのギャップ。主にサービスの結果や品質に焦点を当てる。 具体例: ・診療待ち時間が期待よりも短いかどうか ・治療結果が期待に沿っているかどうか |
患者・利用者がサービスを受ける際に経験する具体的な事象全般を対象とする。スタッフとのコミュニケーション、治療・ケアのプロセスなどを含む。 具体例: ・診療時の医師や看護師の態度 ・治療中の痛みの管理の適切さ・施設の清潔さと快適さ |
| 評価方法 (表2参照) |
非標準化のアンケートなどを用いることが多い。評価が主観的であり、一面的になりがち。 具体例: ・5段階評価の満足度アンケート ・フリーコメントによる意見聴取 |
標準化された尺度を用い、具体的な経験を多面的に評価。信頼性・妥当性が検証されている。 具体例: ・標準化された尺度を用いた事実の評価 ・定量的データによる経験の分析 |
| 活用メリット | 総合的な満足度を把握できるが、具体的な改善点の特定が難しい。評価結果が医療・介護の質を正確に反映しない場合がある。 | 具体的な課題の特定が可能であり、質改善への具体的なアプローチがとりやすい。技術的な質指標とも関連性が高い。 |
表2. 患者満足度(PS)調査と患者経験価値(PX)の設問例
| 患者満足度(PS)調査の設問例 | 患者経験価値(PX)尺度の設問例※ |
|---|---|
| ・スタッフの対応に満足していますか? 【段階評価】 1(非常に不満)~ 5(非常に満足) |
・この入院中、医師(看護師)は礼儀と敬意を持ってあなたに接しましたか? 【数値スケール】 1(一度もそうではなかった)~ 4(常にそうだった) |
| ・待ち時間は許容範囲でしたか? 【単一選択】 はい ・いいえ |
・この入院中、医師(看護師)はあなたの話を注意深く聴きましたか? 【数値スケール】 1(一度もそうではなかった)~ 4(常にそうだった) |
| ・診療中、安心感を持つことができましたか。 【段階評価】 1(全くそう思わない)~ 5(とてもそう思う) |
・新しい薬を渡される前にスタッフは、何のための薬であるかを説明しましたか? 【数値スケール】 1(一度もそうではなかった)~ 4(常にそうだった) |
| ・病院やスタッフに関して、改善してほしい点をすべて選んでください。 【複数選択】 ・スタッフの対応が親切でない・待ち時間が長い・受付の説明がわかりにくい・施設の清潔さが不十分・設備が古い・案内表示が不明瞭 |
・新しい薬を渡される前に、スタッフは、生じうる副作用についてわかりやすく説明しましたか? 【数値スケール】 1(一度もそうではなかった)~ 4(常にそうだった) |
3. PX向上に向けた3つの要素
PXの向上は、患者の満足度を高めるだけでなく、治療効果の向上や医療機関・介護施設の収益増加にもつながります。PX向上のためには、医療と介護が連携し、多職種での協働が不可欠です。PXの向上に向けて検討すべき要素は3つあります。ここでは、それぞれの要素について説明します。
3-1. 包括的なケア提供
患者・利用者の多様なニーズに応えるため、医療と介護が連携した包括的なケアを提供します。これは、単に医療や介護のサービスを提供するだけでなく、患者・利用者の全体像を把握し、個別のニーズに応じた統合的なケアを実施することを意味します。
3-2. サービス品質の向上
患者・利用者の具体的な経験を収集・分析し、サービスの質を継続的に改善します。PX評価ツールを活用してフィードバックを定期的に収集し、具体的な改善点を特定します。
3-3. コミュニケーションの改善
患者・利用者とのコミュニケーションを重視し、信頼関係を築くとともに、医療・介護スタッフ間の情報共有も円滑に行います。共感的な態度で傾聴し、安心感を提供することが重要です。
以上の要素を理解することで、次の4で紹介する課題とその解決策がどのようにこれらの要素に影響を与えるかが明確になります。次に、PX向上を阻む具体的な課題とその解決策について詳しく見ていきます。
4. PX向上を阻む課題とその解決策
PX向上のためには、包括的なケアの提供、サービス品質の向上、コミュニケーションの改善といった取り組みが重要ですが、これらを実現する上で、いくつかの課題が障壁となっています。これらの課題は相互に影響し合い、PX向上の妨げとなる可能性があります。ここでは、主な課題とその解決策について説明します。
4-1. 職種間の理解不足
課題の原因
医療と介護は、それぞれ異なる制度(医療保険と介護保険)の下で運営されており、その制度の内容や趣旨、目的が異なります。
“医療は「治療」を目的とし、急性期の対応や症状の改善に焦点を当てる”
“介護は「生活支援」を目的とし、長期的な生活の質の維持・向上を目指す”
このような制度上の目的や役割の違いが、専門性や業務内容に対する認識のギャップを生じさせ、相互理解が進みにくい状況を招いています。制度の違いによる理解不足が、職種間のコミュニケーション不足や連携の阻害につながります。その結果、ケアの質が低下し、患者・利用者のニーズに適切に応えることが困難となり、PXが低下します。
解決策の例
合同研修の実施:医療保険と介護保険の制度の違いや、それぞれの目的・趣旨について、医療・介護スタッフが一緒に学ぶ研修を実施します。これにより、相互の制度に対する理解を深め、協働の基盤を築きます。
情報共有の促進:制度の違いによって生じる業務上の課題や対応方法について、日常的に情報共有を行います。ミーティングや共有ツールを活用して、現場での具体的な課題や解決策を話し合います。
4-2. 病院・介護施設間でのシステム分断とICTリテラシーの不足による情報共有の困難さ
課題の原因
病院と介護施設で使用する記録システムや情報管理方法が異なり、情報共有がスムーズに行われていません。また、個人情報保護の観点から、情報の取り扱いに慎重になりすぎることもあります。さらに、スタッフの中には、ICT(情報通信技術)への苦手意識を持つ人や、システムの操作に不慣れな人がいます。特に、紙ベースの業務に慣れている場合、新しいシステムへの移行に抵抗を感じることがあります。
情報の共有不足やシステム活用の遅れにより、患者・利用者の状態やケアプランがスタッフ間で統一されず、ケアの一貫性が損なわれます。その結果、患者・利用者の安全性やケアの質が低下し、結果としてPXが低下します。また、情報共有が円滑でないことで、業務効率化が図れず、スタッフの負担が増加する可能性もあります。
解決策の例
情報共有ツールの導入・統一化:病院と介護施設で共通の情報共有ツールやシステムを導入し、情報の一貫性を担保することが考えられます。
ICT研修の実施とサポート体制の構築:スタッフ向けにシステムの基本操作や活用方法についての研修を行います。実践的な内容とし、質問しやすい環境を整えることで、習熟度を高めます。また、システムに詳しいスタッフを配置し、困ったときに相談できる体制を作ります。マニュアルや操作ガイドを整備し、いつでも参照できるようにします。
情報共有ルールの明確化:個人情報保護法や関連ガイドラインを遵守しつつ、情報共有に関する内部ルールを策定します。共有すべき情報や方法を明確にし、スタッフ全員に周知・徹底します。これにより、情報の取り扱いに対する不安を解消し、適切な情報共有を促進します。
4-3. 業務負担の増加による人手不足
課題の原因
人口減少や高齢化により、医療・介護の現場では慢性的な人手不足が生じています。また、業務量の増加により、スタッフ一人ひとりの負担が大きくなっています。業務負担の増加は、スタッフの疲労や職場満足度の低下を招き、離職率の上昇につながります。結果として、ケアの質が低下し、PXが低下します。
解決策の例
業務の効率化:業務フローを見直し、無駄や重複を削減します。ICTシステムを活用して、記録業務の時間短縮や情報検索の効率化を図ります。これにより、スタッフの業務負担を軽減できます。
5. おわりに
患者・利用者の経験価値を高めることは、医療・介護サービスの質を向上させるだけでなく、彼らの生活の質や満足度の向上にも直結します。医療と介護が連携し、互いの強みを活かしたケアを提供することで、高齢者が安心して暮らせる社会を実現できます。 制度上の課題や人材不足など、乗り越えるべき壁はありますが、関係者全員が協力し合い、具体的な解決策を実践していくことが求められます。
筆者プロフィール

株式会社日本経営 組織人事コンサルティング部 課長代理 松永透
医療機関へのITシステムの導入や人事制度の構築支援、第三者機関認定資格取得支援等の業務に従事する。特に、組織人事のコンサルタントとして現場との対話を重視し、現場担当者へのヒアリングや現場ラウンド、ワークショップを通じた、実態に合わせたシステム導入の実現に注力している。また、ITシステムの導入と併せ、業務分析・改善業務の経験を有する。
免責事項
本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。
内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。
関連コンテンツ
-
 【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -
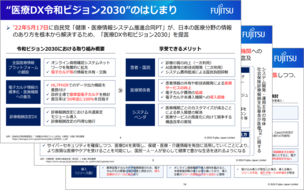 【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -
 【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -
 【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。
富士通のヘルスケアソリューション
富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。
ご不明な点やご要望などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。














