電子カルテ導入の流れとは?
~検討から導入までを徹底解説~【前編】
掲載日:2024年7月30日
電子カルテの導入は「導入が目的」ではなく「業務の効率化が目的」であり、導入時には多くの関係者の協力が必要となります。この目的を達成するためには、準備から導入までの各ステップにおける詳細な計画と適切なプロジェクトチームの運営が必要です。このコラムでは電子カルテ導入における考慮すべき事項について前編、後編に分けて解説します。現在、医事システムのみを導入されている医療機関のみなさまはぜひ参考にしてください。
はじめに
電子カルテの導入には、情報収集から導入までは2年半程度かかるため、早めの準備が必要となります。本コラムでは、電子カルテ導入検討~稼働までについて、「1. 情報収集」「2. 検討~契約」「3. 導入」の3つのフェーズに分けて、電子カルテの導入において知っておくべき流れやポイントを確認していきます。
電子カルテ導入検討~稼働までの各フェーズと期間
| 1.情報収集フェーズ | 2.検討~契約フェーズ | 3.導入フェーズ | |
|---|---|---|---|
| ゴール | 今後の具体的な検討に向け、電子カルテに関する情報や現行運用の主な課題を整理する | 電子カルテ導入の目的をプロジェクトチーム内で合意し、自院に見合う電子カルテを選定する | 自院の運用に合うように、各種マスタ等を設定し、システムを稼働させる |
| 実行者 | システム担当者 | システム担当者 プロジェクトメンバー等 |
全スタッフ |
| 期間 | 約6か月~1年 | 約1年 | 約6か月 |
| 活用概要 |
|
|
|
1. 情報収集フェーズ
今後の具体的な検討に向け、電子カルテに関する情報を収集しつつ、現運用の主な課題を整理します。
- 外部環境調査
全国医療情報プラットフォームを基盤とした電子カルテ情報共有サービスは、2025年度中に開始される予定です。生活習慣病管理への応用など、具体的な活用方法も診療報酬改定に絡めて示されています。今後、電子カルテを未導入の医療機関も、その導入は避けられず、早晩導入が必須となるのではないかと考えられます。 - 各種情報整理
電子カルテの情報について最も詳しいのは電子カルテベンダーです。まずはホームページにアクセスし、どのようなベンダーが候補に挙がるかを検討します。その後、各ベンダーに問い合わせをすることで、それぞれの強みや特徴、納期、予算のイメージなどを把握できます。問い合わせるだけなら一切コストはかからず、むしろ各ベンダーも自社製品のPRに積極的なので、情報収集の初めの一手としては非常にお勧めです。また、展示会や各社のイベントなどを活用するといいでしょう。
既存のシステムの種類や稼働時期を把握し、新システムとの調整や統合の必要性を判断します。次に、院内のネットワーク状況を確認します。安定したネットワークが確保されているか、必要な拡張が可能かどうかも重要です。また、サーバ室の有無や設置可能な場所があるかを確認します。電子カルテシステムの運用は、適切なサーバ環境が必要です。特に、画像データの取り扱いに注意が必要です。放射線画像や心電図、エコーなどのデータがどのように保存・表示されているか、現在の運用方法を調べます。これにより、デジタル化と運用の変化に対応できます。
また、具体的にどのような業務を改善したいのかを評価し、紙カルテの問題点の洗い出しを行います。例えば、外来の新規患者登録から診察までのフロー、入院の決定から病棟への患者情報の伝達など、ワークフローやコミュニケーションの観点での業務改善は重要な課題となります。 - 予算把握
コスト分析や資金確保の可否を検討します。初期導入費用、運用コスト、保守費用の概算を算出し、現在の経営状況に合わせたキャッシュフローについても検討する必要があります。
2. 検討~契約フェーズ
電子カルテ導入の目的をプロジェクトチーム内で話し合い、自院に必要な機能を見極めて電子カルテを選定します。
- 検討準備
電子カルテ導入プロジェクトチームの編成
電子カルテの導入では、プロジェクトチームを編成します。「電子カルテ導入委員会」などの名称で呼ばれる場合もありますが、院内の調整や報告などの業務が発生するため、組織上の位置づけは編成時点で明確にするとよいでしょう。
電子カルテの導入では、プロジェクトオーナー、プロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーによるプロジェクトチームを編成します。- プロジェクトオーナー
電子カルテの導入は場合によっては数億円単位のコストがかかる一大プロジェクトとなるため、一般的には、最高責任者として病院長や副院長など経営幹部が指名されます。 - プロジェクトマネジャー
プロジェクトマネジャーは、電子カルテ導入プロジェクトの全体管理を担当します。具体的には、稼働予定日から逆算したスケジュール管理や人材確保、成果の定義、計画立案、チーム体制整備、ベンダーや院内関係者との交渉、リスク対策、問題解決、計画修正などを行います。プロジェクト成功のためには、計画の実行とチーム状況把握は「プロジェクトリーダー」に任せて、自身は全体管理に終始することが重要です。 - プロジェクトリーダー
プロジェクトリーダーは、電子カルテ導入プロジェクトにおいて、現場に密接した立場でチームの推進力としての役割を果たします。具体的には、プロジェクト計画に基づいて詳細なスケジュールを作成し、プロジェクトメンバーに作業を割り振り、計画を実行に移します。また、マスタ管理や文書管理、運用の検討を行い、電子カルテシステムの適切な導入と運用を支援します。
プロジェクト計画の立案
プロジェクト計画の立案において、まずは目標と期限を設定します。電子カルテの導入はいつからの稼働を想定するのか、予算はどの程度かなどの大枠から決めていくことになります。プロジェクトメンバーが決まったらまずは初回会議(キックオフミーティング)を行い、各メンバーの役割と責任を明確にし、適切なタスクの割り当てを行います。定期的に会議を開催し、プロジェクトの進捗状況をチーム全体で共有します。週次や月次の報告を通じて、プロジェクトメンバー間のコミュニケーションを強化し、情報の共有を促進します。要件定義
電子カルテに必要な機能と要件を明確化し、「要求仕様書」を作成します。例えば、外来や入院への対応の有無、介護との連携機能の有無、連携する部門システムはいくつあるのか、レセコンとの連携、カルテ入力、外来予約機能、帳票作成などの必須機能をリストアップし、各部門の業務フローに合わせたシステムの最低水準を設定します。このタイミングで、端末の台数やそれに合わせたインフラの整備なども検討します。
また、データ保護、バックアップ体制、アクセス権限やログの監視機能などセキュリティ面については、比較の際に重要なポイントになります。ここで洗い出した項目に基づいた評価票を作成することで、デモンストレーションの際にはこれらの評価軸を点数化して比較することができます。 - プロジェクトオーナー
- 検討作業
市場調査とベンダー候補の選定
市場調査を行い、病院が作成した仕様書に沿って製品の特徴や機能を比較します。市場には数十種類の電子カルテが存在しており、自院に適した製品の選定が求められます。信頼性の高いベンダーを選ぶために、市場シェア、サポート体制、納期などを確認し、他の医療機関の導入事例や評価も参考にします。さらに、ベンダーのデモンストレーションを通じて、ユーザビリティ(操作性)や視認性、必要な機能が実装されているかなどを確認します。
システムメンテナンスが病院職員のみで行えるかどうかも重要な確認項目です。加えて、サーバ室の確保は、場所のない病院にとって問題となります。クラウド型電子カルテを利用すれば、専用の広いサーバ室は不要となるため、十分な検討が必要でしょう。予算とスケジュールの策定
予算の策定においては、導入コストだけでなく、運用コストやメンテナンス費用も考慮します。システムのライセンス費用、ハードウェアの購入費、インストール費用、トレーニング費用、そしてサポート契約の費用などを詳細に見積もります。電子カルテの導入期間は、一般にオンプレミスの場合で約6〜12ヶ月、院内にサーバなどのインフラ設置が不要なクラウドの場合で約3〜6ヶ月が目安とされています。ただし、具体的な期間は病院の規模やシステムの複雑さ、病院の準備状況によって変わります。 - 契約
予算とスケジュールが明確になり、ベンダーから製品情報を収集した後は、自院に最適なベンダーを選定します。市場調査やデモンストレーション等の結果をもとに、機能、価格、サポート体制、納期などを総合的に評価します。選定されたベンダーと詳細な契約内容を交渉し、双方の合意により契約を締結します。この段階で、システムの具体的な導入スケジュールやサポート内容を確定させます。
3. 導入フェーズ
自院の運用に合うように、各種マスタ等を設定し、システムを稼働させます。
- 準備
契約締結後は、導入範囲、役割分担、スケジュール、前提条件など、契約者のみではなく、院内プロジェクトメンバー内で認識のずれをなくすなど、院内の周知を図ります。次に、導入の準備として、まず契約内容を確認し、不明点や懸念点がないかをチェックします。また、導入後のサポート体制や問い合わせ窓口の設置も行います。さらに、システム導入に必要なハードウェアやネットワーク環境を整備し、病院内のインフラを確認して必要な設備の追加や改修を行います。 - 運用設計
ワーキンググループの設置
ワーキンググループ(WG)は、各診療部門・検査部門等から少数を選出して編成するプロジェクトチームの下部組織です。WGでは、電子カルテ導入後の具体的な運用方法を検討します。電子カルテ導入でのポイントは、現場における運用の詳細などについては各WGに可能な範囲で権限移譲することです。現場担当者とベンダーの導入担当者が直接話をすることでスムーズに進みます。各WGで判断できない事項については、適宜関係者で話し合うなど、スピード感のある対応が必要となります。文書整理
電子カルテを導入するタイミングで、院内書類の整理を行います。以前は「ペーパーレス」が強調されましたが、現在は必要な文書を適切に管理し、必要最低限の紙文書を効果的に利用することが重要とされています。特に初めてシステム化を導入する病院では、文書管理の一元化が業務効率の向上に繋がります。
現状の書類の整理、重要度の分類、電子カルテに取り込みが必要な場合には取り込みのフロー(いつ・誰が・どこに)など文書の保存方法などを決定します。 - 構築作業
マスタの作成では、オーダー画面のメニューやベッドマップなどのシステム画面を構成し、各種マスタの設定やカルテ書式・テンプレートの作成を行います。具体的には、処置、処方、検査の指示など、電子カルテに表示される基礎情報を整理します。また、現場で使用される書類(同意書やクリニカルパス、患者一覧など)が、電子カルテの帳票作成機能で代用可能かを確認し、運用に合わせたテンプレートを作成することで、業務の標準化を図ります。現状の運用を無理に電子カルテに当てはめるのではなく、電子カルテ内にある既存の帳票やテンプレートをできる限り活用することで、業務を標準化することができます。 - トレーニング
全スタッフに対する電子カルテ操作方法のトレーニングプログラムを実施します。トレーニング後には継続的なサポート体制を構築し、問い合わせ対応や必要に応じて追加トレーニングの計画を立てます。 - テスト
リハーサルでは、本稼働に向けて実際のシステムを使用した運用のプロセスと問題点を確認します。中小規模病院であれば、外来や病棟などに分けて稼働日の2~4週間前に1~2回実施します。 - 稼働
稼働日には、ベンダーが複数のスタッフを配置しますが、その後は必要に応じて人数を減らします。各部署からのフィードバックを集め、システムの最適化と運用効率の向上に努めます。初期トラブルの対応や追加サポートが必要な場合は、速やかにベンダーと連携して問題解決に当たります。
最後に
前編では、電子カルテ導入におけるプロジェクトチームのメンバー編成や電子カルテベンダーの選定、電子カルテの稼働までの流れを解説しました。このようなスケジュール設計や電子カルテ検討プロセスについてのノウハウを持ち、自院にしっかりフィットした提案をしてくれるベンダー営業の存在も重要となります。後編では、電子カルテの導入において、特に重要となる電子カルテベンダーの選び方について解説いたします。
筆者プロフィール

株式会社日本経営 厚生政策情報センター 主幹 森實雅司
臨床工学技士として高度急性期病院で計21年間臨床業務に従事。経営学修士(MBA)取得後、2023年4月に日本経営へ入社し、医療政策情報の発信を担当、病院経営に関する講演や企業研修、医療関連企業のマーケティング支援も行う。
免責事項
本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。
内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。
関連コンテンツ
-
 【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー
「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -
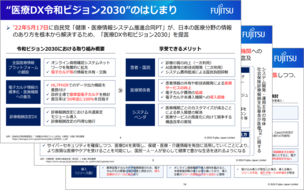 【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編
医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -
 【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」
医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -
 【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~
富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。
富士通のヘルスケアソリューション
富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。
ご不明な点やご要望などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。














