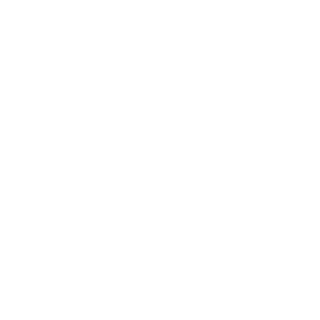Voice(社員の声)
富士通のパーパス実現を支える知財部門の業務内容、またその業務を通じてどのようなキャリアを積むことができるのか、それぞれの分野で活躍する知財部員の声をご紹介します。

 上原 慧
上原 慧
多様な事業と最先端技術を支える知財戦略
富士通入社前は、自動車部品メーカー、電子部品メーカーにおいて、特許権利化、特許調査・分析、契約審査、知財事務等に従事してきました。特許調査・分析業務を経験する中で、より調査・分析業務を究めたいと考え富士通へ入社しました。
現在は、事業部門等の依頼に基づいて作成する調査レポート(IP Insight)を通して、事業戦略策定サポートや顧客対応支援に従事しています。市場動向調査、競合他社分析、特許情報分析など、多角的な視点からの調査・分析を行い、事業部門に実効性の高いインサイトを提供しています。単なる情報収集に留まらず、ビジネスへの活用を常に意識し、提言や富士通ビジネスに資する提案も行っています。前職の特許権利化業務では特定技術などでの深耕でしたが、富士通ではより広い視野で技術とビジネスの接点を探求しています。知財を起点にして「いかにインサイトを生み出すか」「富士通の強みをどう活かすか」「富士通ビジネスをどう描くか」といった観点での調査・分析は、事業戦略、知財戦略に対する多角的な視点を養う上で貴重な経験となっています。
富士通の魅力は、多様な事業領域、最先端技術、そして多様な人材にあります。金融、官公庁、コンシューマ、ヘルスケアなど、幅広い業界の顧客に対応し、それに伴い多岐にわたる事業を展開しています。また、AIや量子コンピューティングなどの最先端技術は、知財面でも知的好奇心をくすぐります。加えて、多様なバックグラウンドを持つメンバーとの協働は、常に刺激と学びを与えてくれます。
現在、富士通のビジネスは、プロダクトからソリューション提供にシフトしています。知財を軸にして、技術とビジネスを融合し、新たな価値を創造するダイナミックな業務に携わることができます。知的好奇心と探究心に溢れ、世界を変えるイノベーションに貢献したいという方に富士通の知財部門は合っています。
 小林 圭
小林 圭
商標業務を通じて、富士通のブランド価値向上に貢献する
大学時代は法学部で知的財産法を学びました。その知識を活かせる仕事がしたいと思い、2017年に富士通に入社しました。その後は一貫して商標業務・模倣対策業務に従事しています。
商標業務では、新しい商品、サービス、技術、コンセプトの名称のほか、キャラクターやロゴなどについて、他者の商標権を侵害していないかを調査し、必要に応じて商標登録出願を行っています。また、ブランドの模倣・不正使用対策にも取り組んでおり、近年は特にドメインやウェブサイトなどのインターネット上における富士通ブランドの不正使用や、富士通グループと無関係なのに「富士通」を社名に使用する不正商号に対する監視や権利行使を強化しています。自身がハブとなり、マーケティング部門や法務部門など様々な関係部署と連携を図りながら、守りだけでなく攻めの体制構築を推進しています。
また、2019年~2024年に日本知的財産協会(JIPA)の商標委員会に参加し、社内業務と並行しながら商標委員会の副委員長として活動しました。その中で特に印象に残っているのは、商標五庁(TM5)会合ユーザーセッションへの参加です。本会合は日米欧中韓の知財庁と民間企業が参加する国際会議で、私はJIPAの代表として2022年にベルギーへ、2023年に韓国へ派遣されました。日本の民間企業の代表として現地で直接意見表明をしたことで、自身の視野が広がっただけでなく、富士通のプレゼンス向上にも貢献できたと感じます。
「富士通」という企業ブランドは、グループの社員全員の努力で築き上げられてきたものです。その毀損につながるリスクを排除し、価値を向上する。それにより富士通の経営に貢献できることが商標業務の大きなやりがいだと感じています。なお、talentbookというサイトでも記事を掲載していますので、商標業務にご興味がありましたらこちらの記事![]() もご覧いただけますと幸いです。
もご覧いただけますと幸いです。
 鈴木 淑乃
鈴木 淑乃
知財に関わる多様な業務と専門性
入社以来、知的財産センターにて、コンピューティング領域、特に量子コンピュータの研究開発部門における特許出願・権利化業務を担当しています。
特許の出願権利化業務においては、研究者から技術をヒアリングし、技術を理解し、先行技術なども考慮しながらより適切な権利を取れるよう日々精進しています。発明の本質を見抜き、それを権利として守るための戦略を練る過程は、知的財産部員としての腕の見せ所です。大学では生命科学系の学部であったため、担当した当初は量子コンピュータに関する知識は十分ではありませんでしたが、研究者の方々や、経験豊富なチームメンバーとの活発な議論を通して、技術に対する理解を深めてきました。現場から信頼される知財部員であるために、専門的なスキルの向上もさることながら、日々現場部門とコミュニケーションを大切にしています。
大変なこともありますが、量子コンピューティングという最先端の技術に携わる中で、自社の技術力や強みを深く理解できる知財センターの仕事に、大きなやりがいを感じています。また、量子コンピュータの研究開発は、国内外の多くの研究機関や企業との共同研究によってグローバルに進められています。そのため、知財関連契約やライセンス交渉も重要な業務の一つです。海外の研究機関との連携も多く、現地のスタッフや代理人と密に協力しながら、知財リスクの回避や円滑な特許出願活動を推進しています。
業務は個々の裁量に任される部分も大きく、主体的に業務を進めることができます。在宅勤務が中心ですが、チームの定例出社日や打ち合わせなど、自身の業務やライフスタイルに合わせて柔軟に働き方を選択できるのも魅力です。リモートワーク環境でも、チームメンバーとの連携は密であり、困ったときにはすぐに相談できる体制が整っています。
 棚田 景子
棚田 景子
AI技術の価値を顧客目線で伝える、知財支援の新たな挑戦
私は入社後、SEの事業部門に配属され、損益管理等の業務に携わりました。富士通の第一線でビジネスをされるSEの方を間近で見ることができ、貴重な経験を積みました。10年間の業務を通じて達成感を得るとともに、「新しいことに挑戦したい」と思い、知財部門への異動を志願しました。そこで、現場部門に寄り添うビジネス伴走型の知財支援に取り組みました。特に商品企画に知財の付加価値を加える業務では、現場の方々との対話を通じて、その熱意に触れる貴重な経験を得ました。
現在は、Kozuchiの知財支援チームに所属し、当社のAI技術(独自IP)の強みを顧客目線で訴求するという新たなミッションに取り組んでいます。
技術の強みを商用版Kozuchiの価値として変換し、お客様がそのメリットを具体的に理解できるよう支援しています。具体的には、お客様が「この技術なら自社の課題を解決できそうだ」と感じてもらえることを大切にしており、お客様が当社製品を選ぶきっかけを提供することを目指しています。
この仕事は、スピード感が求められるだけでなく、常に現場視点を持ち続けることが重要です。時には頭を悩ませることもありますが、現場にとって本当に必要なことを見極め、迅速に対応する業務のやりがいを感じています。また、このプロセスでは、これまでの経験で培った「現場に寄り添う」姿勢を活かし、拡販、セールス、技術部門と密接に連携しながら、知財や特許をビジネスに活用してもらっています。チーム一丸となってビジネス貢献を目指す毎日は新しい発見があり、刺激的で楽しいです。
 深川 大地
深川 大地
富士通でのキャリア形成
富士通に入社する前は、富士通とは異なる業界で特許権利化や特許調査などの業務に携わっていました。業務を行う中で、技術の進歩がより顕著な分野で自身の特許の専門性を高めたいと考えたため、AI技術の研究開発と特許出願に注力している富士通に2023年に入社しました。
入社後は、希望していたAI分野の特許権利化業務を担当しています。技術分野を大きく変えた転職であったため、当初はAIの技術的な内容の理解や、特許のポイントを捉えることに苦労しました。日々知見を深めるとともに、普段担当する一つ一つの案件で深く考え、挑戦的な応答を心掛けたことで、AI分野の特許権利化に関する専門性を高めることができました。印象に残っていることは、社内の重要案件でありながら拒絶理由の克服が困難とされていた中間対応で、徹底的に検討を重ねて特許を取得できたことです。この経験を通して、大きなやりがいと自身の成長を実感することができました。
権利化業務以外にも、知財を通じたビジネス支援、知財関連契約、他社知財部門の方との委員会活動など、様々な業務に携わっています。これまで経験したことのなかった多くのことを経験できていることに、楽しさを感じています。
富士通の魅力は、働きやすい環境にもあります。入社当初、業務遂行に不安がありましたが、上司とチームメンバーが定期的にディスカッションの機会を設けくださり、丁寧に指導をしていただきました。また、リモートワークを中心とした柔軟な働き方が可能な点も魅力の一つです。オフィスに出勤することもでき、オフィスはフリーアドレスで服装自由であるため、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる良い環境だと実感しています。
松本 尚子
過去の業務経験を発揮しながら、新たなキャリアを形成
入社前は、システムエンジニア、特許事務所、異業種の知財部などに従事していましたが、社会人として培った経験を全て使いながら新しいことにも挑戦できる環境で働きたいと思い、富士通に入社しました。
私が所属する知的財産センターは、発明抽出、特許の出願権利化を主に行っています。この部署で私は、主にAIを含むコンピュータ・ソフトウェア関連発明を担当しています。入社当初から担当している部門は共同研究も行っており、海外の他社の知財部門とコミュニケーションをとることもあります。また、富士通では、常に最新の動向と活用状況を意識しながら権利化業務を行っています。そのため、特許出願後や権利化後、社外に技術が展開されていく際にも、複数の知財部門と協業しながら、富士通の技術を知財面でどうサポートしていくのかについて、特許PF構築担当として参画することもあります。そのため、活動の範囲が単なる権利化業務のみに留まりません。技術内容を深く知り、権利化業務を中心に広い範囲での活動を行えることに責任を感じるとともに、日々新しいことに挑戦でき、新たな視点を学べる仕事にやりがいと楽しさを覚えています。
コロナ禍入社のため、入社時から働き方はリモートワークが中心です。オンラインでありながらも、過去の経験を活かせる業務はもちろん、社内の他の部門との横断プロジェクトやJIPAといった社外の活動など、新たな活動の幅を広げられる業務の機会にも挑戦することができています。他社知財部門の方々とディスカッションするのは、自身の視野と人脈を広げることができ、自身の成長をより感じています。このように、富士通社員として社内外で広く活動できることはこの職場の魅力だと思います。
 三浦 夏美
三浦 夏美
開発でのキャリアを生かした知財からのビジネス貢献
私は開発職として富士通に入社しました。ハードウェアからソフトウェアまで幅広い製品の開発・企画に携わる中で、学生時代から興味のあった知財への関心が高まり、弁理士資格を取得したことを機に知財部門へ異動しました。
異動後は知的財産センターで主にAI関連のソフトウェアやシステムの権利化を担当しました。実務経験ゼロからのスタートでしたが、出願から中間対応まで一から丁寧にご指導いただきました。特に中間対応と並行して明細書を複数作成させていただいたことで、より良い権利を取得するためのノウハウを身につけることができたと感じます。
現在は知財戦略室に所属し、富士通の技術をどのように社会実装しビジネスに昇華するか、知財の側面からサポートする業務に携わっています。具体的には、知財戦略の策定、知財動向の社内への情報発信、政策活動を通した対外的な意見発信などを担当しています。富士通は5つのキーテクノロジーに注力しており、特にAIは著作権に対する課題や政策・法制度への影響が大きいことから、知財観点でも注視する必要があります。これらの動向をウォッチするには、技術的な知識はもちろん、特許法以外にも幅広い知財に関する知識が求められます。変化の激しい状況に対応していくのは容易ではありませんが、世の中の動きを肌で感じられるのがこの業務の醍醐味であり、やりがいにつながっていると感じます。
開発職時代は様々な製品に携われる一方で自分の専門性に不安を感じていましたが、知財部門に異動し、開発で培った技術やビジネス化の知識と知財の知識を掛け合わせることで、新たな側面から富士通のビジネスに貢献できていると感じています。富士通は常に最先端のテクノロジーに取り組んでおり、知財部門の中でも様々な業務があります。専門性を高めるだけでなく視野を広げる機会も得られ、自身のさらなる成長につながるのではないでしょうか。
2025年3月実施
本稿中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものです
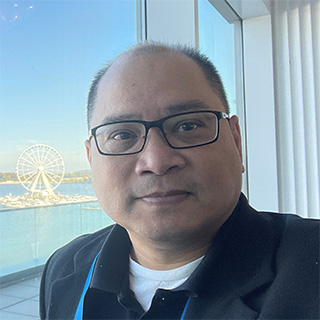 Tiep Nguyen
Tiep Nguyen
Enhancing Fujitsu brand through promotion and protection of Fujitsu’s Technologies
I am the Director of Fujitsu Intellectual Property Center (FIPC), an intellectual property (“IP”) team remotely located in the Washington DC area, near the USPTO. I joined Fujitsu in 2008 to assist in FIPC formation. Our team is tasked with patent promotion and other IP-related activities for Fujitsu companies and research facilities outside of Japan, including North America, Europe, India, and Israel. Such activities include harvesting and protecting innovations from global Fujitsu research facilities via patent filing and prosecution, managing Fujitsu’s patent portfolios, IP training for Fujitsu researchers and IP personnel, negotiating research and joint IP agreements, and preparing legal opinions on patent infringement and invalidity. I am also a member of Fujitsu’s IP Center of Excellence which is tasked with developing and implementing Fujitsu’s global IP strategies.
Prior to joining Fujitsu, I spent 9 years in private law practice in the U.S. and 6 years as a USPTO Patent Examiner. My prior experiences made me realize that I wanted to be closer to innovations when and where they happened. At Fujitsu, I have gained a deeper technical knowledge of its technologies and understood the strategic and business reasons behind my work of protecting Fujitsu’s innovations in such technologies. I found much satisfaction helping technical researchers express their innovations to enhance Fujitsu’s products and services. It is a joy for me to see their pride when they realize that Fujitsu values their work through protection of their innovations with patent, trademark, and/or copyright registration. I enjoy the camaraderie and teamwork with colleagues in Legal & IP Unit in negotiating and preparing joint research agreements between Fujitsu and universities and other companies to further advance Fujitsu’s technologies. My active participation in the American IP Law Association (“AIPLA”) provides me with networking opportunities in the US and worldwide, which allows me to stay abreast of new IP law and regulations that I can share with my colleagues in Legal & IP Unit. Together, we work to ensure that Fujitsu takes full advantage of the available legal avenues to protect Fujitsu’s IP rights worldwide, enhance the Fujitsu brand as a technology company and its business, while also enhancing society with sustainability.
 郷家 隆志
郷家 隆志
グローバル経験を通じたキャリアと人脈形成
研究開発職として入社し、自分の発明案件や他社特許の分析などを通じて知的財産に関心を持ち、自らの希望で知財部門に異動した後に弁理士の資格を取得して本日に至ります。 知財部門ではグローバルなビジネス展開に応じた知財ポートフォリオを構築し活用していくことも重要なミッションとなります。これを実現させる一つの手段としてグローバル全域のイノベーションの抽出と展開を加速させるために海外拠点の実務的な知財活動状況を共有できる情報交換の仕組みを構築する施策を自ら提案し、海外リージョンメンバーと連携して構築しました。また、コロナ禍において駐在員の派遣を停止した海外拠点の知財部門をリモート環境でマネジメントする体制を構築して海外から創出されるイノベーションを適切に保護してきました。何れの施策も言語や時差の壁は当然のことながら、文化の相違から生じる課題解決のアプローチが様々であり、お互いを理解する努力が必要となる場面にも直面したりしましたが、誠意と信念を持って対話を重ねることで信頼関係を構築し、課題解決に共に取り組んできました。
この様なグローバル経験を通じて国内のみならず海外実務に関する知識・経験を研鑚できたことは勿論のこと、お互いに何でも相談したり助け合える世界中の仲間と巡り会えたことはかけがえのない財産と考えております。
現在は近年新設されたインドの研究所に駐在しており、非常に活気あふれる環境の下で知的財産のみならず法務や安全保障輸出管理など多面的な実務に取り組んでおり、常に新しいことに挑戦できることに大きなやりがいと責任を感じております。
最後になりますが当社ではグローバルにチャレンジを希望する社員をサポートするプログラムを提供しており、新入社員の方々も積極的にプログラムに参加しています。当社に入社される皆様にもグローバルにご活躍していただければとても嬉しく思います。
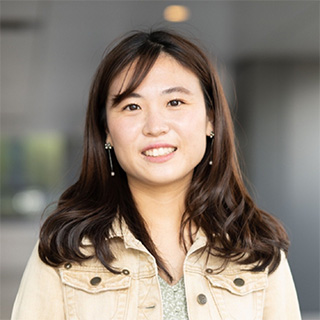 小松崎 舞佳
小松崎 舞佳
様々な業務に携わり、知財部員として成長できる
入社後、特許の出願から権利化を主に行う知財センターに配属になり、現在はコンピューティング研究所の量子化学計算に関する発明を担当しています。大学時代に化学を専攻していたことから、分子式や化学系の単語に対しての抵抗はあまりありませんが、権利化や中間処理を適切に行うために、コンピューティングに関してはもとより、化学系の分野についても発明の内容を理解するためには技術的な知識を身につける必要があります。本や論文等を用いながら技術について学びますが、理解できない部分も多々あり、発明のポイントがどこであるのか特定するのに初めはかなり苦労しました。それでも、技術のスペシャリストである発明者に直接、基本的な部分から質問したり、一から説明してもらうことで、段々と自分の中で、発明者との関り方や発明のポイントを見いだせるようになり、少しずつ自信が生まれてきました。
また、米国代理人が来日した際には、自分の担当している分野の案件についてディスカッションを行う機会もあり、英語で技術内容を説明し、対応方針について理解してもらうのはなかなか大変でしたが、代理人から有益なフィードバックをいただけ、無事に特許査定を得られたことは良い経験になりました。
海外に拠点を置く現地の知財担当者や共同研究相手先とも連絡を取り合うこともあり、知財の各部署のメンバーとも連携しながら必要な情報を収集し、業務を進める毎日です。入社時から働き方はリモートワークが中心ですが、上司、同僚と定期的に出社する日を揃え、出社した際は、ホワイトボードを使いながら対面で議論をしたりしています。周りに、知識と経験が豊富な社員がいて、業務の相談や知財について様々な観点で学べ成長できる環境があることも魅力だと思います。
 森田 岳
森田 岳
特許の専門家から知財のジェネラリストへ
入社以来10年間、主にAIを含むコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許業務に従事してきました。特許業務には、技術的な思想である発明を文章で表現するという作業があります。この作業は、特許紛争、アライアンス構築など特許の活用シーンを考慮し、様々な観点でより良い表現を目指して推敲を重ねて行うものです。国内外の特許出願に関して数十件、数百件と経験を積むことによって、発明を表現するスキルを習得していきます。幸い、富士通は技術を重んじる会社で特許出願件数も比較的多く、社内に脈々と受け継がれているノウハウもあり、特許技術者としての成長環境は恵まれていると思います。
成長を感じる経験の1つに、約7ヶ月間に渡る米国研修があります(写真はCityCenterDCにて)。米国研修では、ワシントンDCにある法律事務所に滞在し、特許弁護士と対峙しながら米国実務を直に学んできました。教わるばかりではなく、時には異を唱えることによって、彼らと信頼関係を構築しました。帰国後も連絡を取り合っており、日々の業務の中で彼らの知見を上手く活用することができています。また、研修期間中に、パテントエージェント試験に合格するという目標も達成でき、実りある経験をさせていただきました。
23年度より知財戦略室に異動し、知財の何でも屋となっています。主には海外の知財部と連携しながら海外の研究開発拠点の知財活動のマネジメントを行っていますが、その他、AI技術のライセンス供与を活用した米国スタートアップへの投資、買収企業の知財事項に関するPMI、国策に関わる関係省庁からのヒアリング対応等、様々な業務に携わっています。10年間で培ってきた特許技術者のスキルをベースとして、その上に様々な知財の経験やスキルを積み上げているところです。
今後も、国益に資する知財人になるべく精進していきたいなと思います。
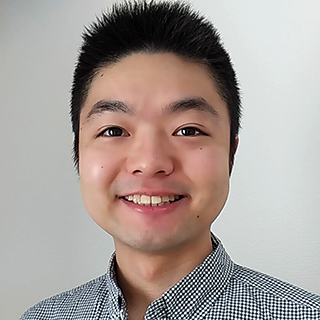 髙橋 知明
髙橋 知明
知財を活用することで富士通のビジネス、そして、社会に貢献する重要な業務
私は学生時代に知的財産センター受入れのインターンに参加したことがきっかけで、特許業務は特許法の知識だけでなく技術を理解する力も求められることを知り、知的財産センターへの配属を希望して入社しました。学生時代から物の構成や動作原理を考えることは好きでしたが特許法の知識はなかったので不安もありましたが、社内外の研修や先輩方からの指導などを通じて特許業務について基礎から学ぶことができ、入社時には特許について初心者だった私でも半年後には実際の案件を担当させてもらえるまでになりました。その後は、特許出願・権利化業務を担当し、発明者の技術資料を元にして特許出願するための説明資料の作成や、特許庁から特許されないと判断された発明における特許庁への反論方針の検討などを行っています。技術を理解するのに時間を要し苦労することもありましたが、特許出願・権利化業務を通じて説明力を培いながら、狙った権利範囲で特許査定を受けた時には達成感を得られました。
現在は、知的財産戦略室に異動し知財活用施策の検討および実行を担当しています。担当業務の一つに、イノベーションにより持続可能な世界を実現するため、SDGs達成に貢献する特許やノウハウなどの知的財産を企業・学術機関にご活用いただく取り組み「FUJITSU Technology Licensing Program™ for SDGs」があります。他の企業に直接、あるいは、学生が創造した新商品のアイデアをベースに他の企業に当社の知的財産をご活用いただきますが、当社が提供する知的財産について発明の特徴部分などを分かりやすく説明する必要があります。そこで、これまで特許出願・権利化業務を通じて培ってきた説明力が発揮されていると実感しています。この取り組みで他企業・他機関と共創することで実際に商品化された事例もあり、自社そして社会に貢献する、そのような重要な仕事に携われ、日々やりがいを感じながら仕事をすることができています。
2024年3月実施
本稿中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものです
 余吾 貴彦
余吾 貴彦
知財の専門家として成長できる環境
入社後、6年間コンピュータ・ソフトウェア関連発明の知財権利化業務に従事し、現在は権利化業務で得た知見を活かして知財情報を活用したインテリジェンス解析業務に従事しております。本業務では、事業部からの依頼に対し、知財情報やマーケット情報、論文情報等を統合的に分析し、今後のビジネスに役立つインサイトを見出す調査レポート(IP Insight)を提供しています。自身の経験を踏まえ、富士通知財部門の魅力は大きく2つの環境にあると考えます。
1つ目は様々な研修を通し、多くの知識を得られる環境です。知財を学ぶJIPA研修、社外の知財部門の方と知財に関し議論するJIPA委員会&知財情報活用分科会、海外への語学研修や大学のビジネススクール等、自身の成長につながる様々な学びの機会をいただき大変刺激になりました。
2つ目は様々な観点から知財の活用方法を学べる環境です。私は入社前、知財の業務として権利化やライセンスをイメージしておりました。しかし、入社後、それらに加え、知財をどう活用するかを考えることの重要性を学びました。知財の活用の仕方は多岐に渡り、無限の可能性があります。富士通知財部門では常にその可能性を模索し、複数のセンター・室がそれぞれ違った立場から知財の活用に取り組んでおります。
私自身、権利化業務に従事していた際には自身が担当した部門や技術領域の特許を実ビジネスへの貢献につなげるためにどうアピールするかという観点での活用をメインに取り組んでおりました。一方、現在の業務では、競合他社や業界の特許を分析し、ビジネスの方向性に関する知見を得るために活用しております。前者が知財の権利としての活用、後者が知財の情報分析としての活用であり、これら二つだけでも大きく異なる活用方法となります。
富士通の知財部門では上記活用以外にも様々な活用が実践されており、知財の活用を様々な観点から学び、経験できる魅力的な部門であると感じております。
 足立 夏子
足立 夏子
「富士通のブランドとデザインを知財で支える」
私はブランド・デザイン知財戦略グループで、商標と意匠の権利化と使用等にあたってのリスク回避を主とした業務を担っています。
デザインに関していうと、今後のサービス展開や使われ方を想定し、競合他社の状況も踏まえたうえで、意匠法やその他関連法に則り権利範囲を定めて出願の方法を検討しています。
また、企業の知財担当ならではですが、完成したデザインを権利化するだけではなく、社内に向けた知財の啓発にも積極的に取り組んでいます。会社全体のポートフォリオはもちろん、法改正や他社状況などを常にキャッチアップし実務や施策に落とし込み、活発且つ安全な知財活動を促すために、セミナーの開催やe-learning講座を作成したり、創作活動のモチベーションを高める施策の検討などを行っています。また業界団体として関係省庁への法整備の働きかけなど、種を蒔く前の土つくりから長いスパンで携わり業務は多岐に渡っています。
未だ世の中にない新しいデザインを戦略的に権利として抑えるにあたっては、法律の側面だけではなく、最先端の技術やデザインに触れて、それが広がることで新たな便利で美しい世界が生まれることを想像し、年を重ねるにつれ薄れてしまいがちですがワクワク感やミーハーな感覚を持つことも大切だと考えます。その想いとデザイナーへのリスペクトを持つことで、創作の背景にある物語を引き出し、いい権利が生まれるのではないかと思います。
自分らしく働き自分軸で生きる人生を
時間や場所に捕らわれない新しい働き方が可能な時代になりました。通勤やそれに付随する時間が省略されたことで、自分を成長させる時間や時には甘やかす時間、家族と過ごす時間を保つことができ、また子供の成長を近くで見守ることができるのは何にも代えがたいものです。時間のコントロール主が自分になることで、それは自身を律する責任を伴うことではありますが、人生100年時代を”自分軸”で働くことができ、よりよい人生の歩みに繋がっていくと思います。
2022年9月実施
本稿中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものです
富士通の知的財産に関するお問い合わせ
-
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
0120-933-200(通話無料)受付時間:9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)