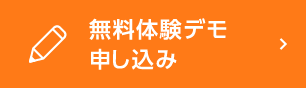宮崎県庁 様 導入事例
口蹄疫に対する防疫対策と復興支援に関わる、 現場の被災情報整理にSaaS型システムが大きな力を発揮

口蹄疫で揺れた宮崎県では、初感染の確認から最終発生確認までの2ヶ月半余の間、感染は急速に拡大し続け、すぐに既存のパソコンでの情報収集・集計が限界に達した。こうした中で、大きな力を発揮したのがSaaS(Software as a Service)型システム。新たにハードウェアを準備する必要もなく、わずか10日間でスピード導入。防疫措置のための迅速な情報収集・集計を可能にするとともに、被災農家の復興支援に向けたデータベース化を実現した ... 続きはPDFにてご覧いただけます。
| 製品: | CRMate(シーアールメイト)/お客様接点力 |
|---|---|
| 適用業務: | 緊急時の情報収集 |
- 課題対策に追われ、システム構築の時間も投資の余裕もない
- 効果既存のパソコンと県庁LANを利用することで新たな投資が不要。システム導入に関わる県側の作業負担も軽減
- 課題毎日現場情報を取りまとめ、国や関係機関へ報告
- 効果各地で集めた情報を一元管理。既存のパソコンでの集計作業等でかかっていた時間が短縮でき、業務の効率化を実現
- 課題防疫対策とともに被災農家の復興支援が急務
- 効果家畜評価や手続き進行状況の情報をデータベース化。補償金の交付などを円滑に進め、復興支援に役立てる
導入の背景
感染拡大で対策本部に激震が走る
 高島 俊一 氏
高島 俊一 氏
農政水産部長
宮崎県で口蹄疫の初感染が確認されたのは、4月20日未明のことだった。口蹄疫は、主に牛や豚などの偶蹄類動物(ひづめの数が偶数の動物)が感染する家畜伝染病である。極めて伝染力が強く、放置しておくと周りの牛や豚などに急速に伝染し、発育や乳量の低下などを引き起こす。経済的損失が大きく、国際的にも最も警戒すべき家畜伝染病として、発生予防やまん延防止が求められている。国内では、家畜伝染病予防法により、まん延防止措置として、殺処分・焼却・埋却などの対策を県が実施することになっている。
宮崎県ではすぐに対策本部を置き、その日のうちに半径10kmの移動制限区域、半径20kmの搬出制限区域、そして制限区域の円周上の4ヶ所に消毒ポイントを設置した。しかし、日を追って感染が瞬く間に広がっていった。
「とにかく、防疫対策を一番に考え、地域内で抑え込む封じ込めを行い、何よりも県外には絶対に出さないという決意で臨みました」と、農政水産部長の高島俊一氏は語る。周辺への拡大防止を図り、封じ込めを行うためには、県民に対して不要不急の外出自粛やイベント等の延期、消毒の徹底等が欠かせないということから、5月18日には「宮崎県口蹄疫非常事態」を宣言し、県民全てに緊張が走った。
導入の経緯
感染が拡大し、手作業の情報整理が限界に達する
 大久津 浩 氏
大久津 浩 氏
農政企画課主幹(農政計画)
非常事態宣言後も感染は県内各地に飛び火し、依然拡大を続けていた。この時点で発生戸数159戸、殺処分対象頭数は約13万頭に及んだ。このため、これまでの疑似患畜の殺処分による防疫措置では、感染拡大は防げないとのことから、5月22日、我が国では初めてとなる口蹄疫に対するワクチン接種が始まった。
県職員にとっては、ワクチン接種、殺処分、埋却といった「防疫措置」と並行して、「被災農家の復興支援」も緊急で行う必要があった。移動制限区域の設定により家畜を動かすことができなかったことに加え、県内全域で家畜市場が閉鎖されるなど、多くの畜産農家が収入の手段を絶たれた。このような農家にとっては、行政による緊急支援が急務であった。
情報管理の観点では、防疫作業の進捗管理や新たな発生情報などを毎日収集し、国や関係機関に報告する必要があった。情報収集と整理作業のために連日夜を徹して行われ、疲労はピークに達していた。
「防疫現場作業に多くの農政職員がかりだされ、対策本部において、日々各地での進捗の情報を収集するためには、JAや市町村職員など多くの方の協力が必要です。感染が拡大するにつれ、扱う情報量は膨大になり、情報の錯綜などもあり既存のシステムやパソコンでの集計作業等では限界を感じていました。何よりも、毎日の現場情報をとりまとめ、国や関係機関への報告やマスコミ等へ発表するためには、各地で集めた情報を一元化し、情報統制する仕組みが必要だと強く感じていました」と、対策本部で広報窓口を担当していた農政企画課主幹の大久津浩氏は、対策本部での苦労をそう語る。
システムの概要
10日間という短期間で導入。刻々と変わる手順にも柔軟に対応
 金丸 裕一 氏
金丸 裕一 氏
情報政策課長
各地で集められた情報を朝4時までかけて、1枚の報告書にまとめる。それを常駐していた国の本部会議で毎朝9時に報告する。そして、夜も毎晩、記者発表対応などに追われ、期間中、職員は休日も休みを取れず、県庁の部屋で2~3時間仮眠を取るだけというほとんど徹夜の状態で対応にあたっていた。
「畜産農家にとっては自分たちが大切に育ててきた牛や豚ですから、処分といっても家族を殺されるようなつらい思いだったと思います。そうした農家の思いを受け止め、少しでも負担を軽くしていきたという使命感に支えられて、職員たちは日夜作業をしていました」(高島氏)。こうした状況の中、富士通は5月31日、宮崎県に対して支援の申し入れを行った。
「農家別の情報管理や家畜評価、補償金支払の手続きなど、大量の情報を管理しなければなりませんでしたが、職員は防疫対策で手一杯の状況でした。特に復興支援に向けた情報管理は絶対に必要でしたので、新たなサーバを用意することなく、短期間で導入可能なSaaS型システムの提案を受けた時は、本当にありがたいと思いました」と、情報政策課長の金丸裕一氏は語る。
今回のシステムでは、SaaS型アプリケーションサービス「CRMate/お客様接点力」を活用した。県庁にある既存のパソコンと県庁LANを利用することで、新たな投資はいらなかった。また、セルフカスタマイズ機能により、状況を見ながら随時画面修正し、確認を得て作業が進められたことで、システム導入に関わる県側の作業負担も軽減できた。検討開始からわずか10日間という短期間での導入を実現。導入後も、刻々と変わる対応手順に柔軟に対応することができた。
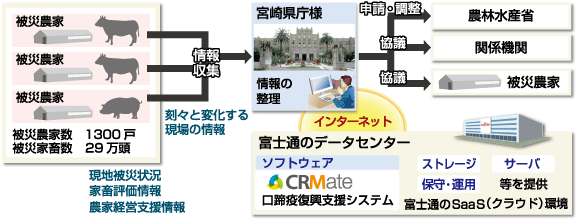
将来の展望
口蹄疫復興支援システムとして被災農家の復興を支える
今回導入したSaaS型システムは「口蹄疫復興支援システム」として使われている。事業者の住所や氏名、家畜の血統や殺処分履歴、経営を再開するかしないかの意向調査結果などをデータベース化。県、市町村、JA等で情報を一元化し、共有化することで、家畜の殺処分に伴う手当金の交付などを円滑に進め、被災農家の復興支援に役立てている。
最終的に、殺処分した家畜は約29万頭、被災農家は1300戸にのぼった。7月27日には非常事態宣言を解除。8月27日にはすべての防疫措置が終了したことで終息宣言を出した。しかし、まだ戦いは終わったわけではない。壊滅的打撃を受けた被災農家の経営再建には最低でも3年は必要と言われている。新たに設置された復興対策本部では、被災農家1300戸に対して詳細な経営再建意向調査を実施した。これらの情報もシステムの中にデータベース化した。もし、システムがなかったら、調査は紙で聞き取りすることになり、共有や検索ができず、個人情報のセキュリティ管理の面でも不安が残るものになっただろう。
「私自身3年前に鳥インフルエンザを現場で経験しましたが、今回の口蹄疫ではやはり日頃からの準備の重要性を感じさせられました。鳥インフルエンザを含め、日常の情報管理や、発生時の対応、メドが立った後の復興支援のあり方など、PDCAサイクルをどのように回していくのか。そこに今回のシステム基盤をどう活用していくか。広い視点から考え、今後の仕組みを整えていきたいと思っています」(金丸氏)。
被災農家の復興支援、そして鳥インフルエンザなど今後の家畜伝染病の流行に備えたPDCAサイクルの確立など、課題は多い。しかし、刻々と変化する現場の情報を把握、活用することが一日も早い復興支援の推進に繋がるに違いない。
詳しい内容は、PDFにてご覧いただけます
導入事例詳細 PDF版
PDF版では、導入事例の詳細を写真や図表を添えて詳しく解説しています。
各種資料・導入事例ダウンロードページからどうぞ。
【目次】
- 早朝の陽性連絡から蹄疫への長い戦いが始まった
- 感染拡大で対策本部に激震が走る
- 殺処分、埋却地の選定など県職員は徹夜の対応に追われる
- 感染が拡大し、手作業の情報整理が限界に達する
- 新たなサーバを用意することなく短期間で導入可能なSaaS型を提案
- 10日間という短期間で導入刻々と変わる手順にも柔軟に対応
- 口蹄疫復興支援システムとして被災農家の復興を支える
- 鳥インフルエンザ対策などにもシステムを活用していきたい

宮崎県庁 様 概要
| 所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10-1 |
|---|---|
| ホームページ | 宮崎県庁ホームページ |
[2010年11月26日掲載]
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
本事例に関するお問い合わせ
-
入力フォームへ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
富士通コンタクトライン (総合窓口)0120-933-200(通話無料)
受付時間 : 9:00~12:00および13:00~17:30(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)