宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所(ISAS) 様
researchmapのデータを活用して自社サイトで研究者情報を発信
研究者情報の見える化、情報発信力の強化、業績管理の作業効率化を実現

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙科学研究所(ISAS)では、研究者の業績情報の見える化、情報発信力の強化、業績管理作業の効率化を目指し、富士通Japanの提案した「FUJITSU文教ソリューション Ufinity研究者業績サービス」を採用。これにより専用の研究者業績情報サイトである「あいさすmap」を公開し、研究者情報の見える化を実現した。研究者情報データベース「researchmap」のデータを活用することで登録や管理作業も大幅に効率化している。
課題と効果
- 課題研究者や研究業績の情報を自機関サイトで見える化したい
- 効果Ufinity研究者業績サービスを活用し、専用の研究者業績情報サイトを構築
- 課題宇宙科学研究所(ISAS)として研究者の情報発信力を強化したい
- 効果情報の登録作業を簡素化し、ISASの研究者が容易に情報を発信
- 課題研究業績管理の作業を効率化したい
- 効果researchmapのデータを利用し、研究業績管理作業の大幅な効率化を実現
導入の背景
宇宙科学分野の発展と大学院教育を担うISAS
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2003年に宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団の3つの機関が統合して発足。統合前の宇宙科学研究所は4つある本部の一つとして、宇宙科学研究本部となり、2010年4月にはJAXAにおける宇宙科学研究をさらに推進するために、宇宙科学研究所(以下、ISAS)へと組織および名称の変更を行っている。
太陽系科学研究系 教授の齋藤 義文氏は、「ISASは日本の科学衛星の開発や運用、データ解析、観測ロケット・大気球実験など、さまざまな研究活動を行っています。2020年12月には小惑星リュウグウのサンプルを採取した小惑星探査機「はやぶさ2」の再突入カプセルが地球に帰ってきました。このサンプルリターンの技術をさらに進化させた、火星衛星探査計画MMXも進めています」と紹介する。
ISASは科学プロジェクトを推進するとともに、研究者の自主性を尊重した宇宙科学研究も事業として進めている。さらに大学共同利用の機能も担い、宇宙科学の発展と同分野の大学院教育の中枢として位置付けられる。「要請に応じて大学院教育への協力も行っています。ISASの中に閉じた形で研究を進めているのではなく、教育も併せて行っているところが特色の一つになります」と説明するのは、科学推進部 計画マネージャの遠藤 敬氏だ。
ISASではこれまで、年度ごとに図書出版委員会が研究者の研究業績や活動を取りまとめ、年次要覧を作成していた。「各研究者の業績の管理は、毎年度末に各研究者から提出されるデータを取りまとめ、評価や年次報告用の要覧を作成してきました。ただデータ量が多く作業が煩雑ということに加え、年度末ごとの取りまとめのためにタイムリーな公開ができていませんでした」と齋藤氏は振り返る。
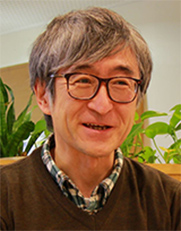 齋藤 義文氏
齋藤 義文氏国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所
太陽系科学研究系
教授
 土居 明広氏
土居 明広氏同左
宇宙物理学研究系
助教
 遠藤 敬氏
遠藤 敬氏同左
科学推進部
計画マネージャ
 八木 綾乃氏
八木 綾乃氏同左
科学推進部
課題と経緯
研究者・研究業績情報の管理と発信に課題
これらの問題を解決するために、図書出版委員会は2020年度に研究情報委員会と名称を改め、従来の活動に加えて、研究情報発信力の強化や研究者の業績管理を効率化するための取り組みを始めた。委員長に任じられた齋藤氏を中心に、研究情報の管理と公開について、その基盤となる仕組み作りの議論を行っていった。
基盤を構築する上での課題と目標について、「ISASの研究者や研究情報の見える化、ISASとしての情報発信力の強化、研究者や研究情報の業績管理のための作業負荷軽減、という3つの課題を設定し、その解決を目指しました」と話すのは、前ワーキンググループ長を務めた宇宙物理学研究系 助教の土居 明広氏だ。
そして、他の研究機関や大学では研究者・研究情報をどのように管理、発信しているのかの調査を実施したところ、主に2つの方法で行っていることが分かったと土居氏は話す。
「一つにはその機関独自のシステムで研究者総覧を一から構築する方法、もう一つはすでに国内で多くの研究者が登録している“researchmap”を上手く活用する方法、主にこの2つです。ヒアリングしたところ、前者の独自システムの構築・維持・管理には手間や費用が多く掛かり、また研究者にとっても独自システムとresearchmapの2つへ登録するという二度手間になることから、ISASでは後者のresearchmapを上手く活用するのが良いという結論になりました」(土居)。
researchmapは、研究者が業績をインターネット上で管理・発信することを目的とした、データベース型の研究者総覧。WebAPIを公開しており、取得した情報をもとに各機関が統計・分析を行うためのデータベースとして利用できる。このresearchmapを活用した研究者情報の管理・発信を実現するシステムの検討がスタートした。
導入サービスの概要
researchmapのデータを活用して運用の負荷・コストを軽減
複数のresearchmapをベースとしたシステムそれぞれのメリット/デメリットを比較検討した結果、富士通Japanの提案した「Ufinity研究者業績サービス」が選択された。Ufinity研究者業績サービスは、researchmapに登録されている研究者の業績情報を活用した、機関・大学ごとに研究者の研究業績が公開可能なSaaS型サービス。
SaaS型のため、ハードウェアの購入や運用・管理は不要で、セットアップ費用と月額費用のみで運用が可能だ。researchmapのデータを使うことで、セットアップの費用も軽減できる。各研究者がresearchmapに業績データを登録すると、そのデータがUfinity研究者業績サービスにも自動的に反映されるため、学内のデータベースなど別途の登録は不要。
土居氏は、「Ufinity研究者業績サービス」を採用した理由について、「researchmapと連携していることで、研究者にとっては作業工数が大幅に減ります。登録の二度手間もありませんし、新規で着任したときなどは、前職での研究業績データをそのまま利用することが可能です。他にも、researchmapが管理していない項目を、オリジナル項目として独自に管理できる点もよかったです。ISASとしての発信したい情報を設定できることは、情報の発信力強化にも繋がっていきます」と話す。
2020年8月にはISASの全体会議で承認され、同年10月より導入が開始。導入においては、researchmapへ未登録の研究者の登録とともに、顔写真の掲載を促すための写真撮影会を実施した。オリジナル項目の設定、researchmapと「あいさすmap」の連携作業などを行い、2021年2月には「あいさすmap」が正式に公開となった。
■宇宙科学研究所 研究者総覧「あいさすmap」 
効果と今後の展望
事務作業の負荷を劇的に軽減、研究者同士の理解も促進
2022年1月の段階で登録者数は163名。ISASの学術研究を本務として担う研究者は基本的に全員登録、加えて様々な立場でISASの研究に携わる方も任意で登録している。
Ufinity研究者業績サービスを利用して「あいさすmap」を公開した効果・成果については、「研究者が慣れ親しんでいるresearchmapがベースということで登録はスムーズに進みました。事務方目線ですと、「あいさすmap」ができたことで年次要覧の作成などの事務作業に関する負担は劇的に軽減できましたし、研究者にとっても、業績の取りまとめがresearchmapへの登録に一本化されたことで、本来の研究に集中しやすい環境になったと思います」と遠藤氏は話す。
ISASではポスドク(博士研究員)の採用を行っており、応募する際に研究者情報を事前に見てもらうツールとしても「あいさすmap」を利用している。「外に対してISASの間口を広げて、研究者やその業績を分かりやすく紹介できるようになっています」と遠藤氏は付け加える。
科学推進部の八木 綾乃氏は、「ちょうど公開した2021年2月はコロナ禍ということもあって、なかなか対面で人に会えないという状況でしたが、そうした中で若手の研究者の方や新たに着任された方から、「あいさすmap」を通じてお互いの顔や研究内容を知ることができるのでとても役立った、という嬉しい報告がありました。今後は、ツールで分析をしているのでその結果を参考に、各研究者と、外部の大学、企業・学生を繋げるような方策を実施していきたいですね」と話す。
最後に齋藤氏に今後の展望を聞いた。 「あいさすmap」により、研究者同士の理解が深まっていますし、研究者自らが成果を発信しようという意識も強くなりました。今後は、宇宙科学にあまり接点がない方にもISASの研究者や研究内容に興味を持ってもらえるように、ページの作り方なども工夫していけたら良いと思います」(齋藤氏)。
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所様
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1 |
|---|---|
| 代表者 | 所長 國中 均 |
| ホームページ | https://www.isas.jaxa.jp/ |
| 発足 | 2003年 |
| 概要 | 宇宙科学研究所は、日本の宇宙科学研究を推進する中核機関。 |
[ 2022年3月 掲載 ]
