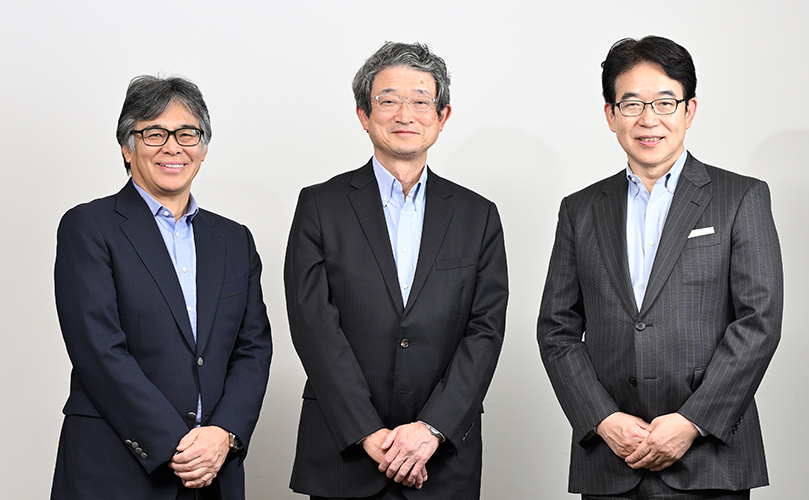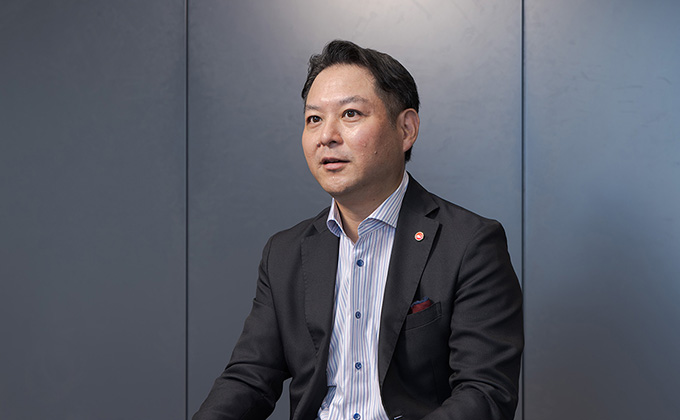- トップ
- モダナイゼーションの重要性
- モダナイゼーションの手法
- 特集記事
- モダナイゼーションを語る
- 経営者対談
- 導入事例
- ホワイトペーパー
モダナイゼーションで競争力を高める
オリックス銀行のクラウドファースト戦略 富士通と語る、実現への道筋

2018年度からクラウドファースト戦略を推進するオリックス銀行。2023年度末にはクラウド化率が86%に達する見込みだ。クラウドファースト戦略に踏み切った背景には「システムの内製化」という大きな決断があった。開発スピードを上げ、経営施策やビジネスアイデア、新規事業などをすぐに反映できる仕組み作りを急ぐ。銀行業だけに、セキュリティとリスク管理には厳しい目を光らせる。プロジェクトに伴走したのは富士通。オリックス銀行の決断とIT戦略の実像とは? 両社の経営陣が振り返る。
(聞き手:日経BP 総合研究所 所長 林哲史)
※所属、役職名は取材当時のものです。
オリックス銀行株式会社
業種:金融
本店所在地:東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル
https://www.orixbank.co.jp/ ![]()
クラウドファーストでシステムを適材適所へ
オリックス銀行の特徴を教えてください。
錦織:オリックス銀行は2023年に設立30周年を迎えました。当社の最大の特徴は、実店舗を持たず、預金を主にインターネットで集めていることです。高効率な経営により、収益性の向上に努めています。個人預金を中心に獲得し、お預かりした預金は、ワンルームマンションやアパートなどを購入する個人向けの投資用不動産ローンを中心に融資しています。オリックスグループでは、事業の意思決定においてサステナビリティを考慮することが極めて重要だと考えています。当社も環境に配慮した不動産や再生可能エネルギーなどの分野へ、積極的に資金を供給しています。
時田:御社はセキュリティやリスクに厳しい銀行業でありながら、クラウド活用を進め、クラウドファーストに大きく舵を切ったのは、かなり先進的であったと思っています。
寺元:はい、2019年度の信託システムのクラウド化を皮切りに、OA系や、情報系それぞれ適材適所にクラウドを選択、2022年度には富士通のクラウドも含めて採用、リフトアップし、2024年1月現在、クラウド化率は80%以上を達成しています。2年後にはこれを、95%まで高めていく計画です。

2023年度末にクラウド化率86%へ
モダナイゼーション
オリックス銀行はなぜシステムのクラウド化を選択したのでしょうか。
寺元:最大の理由は「システムの内製化」という大きな決断をしたことです。開発スピードを飛躍的に向上させ、経営戦略の変更やビジネスのアイデア、新規事業、業務フローの改善などを、すぐにシステムに反映できる体制を作ろうとしています。外部環境の変化に強い企業体質を作り、市場競争力を高めていきます。その実現には、膨大な保守管理業務を削減できるクラウド化が不可欠と判断しました。
「COVID-19」パンデミック以降、半導体の供給が滞り、サーバーを購入しようにも半年待たないと納品されないような状態が続きました。クラウド化すれば、そうした外部要因にも影響されなくなります。
錦織:パンデミック以前、金融業界は基本、お客様との契約は対面で署名などをいただいていました。当社も、投資用不動産ローンの契約は全て紙ベースで行われていました。現在では業務自体をデジタル化し、基本的にはすべてリモート、非対面、ペーパーレスとなりました。お客様の利便性につながると同時に、パンデミックや災害のような不測の事態が起きても、業務を続けられるようになりました。
時田:ここまで思い切ったクラウド化を進めた背景には社会の変化への対応は勿論、自らの改革への大きな挑戦があったと思います。パンデミックがきっかけになったとはいえ、クラウドがもたらしたペーパーレス化、生産性の向上により、組織の価値観も大きく変わられたことでしょう。

ポイントは「内製化」
理想的なDXの姿とは?
新規ビジネスへの挑戦は進んでいるのでしょうか。
錦織:経営とDX戦略をマッチさせるカギは、人材です。ユーザー部門の現場を知る若手社員をシステム部門に異動して、そこで内製開発に登用するなどの施策を進めています。これにより、業務部門とシステム部門の一体感が生まれるようになりました。システム部門の要員に余裕が生まれてきたら、ユーザー部門への異動を行って、一段と連携を強めていきたいと考えています。
時田:DXもSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)も、最大のポイントはやはり、内製化ですね。社員1人ひとりが自ら手を動かしてデータを分析し、使いこなす時代です。これからは、そこには人工知能(AI)も入ってくるでしょう。
寺元:かつてのデータ活用は、イタチごっこのような状況が長く続いていました。社内に散らばっているデータを集めて加工しても、できた頃にはユーザー側のニーズが変わっている。しかし、今はクラウド型の新しいデータ基盤があります。全社のデータを1カ所に集めてデータレイクを作り、BIツールを使って各自が自在に分析しながら、業務に活用できる環境を整えています。
時田:全社が1つのデータレイクを使い、データを皆で加工して活用できるようにする。そうして、データに裏打ちされた社員1人ひとりのアイデアがビジネスに生かされていく。その姿は、理想的なDXだと感じます。オリックス銀行の取り組みは、多くの企業にとって有益な事例となるでしょう。
富士通でも同様に、社員が誰でもデータを分析できる環境を整え、様々なアイデアに活用しています。その分析情報や活用事例は社内SNSなどを通じて、社員自らが積極的に発信し、活用の輪が広がっています。
クラウド化と内製化によってデータ活用が進むと、組織はどう変わるのでしょうか。
錦織:当社の組織は大きくありませんが、社員の全社横断的な視点が弱いと感じてきました。そこで1つのデータレイクを作ると、社員は社内の様々な部門が個別に管理してきたデータを横断的に利用できるようになり、自然に会社全体のことを考え始めます。そうしたカルチャーを、今後も醸成していきたいと考えています。
寺元:また、内製化を進めることでスピード感が大きく変わり始めました。SaaS型のデータ基盤は、どんどん進化します。ニーズに合わせて独自に構築するというより、世の中で標準的なベストプラクティスを使うという発想に切り変わるのが、クラウド化と内製化の大きな流れだと認識しています。
時田:様々な企業とお話する中で、そうした流れは私も実感しています。またその流れは、広がっていくと思います。内製化により開発スピードが上がる、社内にノウハウが蓄積されるなどメリットが挙げられますが、私が注目しているのは、内製化の副産物として、社内でのコミュニケーションが活発になり、雰囲気がよくなることです。

データ管理の透明性が高い「FJcloud」を選択
今回、パートナーとして富士通を選択していただいた理由をお聞かせ願えますか。
錦織:20年以上のお付き合いの中で、一般的な銀行とはビジネスモデルが異なるオリックス銀行の特色をよく理解していただいている点が、まずは大きいです。
寺元:銀行業にとって、セキュリティとリスク管理は絶対的に重要です。その心臓部とも言える勘定系システムを、どのクラウドで運用すべきか。多角的な議論の末、勘定系システムはデータ運用において信頼性の高い富士通のFJcloud(FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud)に任せることにしました。
他社のクラウドには「データセンターが地球上のどこにあるのか明かせない」というものがあります。富士通の場合は、オンプレミスとクラウドのシステムを、どちらも国内のデータセンターに置くと約束してくれました。
時田:大切なデータがどこにあるのか、所在をしっかりと把握しておきたいというお客様は増えています。そのニーズに応えることの重要性は、私たちも理解しています。
寺元:当社はオンプレミスとクラウドを一体的な仮想基盤として運用し、その上にアプリケーションを載せて運用します。全てのデータとアプリケーションが国内にあれば安心です。しかも同じ拠点にあるのですから、レイテンシーの問題も起きにくくなります。
錦織:当社は、デジタルと人を組み合わせたハイブリッドな組織に変わってきており、両者をうまくバランスさせていくことが重要だと考えています。DXを担う人材を増やし、ビジネスの価値を高めながら、最適なバランスで経営していきたいと考えています。
時田:先を見据えた経営ビジョンとIT戦略をリンクさせることの重要性を、今日は改めて認識させていただきました。
テクノロジーを安心して導入し、経営や成長に十二分に活用していただく。そのフィードバックをいただきながら、次のテクノロジーに生かす。それが富士通の使命と心得ます。御社のDXにしっかりと伴走させていただき、さらなる価値を提供できるよう、一層努力していきます。
商標について
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
本記事は、日経クロステック Specialに、2024年4月に掲載された記事を再掲したものです。所属・役職は取材当時のものです。記事・写真・動画など、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。
既存情報システムを最適化し、DX基盤としてのあるべき姿に
富士通は、独自の強みをお客様の価値に変え、お客様資産の最適化とDXをご支援します。
ご不明な点やご要望などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
モダナイゼーションに関するお問い合わせ・ご相談
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。