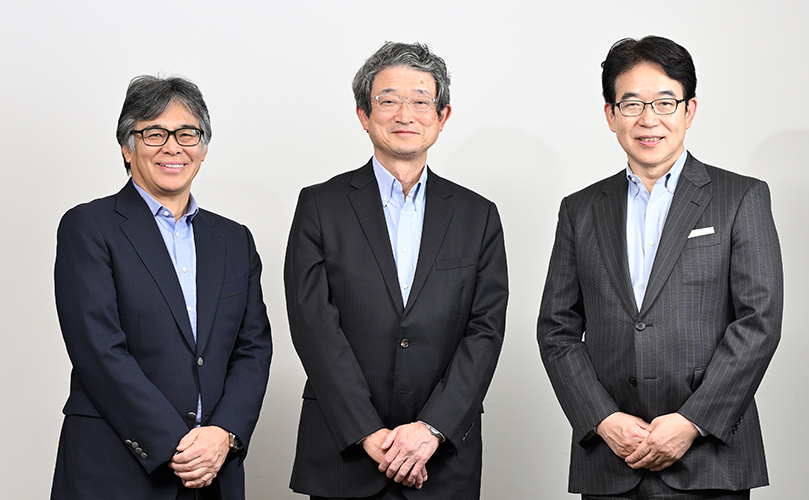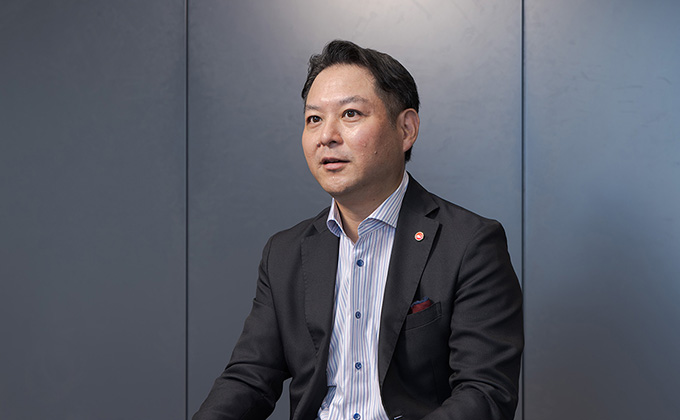- トップ
- モダナイゼーションの重要性
- モダナイゼーションの手法
- 特集記事
- モダナイゼーションを語る
- 経営者対談
- 導入事例
- ホワイトペーパー
情報価値が企業ブランドに直結する時代
オープン化戦略を、モダナイゼーションでやり遂げる 「カギはパートナーシップ」三菱食品、富士通が熱く議論

食品卸大手の三菱食品は、約6500社のメーカー、約3000社の小売事業者を主な取引先とし、年間約12億件のデータを扱う。独自の基幹業務システム「MILAI」を、時代に合わせてモダナイゼーションしてきた。2024年度から本格的にクラウドへの移行を開始する。大きな目的の1つが、経営の舵を「オープン化戦略」へ切ることだ。三菱食品の京谷社長、石崎CIO、そして富士通の時田社長が、経営環境の変化と企業成長の条件について、熱く語り合った。
(聞き手:日経BP 総合研究所 フェロー 桔梗原富夫)
※所属、役職名は取材当時のものです。
三菱食品株式会社
業種:食品卸
本店所在地:東京都文京区小石川一丁目1番1号
https://www.mitsubishi-shokuhin.com/ ![]()
企業ブランド価値の源泉は「データ」にあり
京谷:2021年に社長に就任したのと同時に「中期経営計画2023」を作り、「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する」というパーパスを打ち出しました。このタイミングでパーパスを発表した背景には、2つの大きな要因があります。
1つは社会の変化です。日本の人口減少が、この時期から加速しました。食品ビジネスにとって、人口減少は大きな課題です。加えてコロナ禍の中でデジタル技術の進化もあり社会が大きく変化しました。もう1つは、社会の価値観が変わり始めたことです。環境問題、多様性、ESGなどの新たな価値観が浸透し始めました。その中で、企業は何を目的にビジネスをしていくのか、姿勢と立ち位置を明確にすることが求められました。
三菱食品は、4つの食品卸会社が2012年に統合されて誕生した会社です。経営形態も取扱商品も違う4社の統合は、容易ではありませんでした。関連会社の整理なども含め、約10年を経てようやく完全に統合できたことを実感できたタイミングでもありました。
三菱食品には、「食のサプライチェーンを守る」という大きな使命があります。当社が誕生した2012年は、東日本大震災の直後でした。当社は被災地に向けて、懸命に食品供給を行い続けました。食のサプライチェーンは日常生活に欠くことのできない機能であり、社員一人ひとりがその責任感を持ち、食品供給の面で大きく貢献していると自負しています。そのマインドをさらに外へ向け、新しいことに挑戦する社内カルチャーを醸成したいという思いも、パーパスに込めました。
人口減少により、当社のビジネスの「量」的側面が頭打ちになることから、今後は「質」的側面が重視されます。「質」とは「新たな価値を生み出すこと」です。新たな価値には「情報価値」と「物理価値」が含まれます。
情報価値とは、平たく言えば企業の「ブランド価値」のことであり、その源泉はデータにあると考えています。デジタル技術が進化し、データを多彩な形でビジネスに生かせるようになってきました。この部分は、まさに富士通さんと一緒に作り上げてきたものです。
一方、物理価値の中心には物流があります。頭打ちとなった「量」の価値を、どうやって「質」の価値へ転換していくのか。1つの企業で取り組むには、やはり限界があります。多くのメーカー様や小売業様、同業他社と協力することで領域が広がり、新たな物理価値を生み出すことができるでしょう。それには一緒に仕事をするためのデジタル基盤が必要です。
三菱食品と一緒に仕事をすると、新たな価値を生み出せる。それこそが三菱食品のブランド価値になります。多くのパートナー企業と協力して社会課題の解決に取り組むことが、成長の源泉になっていくと考えます。

時田:同感です。外部とのコラボレーションは、企業の成長を支える重要な柱になっていきます。
富士通は、あらゆる業種業態のお客様を持つことを強みとし、従来型のSIビジネスでは、1社1社のお客様に向き合ってきました。今後は企業や業種を横断して力を合わせ、大きなエコシステムを作っていく必要があります。当社もそこに目を向け、クロスインダストリーの新たな事業モデルとして「Fujitsu Uvance」を立ち上げました。この取り組みを通して業種間の垣根を取り払い、お客様同士をつなげる役割を担っていきます。そのために、当社でも「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」というパーパスを定めて、事業の方向性を示すことで、社員一人ひとりの行動変容を促していく必要があると考えています。
全社一体で取り組まなければ
モダナイゼーションは成功しない
京谷:今の富士通さんの経営方針には、共感できる部分が多くあります。情報価値と物理価値を生み出すには、外部とのパートナーシップが重要です。個社では解決できない大きな社会課題が山積みする中で、経営の質的変化が求められているのです。
「和食」は、日本人の伝統的な食文化であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。日本の食文化は多様であり、それぞれの地域には継承され、守られた個性豊かな食や味があります。地域ごとに特色を持つ、個性的で多数のメーカー様や小売業様が、その食文化を支えています。当社は日本のユニークな食文化を守るため、全国の企業と連携し、持続可能なあらゆる取り組みを考えていかなければいけません。それをスムーズに実行するためには、まさに富士通さんがやられているように、共通基盤をどう作り、浸透させていくかがポイントになります。
石﨑:当社とお取り引きのあるメーカー様は約6500社、小売業様は約3000社、タッチポイント(店舗等)は約16万件という大きなネットワークを抱え、年間12億件以上のデータを扱っています。受発注、物流、経理など、あらゆるプロセスを管理・運営する基幹システムは、事業の持続可能性と成長を支えるために24時間365日稼働し続けることが求められており、まさに事業の生命線となっています。
当社の変革と成長を加速する為、情報システムはより一層重要な役割を果たす必要があります。常に新しい技術の戦略的な取り込みに挑戦し、経営環境の変化に素早く対応するとともに、情報セキュリティ対策も強化していきます。
1980年代に構築した当社の基幹業務システム「TOMAS」は、1990年代半ばに「NEW TOMAS」へと進化してきました。2013年発足の「MILAIプロジェクト」で、それまでのメインフレームを脱してオープン化を実現しました。富士通さんの技術者に、当社の業務内容と取引環境の変化による課題を理解してもらい、Javaで一から開発し直しました。その際に、基幹システムのドキュメントを網羅的に作成できたことは、重要な成果のひとつだったと思います。
そして2024年度から、本格的にクラウドへの移行を開始します。リフト&シフトによる「MILAIクラウドプロジェクト」のスタートです。

時田:モダナイゼーションの目的は、企業ごとの環境や狙いによって異なります。しかし全てに共通することは、ビジネス環境や市場ニーズの変化、商品やサービスの特徴とコンセプトをしっかりと取り入れ、経営の変化を支えていける基盤にすることです。富士通にとってお客様とのパートナーシップは非常に重要です。お客様からフィードバックをもらいながら、何が望まれ、どのようなテクノロジーを活用すべきなのか。お客様のパーパス実現に寄与できているのかを考えながら進めていく必要があります。
石﨑:2013年の「MILAIプロジェクト」では、モダナイゼーションを全社プロジェクトと位置付けました。社内のすべての本部や主要部署から人を集めました。現場の担当者、経営陣、富士通さんを中心とする外部パートナーと1つのチームを組み、一体感を持って進められたことが、成功できたポイントだと考えています。また、この基幹システムの刷新は、4社統合後の会社を一つにしていく大きな役割を担ったとも考えています。
時田:システム開発には、困難やコンフリクトがつきものです。それを乗り越える際に、「全社一体」が実践できているかどうかが試されます。それには経営トップの強い意志があり、目的がしっかりと調整、確認されている必要があります。
モダナイゼーションは、現場も含めて全社一体となって進めることが重要です。IT部門とベンダーに任せておけばよいという考えでは、成功しません。なぜなら、モダナイゼーションは新規開発と異なり、過去の遺産をどこまで引き継ぎ、何を捨てるのか、数多の重要な経営判断が求められるプロジェクトだからです。富士通はお客様のビジョンを理解し、テクノロジーの面からそれを支える役割を果たしています。

ただ「変われ」と言っても人は変われない
石﨑:現在の「MILAI」は、スクラッチで開発した一枚岩のシステムです。これを変革する次の「シン・MILAI」プロジェクトでは、従来のように「独自のシステムを開発する」という考えだけではなく、「世の中にあるベストなものを使っていく」という方針も取り入れます。三菱食品だけが持つ門外不出のマスタやデータはしっかりと自社内でシステムを構築していきますが、それ以外のものは、実績が豊富で標準化されたシステムを活用し、クラウド上で組み合わせて構築していきます。
例えば、貿易業務プロセスのシステムそのものに差別化や競争優位性を生み出すことは難しく、そうした領域は自社開発より、ベストプラクティスを知り尽くした外部のシステムを活用すべきです。導入実績が多く標準化が進んだシステムを積極的に採用することで、他の企業とも連携が容易になるでしょう。このようなオープン化戦略を「シン・MILAI」プロジェクトの基本的な方針としていきます。
京谷:企業成長にとってオープン化戦略は重要になっていきます。前述したパートナーシップとは、まさにデータ連携そのものと言えます。そのインフラが当社側に整っていなければ、戦略の実現はなしえません。
3年間の中期経営計画の期間において、仮説を立てながら数多くの挑戦をしてきました。失敗もありますが、多くの成果を出すこともできました。私たちの仮説は正しいという確信が、社内に広がりつつあります。新しいことに挑戦する風土が強まり、業績拡大の最大の原動力になっていると感じます。それを支えていく重要な要素の一つが、情報システムの刷新であることは間違いありません。
個社のデータのみならず、広く外部のデータと掛け合わせ蓄積していくことで新たなバリューが産まれています。三菱食品は、そういった基盤を作るチャレンジをこれからも続けていきます。
物流分野においては、業界をあげての連携や全体最適の追求は、環境問題の解決にも同時に繋がっていると社員は理解してきており、マインドセットも変化してきています。データを使ってどんどん見える化し、新たな価値を生みだすサプライチェーンを維持することが、持続可能な社会を作っていくと考えています。
石﨑:富士通さんは、三菱食品の変革に欠かせないパートナーです。そこには2つの期待があります。1つは、イノベーションの推進や事業戦略の進化に応じたシステムをタイムリーに提言していただきたいということ。
もう1つは、食品流通業界全体を俯瞰した課題解決のアプローチや、エコシステム構築などを通じた「顧客を巻き込む力」をさらに高めていただきたいということです。それが、当社の「シン・MILAI」プロジェクトの成功にも繋がると信じています。
時田:データ交換とは、まさに価値の交換そのものです。それによって企業間の連携が強くなり、エコシステムが強化されていきます。当社がパーパスドリブンとともに、データドリブンを進めている理由もそこにあります。パーパスを打ち出すだけでなく、それがビジネスに良い影響を与えていることを、社員に理解してもらう必要があります。ただ「変われ」と言っても、人は変われません。変わっていく会社の姿をデータで可視化し、良い変化の兆しを全員が共有すれば、変革を進める原動力になります。
三菱食品様のように、データ活用をパートナーシップの拡大に生かしていく例は先進的です。多くの企業にとって参考になることでしょう。
商標について
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
本記事は、日経クロステック Specialに、2024年5月に掲載された記事を再掲したものです。所属・役職は取材当時のものです。記事・写真・動画など、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。
既存情報システムを最適化し、DX基盤としてのあるべき姿に
富士通は、独自の強みをお客様の価値に変え、お客様資産の最適化とDXをご支援します。
ご不明な点やご要望などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
モダナイゼーションに関するお問い合わせ・ご相談
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。