いまこそ学ぶドラッカー流「起業家社会」実践法
日本流イノベーション戦略への教え
ヨーロッパ・ピーター・ドラッカー・ソサイエティ創設者 兼 理事長 リチャード・ストラウブ氏来日記念セミナー
経営におけるアントレプレナーシップ(起業家精神)と人材育成の重要性を説いた現代経営学のカリスマ、ピーター・ドラッカー。いま始まりつつある起業家社会のなかで、日本企業は果たしてその要請に応えることができるでしょうか?
2017年9月21日富士通は、東京・浜松町のFUJITSU Digital Transformation Centerで第11回トポス会議に先駆けた特別イベントを開催しました。そのタイトルは「日本を『起業家社会』に変えるために - ドラッカー・イノベーション論の再発見 -」。

多摩大学大学院の紺野登教授を進行役に招き、リチャード・ストラウブ氏(ヨーロッパ・ピーター・ドラッカー・ソサイエティ創設者 兼 理事長)と高重吉邦(富士通 マーケティング戦略本部 VP)が、ドラッカーが強調した「イノベーション」や「イノベーションが起業家社会に与える影響」をテーマに講演。最終セッションのパネル・ディスカッションでは、来るべき起業家社会における日本企業の課題と挑戦について会場を巻き込んだ熱い議論が交わされました。
新たな「日本型経営」を

「最近の若い人たちは日本的経営と聞くとどうも古臭いと思うようだが、いまこそまさに21世紀の日本的経営を考えるべきなのではないか?」 冒頭で本イベントの趣旨を述べた紺野登教授は、まず会場にそう問いかけました。
「ドラッカーの言葉や考えを軸に今日はそのこと、すなわち、日本のビジネスをもっと起業家精神に溢れたものに変えていくにはどうすればいいのか、ということについて考えていきたい」。
70年代、日本的経営とそこから生まれる斬新なイノベーションは、欧米の大学やビジネスの注目を集めました。そこには欧米にはない独自の強みがあるとドラッカーは唱えました。しかし今日、その強さは影を潜め、企業もかつての輝きを失ってしまったように見えます。
一方、海外に目を向ければ、各都市でベンチャーが次々と産声をあげ起業家社会の波が押し寄せています。はたして日本は、このトレンドに乗ることができるのでしょうか?
ヒントはドラッカーの言葉のなかにあります。「日本の若い経営者にとって、ドラッカーの著作は、決して読むべくして読む古典ではなく、今日や明日の課題に対処していくための実践書です」と紺野教授は話し、バトンをストラウブ教授に渡しました。
日本に愛されたウィーン人
 ヨーロッパ・ピーター・ドラッカー・ソサイエティ創設者 兼 理事長
ヨーロッパ・ピーター・ドラッカー・ソサイエティ創設者 兼 理事長
リチャード・ストラウブ氏
特別講演に登壇したリチャード・ストラウブ氏はまず、ドラッカーの著作が日本でよく読まれていること、そしてその経営論が今日も有効性を失っていないことに触れました。
「欧米でドラッカーを読む世代といえば、ベビーブーマーくらいです。X世代は多少読みますが、Y世代にいたってはドラッカーの名前を耳にしたことがあっても実際に読んではいません」とストラウブ氏は話します。「一方、日本では若い読者もおり、彼の主張がよく理解されている。世界で一番ドラッカーが読まれている国、それはまぎれもなく日本です」。
人重視の視点
ドラッカーが生きた時代のウィーンには精神分析学のフロイトや哲学のウィトゲンシュタイン、そして経済学のシュンペーターがおり、とくにシュンペーターとの親交は知られています。そんな時代の知的な空気のなかで企業経営や社会に対する彼の思索が深まっていったのです。
また、ドラッカーは「現実をしっかり見据えていた」とストラウブ氏は強調します。生前彼は、友人のジム・コリンズに、「自分は決して未来を夢見ているわけではない」と話していました。彼は、目の前に歴然とありながら誰もが見落としていることをそのまま語ろうとしていたのです。
ストラウブ氏はさらにドラッカーの思想にある人間尊重の姿勢を強調しました。「成果をあげない企業は生き残れない」と述べたあと、「人間のことを忘れて企業が成果をあげることはできない」とつけ加えます。企業活動の核にあるのは「成果」ですが、そこには必ず「人間」がいなければなりません。生前のドラッカーの人となりについて「人間を大切に考える人だった」とドラッカー夫人も話しています。
ドラッカーはまた、企業や自己の管理についてもひとつの信念を持っており、「セルフマネジメント」と題する記事をハーバード・ビジネス・レビューに寄せています。
経営の三つの側面
こうしてドラッカーの思想をたどりながら、ストラウブ氏は次に経営というものを理解するための3つのレイヤーである「WHAT」「HOW」「WHY」について話しました。
「WHAT」は主に知識を表し、経営の理論やコンセプトに関わります。
「HOW」は技能を表し、ビジネス・モデルや事業計画など方法論やツールに関わります。
「WHY」は叡智を表し、事業の目的・価値・倫理など、人や社会に関わります。
3つのうち最も重要なのが、「WHY」であるとストラウブ氏は強調しました。「なぜなら、それが企業に根本的な問いを投げかけるものだからです。それは社会との関わり、単なる利益を超えた価値、地域貢献、倫理性といったことについて問いかけてきます」。
ドラッカーにとって経営とは単にビジネス上の職務ではなく社会的な役割を意味していました。
イノベーションと起業家社会
ドラッカーが親しんだシュンペーターは、事業とイノベーションについて語った先駆者のひとりです。彼は1934年、『経済発展の理論』のなかで「資本主義における中心的存在は資本家ではなくイノベーションを通じて社会に富をもたらす事業家である」と書いています。
たしかにこの250年、数多くの事業がその成果によって社会の富を増加させました。「社会保障、教育、医療、交通などさまざまな分野でイノベーションが生まれ、人々の生活は大きく向上しています」とストラウブ氏は語ります。「もちろん金融資本も大きな働きをしましたが、しかし、本質的な役割を担ったのは事業家たちでした」。
ドラッカーはこの考えを引き継ぎ、『イノベーションと企業家精神』のなかでシュンペーターの思索をさらに発展させたとストラウブ氏は指摘します。「イノベーションと企業家精神をこのように体系的に扱ったのはドラッカーが初めてです。その主張は、現在でもまだ有効です」。
多様性とイノベーション
ドラッカーはまた哲学や文化にも深い関心を寄せていました。浮世絵の展覧会を観た彼は江戸美術の多様性に心を打たれました。「江戸期の美術は百花繚乱。その多様性はイノベーションの源泉です」とストラウブ氏は話します。
起業家社会への道は決して一つではありません。意思決定において多様性を重んじるのか、それとも同一性を尊ぶのか、社会のルールと個人主義との間にどんな折り合いをつけるのか。選択はそれぞれの人に委ねられています。
「日本人があえて欧米人のように振舞う必要はありません。米国には米国の、ドイツにはドイツの起業家社会があるように、日本には日本の風土と文化にあった起業家社会があるのではないでしょうか。ぜひ、それを見つけてください」。ストラウブ氏は、そう言葉を結びました。
イノベーション社会への挑戦
 富士通 マーケティング戦略本部 VP
富士通 マーケティング戦略本部 VP
高重 吉邦
ストラウブ氏の特別講演に続き、富士通の高重吉邦が登壇。さまざまな事例を紹介しながら、日本におけるイノベーションについて講演しました。
ドラッカーは明治期の日本のイノベーションを高く評価しています。しかし、それは、技術的なものというより社会的なイノベーションだったと高重は指摘します。当時日本は、教育や銀行などの仕組みを欧米から学びつつ、日本のものとして取り込みました。また、ものづくりにおいてもソニーのトランジスタラジオやセイコーのクオーツ時計などのように、海外の技術を独自の製品に昇華させ、当時グローバル市場を握っていた欧米企業の隙をついて大きな成功を収めました。ドラッカーはこれを「柔道戦略」として賞賛しました。
富士通もドイツのシーメンスの通信機器技術を導入してクロスバー型交換機を製造しましたが、そのリレー部品技術の応用がのちに国産コンピューターの開発につながっていきます。
デジタル社会へのパラダイムシフト
こうした成長発展の時代の後、1990年代初頭にバブル経済が崩壊し、いわゆる「失われた20年」が始まります。
この20年の間に世界市場はすっかり様変わりしました。時価総額のランキングでは、かつての優良企業に代わって、アップル、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックといった新しいデジタル技術を使ったプラットフォーマーが上位を占めるようになっています。
「今、デジタル社会へのパラダイムシフトが起こっている」と高重は強調します。
AIやIoTをはじめとするデジタル技術がビジネスや社会の根幹的なプロセスに織り込まれていくことによって、産業構造の大きな変革が起こっています。デジタル技術が取引コストを大幅に低下させたため、標準化された商品を大量生産するために作られた垂直統合のビジネス・モデルは、もはやあまり意味を持たなくなってきました。今、業種の壁を超えて企業と企業、企業と消費者がつながる共創(Co-Creation)のエコシステム「デジタル・アリーナ(価値を生み出す場)」が形成されつつあります。
その一例として、高重は自動運転を挙げました。デジタル時代には、自動車はデジタル化されたハードウェア、ソフトウェアやクラウド・サービスを組み合わせて構成されるようになり、自動車会社、部品サプライヤ、デジタル・サービスプロバイダーなどの広大なエコシステムがそこに立ち上がります。「これは、自動車というモノを供給するのではなく、モビリティ(移動の利便性)という価値を共創するデジタル・アリーナです」と高重は話します。
イノベーションに向けての取り組み
「しかしながら、既存の企業がイノベーションを生み出すのは決して容易ではない」と高重は続けます。起業家精神を活性化するためには、未来のビジョンを起点に今何をすべきかを構想すること、計算されたリスクを積極的に取るべくチャレンジすること、イノベーションを潰さないためにトップダウンでアプローチすること、そしてエコシステムを活性化するためにイノベーションのコミュニティに主体的に貢献(“Give”)することが重要だと強調しました。
富士通では毎年、ビジネスや社会の将来ビジョンを示し、企業がテクノロジーを活用してどのようにイノベーションを起こしていけるかについての考えをまとめた「Fujitsu Technology and Service Vision」を発信しています。「これは富士通自身がイノベーション企業としてさらに変革していくためのロードマップとしての役割も果たしている」と高重は話します。
また、そのほかにも富士通はデザイン思考の活用やコミュニティ形成によりイノベーションを加速していく取り組みも行なっています。例えば、ここDigital Transformation Centerを始めとして、富士通と顧客企業がワークショップを通じて共にアイデアをかたちにしていく共創の場を運営。また、企業間のオープン・イノベーションを推進するために、「Open Innovation Gateway」を米国シリコンバレーに設置する他、ベンチャー企業のコミュニティづくりにも積極的に取り組んでいます。
講演を終えるにあたり、高重は来るべきイノベーション社会について語りました。グローバルな課題解決に向けた国連の持続可能な開発目標(SDGs)に対応し、富士通は、例えば食・農業、健康・生活の質、持続可能な都市といった分野でデジタル・アリーナを形成する試みを多くのパートナーとともに進めています。「これらのデジタル・アリーナは独立して機能するというよりも、多くのアリーナが相互につながることを通じて、より大きな価値を生活者のために生み出す可能性を持っています。これが、企業や起業家がイノベーションを共創し、社会の共通善を実現するイノベーション社会へと発展していくのです。社会の共通善への貢献は、ドラッカーが企業の最重要使命として挙げたものです。それこそが、私たちが掲げている未来ビジョンであるヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティです」。
イノベーション経営とは?
本業を持つ企業がイノベーションを生み出すためには?
 多摩大学 大学院教授
多摩大学 大学院教授
紺野 登 氏
続いて会場では、本日の進行役である紺野教授がみずから代表理事を務めるJapan Innovation Network(JIN)![]() の活動を紹介しました。JINは、大企業を対象にイノベーション経営のための人づくり、組織づくり、プラットフォーム構築などを支援する非営利団体です。
の活動を紹介しました。JINは、大企業を対象にイノベーション経営のための人づくり、組織づくり、プラットフォーム構築などを支援する非営利団体です。
「日本の大企業にはまだまだ人的、経済的なリソースが眠っており、それらを活性化させることで国内のイノベーションを加速させていくことができる」と紺野教授は話します。そこでJINは、1. イノベーション経営の普及、2. 実践、3. プラットフォームの構築・運営の三分野にフォーカスして支援活動を行なっています。
- イノベーション経営とは効率的に試行錯誤を行うスキーム作り、と紺野教授は説きます。通常の事業では失敗は歓迎されません。しかし、イノベーションを生むためには多くの創造的失敗が求められます。
- 実践面では、企業内でイノベーション・コミュニティを形成し、ベストプラクティスを共有。また、社内の支援者を増やす目的でソニー生命名誉会長の安藤国威氏を塾長に「イノベーション塾」なども開催しています。
- プラットフォームの構築では、国連開発計画(UNDP)とパートナーシップを結び、世界170以上の国と地域から現地の課題を吸い上げ、会員企業と協力してイノベーションを生みだす仕組みを立ち上げています。これはJINの持つ企業ネットワークを世界の課題につなげる情報プラットフォームともいえます。
「事業家はビジネスの成果によって社会の共通善に寄与する」というドラッカーの言葉を示しながら、JINのこうした取り組みもその方向性に向かうもので、それは日本企業の文化にもよく合っていると紺野教授は話しました。
パネル・ディスカッション

締めくくりとして、企業内イノベーションと起業家社会の到来をテーマにパネル・ディスカッションが行われました。冒頭、紺野教授は登壇者に3つの問いを投げかけ、発言を促します。
Q1. 日本の産業界は大企業主体だが、かれらは起業家社会に生き残れるのだろうか?
Q2. これまで企業競争は技術が中心だったが、ドラッカーは人間的価値や文化的価値で競争する社会を思い描いている。そうした社会は生まれうるのか?
Q3. そのような人中心の社会を生み出すには何をすべきか?

ストラウブ
私の見るかぎり、世界の大企業は今日、まるで効率機械のように動いています。それを私は”効率カルト(Cult of Efficiency)”と呼んでいます。イノベーションや起業についても同様です。
この傾向は米国でとくに顕著です。株式市場で短期的な利益を狙う。そしてその利益は投資家の手に戻されます。
しかし、長期的に見た場合、これは健全なことといえるでしょうか? IBMに勤めていた頃、メインフレームやPC事業の展開を見ていて思ったことがあります。それはあまりにも技術中心で、人間が置き去りにされているということでした。
技術ではなく人中心に事業を進めることが大切です。富士通はその方向で動いているようで、それは嬉しいかぎりですが、一方でそれはなかなか難しい。まず技術を理解し、そのうえで文化や歴史を知り、文化人類学などにも通じていなければなりません。そうした理解のうえに立って初めて技術がどう人間に役立つかわかってくるからです。
AIは人よりも上手く仕事ができるのでしょうか?人は決してデータだけでできあがっているものではありません。
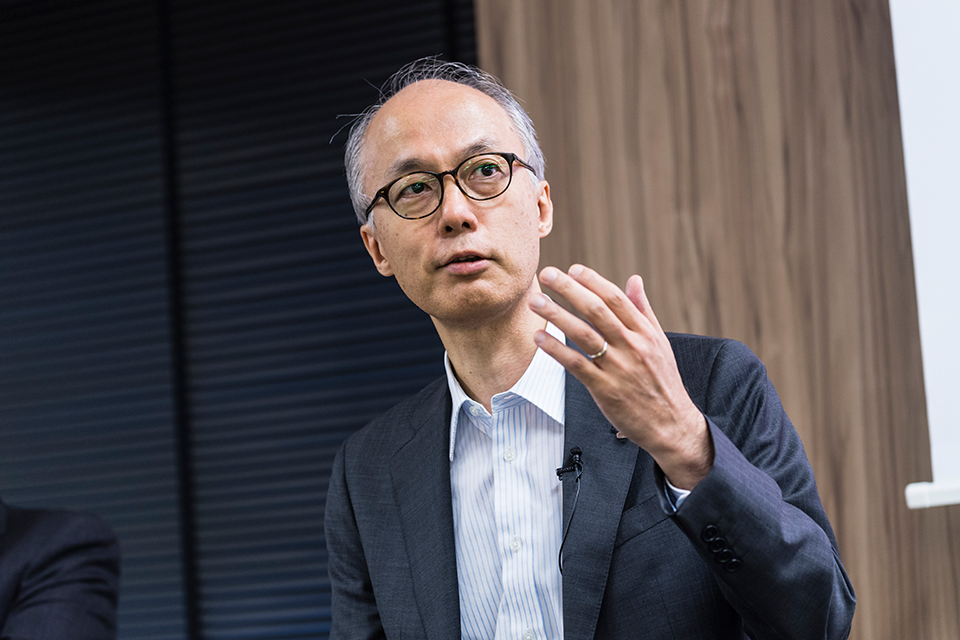
高重
元IBMの方と意見が合うというのは嬉しい限りです(笑)。富士通はヒューマンセントリックをビジョンとして掲げて、すべてを人を中心に考えた事業活動を行なっていますが、これからは企業が人というものをもっとしっかり考えていくべき時代だろうと思います。
一方で、企業はどうしても人を損益計算書上のコストとして考えてしまうところがある。その人が価値を創造する人間であるところを見ようとしません。人には多くの可能性がありますが、それを評価することができないのです。
リスクを取る姿勢を呼び覚ますためには、若い人材にいろいろな経験をさせ、鍛えるべきだと思います。ただ、昔は人もいなかったので自然にやっていたかもしれませんが、今はなかなかそうもいきません。
特に既存の事業を回している実働部隊でイノベーションにチャレンジするのは難しい。たとえば富士通では企業向けシステム開発の仕事をやっていますが、エンジニアは顧客から要求された仕様に正確に基づき、ミスが無いように納期どおりに開発を進めます。これ自体は悪いことでは全くありませんが、ことイノベーションに関しては、顧客自身もわからない課題や機会に挑戦していかなくてはならない。そのためには、独立した組織やチームが必要になります。富士通では、今年から新組織を立ち上げ、ビジネスプロデュース、デザイン、デジタルエンジニアリングなどの新しいスキルを持つ人材の育成に努めています。
「大企業は起業家社会で生き残れるのか」という問いかけがありましたが、いずれにせよ、垂直型のバリューチェーンが分解されていく過程で、大企業は今後10年で大きな変革を経験することになると思います。パートナーとのエコシステムを構築し、イノベーティブな企業に変革していくことが鍵です。

紺野
先ほどストラウブさんが“効率カルト”とおっしゃっていましたが、現実にはやはり投資の短期回収を求める資本市場のプレッシャーが歴然とあり、人中心の起業家社会などというと青臭いとか夢や幻想だなどと批判する向きもあります。
しかし、一方で日本の経営者はアメリカほど株主利益を気にしていない。これは日本が欧米より経営環境としてイノベーションにより適しているといえるのでしょうか?
ストラウブ
最近、フランスの総合建設会社ヴァンシのCEOに会う機会があったのですが、聞いたところ、この会社の企業価値はFacebookの1/10ほどということでした。しかし、ダムや地下鉄の建設で人々の暮らしを支えているこの企業の社会的価値は、Facebookよりももっと高くあるべきなのではと私は思いました。
この企業価値の問題については来年のドラッカーフォーラムで、“Human Capital”をキーワードに議論を深める予定です。企業にとって最も価値がある資産はなにかといえば、それはやはり人。人をコストと考えるのは間違っています。
高重
アメリカのコーネル大学のMBAプログラムで学んでいたとき、最初の講義で企業の目的はそのオーナーである株主の利益の最大化だと教えられ、正直驚いた経験があります。その時は凄いなと思ったのですが、その後ヨーロッパの企業と仕事をする機会にも恵まれたのですが、そこではアメリカよりも従業員の権利などを重視することを知りました。
現在の企業は、株主以外に従業員や顧客そしてコミュニティも含めてステークホールダーと考えるようになってきていると思います。とくに1980年代以降に生まれたY世代は、ソーシャルバリューにも敏感で、社会に貢献しない企業のブランドは買わないというような意識が根付いているようにも思えます。
ここで紺野教授は、会場から登壇者への質問を募りました。

聴衆A(IT企業社員)
さきほど高重氏は、企業内でイノベーションを興す場合、新規部門を立ち上げるとおっしゃっていましたが、そのための人材の登用や教育はどうされていますか?
高重
国内のIT業界の大手企業では、プロジェクトをグループ内等のソフトウェア会社に発注するケースが多かったと思います。非常に効率的でしたが、尖った人材を育成する面ではどうだったかとも思います。
富士通は、システム開発のグループ会社を本体に吸収した上で、デジタルイノベーションに取り組む新しい組織を立ち上げ、顧客向けのイノベーションを促進しています。そういうやり方で社内の人材を再配置・教育し、デジタルイノベーターを育成しています。
欧米では、人材を獲得するためにM&Aを行うこともやられていますそういった方法も考えながら、私たちはまず社内の人材を強化するかたちで進めています。
ストラウブ
ひと言付け加えたいのですが、いま大企業では社員のエンゲージメント率(みずから熱心に仕事をする割合)がとても下がっています。従業員は潜在力を秘めているのにやる気を失っているのです。これでは誰もイノベーターになることができず、企業にとってはイノベーションの機会喪失だといえるでしょう。このエンゲージメント率を大幅に高めることができれば、企業はもっと大きく変わるのではないでしょうか。
紺野
たしかに今日、やる気ある社員の不足という問題は見過ごせません。会社で目的を持って働いている社員は全体の3割弱しかないというような報告もあり、これは経営上の大きな脆弱性を表しています。イノベーティブなマインドを持った社員が1割いたとして、残りの9割が違う意識を持っていたとしたら、その1割も結局潰されてしまうのではないでしょうか。
聴衆B(大学院教授)
ストラウブ氏に価格のあり方について質問します。現在、ものの価格はコストベースで決められていますが、これをユーザーエクスペリエンスなどのバリューベースで決定できるようになれば、社会も変わっていくと思うのですが?
ストラウブ
バリューにもとづいて製品価格を決定するというのは賛成です。インターネット企業などはすでに従来の企業とは異なる価格戦略を持っています。顧客のデータと引き換えにさまざまな情報や利便性を提供するというようなやり方です。当初ユーザーはそのリスクに気づきませんでしたが、最近では意識しはじめています。
いずれにせよ厳しい競争市場のなかで製品バリューにもとづく新しい価格メカニズムを作り上げるのは容易ではないでしょう。
高重
価格設定は、富士通でも課題です。たとえば、システム構築の価格は人月あたりの単金で設定されることが多く、完成したシステムがどのようなバリューを生み出すかが価格に反映されることはあまりありません。
バリューベースで価格を決定するためには、お客様との間で新しいテクノロジーが生み出すビジネスへのインパクトや成果(アウトカム)の共通理解を築かなければなりませんが、これはそれほど簡単ではない。デジタル時代に日本の産業界全体で真剣に取り組んでいくべき事だと思います。
紺野
その点は先ほどストラウブ氏がお話されていたことにもつながりそうですね。フランスの総合建設会社の企業価値がFacebookの1/10だったという話です。

聴衆C(JIN職員)
たいていの企業は四半期や年度ベースで業績を評価しますが、組織がイノベーションに取り組む場合、人事も含めどのようなタイミングで評価をするのが適切でしょうか?
高重
既存の事業オペレーションは高い精度で予測可能なので、四半期などで数値管理することが容易にできますが、イノベーションプロジェクトにはそれが当てはまりません。イノベーションは、トップが明確なゴールやマイルストーンを設定した上で、進捗管理していくことが重要です。インセンティブや人事評価も、イノベーションの独自性を考えてそういったゴールやマイルストーンと関連づけることが必要だと思います。
紺野
ストラウブ氏に伺いたいのですが、日本企業は大体決算時に業績をアピールする成績表型。米国企業はテスラのように将来に向けての製品戦略で市場に訴えるイノベーション自己アピール型。では、ヨーロッパの企業はどうなのでしょうか?
ストラウブ
株価で評価されるという意味で、ヨーローパの企業も米国型とほぼ変わりません。これは一種の病気ですね。ひとつ違いがあるとすれば、ヨーロッパでは株式市場で健闘している同族系の中小企業が多いということです。
こうした会社は一般の企業経営と家族経営の混合形態をとっており、従業員のエンゲージメント率がとても高い。オーナーが経営者だからでしょうか。私は、エンゲージメント率というのは企業評価にとてもよい指標だと思っています。従業員のエンゲージメント率が高い企業は成長が期待できる反面、それが低い企業は存続が危ぶまれます。
聴衆D(ベンチャー企業社員)
アントレプレナーとして優秀な人材は、スピンアウトすることが多いと思いますが、大企業はどうやってかれらを社内に引き留めるのでしょうか?
ストラウブ
スピンアウトすればそこには成功とともに大きなリスクも待っています。一方、企業に留まれば、そこには自分をサポートしてくれる組織とリソースがある。この二者択一の選択はそのアントレプレナーに委ねられています。 大企業というものは本来官僚的なものです。事業プロセスが複雑に入り組み、多様な判断のなかから安全を担保していかないといけないので、それは当然です。したがって組織も自然と中央集権的になる。おそらく、優秀なアントレプレナーを社内に留めていくためには、大企業はみずからフラットな組織を作り上げる必要があるかもしれません。
高重
海外企業との戦略アライアンスを担当していたころ、パートナーのシスコシステムズが「スピンイン」とでも言うべきいう興味深いやり方をしているのを見ました。これは組織内で革新的なアイデアを思いついたチームをいったんスピンアウトさせ、社外で自由にやらせたあと、成功の見通しがついた所でもう一度社内に戻すという手法です。大企業が社内起業家をどうマネージすべきかという問いへのひとつの解ではないかと思います。

聴衆E(IT企業社員)
ダイバーシティについて質問します。企業内の人材、思考、経験の多様性がイノベーションやクリエイティビティにつながっていくのではないかと思うのですが?
高重
イノベーションを生むには多様性が重要という調査報告もあります。個人的な実感として、能力のある女性はやる気にあふれているので、大きな仕事や課題に早くからもっと挑戦させていくべきだろうと思います。
ストラウブ
IBMにいたころT字型のスキルが必要とよく言われました。Tの縦軸は深い専門知識です。一方横軸は専門外の知識です。専門と専門外の知識がT字となって一点で繋がっている。
フィナンシャルタイムズの編集者のジリアン・テットは、昨年出版した著作のなかで「複雑な状況やイノベーションの課題に適切に対処するため、企業は文化人類学を学ぶべきだ」と言っています。企業にはこうした思考の多様性も求められるのではないでしょうか。

聴衆F(建設企業社員)
いま震災復興事業で多くの企業が協力と競争を繰り返しています。どうすれば業種を超えて生産的な協業を実現できるでしょうか?
ストラウブ
日本の建設業には詳しくないのですが、ひとついえることは、すべてのステークホールダーと話をしてコンセンサスを作りあげること。そのうえで共にプロジェクトを進めていくということです。たとえばフランスなどでは大きな事業を進めようとすると必ず各方面から反対の声が挙がってきます。辛抱強く丁寧に関係者と話をして、それぞれの利益を見出していかなければ、とてもうまくいきません。
高重
私たちはよくそういう場合に「ビッグピクチャーを描く」という言い方をします。たとえば、(簡単ではありませんが)建設業界と他業種の経営陣が真剣に議論して、将来ビジョンを描いてみるわけです。そこから共通のゴールなりバリューを導き出し、具体的な各論に落としこむ、というのがよいのではないかと思います。
議論の終わりに、紺野教授は登壇した二人に起業家社会についての期待を尋ねました。
高重
起業家社会への一つの鍵は、大企業がコミュニティに対して積極的に“Give”を行い、エコシステムを育てていくことだと思います。大企業自らが人材やリソースを貢献していく活動を通じて、シリコンバレーとは違う形の日本型のエコシステムが生まれてくると確信しています。
ストラウブ
起業家社会というのはスタートアップやベンチャーに限ったことではなく、人々の心のなかにあるマインドセットのことでもあります。これまでの社会はどちらかといえば従業員社会、雇用者社会でした。これは起業家社会とはまったく異なります。
世界はすでに様変わりし、テクノロジーの進展によって個人と企業は新しい関係を結びはじめています。この変化のなか、私たちは社会や文化や経済とどう関わっていくべきなのか。その在り方が重要です。新しい視点で物事を眺めなければなりません。企業に所属しないで働く人の数も増えてきました。
これは社会契約の話です。起業家社会は、私たちにこれまでとはまったく異なる社会契約を求めているのです。
最後に紺野教授は今回のセミナーのテーマを振り返り、こう結びました。
私たちはもうすでに新しい社会のなかにいるのに、まだそれにはっきりと気づいていないのかもしれません。21世紀の日本的経営ということを一方で考えながら今日は議論を進めてきましたが、もしかすると株主利益か社会の共通善かというような問いかけすら不要だったかもしれません。米国式経営、ヨーロッパ式経営などとあまり教条的にならず、自分たちにあったスタイルをそのまま受け入れれば、それが自然と日本型経営になるのかもしれません。
自由闊達にいろいろなものを吸収し、それを巧みに自家薬籠中のものとするのは、もともと日本に備わった美点のひとつかもしれないからです。




