人生のマルチステージ全てで輝く人が持つべき資産と企業のあり方
もはや他人事ではない「人生100年時代」
100歳社会に向けて、人はデジタル技術をどのように活用すればよいのか —経営者が、今なすべきことは何か—
今、生まれてくる子供たちの半数は、100歳以上の人生を生きることになります。一方で、デジタル技術が急速に進化する中で、人は人工知能やロボットとの新しい付き合い方を模索しなければなりません。人はどういう戦略でこれからの長い人生に立ち向かわなければならないのでしょうか。そして、企業や社会にとって何が重要課題となるのでしょうか。


富士通は2016年10月26日、FUJITSU Digital Transformation Center![]() (東京・浜松町)において、「100歳社会への挑戦」と題した経営者フォーラムを開催しました。特別講演には、新著『ライフ・シフト 100年時代の人生戦略』を発行した、ロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授が登壇。人材論や組織論の世界的権威であるグラットン教授は、世界中でベストセラーとなった『ワーク・シフト』の著者として知られています。後半のパネル・ディスカッションでは、知識経営の生みの親として知られる、一橋大学の野中郁次郎名誉教授とともに、白熱した議論を行いました。
(東京・浜松町)において、「100歳社会への挑戦」と題した経営者フォーラムを開催しました。特別講演には、新著『ライフ・シフト 100年時代の人生戦略』を発行した、ロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授が登壇。人材論や組織論の世界的権威であるグラットン教授は、世界中でベストセラーとなった『ワーク・シフト』の著者として知られています。後半のパネル・ディスカッションでは、知識経営の生みの親として知られる、一橋大学の野中郁次郎名誉教授とともに、白熱した議論を行いました。
デジタル技術を活用して100歳社会に貢献

グラットン教授が主催する働き方の未来を検討するコンソーシアム「Future of Work」では、富士通を含む100社以上のグローバル企業が働き方の未来について活発に議論しています。フォーラムの冒頭、富士通代表取締役社長の田中達也は、「富士通は、人を起点に考えるヒューマンセントリックというビジョンを掲げています。近年、デジタル技術が著しく進歩し、人の生活、社会やビジネスに大きな影響を与えています。このような時代だからこそ、テクノロジーが人をサポートして、より高い創造性や能力を発揮できるようにしなければいけません」と述べました。
「人を支えるテクノロジーに加えて、人が生き生きと働くための改革が今後のビジネスの成長に欠かせません。本フォーラムでは、100歳社会の中で今後、企業が取り組むべき課題や、人工知能の活用などについて議論したい」と熱く語り、グラットン教授にバトンを渡しました。
特別講演
リンダ・グラットン教授 『ライフ・シフト:100年時代の人生戦略とは?』
100歳社会の未来

世界の平均寿命は1840年から10年に2~3歳のペースで延びていて、「2007年に先進国で生まれた子供たちの半数は100歳以上まで、日本の子供たちに至っては107歳まで生きることになります」と、グラットン教授は語り始めました。寿命が100歳ともなると、実に21万8000時間も生産的な活動に振り向けることができます。このような100歳社会では、70歳でも80歳でも仕事をすることは十分に可能で、「シニアな人たちがずっと若々しく活動し続ける時代になります」と続けます。
世代の異なる3人の人生
グラットン教授は、1945年生まれのジャック、1971年生まれのジミー、1998年生まれのジェーンという、生まれた年代の異なる3人のモデルを例に取って、どんな風に違う生き方になるかを説明しました。ジャックの家庭は、夫であるジャックが働き、妻が専業主婦です。就職してから同じ会社で働き60歳で退職しました。マイホームを持ち、年金も十分にもらえています。一方、ジミーの家庭は共働きで、ジミー自身は複数回転職をしています。しかし、年金制度は崩壊の危機にさらされています。
ジャックとジミーの老後は大きく異なります。年金が十分にもらえないにも関わらず、寿命が延びたため、ジミーにはジャックよりも長い退職後の生活が待っています。老後の生活を支えるためにジミーは毎年、所得の17%以上を貯蓄しなければなりません。所得の4%を貯蓄すればよかったジャックに比べると、この数字が大変な額であることがお分かりいただけると思います。グラットン教授は「現代、ジミーの年代に属する多くの人が、その目標を達成できておらず、アメリカでは大きな問題になっています」と指摘します。
3つのステージからマルチステージの人生へ

最も若いジェーンは、100歳まで生きる「100年世代」であり、実に35年にも渡る退職後の生活が待っています。この生活を支えるためには毎年、所得の25%を貯蓄しなくてはなりません。それができなければ、80歳まで働く必要があります。そうなると、社会にどのような変化が起きるのでしょうか。その変化について、グラットン教授は「3ステージからマルチステージの人生になります」と語ります。
これまでの典型的な人生は、「教育→仕事→引退」という3つのステージで構成されていました。しかし、「ジェーンの場合は1度の教育だけでなく、何度も自分のスキルセットを新たに磨かなくてはなりません」と強調します。ジェーンは、マルチステージの人生を歩むことになるのです。
グラットン教授は「こうしたマルチステージの人生では、貯蓄や財産などの有形資産に加えて、無形資産がより重要になります」と続けます。無形資産とは、知識や仲間、健康、多様性に富んだネットワークなどです。この無形資産を充実させることによって、長い人生をより幸福に送ることができるのです。
4つの新しいライフ・ステージが誕生
グラットン教授は、今後「エクスプローラー」「インディペンデント・プロデューサー」「ポートフォリオ・ワーカー」「移行期間」という4つのステージが生まれると説明しました。
「20歳の若者がギャップイヤー(卒業から就職までの期間をあえて長く設定すること)を取って人生経験を積むように、70歳の人がエクスプローラーとして世界をもう一度見る時間をとって、様々なことを学んでもよいのではないでしょうか」と、グラットン教授は提言します。
「インディペンデント・プロデューサー」になるためのツールとして、グラットン教授はデジタル技術を挙げます。手編みのセーターを地域内で流通している村でWebサイトを立ち上げ、今では世界中にセーターを販売しているという若者の事例を紹介しました。「人工知能などのデジタル技術は、ビジネスの機会を与えてくれる」と指摘しました。
「ポートフォリオ・ワーカー」は、様々なことに同時進行で取り組むステージです。人生の「移行期間」のステージで何を実現していくかということを考えることにも役に立ちます。これからは、余暇の時間を自己への再投資に充てることが重要になってきます。「ジェーンは今までの世代とは比べものにならないほど、多くの移行と変化を経験するため、余暇の時間に自分へ投資しなければいけません」と、グラットン教授は強調します。
では、このような社会の変化に企業はどう対応すればよいのでしょうか。その1つが、採用プロセスの変革です。これからは、企業に就職したら一生その職場で働くという終身雇用の時代ではありません。45歳の人物にも門戸が開かれるように採用プロセスを見直すことが必要だとグラットン教授は指摘します。「今、世界は試行錯誤の時代に突入しています。何ができるのか、何をすべきなのかということを常に考えて、困難な課題をポジティブな機会に変えていかなければなりません」。グラットン教授は、こう語って講演を締めくくりました。
富士通講演
マーケティング戦略室長 高重吉邦 『デジタル革新の鍵は人』
グラットン教授に続き、富士通でマーケティング戦略室長を務める高重吉邦が、デジタル時代における人の重要性について講演しました。
デジタル技術がもたらす大きな変化

今、デジタル技術を活用したビジネスの変革が最優先課題となっています。このデジタル革新は、4つの大きな波![]() によって引き起こされています。第1の波である「インターネット」。それに続く第2の波が「モバイル・インターネット」。今、押し寄せてきている非常に大きな第3の波が「Internet of Things(IoT)」です。そしてもうすでに、第4の波である「人工知能やロボット技術」が現実のものになろうとしています。現在は、「これらのビッグウェイブに叩き付けられて破壊されてしまうか、それともうまく波に乗って大きなビジネスチャンスを手にするかの分かれ目」だと強調します。まさに、全ての産業に影響を与える、新たな産業革命が到来しているのです。
によって引き起こされています。第1の波である「インターネット」。それに続く第2の波が「モバイル・インターネット」。今、押し寄せてきている非常に大きな第3の波が「Internet of Things(IoT)」です。そしてもうすでに、第4の波である「人工知能やロボット技術」が現実のものになろうとしています。現在は、「これらのビッグウェイブに叩き付けられて破壊されてしまうか、それともうまく波に乗って大きなビジネスチャンスを手にするかの分かれ目」だと強調します。まさに、全ての産業に影響を与える、新たな産業革命が到来しているのです。
人の創造性がイノベーションを創出
この変化の時代に企業がデジタル革新を実現していくために、富士通は『ヒューマンセントリック・イノベーション![]() 』というアプローチを提唱しています。これは、IoTによって様々なモノをつないで情報を収集・分析し、最先端の人工知能ベースのアルゴリズムなどを活用して新たなインテリジェンス(洞察)を生み出し、そのインテリジェンスを使って人をエンパワー(力づける)ことによって、新たな価値を実現していくことです。高重は「イノベーションを生み出すのは人の創造性です。デジタル技術を活用することによって、人を中心に考えた、新たな価値を生み出していく必要があります」と語ります。
』というアプローチを提唱しています。これは、IoTによって様々なモノをつないで情報を収集・分析し、最先端の人工知能ベースのアルゴリズムなどを活用して新たなインテリジェンス(洞察)を生み出し、そのインテリジェンスを使って人をエンパワー(力づける)ことによって、新たな価値を実現していくことです。高重は「イノベーションを生み出すのは人の創造性です。デジタル技術を活用することによって、人を中心に考えた、新たな価値を生み出していく必要があります」と語ります。
デジタル技術が人の創造性をサポート
進化した人工知能が人間の職を奪うという懸念も広がっていますが、高重は「人の知と人工知能の知を補完的に活用し、これまで考えられなかったブレークスルーを生み出すことが重要」だと指摘します。「私たちは、脳だけでなく、身体を持ち、感情や直観、そして何よりも創造性や社会性を持っています。これらが人の知が優れるところです」と強調しました。そして、「このデジタル時代に、人の創造性を重視した企業文化や制度をどのように確立していくかが大きな課題です」と語りました。

富士通は、人が創造性を発揮してイノベーションを共創する場を数多く展開しています。その一例が、まさにこの経営者フォーラムを実施したデザイン思考実践の場である「 FUJITSU Digital Transformation Center![]() 」です。その他にも、誰もがモノづくりにチャレンジできる「TechShop
」です。その他にも、誰もがモノづくりにチャレンジできる「TechShop![]() 」、シリコンバレーのスタートアップ企業や大学との共創の場としての「Open Innovation Gateway
」、シリコンバレーのスタートアップ企業や大学との共創の場としての「Open Innovation Gateway![]() 」、ベンチャーとの共創の場である「MetaArcベンチャーコミュニティ
」、ベンチャーとの共創の場である「MetaArcベンチャーコミュニティ![]() 」などがあります。「このような人の創造性を活性化する活動や、デジタル技術を活用したサービスやソリューションの提供を通じて、お客様のビジネスパートナーとして、人が主役の新たな未来の共創に邁進していきたい」と高重は力強く語り、講演を締めくくりました。
」などがあります。「このような人の創造性を活性化する活動や、デジタル技術を活用したサービスやソリューションの提供を通じて、お客様のビジネスパートナーとして、人が主役の新たな未来の共創に邁進していきたい」と高重は力強く語り、講演を締めくくりました。
パネル・ディスカッション
『100歳社会に向けて、企業が変革すべきこととは何か?』

フォーラム最後のセッションとなるパネル・ディスカッションには、グラットン教授に加えて、一橋大学の野中郁次郎名誉教授、富士通の松本端午・執行役員常務が登壇し、先ほど講演した高重がファシリテーションする形で進められました。
「100歳社会を迎えるにあたって、企業にとってどのような戦略が重要になっていくのか」そして、「人工知能やロボット技術が急速に進歩する中で、企業はどのような戦略をとるべきなのか」という2つのテーマの下で、活発な議論が展開されました。
100歳社会における企業のありかた

野中名誉教授は、「『ライフタイム・コミットメント』ということが日本の企業経営の基盤になっている」と述べて、議論をスタートしました。ライフタイム・コミットメントとは、1958年に『日本の経営』を著したジェームズ・アベグレン氏が、日本的経営の強みの1つとして掲げたものです。これは、野中名誉教授によると、「働く人と職場共同体との間に生涯にわたる強い結びつきがある」状態を意味します。「従業員が会社を自己成長の場と認識して働くことによって、組織として持続的に知が創出・蓄積されるようになり、これが競争優位の源泉になります」と説明します。「日本的経営の本質は、知を蓄積するためのコミュニティであり、ライフタイム・コミットメントに値する企業体を創ることが、まさにこれからの100歳社会において企業のリーダーが果たすべき最も重要な使命ではないか」と主張します。

これに対して、グラットン教授は、「日本企業において、ライフタイム・コミットメントが持続可能な知の創造につながっていることは、とても素晴らしいことです」と評しました。同時に、「欧米では、ひとつの会社で働きあげるという、結婚のようなことは想定しにくい」と述べました。「欧米では、ひとつの会社に継続して勤務するのは、せいぜい4年位でしかありません。そのような環境下では、従業員の発展は誰の責任なのかという議論もあります。一方で、マッキンゼーのようなコンサルティング会社では、在籍時にスキルを高める、と同時に退職後も元社員としてのつながりや、クライアントとのネットワークを構築できるという場を提供しています。違った形での関係作りの場といえ、双方にプラスがあるような関係性で、こういったスタイルが欧米にはあります」と述べました。
野中名誉教授は、「ライフタイム・コミットメントは、ライフタイム・エンプロイメント(終身雇用)ではなく、会社を辞めることも自由」と説明しました。「しかし、会社に入った後は、その会社にコミットします。そして、転職していっても良い会社だったなと思えるような普遍的価値を追求することが重要です」と述べました。このような会社が、ハイクオリティな知を提供し、人間を絶えず育成していくのです。「企業を去った後もいつでもつながりを持てるような、オープンなコミュニティを作り上げ、知を共有していくことが、企業に求められる」と語りました。グラットン教授も「そのとおりですね」とうなづきます。
このテーマの議論の最後に、松本は「リアルな場におけるコミュニケーションが最も重要ですが、デジタル技術を活用すれば、時間と空間を超えて知を伝承することが可能になります。デジタル技術が、知を蓄積し、それを次の世代へ受け継いで、人々の創造性をエンパワーしてくれるのです。ひとつの形で、みんなで共有できるようになることがデジタル化の一番のメリットではないでしょうか」とコメントしました。ここから、議論のテーマが、「人工知能とロボット技術が進化する時代の経営戦略」に移っていきます。
人の知と人工知能の知は、何が違うのか
野中名誉教授は、「人工知能で生み出される知は、普遍的なものを抽出して形式化されたもの」だと説明しました。そして、「人工知能は人間の創造性を高めるものであって、人間とヒューマンセントリックな形でコラボレーションさせて、大いに活用するべき」と唱えます。同時に、「人間にしかできないことがある」と指摘しました。「私たちの過去・現在・未来も含めて一人一人がこういう生き方をしたいというクオリア(感覚・質感)を持つことや、人生の中の一瞬一瞬の経験において、自分の全人格(whole person)をかけて獲得している知というのは、客観的なITで実現することは難しい。人が目的を示し、ITを徹底的に活用することが重要」だと、野中名誉教授は主張します。
例えば、GEは徹底的にIoTを活用する戦略に経営の舵を切ったと同時に、企業のミッションをGE Beliefs(想い)に変更しました。想いや目的意識を持って徹底的にIoTを使い、自分の思いを実現するためにIoTがあるというコラボレーションを実現しています。「代替するのではなく、人の創造性を強化する、そのような補完的な関係が重要」だと指摘します。
人工知能やロボットは脅威なのか
これに対して、グラットン教授は、「この会話は人工知能と人間についてのまさに最先端の議論」と評した上で、「欧米では脅威論が先に来ています」と紹介しました。2年前のダボス世界経済フォーラムのパネル後のメディアとのインタビューで、「ロボットが人間を置き換えるのかという点に関して人間がもたらす本質的な価値は何であるのかについて議論をしたという話をしたところ、ロボットが人間を破壊するというタイトルで記事になってしまいました」と語ります。「ここには、人々が本当に懸念していることが浮き彫りになっています。人間がより優れたところは何なのか、何ができるのかというところが十分に認識されていないのです」と指摘します。
例えば、アメリカで自動運転が非常に問題になっています。普及していくと、今現在、運転手をしている何百万もの人の仕事がなくなってしまうということに繋がります。非常に深いレベルで多くの方々が不安に感じているということは、軽視してはいけません。「自分の仕事がどうなってしまうのか、という懸念に私たちはまだ答え切れていないのです」と述べました。
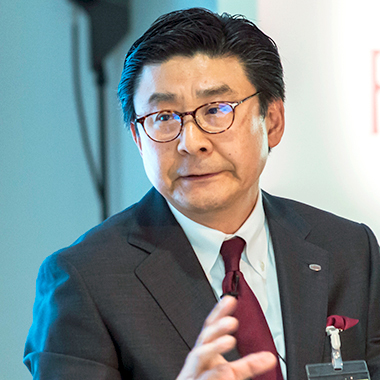
欧米よりも日本においてより前向きな見方が多いことに関して、松本は個人的な意見とことわりながら、「日本人は決して楽観論者ということではなくて、社会に貢献するというベースを共有していて、新しい技術をそのために利用しようという意識があるのではないか」とコメントします。さらに、日本人は「ロボットなどに対して性善説を持っているのかもしれない」と指摘しました。鉄腕アトムや鉄人28号の例を挙げて、「日本人にとってロボットは、昔からフレンドリーなものでした」と語ります。その上で、科学技術の結果というものに対する様々な警鐘が日本でも上がっている中で、最も重要な点は、「人間が何を目的に、技術を活用するのかをしっかり議論するべきです」と述べました。
以前にも、このような脅威を人は経験してきましたが、昔はテクノロジーの進歩のスピードがゆっくりしていたので、人がその仕事を変えるための再教育に十分な時間を取ることができました。しかし、今では、技術がもう日進月歩で変わっていて、自動走行車もそろそろ実用化されようとしています。そうなった時にそのインパクトをどう社会が、企業が受け止められるかというところに、企業経営者や研究者が取り組む必要があります。
人と人工知能が共生・共創する社会に向かって
セッションのクロージングにあたって、野中名誉教授は、次のように指摘しました。「従来の脳科学では、脳がすべての指令を発しているという考えでしたが、最近の研究で身体と心は分離できないということが分かってきました。つまり、身体化された心というものです。脳は直接、外界を検知することはできません。我々は五感の中で直感的に微細な変化に気づくことができます。これらの直感と暗黙知、形式知をシンセシス(綜合)することによって、コンセプトを創り出し、ものすごい創造性を発揮することができます。このような人間の知を、人工知能のようなITがオーグメント(補完・強化)するべきなのです」。

グラットン教授は、「日本は人工知能やロボット技術で世界の最先端にいます。富士通のようなIT企業が、どのようにテクノロジーを活用し、どのような未来になっていくのかというストーリーを現実的に描き出していくことが大切です」と述べました。これを受けて、松本は「人を幸せにするようなテクノロジーの活用方法を提示していくことが、富士通の使命だと考えています。人工知能が人間に近づいている今、我々、人間が機械よりもっともっと人間らしくならなくてはいけないと思いました」と語り、セッションを締めくくりました。
※本ページに記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。
2016年12月5日 公開




