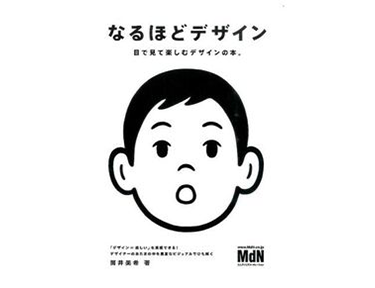仕事に役立つ本を読みたいけれど、何を読めばいいか分からない、ということはありませんか。今回は、富士通デザインセンターの社員3人がおすすめする本をご紹介します。それぞれが、本への思い入れを大変熱く語ってくれました。興味をひかれた本があったら、ぜひ書店で手に取ったりインターネットでレビューを参考にしたりして、読んでみてはいかがでしょうか。この中の1冊が、あなたの仕事にも良い影響を与えるかもしれません。
富士通デザインセンターのデザイナー3人が推薦する
「仕事するうえで影響を受けた本」4冊

富士通デザインセンターのデザイナー3人が推薦する
「仕事するうえで影響を受けた本」4冊
掲載日 2022年7月21日
デザインを学び始めたころの原点を思い出して背筋が伸びる本
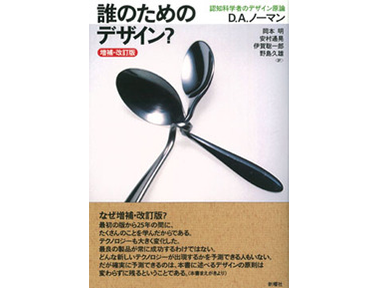

ビジネスデザイン部 デザイナー 富士 聡子(ふじ さとこ)
専門はUX・UIデザイン、情報設計、ユーザビリティ、アクセシビリティ、プロジェクトマネジメントなど。
主な担当業種は公共。
人間中心設計専門家。
私は美術大学で情報デザインを専攻していました。大学入学当時のデザインについての興味は、「美しいものを作ること」といった表層的なものでした。そんなときに課題図書として出会ったのがこの本です。この本を読んでデザインへの理解が一気に深まり視界が広がりました。
現在は、デザイン思考などについても加筆されている増補・改訂版が発行されていますが、私の手元にあるのは1990年に初版が発行された旧版です。「デザインとは」「デザインされたものが世に出るということは」など、デザインについて認知科学の観点から解説されており、この本で「情報デザインとは情報の構造から設計して最終的に使いやすいように、見た目も含めてデザインすること」だと学びました。 人はさまざまな道具を使って生活していますが、なぜ使いにくい、分かりにくいと感じることがあるのか、その背景を事例とともに丁寧に説明しています。例えば、電話、電子レンジなどのプロダクトデザインの問題点の例のほか、「引いて開けるドアを押してしまったり、押して開けるドアを引いてしまったりするのはなぜか」というドアの事例は、学生だった私にも分かりやすく大変印象的でした。また「悪いデザインで自分を責めてしまうユーザーがいた」といった小話も紹介してあり、実用書でありながら読み物としても面白いです。デザインの原則である「可視性があって、良い概念モデルがあって、良い対応付けがあって、フィードバックがあると良い」をこの本で学びました。
そのほかにも心に留まった内容はありますが、具体的な内容というより、表紙を見るだけでデザインを学び始めたころの原点を思い出して背筋が伸びる教科書のような本で、学生のときの、自分のデザインの定義範囲が一気に広がった気持ちがよみがえります。デザインの仕事をするとき、「誰かに言われたから」「お客様がこう言うから」ではなく、ユーザーの立場に立って隅々まで考えてデザインできているか、この本を思い出して自問しています。
製品開発はデザイナーだけではできません。開発者、設計者、お客様、営業など全員が同じ方向を向いて取り組む必要があります。ですからデザインに興味があるデザイナー以外の方にも、よくこの本を紹介しています。まずは「デザインするとはどういうことか」のマインドセットとしてこれを理解していただきたいという思いで、デザインのテクニックやノウハウ、UX・UIの本と合わせてこの本を紹介したりしています。
デザインの分野では、新しいトレンドの本が次々発売されるため古い本は捨てることも多いのですが、この本は捨てられません。人間中心設計専門家としてデザインをするときの教科書、バイブルのような本。何回か引っ越しをしても、捨てずにずっと持っています。
この2冊がデザイン職へ異動するきっかけになり、自信をくれた
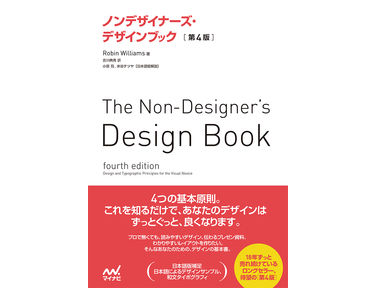
『ノンデザイナーズ・デザインブック 第4版』
著者:Robin Williams
監修・翻訳:米谷 テツヤ,小原 司
翻訳:吉川 典秀
出版社/出版年:マイナビ出版/2016年
書誌ページ(外部サイト) >

経営デザイン部 デザイナー 佐藤 美紀子(さとう みきこ)
社内ツールの開発プロデューサー、Webサイト「富士通のデザイン」ディレクター、富士通ブランドリフレッシュプロジェクトのサポートなどを担当。
私は美術大学でデザイン・アートを学び、就職の際にはデザイナー職を志望していました。ところが新卒で入社した前職の会社ではデザイン部に配属されたものの、希望とは別の職種。「配属ガチャ」に外れたと思いました。同期がどんどんデザイナーとして実践を積む中、デザインの仕事ができず悶々としていた社会人数年目。なんとか現状を打破したくて本を読み漁っていたときに出会ったのがこの2冊です。
1冊目の『ノンデザイナーズ・デザインブック』は初版が1998年と古いのですが、今でもとても参考になります。「ノンデザイナーがデザイナーを目指すための本」で、デザイナー以外の方が読んでも分かりやすい内容になっています。多くの社会人に役立つ、資料作成の際のヒントなどが多数盛り込まれています。具体的には色の使い方、情報の並べ方など、デザイナーが無意識にやっていることが言語化されており、今日から使える実用的な内容です。
2冊目の『なるほどデザイン』はより実践的な本で、例えば朝食について雑誌の紙面をデザインするとき、「丁寧な暮らしをしたい人」向けなのか、「朝食のレシピを知りたい人」向けなのか、目的によって求められるアウトプットが異なることを、複数のデザイン例を比較しながら解説しています。この2冊は似ている点もありますが、『ノンデザイナーズ・デザインブック』はデザインの基本的な内容、『なるほどデザイン』はデザインする目的に合わせたアウトプットについて説明している本だと言えるでしょう。
どちらの本も図解が多く、良い例、悪い例を分かりやすく図で説明しているので、読書というよりパラパラ眺めるだけでも気づきが得られます。疲れているときでも、ページをめくると「このデザインのどこが良くないのかな」などと気になってつい見てしまいます。この2冊を読んで、今まで何となくデザインしていたことが言語化されました。そしてなぜこうしたのか、自分のデザインをきちんと説明できる自信が生まれました。 以前の職場には朝礼の時間があり、この2冊を参考にしてデザインのお役立ち情報を発表し続けました。すると、デザイナー職ではないにもかからず、デザインの仕事をもらえるようになり、最終的には希望職種へ異動することができました。この本のおかげで自分の力を認めてもらった気がします。
私は、電子書籍ではなく紙の本を読むのが好きです。また、本はたいていネットではなく、実店舗でポップなどを参考にして購入します。購入したらすぐに「7日後発送」としてフリマアプリに出品。新刊本などはすぐに買い手がつくので、実質1週間で読み終わらなければ損をしてしまいます。こうやって怠けないように自分を追い込んで読書量を増やしています。実は今回ご紹介したこの2冊も、読み終わって売ってしまったので、今は手元にありません。でもこの2冊は読み返したくなることがあり、それぞれすでに3~4回ずつ購入しています。
不確実の海を泳ぐための勇気をもらえる本
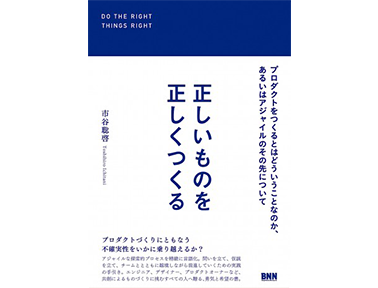
著者:市谷聡啓
出版社/出版年:ビー・エヌ・エヌ新社/2019年
書誌ページ(外部サイト) >
著者:市谷聡啓
出版社/出版年:ビー・エヌ・エヌ新社/2019年
書誌ページ(外部サイト) >

経営デザイン部 プロダクトマネージャー 吉川 嘉修(よしかわ ひろまさ)
UI/UXデザイナーとしての経験を活かし、4月から社内向けアプリケーション開発チームのプロダクトマネージャー(PdM)に。ユーザー中心のプロダクト開発とアジャイルチーム作りに携わる。人間中心設計専門家、認定人間工学専門家。
この4月からプロダクトマネージャー(PdM)をしており、アジャイル開発などに携わっています。これは以前のプロジェクトのスタジオに置いてあって「面白いタイトルだな」と手に取った本です。
私の原点である人間中心設計やUXデザインは、アジャイル開発と同じモノづくりとしての共通点が多々あると思います。しかし、自らが主体となってプロダクトやサービスを開発するにはデザイナーとは違った視点が必要です。アジャイル開発については、短期間のイテレーション(反復)を回しながら段階的に開発していくという認識はありましたが、不確実性の高いプロダクト開発を進めていくための方法論やアプローチを、詳細には理解していませんでした。そんな時にこの本に出会い、デザインからプロダクト開発全体へと、自分の視野が大きく広がりました。
アジャイルではチーム作りが重要ですが、この本では継続的な学びを重視する、柔軟で強いチーム作りのノウハウもまとめられています。実際プロジェクトでは、「これはデザイナーがやる仕事でしょ」あるいは「それはエンジニアがうまく吸収してよ」といった衝突が起こりがちです。この本には「チームが衝突したときに何が起きているのか」が解説してあり、「チーム全員で一人の人間になるような意識が重要」と導いてくれます。エモーショナルな本ではありませんが、私はとても勇気づけられました。アジャイルのような設計図のない開発プロジェクトでは心が折れやすいものですが、不確実の海の泳ぎ方を指南してくれるような本です。
よく自転車に例えるのですが、いくら自転車の乗り方の説明を聞いても、机に向かって勉強しても、乗れるようにはなりません。実際に自転車に乗って、転んでもけがをしないような環境で何度か転びながら練習するしかありません。同じようにアジャイルプロジェクトも、小さな失敗を繰り返して修正しながら進むことが大切だと気付けました。
このように、この本では不確実の中でいかに正しいものを見つけるか、また強いチーム作りや優先順位の決め方などの方法論が大変興味深く説明されています。アジャイルが失敗する理由なども詳細に解説してあり、まるでレクチャーを受けているかのように分かりやすいです。不確実性に正しく向き合い、チームと共に進むための価値観やマインドセットが学べました。新規事業や新規サービス開発を行っている方にとっては、アジャイル開発のプロセスが学べるだけでなく、勇気をもらえる内容だと思います。アジャイルの基礎や用語を説明した本を1冊目とするなら、2冊目としておすすめで、私も今後も折に触れて読み返したいと思っています。