ひとりひとりの感性と企業の技術が、新しいビジネスの価値を創る
デジタル技術を使ったクリエイターの働き方
人は、デジタル技術を活用して今以上に創造性を発揮し、都市をプラットフォームに誰もがイノベーションへのチャレンジャーになっていく。
2018年10月、東京の六本木アカデミーヒルズで開催されたInnovative City Forum 2018。「都市とライフスタイルの未来を描く」をテーマに毎年開かれるこの国際フォーラムは、先端技術から現代アートまで国内外の多彩な人材を集め、3日間にわたり活発な議論を行います。

19日、同フォーラムの「Innovative Business Session」を主催した富士通は、「クリエイターが起こす第4次産業革命 -- DevOpsで自らを変革する都市の未来」と題するパネルディスカッションを行いました。
登壇したのは、「空飛ぶクルマ」を開発する有志団体CARTIVATOR 共同代表の中村 翼氏。ANAホールディングズで「アバター」プロジェクトを展開する、デジタルデザインラボ AVATARプログラムディレクターの深堀 昂氏。ものづくりの先端技術と伝統工芸の発想を融合させながら造形的な服飾デザインを試みる、ファッションデザイナー・デジタルファブリケーターの中村 理彩子氏、そして、日本最大級のメーカースペースで個人や団体のものづくりを支援するテックショップジャパンの代表取締役社長 有坂 庄一氏。進行役は、富士通で未来ビジョン発信をリードするマーケティング戦略本部 VP 高重 吉邦が務めました。
クリエイターが起こす第4次産業革命
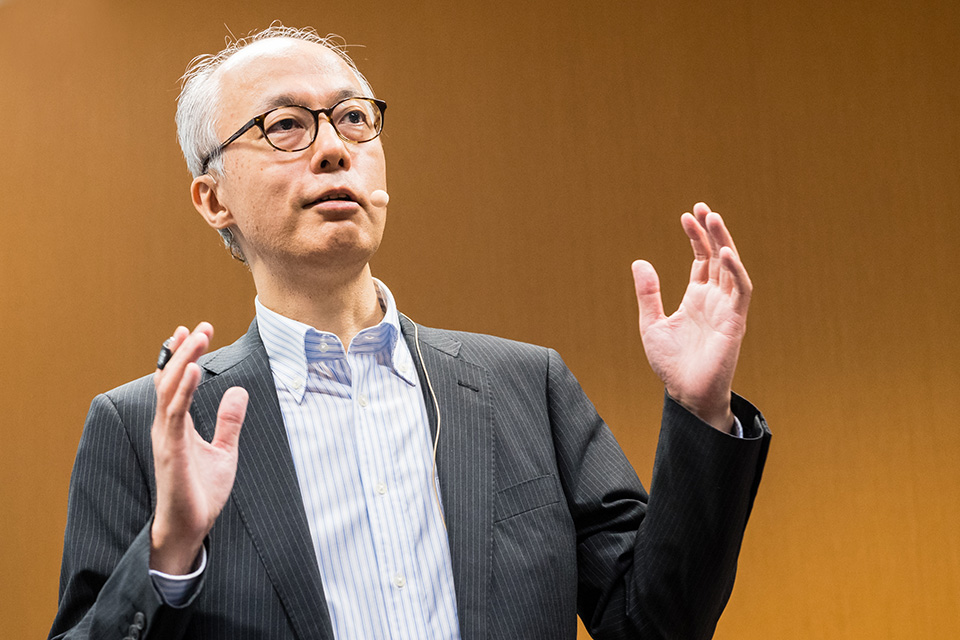 高重 吉邦
高重 吉邦
(富士通株式会社 マーケティング戦略本部 VP)
「地球温暖化や人口問題など、世界はいま多くの課題を抱えています。一方で AIやデジタル技術は加速度的にわたしたちの生活の中やビジネスに浸透し、生産性が飛躍的に向上してきています。この第4次産業革命と言われる大きな変革の中で、デジタル技術の使い方の鍵となってくるものがDevOpsという新しい方法です。民主化されたデジタル・プラットフォーム上で開発(=Development)と運用(=Operations)を一体化し、早いサイクルで開発・運用を廻してビジネスの成果を実現していきます。このDevOpsで最も大事なのは、「人」ではないかと思います。開発するクリエイターとしての人と、それを使い、運用する人を一体化するように、人のスキル・組織・文化を変えていくことです。DevOpsをアナロジーとして使い、同じようなやり方で、都市を再創造できないか、ということを皆さんとともに考えていきたいと思っています」。
そう語り始めた高重は、セッションのテーマ「クリエイターが起こす第四次産業革命」のマニフェストを、次のように宣言しました。「AIが進化し、人とAIがコラボレーションする時代がいよいよ始まります。そうした時代、人に最も必要とされるのは共感とクリエイティビティ、そして課題解決力です。AIなどのデジタル・テクノロジーが民主化していき、人と人がつながってアイデアがカタチにされていく…生産と消費がその場で行われる共創を総クリエイターが担う世界。都市の役割は人=クリエイターをエンパワーするプラットフォームとなり、生産と消費はDevOpsのように一体となってつながり、都市は自らの課題を自ら解決するヒューマンセントリックな生態系(エコシステム)へと進化していきます。この六本木でも生態系づくりは始まっています。未来のシードはすぐそこにあります」。

製品のみの提供から利用者視点の総合的なサービス提供へとシフト
このビジョンの中核にあるのは、ヒューマンセントリックな生態系です。これまでの企業や政府が標準化された商品やサービスを提供してきたプロダクトアウト型のビジネスモデルは終焉し、業種の壁は意味をなさなくなっています。今、多様なプレイヤーがデジタル技術を活用してつながり、本当に人が必要とするヒューマンセントリックな価値を共創する生態系が生まれてきています。
高重は「このエコシステムにおいては、一人ひとりの人が課題を解決するクリエイターになることができます。AIなどのデジタル技術をはじめ、都市が提供するさまざまなサービスを活用することによって創造性を発揮し、専門家や企業・公共機関とつながってアイデアを自在にかたちにし、都市そのものも創りかえていく可能性を手にしています」と強調しました。
都市をプラットフォームとして、誰もがクリエイターとなりえる時代。そのビジョンをもうすでに実践している先駆者たちが本セッションのパネリストたちです。そして、彼らイノベーターたちが共通して活用している都市のプラットフォームが、パネリストの一人である有坂氏が率いるテックショップジャパンです。富士通が2015年に森ビルとコラボレーションして六本木アークヒルズにオープンした日本最大級のものづくりのオープンイノベーション・スペースになります。高重のイントロダクションに続いて、登壇した4人はそれぞれの思いと取り組みを語りました。
五輪の空に舞う「空飛ぶクルマ」
 中村 翼
中村 翼
(一般社団法人 CARTIVATOR)
東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場。そこに颯爽と走り込んできたクルマが空高く舞い上がり、聖火台に火を灯す。そんな夢を語るのは「空飛ぶクルマ」SkyDriveを開発する有志団体CARTIVATORの中村 翼氏です。
大手自動車メーカーで量産車の設計に携わっていた中村氏は、少年時代に思い描いていた自由なクルマ作りがしたいと2012年に有志団体CARTIVATORを立ち上げ、2014年から「空飛ぶクルマ」SkyDriveの開発を指揮しています。現在のメンバーは100名超。平日の仕事終わりや土日などで活動を行い、自動車や航空機のエンジニアからなる技術チームと広告代理店社員や銀行員、起業家、大学生などからなるビジネスチームに分かれ、テックショップなどに集まってプロジェクトを進めています。中村氏は「様々な業種から集まった専門家からなる最強のボランティア集団」と表現します。
ミッションは「モビリティを通じて次世代に『夢』を提供すること」と熱く語り、「いまできないことをできるようにし、次世代により良い世界を届けたい」と中村氏はその意欲を表しました。2050年のビジョンとしては「誰もがいつでもどこでも空を飛べる時代を創る」ということを掲げ、東京オリンピックが開催される2020年をターゲットに、空飛ぶクルマを使ってデモフライトを行うことを直近の目標としていると話します。
彼らの夢に賛同した大学、自動車会社、自治体などから技術アドバイスや開発環境提供などさまざまな支援も受け、共感と創造力をつなぎながら、日本発の「空飛ぶクルマ」の実現に向け共創の場を広げています。
「アバター」で体験の境界を跳び越える
 深堀 昂
深堀 昂
(ANAホールディングス株式会社
デジタルデザインラボ AVATARプログラムディレクター)
地上にいるエンジニアが、遥か彼方の月面で基地を建設する。病室にいる子どもが、出かけられない海岸で友達と遊ぶ。離島に住む病人が、会えない医師の診察を受ける。僻村の子どもたちが、遠く離れた都会の学校で授業を受ける……
そんなビジョンを熱く語るのは、ANA で、「ANA AVATAR VISION」プログラムを推進する深堀 昂氏。できるだけ世界中の人たちをつなげて社会に貢献することを創業時から追い求めてきたという言葉とともに、「どこでもドア」のようなサービスを、技術を使って実現するのがANAのAVATARだと紹介します。そして、ロボティクス、VR、AR、センサー、通信、ハプティックス(触覚)技術が急速に発展する今日、「アバター」をスマートフォンのように当たり前のように使う時代になると語ります。アバターとは、遠隔地に置かれた遠隔操作ロボット(アバター)に接続して自分の意識、技能、存在感を伝送して、コミュニケーションおよび作業を視覚、聴覚、触覚のフィードバックを感じながら行う技術です。また意識の瞬間移動だけでなく、人がいけない場所に行けたり、身体的な制約がありできなかったこともできるようになります。
有人宇宙旅行や民間月面探査の国際賞金レースで知られるXPRIZE財団の次期レーステーマを決定するコンペに参加したことがきっかけでした。XPRIZE財団とは、「イノベーション界のカリスマ」として有名な、ピーター・ディアマンデス氏が設立した財団でアメリカ西海岸を拠点に、多数の財界人や起業家などが支援し、民間によるイノベーションを推進している非営利団体です。2016年に、ANAチームが提案した「ANA AVATAR XPRIZE」がグランプリを受賞し、次の国際賞金レースのテーマとして採用されることが決定しました。
また、国内でも、大分県全土をAVATARのテストフィールドにして、県庁とタイアップをして、既存の技術をユーズケースに基づいてサービス化するなど、産官学連携による実証実験が始まっており、実証実験の場として、テックショップを活用しています。
なぜこのように共創の輪が広がっていくのか、その理由について深堀氏は、「一企業の事業を超えた人類の希望にある」といいます。「いままでずっとわたしたちを縛ってきた身体的制約、移動の時間、コストなどあらゆる壁を跳び超え、心のままに世界を瞬間移動し体験したいという夢。それが共感を呼び、このプロジェクトを動かしているのだと思います」。
結びのメッセージとして、「これからAIの時代になっていき、人間も進化が必要になってくると思います。なぜ、これまで進化できなかったかと言うと、1時間にできることが決まっているからです。アバターは人を置き換える技術ではなく、人を拡張させ進化させる技術です。アバターを活用することで色々な人に出会って、体験、発明をして、ビジネスを創造し、それを共有して社会課題を解決する時代になっていきます」と力強く語りました。
服飾の未来をデザインする
 中村 理彩子
中村 理彩子
(ファッションデザイナー・デジタルファブリケーター)
高性能なスキャナーを使って、布や体の一部をスキャンして、3Dプリンティング、モデリングで加工。また、漆芸を試す。そうしてできあがるのは、「自分だけの服」。そんな究極のファッション・デザインを行っているのは、デジタルファブリケーターの中村 理彩子氏です。
工業用デジタル・テクノロジーと日本の伝統工芸にインスピレーションを得ている彼女は、テックショップジャパンといったものづくりスペースで試作を行い、さらに手工業の職人たちに伝統の技を学んでいます。
そのなかで彼女が感じるのは、テクノロジーの進展によって窮地に追いやられる伝統工芸のジレンマ。一方で、都会のものづくりスペースに集う人たちとの共創に大きな可能性を見出しています。「テックショップのような場で色々な気付きを得て、そこでイノベーションが起きているというのを自分で作っていて実感しています」と活き活きとした表情で話しました。
テクノロジーが作る服飾の未来を想いながら、彼女があらためて強調したのは「手を動かすことの大事さ」でした。「なにをしようかと腕組みして考えているのではなく、とにかくやってみることです。そうやってとにかく早く試行錯誤していく。デザイン思考でいう”ラピッドプロトタイピング“の考え方がとても重要です。そして、必要なのはコミュニティで、インターネットとコンピュータが接続されて得られた功績とは、他人の成果が重ねられるというイノベーションだと考えます。私も最近は木工室にずっといるのですが、まさにテックショップはそういう場所だと感じています。木工室にはバイオリンを毎日作っているおじさんがいて、その方にいろんなことを教わりながら、全く繊維とは関係のないところで新しい問題を認識することができます」と力強く語りました。
共創を生み出すメーカースペース
 有坂 庄一
有坂 庄一
(テックショップジャパン株式会社 代表取締役社長)
六本木アークヒルズ3階にある1,200㎡の会員制メーカースペース。最先端のレーザーカッターや3Dプリンター、木工旋盤をふくめ約50種類の工作機を備え、専門家によるアドバイスや会員同士の交流、投資家とのマッチングなどが活発に行われているのが、このテックショップジャパン。
アイデアをただかたちにするだけではなく、それをビジネスにつなげる仕組みも用意されているこのスペースは、学生から起業家まで、約1,070名のさまざまなクリエイターが集う共創の場だと代表取締役社長の有坂 庄一氏は話します。
「企業が、新しいビジネス、プロダクトやサービスのアイデア創出から試作までオープン・イノベーション型で、一般参加者を募った形で行いたいといったような案件も多くあり、そういったワークショップをNTTさんやヤマハ発動機さん、クックパッドさん、LIXILさんなどと一緒に実施したりしています」。
有坂氏が強調したのは、この場で行われる共創が”DevOps”のアプローチで進められるということ。「新しいものが生まれる時のプロセスはすごく簡単に言うと、アイデアが出て、それを形にして、実証、検証して、事業化というプロセスになります。われわれのテックショップでは、ものづくりの最新設備、それを支えるスタッフ、そこに集う人々がうまく融合して、アイデアをその場でかたちにしていく環境が作られています。そうやってアイデアの検証を行い、新規事業創出や量産につなげていく。まさに今回のテーマのDevOps的な環境を用意しています」と話します。
パネルディスカッション
企業のかたち、働き方は変わるのか?

高重氏はパネルディスカッションを会場の参加者に対する次のような問いかけで始めました。
「このように有志団体や個人をサポートする仕組みが生まれてくると、ものづくりのあり方も変わっていきます。今後10年を見据えて、皆さんはどう考えますか?人の働き方や企業の形は劇的に変わっていくのでしょうか?」
この問いかけに対し、会場はほぼ全員が「変わる」と回答しました。その理由はさまざまです。ある参加者は、産業界で深まる中国の影響力を挙げ、それに対抗するために日本企業は変わらざるを得ないと話しました。
この意見に「空飛ぶクルマ」開発の中村氏も「変わっていかないと先がない」と同意します。「いまはネットを利用して資金集めや仲間集めもやりやすい環境になっている。わたしたちもプロジェクトを通じて変わっていく場を作れたらと思っています」。
深堀氏は、「オープン・イノベーションにはやる気を持ったプロデューサーが必要」と話しました。「すべてに通じた専門家はいません。そこで思いがある人がそれぞれの分野に通じた人を集め積極的にプロデュースしていく必要があります」。
誰もが作り手になる”総クリエイターの世界”がやってくる?

次に、高重は、一人ひとりが変われるかという点に着目し、「AIやデジタル技術の進展によって、誰もが自らのアイデアをかたちにできる時代がやってきています。皆さんは、誰もがクリエイターになる”総クリエイターの世界”がやってくるということを自分のこととして感じていらっしゃいますか?自分自身がクリエイターになることができると思いますか?」と会場に問いかけました。
この質問に対しては、最初の質問ほど圧倒的ではないですが会場の半数以上の人がYESと回答しました。「いま具体的なビジョンはないけれど、身の回りの小さなことからはじめて、それを大きなものに育てていきたい」という若い学生、「仮想通貨で活用されるブロックチェーンの技術を高め、その成果を次世代に手渡したい」という金融サービス会社に勤めるエンジニアの声などが聞かれました。
有坂氏は「すべてのアイデアは良いアイデアで、それは試す価値がある」というテックショップの生みの親であるマーク・ハッチの言葉を引用しながら、いまは誰もがクリエイターになれる時代だと話しました。「モノを目の前に置いて話すと誰もが前向きになります。そこに力が生まれる。テックショップにやってきたある高齢の女性ユーザーは当初まったくの素人でしたが、ものづくりを体験し、専門家や周囲の人たちと交流するうちにすっかり”アーティスト“になってしまいました。人はこんなにも変われるものなのかとびっくりしたくらいです」。
こうした議論のなかで、中村 理彩子氏は”クリエイター”を「いままでにないものを創る人」と定義しました。そして「新しいものを創ろうとするときに大事なのは、ゼロからすべて新しく作ろうとすることではなく、既存のモノや文化に触れ、それをいったん咀嚼したうえで自分流にカスタマイズする作業が必要だ」と話しました。
“顧客”から”共創のパートナー”へ

議論の終盤、会場からさらに二つ興味深い質問が出されました。ひとつは。「”プロダクトアウト”から”ヒューマンセントリック”へ」という高重の冒頭の説明に関連した質問です。
その参加者はこう問いかけました。「これからは個人が自分でものを作る総クリエイターの世界がやってくるというお話でしたが、そうなったとき、モノを買うとか、顧客である、ということはどうなってしまうのでしょうか?」
これについて高重は、共創における”顧客”の重要性を語りました。「これからの時代に大事なことのひとつは、企業と顧客が一緒になって新しい価値を創っていくことです。これをわたしたちは”Co-creation”と呼んでいます。このとき顧客は単なる”お客様”ではなく、“共創のパートナー”となります。企業は顧客のために商品やサービスを開発するわけですが、同時に顧客の側もその開発の当事者となり、自分たちの体験にもとづいた独自の視点やアイデアを提供します。企業と顧客が互いを認め、高め合う関係になっていく。それがこれからのビジネスのあるべき姿ではないでしょうか」。
深堀氏もこの考えに賛同を示しました。「実際に、わたしたちがいま作ろうとしているアバターも、どういうふうに使うのが一番良いのか分からないものなので、ユーザーの方々とともに実証実験を行っています。ロボットを作って売りつけようというのではなく、お客様と一緒に価値を創造し、お客様の使いやすいものを作りたいと考えています」。
夢をいかにマネタイズしていくか

もうひとつ会場から飛び出した質問は、イノベーションをどのようにビジネス化していくかについてです。「聴いていて非常に面白かったのですが」そう話す参加者は、続けてこう問いかけました。「しかし、ひとつ気になることがあります。いま取り組まれているそれぞれの夢をどのようにマネタイズしていくお考えでしょうか?」
これについて「空飛ぶクルマ」の中村氏は、当面は「次の世代に夢を届ける」ということをミッションに、クルマの開発に全精力を傾けたいと答えました。「マネタイズの部分は、クルマが実現したあとで、その技術やサービスをビジネスにつなげていければと考えています」。
深堀氏は、アバタープログラムの柱のひとつを企業ブランディングと位置づけ、国際賞金レースなどへの出資は広告宣伝費としてとらえる考えを示しました。マネタイズに関しては、最終的に作りあげた代理ロボットやビジョンシステムなどを事業として立ち上げる方針だと語りました。
2030年への”ワイルドな未来予想”
セッションの終わりに、高重は登壇者それぞれの”2030年に向けたワイルドな未来予想図”を聞きました。有坂氏は、3Dプリンターで実製品を作ることが当たり前となり、アイデアをかたちにすることが限りなく簡単になる未来。中村 理彩子氏はさらにそれを一歩進めて、時間とともに形状が変化する4Dプリンターの登場を期待します。中村 翼氏は「空飛ぶクルマ」で人々が自在に移動する世界を語り、深堀氏はアバターが暮らしのあらゆる場面に浸透した代理体験の時代を素描しました。
夢を現実にすることは簡単ではありません。そのための悪戦苦闘を日々続けているパネリストたち。かれらは賛同する仲間を集め、コミュニティを作り、これまでの企業と個人の枠を破った全く異なるやり方でイノベーションの共創にチャレンジしています。誰もがクリエイターとなって未来の都市を自ら創りあげていく彼ら先駆者の根底にあるのは、次の世代により良い世界を手渡そうとする情熱です。セッションの最後に、彼らの情熱に対して会場から大きな拍手が送られました。




