ハードウェアソリューションのトータルプロバイダーとしてITインフラサービスを提供

当社はお客様の最適なITインフラ環境の実現のために、ハードウェアソリューションのトータルプロバイダーとして「ITインフラサービス」を提供しています。
これまで培ってきたお客様、社会の安心・安全を支える姿勢を大切にしながら、さらにその先の豊かな未来をお客様と共に創ります。

プロダクト技術支援
- システムインフラ構想支援サービス
- システムインフラ検証サービス

マネージドインフラストラクチャサービス
- ハードウェア導入・撤去、各種工事
- デバイス導入・運用
- Windows11導入・運用
- PC予備機対応サービス
- デスクトップ仮想化サービス
- マイクロソフト製品導入・運用
- スマートデバイス-LCMサービス

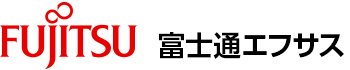
-202x49px_tcm102-7514827_tcm102-2750236-32.png)
