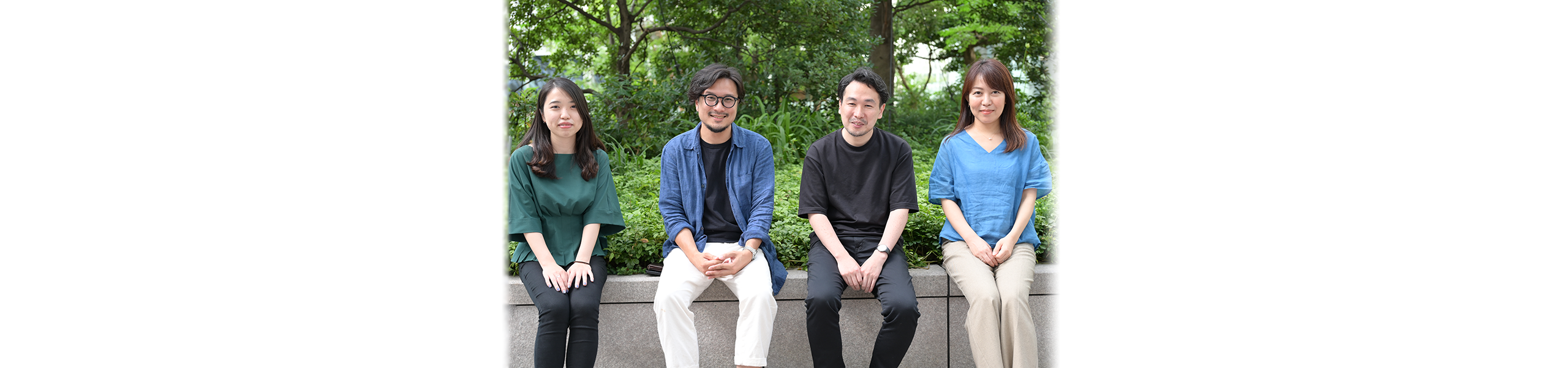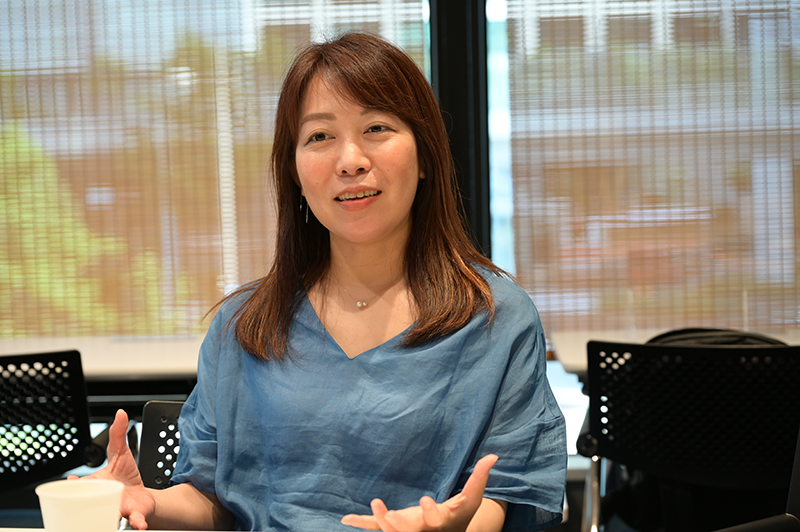——— ミナヨクでは具体的にどのような活動をしているのですか。
湯浅: ミナヨクは、「半年程度の限られた期間で企画を生み実証実験をする場」です。7回ほどのワークショップを開催し、麻布を良くする企画を考え、チームを作り、企画推進方法を検討し、実際にまちで試すところまでを伴走します。富士通や港区が主導するのではなく、多様なバックグランドを持つ参加者が、それぞれの視点で力を合わせる共創型のプロジェクトで、富士通デザインセンターがその運営を行っています。
デザインというと目に見えるもの、形のあるものが対象だと思われがちですが、近年デザインの領域は、モノからコトへ、コトからサービスや社会へと広がりを見せています。このプロジェクトには、社会のデザインに関心のあるデザイナーが集まりました。プロジェクト運営にはデザイン思考を取り入れており、UXデザインの一種だと捉えることもできます。
おきな: どこの自治体でも、住民自らの手でまちづくりや地域を盛り上げるプロジェクトをやってほしいと考えていますが、かといって行政側が依頼してやってもらうことも難しいというジレンマを抱えています。ミナヨクのようにデザインという手法を取り入れて、住民の自主的な活動をサポートするという取り組みはとても重要だと思います。
——— ミナヨクに参加されているのはどんな方ですか。
境: 港区の麻布地区にお住まいの方が多いですが、「住民であること」という参加規程はありません。昨年度は現役で仕事をされている方が多く参加されていました。ですから期間中、ワークショップで終わらなかった課題を夜や休日に、オンラインで話し合ったりしました。
岩田: おきなさんは、参加者に1対1でサポートするなど、参加者の懐に入るのがとてもうまく、仲良くなるのが早いんです。経験に基づくアドバイスに重みがあって参加者からの信頼も厚く、我々も頼りにしていました。
——— このメンバーで臨まれた昨年度の活動について教えてください。
湯浅: 昨年は、過去のミナヨクの修了生が再度活動をするという初の企画で進められ、参加者は2つのチームに分かれて活動しました。1つ目のチームでは、まちあるきや修了生の同窓会「みなゆかば」を企画したり、LINEのオープンチャットで交流したりしています。月1回程度のまちあるきは現在も活動を継続しています。ミナヨクの会期終了後も活動が続いているのは大きな成果で、サポーターのおきなさんがチームをうまくまとめてくれた功績も大きいと思います。
岩田: 大学生を中心とした2つ目のチームは、アートやデザインを通じてこどもたちがストレスを発散し楽しめるイベント「みないろ」を企画しました。学生さん、お子さん、親御さん、みなさんとても楽しそうに参加されていて、私もこどもに戻って参加したいなと思ったくらいです。