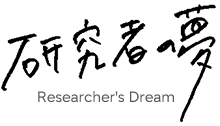数学を学んで実践する
中学生の頃、父親から『虚数の情緒』という数学の本を紹介されたことが、数学に興味を持つきっかけでした。本は厚みがあり、約1000ページもありました。その内容は、数学の歴史や物理への応用、様々な数学問題に挑戦する姿が描かれていました。この本を読み進めるうちに、未解決の数学問題に挑戦してみたいという気持ちと同時に、新しい概念を学ぶことの楽しさを感じました。数学の魅力は、一見簡単そうに見えても、実際に解いてみると難しいということがあります。自然科学は観察から理解を得るのに対し、数学は論理的な推論や抽象的な概念に基づいて理解を得ます。数学を通じて、ものごとの成り立ちや原理などを突き詰めて考える習慣が養われ、基礎的な部分をしっかりと理解する大切さを覚えました。大学で数学を専攻したのも、数学理論を深く学んでみたいと思ったからです。大学院に進み、将来は純粋数学の研究を続けるか、数学を活かし世に還元できる技術を生み出す道に進むか悩んでいた時期に、富士通、そしてブロックチェーン(*1)と出会いました。

異なるブロックチェーン同士を繋ぐ
ブロックチェーン技術は、暗号学や数学の知識が重要な役割を果たします。数学を活かせるという点と、未知の分野に挑戦したい気持ちから、この分野の研究開発に注力する富士通に魅力を感じ、入社を決めました。私は入社まもなく、異なるブロックチェーン同士を繋ぐ技術の研究開発に取り組みました。異なるブロックチェーン同士の取引は、チェーンを横断する場合、取引の透明性を保証できない難しい課題があります。例えば、片方の取引処理が失敗した場合、取引の整合性が損なわれる可能性があります。ブロックチェーンの黎明期において、私は先輩と二人で、上記のような課題を解決できるトークン台帳を連携させる技術の発案から実装まで担当し、プロトタイプを作成しました。
その技術は、システムを跨ぐ取引記録を、証拠性を担保した台帳で管理し、取引の透明性を確保するもので、そのプロトタイプは、のちのConnectionChain(*2)技術となりました。この技術はのちに、Hyperledger Cactus(*3)という形となり、オープンソースソフトウェア基盤ソフトの開発へも貢献しました。自分の開発した技術が多くの方々に使用され、非常に嬉しく思っています。当時、私は、スケジュールが厳しい状況でも、基礎的な学習にしっかりと時間をかけました。ブロックチェーン技術は、暗号やデータベース、ネットワークなど幅広い領域の知識が必要です。曖昧な点を残さず、徹底的に勉強することが、結果的に開発のアイデアや疑問の解消などを促進し、良い成果を生み出すことができた要因だと感じます。
ランニング、ピアノ、お酒。そして物事を最大限に楽しむ
仕事が終わった後は、ほぼ毎日1時間のランニングをしています。中学や高校では陸上部に所属し、長距離走をしていました。その後も健康管理のために走り続けています。走りながら考え事をすると、机上で解けなかった問題の解や新しいアイデアが浮かぶこともあり、私にとって頭を整理するために有益な時間です。また、ランニングを通じて同じ趣味を持つ仲間とつながりを築いています。お互いの近況を共有したり、業務以外の交流をしています。そのような場を通じて、素晴らしいコミュニティが形成されており、今後も皆と絆を深めていきたいと思います。
ランニング以外では、2年ほど前からピアノを始めました。大人になってから何かをゼロから始めるのは難しいですが、クラシック、ゲーム音楽などを弾いてみたいと思ったことがきっかけでした。学生時代に習ったフルートを継続しても良かったのですが、ピアノの高い表現力に魅力を感じました。また、お酒も好きで、仕事の後で妻と晩酌することが多いです。今年の5月には、夫婦でベルギーへ行き、本場のビールを満喫しました。その土地の食や文化を体感することができ素晴らしい経験でした。今後も、様々なものに触れ見聞を広める旅をしたいと思います。

誰もが安心して使用できるAI技術を目指す
最近、ChatGPTやDiffusion modelなど、文章や画像を生成するAI技術が急速に進化しています。AIは私たちをサポートしますが、AIの導入や活用と同時に新たなセキュリティ上の問題も生じます。現在の部署では、私は、利用者が安心してAIを利用できるように、AIのトラスト向上のための技術開発の向上に取り組んでいます。例えば、AIの利用によってAI自身から必要以上の情報が漏れないようにする、またAIの誤判断を誘発するなどの攻撃をされないようにするには、AIだけではなく、セキュリティの知識が重要な役割を果たしています。
現在のチームは、メンバー同士が率直に意見を交わせる雰囲気があり、本音を言い合える心理的安全性が高い職場だと感じています。また、イスラエルやイギリスの海外メンバーが多く、多様性があります。様々な垣根を超えて、グローバルな視野を持ったメンバーと共に、最先端の研究開発をスピード感ある環境の中で進めています。利用者は意識していないかもしれませんが、セキュリティ技術は急速に進むAIの発展と共に欠かせない重要な役割を担っています。このような研究に携わり、安心して利用できる技術を支える一員であることを誇りに思います。
関係者からのメッセージ
物事を多面的に分析する力と独自の視点を持つ一押しのセキュリティ研究者。常に誠意と熱意をもって研究に取り組む清水さんは社内でも人望が厚い人です。(データ&セキュリティ研究所 海野 由紀)
清水さんの活躍は、同期として同じ部署に配属されて以来、常に近い位置から見てきました。膨大なサーベイに裏付けされた最先端の研究テーマ提案、スピーディな実装、丁寧な論理立てによるわかりやすいプレゼン、グローバルで的確なディスカッションなど、何を行っても優秀で、私にとっては同期の希望です。(データ&セキュリティ研究所 町田 卓謙)
-
(*1)
-
(*2)
-
(*3)
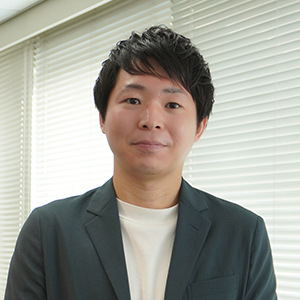
本稿中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものです