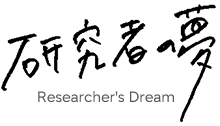生物学とコンピュータ技術を掛け合わせて新しい発見を
子供のころから好奇心が強く、新しいものに興味を持つ性格の持ち主でした。大学でバイオサイエンスを専攻したのは、生物の仕組みを科学の観点から理解し、応用可能な研究を行いたいという思いからです。その頃、世の中では遺伝子の網羅的な研究が進み、遺伝子の変異が特定の病気を引き起こす可能性が明らかになりました。遺伝子解析がブームとなり、遺伝子やそこからできるタンパク質に関する研究に興味を持ちました。大学では細胞とコンピュータを使って遺伝子とタンパク質を解析しました。細胞を観察する際にもコンピュータを使って解析することがありましたが、手作業が多く大変でした。コンピュータをさらに発展させれば、今画面に映っている細胞をひとつひとつ数える必要もなくなり、研究をより加速させることができると考えていました。このような経験から、将来は遺伝子やタンパク質に関する専門性を活かし、最先端のコンピュータ技術を活用して、人の役に立つ仕事がしたいと思うようになりました。

寝食を忘れるほど創薬研究に没頭
入社後、創薬に関連する多くの研究プロジェクトに参加し、経験を積み重ねてきました。その中でも、特に印象深いプロジェクトは、製薬会社、大学、富士通が共同研究を行った抗がん剤設計の研究(*1)です。チーム全員でどのような化合物を合成するかを検討していた時が最も楽しく、また、苦しみを伴う経験でした。コンピュータで設計した薬は、製薬会社の人から「薬の顔をしていない」と言われました。この言葉は、薬が人体で分解しやすく効果が薄い、合成が難しいことなどを意味します。当時は、このような専門的な表現を理解しつつ、課題を克服するために問題点をひとつひとつ明らかにする必要もあり、毎日が勉強の連続でした。
この共同研究の目的は、がんに効果が期待できる化合物の創出です。シミュレーションで設計した化合物は、製薬会社が実際に効果を確認することが必要なため、実験で化合物を合成します。合成が容易な場合には、確認結果が早く出ることがありますが、それでも3週間くらいはかかります。コンピュータ上でのシミュレーションではがんへの高い効果を予測した化合物が、実際に合成して確認してみると予測と違っていたと分かった時には、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。仮説の検証を根気よく繰り返し行い、がんへの高い効果を示す化合物ができた時は本当に嬉しかったです。そして、このような成果を続けて生み出していくことが重要だと感じました。この共同研究の成功は、誰かひとりの知識だけでなく、高い専門性を持つ3つの組織のメンバーが知恵を出し合った成果だと思います。互いの得意分野を認め合い、疑問を解消しながら進んでいく過程で、寝食を忘れるほど研究に没頭する充実感とやりがいを感じました。
子どもの自己成長から得られたヒント
下の子どもが小学校を卒業するまでの13年間、育児短時間勤務を取得しました。時短勤務にも関わらず、共同研究のリーダーに抜擢してくれた上司にとても感謝をしています。私の生物学に関する専門性や研究成果を評価していただき、都度相談に乗ってくれる信頼できる方です。仕事以外の時間は全て子育てに充ててきたので、趣味は子育てと周囲に話してきましたが、逆に子どもから学ぶことがたくさんありました。彼らは立ち、歩き、さらに走れるようになるまで、何度も転びながら成長します。失敗を恐れずにどんどん新しい遊びにチャレンジします。その成長過程を見て、自分も何かをゼロから身につけたい気持ちが湧いてきて、3年前にフィギュアスケートを始めました。今では、ジャンプやスピンもできるようになり、仲間と一緒に練習に励んでいます。

仕事しながら博士課程に挑戦、そして一人ひとりに合う薬の開発を
今年の4月から、会社の社会人博士課程支援制度を利用して、大学院の博士課程で薬品物理化学を学んでいます。博士号を取る夢は、若い頃から抱いていましたが、他の優先事項により実現できませんでした。人生に後悔を残さないために、一歩を踏み出し大学院に入学しました。大学院で学ぶことで、より学術的な観点で研究を深く掘り下げ、長期的な視野で課題を考えることができるようになりました。仕事をしながら博士号を取得することは非常に大変ですが、限られた時間のなかで研究に取り組むことで、研究する意欲が高まります。
私の夢は、一人ひとりに合う薬をコンピュータで設計する技術を開発(*2)することです。薬とタンパク質の関係は複雑で、特にタンパク質の動きの違いによって薬の効き方が変わります。その違いを捉えることで病気のメカニズムを明らかにして、副作用が少なく、切れ味のいい薬(少ない量で速く効く薬)を開発することを目指します。
関係者からのメッセージ
和田さんは、創薬AIの研究を進めるうえで必須の創薬分野と生物分野の両方のスキルを持つ希少な研究員です。和田さんがチームに加わることで、両分野の橋渡しが可能になり、画期的な創薬AIの実現に繋がりました。(人工知能研究所 河東 孝)
入社時はSE部門で、お客様の研究所に常駐して研究リーダーと活発な議論を交わし、今では当たり前になったリモートワークも制度試行段階から積極的に活用していました。これからも持ち前のチャレンジ精神と好奇心で、夢を掴んでください。(富士通Japan株式会社 ヘルスケア事業本部 山下 辰博)

本稿中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものです