近年、特定の企業や管理者による中央集権型のデータ管理とは異なり、自身のデータを自ら管理する自律分散型データ連携の仕組みとそれを支える次世代インターネット「Web3」が注目を浴びています。Web3の特徴を活かした新たなビジネスモデルの創出やさまざまな社会課題の解決が期待される一方で、セキュリティ、プライバシー、著作権保護などの新たな課題も浮き彫りになっています。富士通は、これらの課題を解決しWeb3の要素技術を用いて、デジタル空間上で安心してつながることができる環境や場である「Fujitsu Web3 Acceleration Platform(*1)」を提供しています。今回はWeb3技術の研究開発を担う若手研究員4名に話を聞きました。前編では、富士通がWeb3に取り組む理由とWeb3 Acceleration Platformを支えるConnectionChain(*2)とTrustable Internet(*3)技術を紹介します。後編では、ConnectionChainとTrustable Internetの開発における挑戦と、Web3 Acceleration Platformを通した未来のパートナーと新たな価値創出について内容を聞きました。
2024年2月21日 掲載
RESEARCHERS
-

中山 貴祥
Nakayama Takayoshi
富士通株式会社
富士通研究所
データ&セキュリティ研究所
トラストWeb CPJ
プリンシパルリサーチャー -

米倉 裕貴
Yonekura Yuki
富士通株式会社
富士通研究所
データ&セキュリティ研究所
トラストWeb CPJ
シニアリサーチャー -

長谷川 悠貴
Hasegawa Yuki
富士通株式会社
富士通研究所
データ&セキュリティ研究所
トラストWeb CPJ
リサーチャー -

佐久間 義友
Sakuma Yoshitomo
富士通株式会社
富士通研究所
データ&セキュリティ研究所
トラストWeb CPJ
リサーチャー
富士通がWeb3に取り組む理由
富士通ではWeb3でどのような世界を実現しようとしていますか。
中山:Web3の進展は、DAO(分散型自律組織)(*4)のような新しい組織の在り方や働き方さえも変えていく可能性を秘めています。さらに、近年の社会課題は複雑化し1つの組織や団体では解決できないものが多く存在しています。例えばカーボンニュートラルの実現には、カーボンフットプリントやカーボンクレジットに関するデータを国や業界を跨ぐ地球規模で共有・検証するシステムが必要です。こうしたユースケースでは多くのステークホルダーが協力し合える自律分散型の仕組みが有効です。Web3の技術はこのような自律分散型の仕組みを支え、社会課題の解決に寄与します。我々は、各種サービスおよび技術をWeb3 Acceleration Platformで提供し、自律分散型で個人や企業が互いにデジタル空間上で安心して繋がり、価値を生み出すWeb3の世界を目指しています。
Web3 Acceleration Platformはどのような価値を創出しますか。
中山:Web3の世界を実現するには、デジタル空間上でのデータ共有の安全性と、データ自身の真正性といった、トラストの確保が課題です。組織や個人間でのデータのやり取りにおける課題の具体的な例としてはデータ共有のトラストとデータ自身のトラストがあります。我々は、これまでWeb3を実現するのに必要なデータ流通のトラストを確保するさまざまな技術を開発してきました。Web3 Acceleration Platform を通して、コア技術を利用できるAPIや、さまざまなアプリケーションの開発を試行できるテストベッドを提供しています。また、APIを活用したユースケースなど活用ノウハウもオープンにしていきます。このように技術を広く公開して使っていただくことにより、技術を発展させていきつつ、パートナーの皆様とともにWeb3技術の社会実装を加速し、新たな事業の創出につなげていきたいと思っています。
 中山は、自律分散型で個人や企業が互いにデジタル空間上で安心して繋がり価値を生み出すWeb3の世界を目指していると語る
中山は、自律分散型で個人や企業が互いにデジタル空間上で安心して繋がり価値を生み出すWeb3の世界を目指していると語るデータ共有のトラストを実現し、ブロックチェーン同士を安全につなげる技術ConnectionChain
ConnectionChainは、Web3 Acceleration Platformを支える技術の一つです。この技術は複数のブロックチェーンを接続し、さまざまなデジタル資産交換の取引処理を紐づけ、全体を一つの取引として安全に自動実行・証跡化することを可能にします。また本技術によって、ConnectionChainを活用したサービスを運用する仲介者は共有データに関する連携制御をかけることができ、Web3社会におけるデータ共有のトラスト実現を目指しています。
ConnectionChainの強みを教えてください。
長谷川:ConnectionChainは複数の管理者が存在するコンソーシアム型のブロックチェーンが連携処理を仲介しているため、連携処理にガバナンス制御をかけつつ、安全な自動実行・証跡化を実現することができます。具体的には、共有データの内容・認可等の制御や、処理失敗時のロールバック処理、処理の進捗を台帳に記録する仕組み等を備えています。また、誰でもこの技術を利用可能とするために、Hyperledger Cactiプロジェクト(*5)のコアメンバーとしても活動しており、多種のブロックチェーン基盤とシームレスに接続可能なコネクタをオープンソース化しています。当社はForbesが選ぶForbes Blockchain 50(*6)に2022年に続いて、2023年も選出され、本領域における存在感を示しています。
上記技術はどのように活用されていますか。
米倉:最近、金澤月見光路2023という観光イベント(*7)で、金沢工業大学出展のARアプリと連携し、一般市民を対象にNFT(*8)を発行する実証実験を行い、約100名もの方に参加いただきました。この実験でConnectionChainはイーサリアム(*9)と連携しNFT発行する機能として活用されました。金沢市の職員、地元の新聞社や放送局の担当者の訪問を受け、当社の技術に興味を示してくださったそうです。NFT発行のサービスや事例はよくありますが、ARアプリと連携し、その場で生成した画像を手動でNFT化できる体験は珍しいというコメントをいただきました。イベント参加者から面白いという声をいただき好評だったことで、技術を意識せずに新しい体験を提供することが重要であると改めて考えています。
中山:米倉が説明したように、新しい体験を生み出すことに加えて、開発経験がない学生でも簡単にアプリケーションを構築できるようにWeb3 Acceleration Platformで技術を提供することが価値の一つとなると考えています。
ビジネス領域の発掘はどのように進めていますか。
米倉:金沢工業大学との連携事例のほか、株式会社JTBと訪日外国人富裕層向け観光DXサービスの共同研究を行っています(*10)。本共同研究には、我々研究所からの技術提案が取り入れられています。数年前から、仮想通貨やブロックチェーン技術を基盤とした新しい経済圏のトークンエコノミーを用いた事例の調査やさまざまなユースケースの収集を繰り返しており、現在は蓄積された知見をもとに、新しい体験の創造を検討しています。

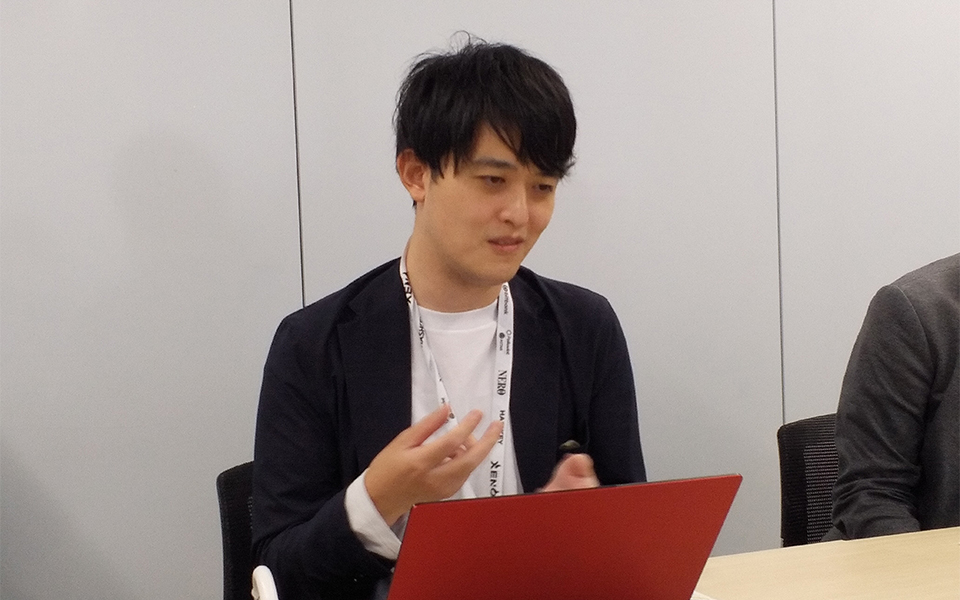
データ自身のトラストを実現し、デジタル世界に信頼をもたらす偽情報対策技術Trustable Internet
Trustable Internetは、真偽が不確かな内容を含むSNS投稿などのWeb上のコンテンツに対して、その真偽の根拠となる情報を簡単に確認できるようにする技術です。コンテンツの閲覧者が偽情報に惑わされることを防止し、Webで流通するコンテンツの質の向上を目指します。
Trustable Internet技術の強みを教えてください。
佐久間:この技術の特長は、Web上のコンテンツに対して、そのコンテンツの発信者以外の主体から提供された根拠を、特定のサービスに依存しない形で閲覧者に提示できることです。これにより、情報発信者が嘘を含む情報を発信していても、第三者がその訂正ができます。また、フェイクニュースの対策技術において、記事の画像がAIによって生成されたことを検出する手法がありますが、我々が提案する技術は画像と文章に対するAIの判定結果を統合的に判断できるマルチモーダルな判定ができることが強みです。また、国際標準化会議でもTrustable Internetについて発表やデモ展示を行い、国内外の技術者や研究者からの認知を得始めています。
上記技術はどのように活用されていますか。
佐久間:Trustable Internetの主なユースケースはWeb上の偽情報対策になります。今後はファクトチェック機関や偽情報対策に関心が深い行政機関・企業等との実証実験により、偽情報問題に対するTrustable Internetの有用性を示していきます。出版や放送業界の企業の中には、ニュースが偽情報か事実か判定するファクトチェックを行っているところがあります。これらの国内外の企業に対して我々の技術の活用提案ができると考えています。
 Web上の偽情報の対策となるTrustable Internetの特長を説明する佐久間
Web上の偽情報の対策となるTrustable Internetの特長を説明する佐久間Fujitsu Research Portalで、先進技術のAPIやWebアプリケーションを無償試用可能
Web3 Acceleration Platform は、Webからのユーザー登録のみで富士通研究所のさまざまな技術を簡単に試行可能な Fujitsu Research Portal を通してお試しいただけます。ConnectionChain、Trustable Internet技術などに興味のある方は、ぜひFujitsu Research Portalをご利用ください。一緒に新しい体験や価値、エコシステムをつくりましょう。
-
(*1)
-
(*2)
-
(*3)
-
(*4)DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、特定の所有者や管理者が存在せずとも、事業やプロジェクトを推進できる組織を指す言葉です。
-
(*5)
-
(*6)
-
(*7)
-
(*8)NFT(Non-Fungible Token)は代替不可能なトークンであり、ブロックチェーン上に記録されたデジタルデータとして唯一無二の固有の価値を示すことができます。
-
(*9)イーサリアム(ETH)は、イーサリアムプロトコルと呼ばれる一連のルールに従う世界中のコンピューターのネットワークです。イーサリアムネットワークは、コミュニティ、アプリケーション、組織、誰でも構築して使用できるデジタル資産の基盤として機能します。
-
(*10)
当社のSDGsへの貢献について
2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。


 SDGs_en.jpg
SDGs_en.jpg kv.jpg
kv.jpg kv_sp.jpg
kv_sp.jpg

