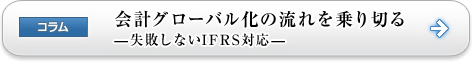IFRS対応先行企業:日本電波工業様

2010年8月公開
2010年3月期より、日本企業が作成する財務諸表にIFRS(国際財務報告基準)を任意適用することが認められ、日本電波工業株式会社様が国内第一号のIFRS任意適用をおこなっています。
日本電波工業株式会社様の開示書類の分析と同社へのインタビューに基づいて、IFRS適用国内第一号の事例紹介を行いたいと思います。
なぜIFRS適用国内第一号となったのか
日本電波工業株式会社様は、水晶振動子、水晶機器等の水晶関連製品の製造、販売をおこなっており、国内子会社3社、海外子会社13社を有しています。売上高の約70%は海外への売上であり、加えて1984年にロンドンで第三者割当増資による資金調達を実施しているため、海外投資家向けのアニュアルレポートを開示しているなど、以前から海外との関係が深い企業でした。
加えて、報告セグメントが単一であり事業構造がそれほど複雑でないことなども考慮すると、日本電波工業株式会社様の社内外の環境はIFRS採用に適したものであったと思われます。
実際、2010年3月期のIFRS任意適用に先駆けて、海外投資家向けには2002年3月期からIFRS財務諸表を継続的に作成、開示しています。
現実に10年近くIFRS財務諸表を作成し、監査も受けているという状況をとっても、IFRS任意適用を前にして会計処理面での大きな問題は存在していなかったと言えるでしょう。むしろ、従来は国内向けに日本基準、海外投資家向けにIFRSを採用していたものが、IFRS任意適用によってIFRSに一本化できることで効率的になる面もあるというのは、日本電波工業株式会社様ならではの現象と思われます。
1990年代後半の日本の会計が国際的に信用を失いかけていた時期に、IFRS適用をいち早く検討した先見の明は素晴らしく、そういう意味では、日本電波工業株式会社様がIFRS適用第一号となったのは当然の結果かもしれません。
日本電波工業株式会社様のIFRS適用の準備の進め方は、これからIFRS適用を行う企業の大多数とはかなり違ったものであるかもしれません。しかし、当初の準備期間も含めると10年以上に渡るIFRSとの取り組みの実践は、他の多くの企業にとっても参考になることも少なくないと思います。
IFRS適用への取り組み
日本電波工業株式会社様では2002年3月期のIFRS初度適用にあたっては、1998年から準備をスタートし約3年が準備期間にあてられました。その間、社内で勉強会を開催し、業務の中で課題を抽出、対応方法を検討し、監査法人と協議するということを重ねることでIFRS対応が進められました。
ただ初度適用でIFRS対応は全て終了ということではなく、2002年3月期以降もIFRS対応は継続されています。例えば、IFRS連結財務諸表における減価償却方法は2010年3月期に定率法から定額法へ変更を行い、耐用年数の見直しも2009年3月期に行われています。収益認識についても、水晶振動子、水晶発振器などの製品の特性上、一つ一つの販売取引ごとに検収書を入手するということが現実的でない状況下で、製品ごと、取引種別ごとに採用すべき計上基準についてIFRSの適用後も継続して対応が進められてきました。
また、IFRS対応で大きな課題といわれていることの一つに子会社対応がありますが、日本電波工業株式会社様の場合はIFRS決算実務を通じて勘定科目の統一、会計方針の統一、マニュアル作成なども進められていました。現在では、子会社も含めたグループ内のIFRSへの理解度は高く、海外子会社13社の個別財務諸表はIFRSに従って作成されています。
昨今のIFRSを取り巻く議論を見ていると、ややもすればIFRS対応についての特徴的な論点に目が行きがちで、またIFRS初度適用までに全ての課題に完全に対応しなければならないような錯覚を覚えてしまうのではないでしょうか。しかし、日本電波工業株式会社様の事例によれば、基準の主旨に沿って、自社にとっての質的金額的な重要性の観点から優先して対応すべき課題を把握し、IFRSの適用を開始した後も対応を継続しておこなっていくということが大切なことのようです。
求められた連結決算作業の早期化
日本電波工業株式会社様は、以前より海外投資家向けにIFRS財務諸表を作成していましたが、日本基準に変えてIFRSを採用する、すなわち決算短信、有価証券報告書をIFRS財務諸表で作成するとなると、決算日程上の課題が生じることとなりました。
特にIFRS任意適用初年度は、日本基準からIFRSへの変更の影響等の開示が必要となるため、決算短信開示時までに日本基準による連結財務諸表とIFRSによる連結財務諸表を作成する必要があり、スケジュールに対応するためには従来以上にタイムリーかつ効率的に決算作業を進める必要がありました。
具体的に対応を要した大きな課題とその課題への取り組みは次のようなものでした。
日本基準連結財務諸表とIFRS連結財務諸表の同時作成
従来は、最初に日本基準の連結財務諸表を作成し、その後にIFRS連結財務諸表を作成するという手順でおこなっていましたが、この方法では日本基準の連結手続が完了しなければIFRSの連結手続に着手できず、日本基準の連結精算表の完成からIFRSの連結精算表完成までにタイムラグが生じていました。このような方法では決算短信の公表時期までに連結作業を完了することが難しいと思われたため、日本基準の連結手続とIFRS連結手続を同時並行に進めることができる連結決算システムの導入を行いました。その結果、日本基準の連結精算表とIFRS連結精算表をほぼタイムラグ無く完成させることができるようになり、1ヶ月以内で日本基準による連結財務諸表とIFRSによる連結財務諸表を作成するという要請に応えることができました。
連結決算業務の効率化
各子会社の個別財務諸表を初めとする連結決算業務の基礎となる情報の作成は、一般的には子会社による作業となります。これらの作業は連結精算表作成の前段階の作業であるため、作業が遅れたり、作成された情報に誤りがあったりすると連結決算業務全体に遅れの原因となります。タイムリーにIFRSに従った連結業務を行うためには、子会社で行う作業の進捗管理や情報の整合性のチェックをきちんと行うことが重要となります。
日本電波工業株式会社様では、従来は子会社からの情報はエクセル等でやり取りをしていたため、作業の進捗度が把握しにくいことや、親会社でのチェックで入力された情報に誤りが発見された場合に手戻りが発生するという課題がありました。
それに対して、新連結会計システムでは各子会社が連結会計システムに直接データを入力するため、親会社側で子会社の入力内容を確認することで作業の進捗が容易に把握でき、また子会社の入力内容に誤りがあれば入力時点でエラー表示がされて修正が要求されることで照合作業の効率化や手戻りの防止をすることができました。
もちろん、新システムを導入しただけで連結業務を効率化することはできません。新システムの導入に併せて、海外子会社も含めた子会社への教育、連結業務マニュアルの見直しを含む連結業務の再構築を行うことによって業務の効率化を実現しています。
連結消去・修正仕訳の自動化
作業の効率化、早期化という観点では、作業の自動化は大きな効果を発揮します。日本電波工業株式会社様では、連結消去・修正仕訳の一部について、子会社が入力した基礎データから自動仕訳を作成することに取り組みました。当然、全ての仕訳を自動仕訳によることは実現困難であるため、優先的に自動化する仕訳を検討し、税効果関連、未実現利益の消去関連等の仕訳を自動化することとしました。
IFRS適用の反響
IFRS適用第一号の反響は少なからずあったようです。
決算発表時の取材やインタビューなどの数も前年までと比較して大きく増えたそうです。
意外な反応としては、アナリストなどからIFRSで開示された数値が従来の日本基準だとどうなるかという質問が少なからずあったということです。IFRSでは特別損益項目を区分表示することができないため、通常の営業収益、営業費用と臨時の利益・損失が一緒に表示されることとなります。業績の予測を行うには、経常的に発生する項目と臨時項目との区分というのは情報利用者にとっても重要なものであり、今後も日本基準に近い業績の把握も行えなければIR対応などで問題が生じるかもしれないという感触があるようです。
IFRS適用第一号として注目されている日本電波工業株式会社様ですが、当分の間は日本企業のIFRS適用の唯一の事例となると思われます。日本電波工業株式会社様では、今後も継続してIFRSによる開示がおこなわれます。そのため、先行企業としての取り組みがどのようにされていくのか、引き続き注目すべき企業です。
講師紹介

公認会計士 森川智之氏
監査法人トーマツに勤務後、独立。 IPO支援、管理会計、ファイナンス等のコンサルティング業務から税務業務などを幅広く行う。
公認会計士、森川アンドパートナーズ会計事務所代表、有限会社フォレストリバー代表取締役。