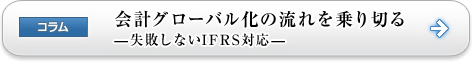第6回「固定資産管理へのインパクト:減価償却と減損」
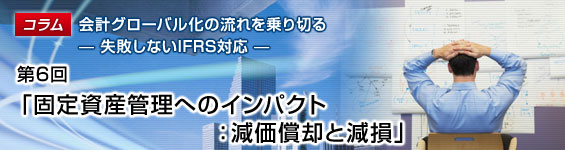
2010年9月公開
IFRS対応にあたって、連結決算業務と並んで大きなインパクトがあると思われるのが固定資産管理業務です。先行対応している企業の事例を見ても、減価償却方法の検討や変更、減損への対応など、固定資産関連の対応のために多くの時間と労力を割いていることがあります。日本基準とIFRSとの間では、固定資産に関する会計処理で少なからぬ差異があるため、大半の企業でシステムの変更や改修を含めた対応が必要となると予想されます。
税法基準による減価償却
一時期、固定資産の減価償却に関しては、IFRSが導入されると減価償却の方法として定率法が認められなくなる等の議論をしばしば眼にしましたが、実のところ、IFRSと日本基準との間には、原則的な減価償却の取扱いには大きな差異はありません。
日本基準では、原則として適切な耐用年数及び残存価額を見積もり、当該見積りに従って毎期規則的に減価償却を実施することが必要、但し、企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、税法基準による減価償却を妥当なものとして取り扱うことができるとされています。
IFRSにおいても経済的耐用年数と見積残存価額によって毎期規則的に償却をするという原則は同じですが、実際に適用する際にはどのようにして耐用年数や残存価額や償却の方法を見積もるのかについては企業ごとに検討することを要求されることとなると思われます。
日本基準のように「不合理と認められる事情のない限り」税法基準を採用できるかは疑問ですが、合理的な理由があれば減価償却の方法、耐用年数等の見積りに税法の規定を使用することは認められる可能性もあります。また、固定資産の減価償却費に重要性が乏しい場合は見積りに簡便な方法を採用することも認められる可能性もあり、重要性の観点から税法基準の採用が許容されることもあり得ると思われます。
いずれにせよIFRS対応における固定資産の減価償却の取扱いが、一律に定額法へ変更を要するというような杓子定規なものとなることはありえません。企業グループごとに、適切な耐用年数や償却方法の合理的な見積りの方法や、重要性などを総合的に考慮して採用する減価償却の方法などを決定することが必要となります。
なお、IFRS対応にあたって、従来の税法基準を採用しないこととした場合、税務申告上の減価償却の方法を変更するか否か、また税務申告上の減価償却の方法とIFRS連結財務諸表上の減価償却の方法が異なることとなった場合は複数の基準に従った固定資産管理をどのような業務、システムで行うのかについても検討しておくことが必要です。
会計基準の統一と減価償却
IFRS対応における減価償却を考える場合、IFRSに要求されているグループ内の会計基準の統一についても考慮しておく必要があります。
特に、グループに外国企業が多い場合、減価償却の方法を日本の税法基準で統一することは困難であると思われます。一方、グループに外国企業が無い場合や外国企業の重要性が小さい場合は、日本の税法基準を用いるというのも現実的な選択肢となるかもしれません。
減価償却にあたっての償却方法や耐用年数の決定については、それぞれの企業において合理的な見積方法を検討するだけでなく、グループ全体として合理的な方法であるか、グループ全体で適用可能な方法なのかという観点からの検討も必要となります。
減損への対応
固定資産業務のIFRS対応にあたって、減損会計に関する日本基準とIFRSとの差異が大きな問題となることが予想されます。
特に、IFRSで要求されている減損の戻入については、日本基準で許容されていないこともあり、ほとんどの企業グループで現状のままでは、戻入限度額の把握や戻入処理などへ対応できないと思われます。
場合によっては、減損の対応のために固定資産システムの大規模な改修をしなければならない可能性もあるため、IFRS減損会計に対応のための課題については、会計処理面、業務面、システム面を含めて早い段階で把握し、対処方針の検討を行うことが必要です。
その他、固定資産管理に関しては、コンポーネント・アカウンティングの影響、再評価モデルを採用した場合の影響など、広範囲において影響が出てくる可能性があります。
IFRS・日本基準・税務の固定資産の取扱いが全く同じではない以上、IFRS連結財務諸表上、個別財務諸表上、税務の固定資産管理や減価償却計算を別々に行い、それぞれの差異を調整することが必要となる可能性があります。
しかし、業務の効率性を考えれば、IFRS・日本基準・税務の規定をそれぞれの対応業務に単純に適用し、部分最適を実現するような対応は望ましくありません。財務報告と業務効率の目的に沿って企業グループの固定資産管理の全体最適が実現できるように、常にIFRS・税務など複数の要素を考慮しながら課題への対応を行うことが重要となります。
講師紹介

公認会計士 森川智之氏
監査法人トーマツに勤務後、独立。 IPO支援、管理会計、ファイナンス等のコンサルティング業務から税務業務などを幅広く行う。
公認会計士、森川アンドパートナーズ会計事務所代表、有限会社フォレストリバー代表取締役。