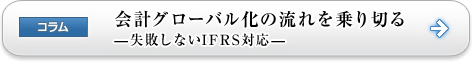第3回「IFRS時代のグループ会計」

2010年6月公開
IFRSでは、連結財務諸表の作成に用いる親会社及びその子会社の財務諸表は、同じ日現在で作成しなければならず、もし親会社の報告期間の末日が子会社と異なる場合には、子会社は(実務上不可能な場合を除いて)親会社の財務諸表と同じ日現在で追加的な財務諸表を作成することとされています。また、連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引及び事象に関し、統一された会計方針を用いて作成されなければならないとされています。
このことに対応するためには、会計方針を統一し、決算期変更をするなどして決算日を統一するというだけでは十分ではなく、勘定科目の取扱いを通じたルールの統一や決算の効率化、早期化にも併せて取り組むことを考えなければなりません。
勘定科目とグループ会計方針の統一
IFRS連結財務諸表をスムーズに作成するためには、親会社、子会社との間での勘定科目の統一が必要です。日本基準の連結財務諸表では、連結財務諸表の注記も比較的少なく、連結財務諸表本体の表示科目は集約された勘定科目となるため、勘定科目が十分に統一されていなくても連結業務に大きな影響を与えませんでした。しかし、IFRSでは、連結財務諸表本体の数値だけでなく膨大な注記に係る数値も連結ベースで開示する必要があるため、勘定科目の統一が行われていなければ連結業務に著しい不効率を生じるなどの問題が起こる可能性があります。
また、勘定科目の統一は、IFRS対応準備期間だけでなく適用後も継続して対応することとなります。子会社の中に親会社と異なる地域や異なる業種に属する会社がある場合には、子会社に関する事業や法令などの要請によって独自の勘定科目の追加、変更などを行わざるを得ないこともあります。それぞれの子会社の事情に応じて勘定科目の取扱いが柔軟にできることと、グループ全体の勘定科目の統一に混乱が生じないことを同時に達成しなければなりません。
先行してIFRS対応を行っている企業の例を見ても、勘定科目の統一への取り組みは重要なことであり、またしっかりと取り組むことでIFRS対応全体が順調に進んだという効果も生じるようです。
また前述の通り、勘定科目の統一だけでなく、子会社は親会社と会計方針を統一することも求められています。これは単に重要な会計方針を統一するだけでなく、同一の取引には同一の会計処理を適用することができるためのルール、マニュアル等、いわゆるグループ会計方針を整備し、運用していくことが必要となります。
このような、業務面も含んだ会計処理の統一をグループ全社に展開するには、多くの時間を要することもありますので、IFRS対応計画の策定にあたっても十分検討しておくことが必要です。
必要となる決算早期化への取り組み
IFRSでは、子会社は親会社と同じ決算日で財務諸表を作成するか、親会社の決算日で仮決算を行うかによることが求められています。
日本基準では、親会社と子会社の間での三ヶ月以内の決算日のずれは容認されていたため、親会社は3月決算、子会社は12月決算の財務諸表によって連結財務諸表を作成することなどは頻繁に起こっていました。しかし、IFRS適用後はこのような場合でも、子会社の決算日を3月決算に変更するか、3月末で仮決算を実施することが要求されることとなります。
その結果、親会社の決算日から連結財務諸表作成期日という短い間に、親会社と子会社すべての個別決算業務と連結決算業務が集中することとなります。多くの企業にとっては、このように決算業務が集中することとなった場合、期日までに監査対応を含む決算業務を完了することは容易なことではないと思われます。IFRS対応にあたっては、無理なく期間内に開示書類を作成するために、決算の効率化、早期化の取り組みも必要となります。
講師紹介

公認会計士 森川智之氏
監査法人トーマツに勤務後、独立。 IPO支援、管理会計、ファイナンス等のコンサルティング業務から税務業務などを幅広く行う。
公認会計士、森川アンドパートナーズ会計事務所代表、有限会社フォレストリバー代表取締役。