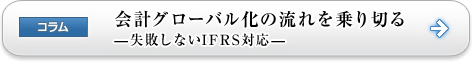第5回「資産・負債アプローチと収益認識」

2010年8月公開
IFRS対応に当たって大きなテーマの一つとなるのが「収益認識」です。収益認識の対応については、会計処理に関する影響だけでなく、販売業務を含めた業務プロセス、販売システムを含めたITシステムなど広い範囲で大きな影響が生じる可能性があります。
収益認識への対応は、「出荷基準を検収基準に変更すればよい」というような画一的な対応でなく、業務プロセスの検討などを通じて、影響の範囲や企業グループにとって望ましい対応方法は何かをしっかり検討したうえで進めていくことが必要です。
資産・負債アプローチによる収益認識
IFRSでは収益の認識基準は以下のとおりとなっています。
物品の販売
次の条件すべてが満たされたときに収益を認識する。
- 物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を企業が買手に移転したとき
- 販売された物品に対して、所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も実質的な支配も企業が保持していないこと
- 収益の額を、信頼性をもって測定できること
- その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
- その取引に関連して発生した又は発生する原価を、信頼性をもって測定できること
役務の提供
役務の提供に関する取引の成果を、信頼性をもって見積もることが出来る場合には、その取引に関する収益は、報告期間の末日現在のその取引の進捗度に応じて認識する。
物品販売の収益認識を見ると顕著ですが、IFRSの収益認識は棚卸資産などの資産の帰属が移転しているかが、収益の認識において重視されています。言い換えれば、IFRSでは収益そのものの定義や認識基準より、資産・負債の定義や計上の要件を明確にし、資産・負債の増減を収益・費用として認識するというアプローチ(資産・負債アプローチ)を採用しているものと思われます。
また、収益認識については2011年にIFRSの大規模な改訂が予定されており、今年6月にその公開草案が公表されました。
従来のIFRSでは、役務の提供の収益認識や工事契約の収益認識などを含め、純然たる資産・負債アプローチを貫いていない部分もありましたが、公開草案では、物品の販売だけでなく役務提供や工事契約についても同じ枠組みで収益の認識基準が定められ、資産・負債アプローチを更に徹底する方向に改訂されることが示されています。
今後、IFRSの収益認識に対応していくためには、企業グループに帰属する資産・負債を明確に把握できること、いいかえれば企業グループに関わる権利、リスク、義務の帰属を把握できることが必要となります。
従って、販売取引に関連する権利、リスク、義務の帰属が曖昧になっている場合や、販売取引のどの時点で権利、リスク、義務が増減するについて曖昧になっている場合などは、IFRSの収益認識への対応が難しくなるかもしれません。そのようなケースでは、IFRS対応のために販売契約の内容の見直しや業務プロセスの見直しなども併せて行う必要があります。
忘れてはならない重要性の原則
また、実際に収益認識への対応を行うにあたっては、重要性の観点も考慮する必要があります。
取引内容の検討によって得意先の検収時に収益認識をすべきという結果が出た場合でも、単価の小さな物品を大量に販売しているケースなど、物品ごとの検収データを把握・集計することが実務上難しく、かつ期末日の検収データを把握することの重要性が小さい場合など、実際の検収データによらず、検収予定日を使用するなど簡便な方法によって収益を認識するということも検討の余地があります。
講師紹介

公認会計士 森川智之氏
監査法人トーマツに勤務後、独立。 IPO支援、管理会計、ファイナンス等のコンサルティング業務から税務業務などを幅広く行う。
公認会計士、森川アンドパートナーズ会計事務所代表、有限会社フォレストリバー代表取締役。