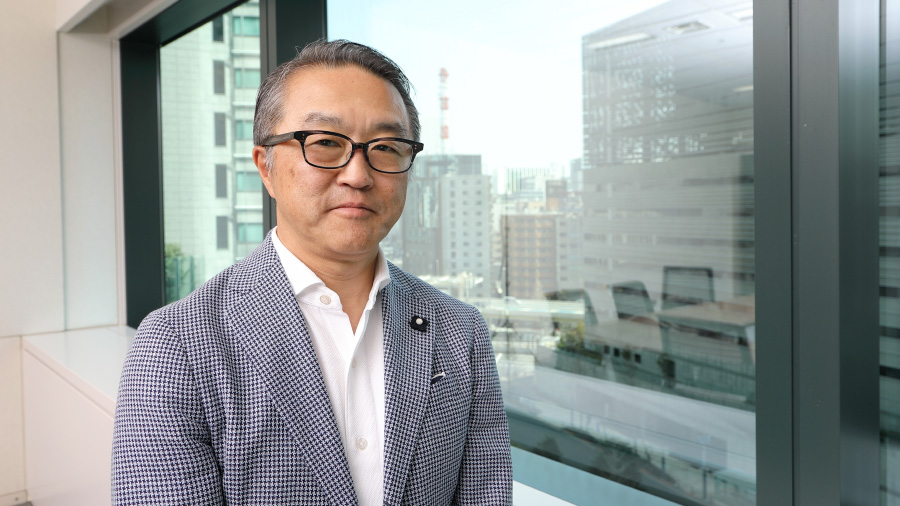
[語り手]
テクノロジーソリューション部門
デジタルソフトウェア&ソリューションビジネスグループ長長堀 泉
(組織名・役職は2020年3月時点)
AIやIoT,5Gなど先端ITが社会に浸透する中,これらを駆使してデータをより高度に利活用することで,ビジネスに変革をもたらすDX(デジタルトランスフォーメーション)が進展しつつある。幅広い産業分野でDXが進んでデータ駆動型社会が実現すれば,個々の企業の成長はもちろん,様々な社会課題の解決や,持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも寄与するとの期待が高まっている。
こうした背景のもと,富士通ではDXビジネスを強化し,IT企業からDX企業への変革を進めていくことを方針に掲げている。本記事では,デジタルソフトウェア&ソリューションビジネスグループ長として,富士通のDXならびにデータ利活用の事業を統括する長堀常務に,富士通の考えるDXがもたらす価値や,富士通が目指すDX企業のあり方,その実現に向けたビジョンなどを聞いた。(2020年3月にインタビューを実施)
本記事は,「【Part1】DXがもたらす価値はどこにあるのか?」「【Part2】富士通が歩むDX企業への道のり」の二つに分けて掲載する。
【Part1】DXがもたらす価値はどこにあるのか?
DXの本質は,「業務改善」にとどまらない「事業変革」を実現すること
-
長堀DX,すなわちデジタルトランスフォーメーションとは,そもそも2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念で,「ITの浸透が,人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というものでした[1]。
より具体的なイメージとしては,経済産業省の定義があります[2]。「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し,データとデジタル技術を活用して,顧客や社会のニーズを基に,製品やサービス,ビジネスモデルを変革するとともに,業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土を変革し,競争上の優位性を確立すること」というものですが,少しまどろっこしいですね(笑)。富士通では,一般的に「先進のデジタル技術とデータを駆使して,革新的なサービスや具体的なビジネスプロセスの変革をもたらすもの」と説明しています。 -
長堀私は長く金融業界を担当していましたので,そこでのトレンドを例に説明させてもらうと,インターネットバンキングはDXとは言えないと思っています。ただ取引をネット上で行えるようになったというだけでは,ビジネスモデル自体は従来と変わっていないからです。
これに対し,ビットコインなどの仮想通貨は,ブロックチェーンのような先進技術をトリガーにして貨幣そのものの構造を変えようとしているので,これはDXと呼べるでしょう。 -
長堀そうですね。既存のビジネスモデルを効率化したり,コストダウンによって低価格化したりするだけでは,「業務改善」にとどまります。そこから一歩進めて,誰にどんな価値を提供し,どういう報酬を得るのかといった生業(なりわい)自体を変える,そうした「事業変革」こそがDXの本質だと考えています。
DXという言葉は,「デジタル(D)」と「トランスフォーメーション(X)」から成り立っていますが,デジタルは方法論であって,肝心なのはトランスフォーメーションを起こせるかどうか。いくら先進のデジタル技術を活用しても,事業変革に値しないものはDXとは呼べないだろうと思っています。 -
長堀現在の産業社会では,いろんな変革が求められていますが,その根底にあるのが企業活動の再定義にあると考えています。
また金融業界の例になりますが,かつてビル・ゲイツが「Banking is necessary, but banks are not.」と語ったように,旧来の銀行のビジネスモデルに対し,ユーザーから「どうしてこの時間までしか窓口が空いていないの?」「どうして自分のお金を引き出すのに費用がかかるの?」といった素朴な疑問が生まれています。こうした課題を先進的なフィンテック企業が解決することで,銀行不要論が沸き上がるという形で,ビジネス構造のディスラプション(破壊)が生じているのです。
このように,既存のサービスをユーザー視点で再定義することを「デモクラタイゼーション(民主化)」と呼び,金融業界に限らず様々な産業分野で進展しています。これがある意味,DXの本質ではないかと思います。
――富士通は,2019年9月に発表した経営方針において「IT企業からDX企業への転換」を掲げ,その実現に向けて,2020年1月にDX専門の新会社「Ridgelinez(リッジラインズ)株式会社![]() 」を設立するなど,具体的な施策を推進しています。こうした取り組みの狙いや意義を語っていただく前提として,まずは,そもそもDXとは何か,富士通の考えるDXの定義についてご教示ください。
」を設立するなど,具体的な施策を推進しています。こうした取り組みの狙いや意義を語っていただく前提として,まずは,そもそもDXとは何か,富士通の考えるDXの定義についてご教示ください。
――だいぶ分かりやすくなりましたが,具体例などを交えて,より噛み砕いて説明すると,どういうものになるでしょう?
――なるほど。デジタル技術を駆使して,従来になかったビジネスモデルや価値を生み出して,初めてDXと呼べるというわけですね。
――DXの本質が事業変革にあることは分かりましたが,そうした変革が求められる背景には何があるのでしょう?
――なるほど。これまでは「当たり前」と思われていた既存のビジネスモデルの問題点を,ユーザーの視点から捉え直して,デジタル技術を駆使して根本的な構造から解決していこうという取り組みが,DXというわけですね。
データ駆動型社会がもたらす,より豊かな社会の姿とは?
-
長堀「データ駆動型社会」という概念も,やや捉えどころがない印象がありますが,私個人としては,デジタル技術の進歩によって,これまでは得られなかった情報をデータとして活用し,それによって社会を動かしていくことだと捉えています。
ビジネスにおける代表的なデータ活用の例が,「経済源流データ」と呼ばれる3つのデータ,すなわち検索データ,購買データ,決済データです。これらのデータを収集することで,企業は消費者がどんな商品の情報を求めていたか,実際にどんな商品を購買したか,どこでいくら支払ったか,などが把握できます。
これをビジネスに利用して,例えばネットショップのレコメンド(推奨)機能のように消費者の嗜好に合った商品情報を提供すれば,企業にとってはビジネスチャンスの拡大に,消費者にとっては満足度の向上につながります。これなどは,データ駆動型社会のクリエイティブな事例ではないかと思っています。 -
長堀IoT社会の到来によって,得られるデータの量が爆発的に増加したことで,特に進化が期待されているのがAIです。
生物学の世界では,生物は目を持ったことで爆発的に種類が増えたとの説があります。これまでのAIが手探りだったとすれば,これからのAIはIoTという目を手に入れたことで,飛躍的な進化を遂げるでしょう。IoTによって進化したAIが,膨大なデータを利活用して様々な課題を解決していく,これもまたデータ駆動型社会の一つのあり方ではないでしょうか。 -
長堀一口に社会課題といっても幅広いテーマがありますが,私たちが貢献できるのは,やはり経済取引に関する分野が中心になると思っています。
例えば,富士通総研の顧問をしていただいていた経済学者の田中直毅さんは,「経済学の視点から見たDXのメリットはトランザクション(取引)コストのゼロ化にある」と語っておられます。これは,経済取引において,行き過ぎた仲介者による不要なコストが生じがちなので,デジタル技術を駆使して,それらをゼロにしていこうという意味です。
実際,小売業界におけるアマゾンの存在や,金融業界におけるクラウドファンディングなどのように,仲介者を通さず,不要な取引コストをゼロにしようとの動きは社会的に大きな価値を生んでいます。富士通が目指すSDGsや社会課題解決の対象も,こうしたところにあるのではないでしょうか。 -
長堀不要な仲介者を廃するということは,コストを抑え,取引のスピードを速めるだけでなく,データの改ざんや盗難,不正利用などを防止することにもつながります。
インターネットは便利なものですが,ある意味,コピー情報をばらまいているだけという側面もあります。それでも,情報量の多さがアセット(資産価値)となって,多くの情報を保有する優位者が,情報を持たないものを相手にビジネスを行うといった,「情報の非対称性」を利用したビジネスモデルが成立していますが,そこにはデータが悪用されるリスクが伴います。こうしたリスクをデジタル技術によって削減していくことも,DXの役割の一つだと考えています。 -
長堀ただコピー情報が飛び交うだけならともかく,それらをデータとしてビジネスに利活用するとなれば,やはり信頼性を担保する仕組みがなければなりません。
例えば金融取引におけるブロックチェーンのような,データの信頼性を担保する技術や,政府が提唱するDFFT(Data Free Flow with Trust:信頼ある自由なデータ流通)のような基盤作りも重要でしょう。
富士通では,お客様企業のDX実現をサポートする一方で,こうしたDXを支える社会基盤作りの面でも,しっかりと貢献していきたいと思っています。
――様々な産業分野でDXが進んで,社会全体に広がっていけば,いわゆるデータ駆動型の社会が実現して,多くの社会課題が解決でき,より豊かな社会になるとの期待もありますが,その実像はどのようなものになるとお考えでしょう?
――様々なデータを活用することで,より効率的なマーケティングを実現したり,より的確な経営判断が下せるようになったりするわけですね。
――データ駆動型社会のありようが見えてきましたが,データを利活用することで社会課題が解決できるとすれば,どのような例が考えられるでしょう?
――確かに,今,挙げられた例などは,DXによる社会の変化と言えますね。
――私たちがデータ駆動型社会のメリットを享受するためには,いかにデータの信頼性を担保するかが問われるというわけですね。
参考文献
【Part2】富士通が歩むDX企業への道のり
富士通がDX企業を目指す背景には,近年の環境変化への危機感がある
-
長堀お客様のニーズや政府の経済政策など,多様な要因がありますが,最も大きいのは,現状への危機感ですね。先ほどのビル・ゲイツの言葉をもじって言えば,「IT is necessary, but IT vendors are not.」と言われかねない時代を迎えていると認識しています。
その理由も様々ですが,例えば価格体系の問題があります。これまでは,ITシステムを構築するために,何人のスタッフが何か月働いたかという「人月計算」で価格を算出していました。そのシステムがどれだけの価値を生み出したかは問われることなく,かかった工数に依存していたわけですが,こうした考え方もこれからは通用しなくなるでしょう。 -
長堀そうですね。近年ではレベニューシェア(成果報酬型)やサブスクリプション(従量課金型)などのビジネスモデルが登場し,これまで以上に費用対効果が問われています。
経済産業省が提唱する「2025年の崖」でも指摘されているように,これまでのIT投資では,既存システムの保守・メンテナンスなどに予算を取られがちでした[3]。そうした「守りのIT投資」は,クラウドなどを活用することでできるだけ削減して,トップライン(売上高)の向上につながる「攻めのIT投資」への提案にシフトしていく必要があると考えています。 -
長堀それこそDXを実践して,富士通のビジネスモデルそのものから変えなければいけません。
今までの富士通のビジネスは,建築の世界で例えれば,発注者の言う通りにマンションを建てるようなもの。そうではなく,どの場所にどんな建物を建てれば,より多くの利益を得られるかを提案するデベロッパーにならないといけません。
外食業界で例えると,今の富士通は料理の素材や厨房機器を提供するだけで,お客様は自分の欲しい料理を自分で調理しなければなりませんでした。これからの富士通は,お客様の求める料理を提供できるレストランにならないといけないと考えています。
このように,お客様が求める価値をしっかりと見据えて,その価値を生むプロセスだけでなく,価値そのものまでをトータルに提供する。こうしたビジネスができるよう,まずは富士通自体がDX,事業変革をする必要があるのです。 -
長堀ビジネス構造を根本から変えていくというのは,並大抵のことではありませんし,多くの課題を乗り越える必要があると考えています。
例えば,先ほど述べた投資効果型の価格体系に転換するとなると,これまで以上の事業リスクを抱えることになります。これまでは,収めたシステムが正常に作動すれば対価をいただけましたが,そのシステムがどれだけの価値を生んだかが問われるようになると,そうはいかなくなるわけです。そうしたリスクに対応するには,これまでと全く異なる能力や人材が必要になります。 -
長堀データ利活用の側面で言えば,データをいかに有効活用するかという問題もあります。扱うデータ量が飛躍的に増加し,膨大なデータのどこに価値があるかが見えづらくなっている中,「情報の非対称性」だけを利用したビジネスモデルで提供できる価値には限りがあります。これからは,何がお客様にとって本当に価値のあるデータなのかを見極めるための専門知識やノウハウが重要になるでしょう。
一方で,富士通自身がデータを利活用できるような仕組みも構築していく必要があります。実は,今の富士通はデータを流通させる基盤を提供しているだけで,そこを流通するデータそのものについては権利を持っていません。そこをいかにクリアするかも課題になるでしょう。 -
長堀企業文化というか,考え方という意味では,やはり「パーパスドリブン」と言われるように,目的志向の考え方が重要になると思っています。なぜ改革が必要なのか,何のために取り組むのか,まずはそこを明確にしなければなりません。
これはお客様のDXを支援する上でも言えることで,かつても「AIを導入して何かできないか?」など,目的が曖昧なまま,とにかくAIを導入したいといったニーズもありましたが,それでは何の価値ももたらしません。 -
長堀だからと言って,「目的が決まったら呼んでください」という姿勢でもダメで,「こういった目的にするべきじゃないですか」と提案できるようにならないといけません。Ridgelinezを設立した狙いもそこにあって,コンサルティング的なスタンスで,ITシステムの要件定義よりも更に上流から,お客様ビジネスの現状や課題を共有するような姿勢が必要になると考えています。
-
長堀確かに,2~3年でできることではないでしょうが,私は富士通ならできると確信しています。なぜなら,富士通には多くの産業分野で培ったノウハウに加え,AIやIoT,クラウド,量子コンピューターなどDXを実現する要素技術面での蓄積があります。加えて,大きな財産となっているのが,既にDXを成し遂げた経験があることです。
もともと富士通は「富士通信機製造株式会社」という社名で,電話機や通信機を造っている下請けメーカーでした。それが1950年代に電話回線を切り替える「リレー」を使ったコンピューターを開発し,コンピューター製造業,更にIT企業への道を歩み始めたのです。これはまさに生業そのものを変える事業変革,DXの実践と言えるでしょう。 -
長堀もちろん,現在では企業規模が当時とは比較にならないほど大きく,事業の内容も多岐にわたっていますから,ある面では変革が難しくなっているかもしれません。
だからこそ,時田社長が「DX企業の定義は何か,一人ひとりが考えるべき」と言っているのでしょう。私の言うDXがみなそれぞれのDXと一緒とは限りません。そういう難しさをしっかり認識して,その上で本気でやっていくのだということを,社内外の皆さんにお伝えしたいと思います。 -
長堀『星の王子様』で知られるサン・テグジュペリの言葉に,「船を造りたいなら,人々に材料を集めさせたり,作業を割り振ったりするのでなく,彼らに海の無限の広さへのあこがれを教えればよい」というものがあります。これはまさに目的志向というもので,何のために船を造るのか,船を造ってどこへ向かうのか,明確なビジョンを示すことが大切かを物語っています。
これからDX企業を目指す富士通の社員やパートナーに対しては,DX企業としての富士通が目指す姿を明確に示していきたいと思っています。また,これからDXを実現したいお客様企業に対しては,DXによって何を目指すのか,ビジョンが明確になるまで一緒に考えるところからサポートしていきたいと思います。
これからの富士通のDX企業への挑戦に,ぜひ,ご期待いただきたいと思います。
――ここからは,富士通の具体的な方針や戦略について伺っていきます。富士通では,IT企業からDX企業への転換を図るとの方針を掲げていますが,その背景にはどのような狙いがあるのでしょうか?
――かかった労力で見積もるのでなく,生まれた価値で見積もるという形に変えていくということでしょうか?
――そうした変化を実現するには,何が必要でしょう?
――なるほど。まず自らがDXを実現しないことには,お客様のDXを支援できない,というわけですね。
DX企業を目指す上で重要なのは,目的志向を徹底すること
――DX企業を目指すという事業方針には,DX事業に注力するという意味に加えて,自らがDXを実践するとの意味もあることが分かりましたが,その実践に向けて,どんな取り組みが必要でしょうか?
――ビジネスモデルを変えることで,必要な人材も変わってくるというわけですね。
――DXを実践するには,組織やビジネスモデルの変革だけでなく,企業文化の変革も必要と言われますが,その点についてはいかがでしょうか?
――何のためのDXなのか,目的をしっかりと見定めた上で取り掛からないと意味がないということですね。
――課題は山積しているという印象ですが,DXを成し遂げるには,かなりの時間がかかるのではないでしょうか?
――確かに,デジタル技術を駆使した事業変革ですから,まさにDXの先取りですね。
――最後に,本記事の読者に向けたメッセージがありましたらお願いします。
本稿に掲載されている会社名・製品名は,各社所有の商標もしくは登録商標を含みます。
