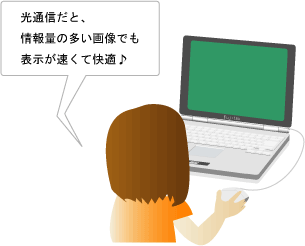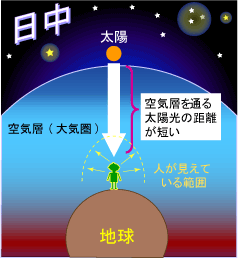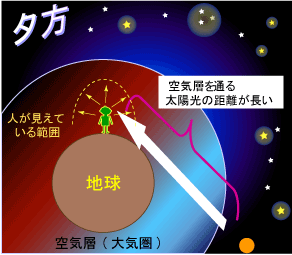「伝える」技術
光通信技術

光通信とは
光通信ってなんだろう
光を使って、情報を相手に伝えることです。
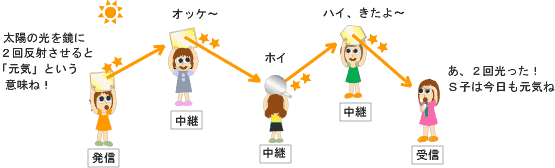
光通信の基本構成
私達の身近なコンピュータや携帯電話は、情報を「0と1」の電気信号で発信しています。光通信は、電気信号を光信号に変換する「送信器」と逆に光信号を電気信号に変換する「受信器」、 そして光を運ぶ路「光ファイバー」で成り立っています。
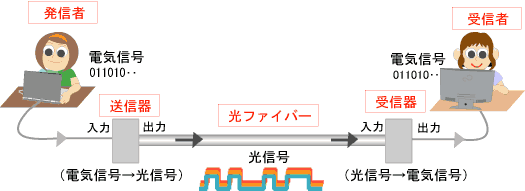
光通信のメリット
- 伝達距離が長く、省エネで経済的
- 1度にたくさんの情報を送れる
- 通信速度が速い
1. 伝達距離が長く、省エネで経済的
1秒間に10ギガbitの情報(100億個の信号)を送る場合、電気通信では100メートルごとに信号を調整する必要があります。これに対して、光通信の場合は調整間隔を100キロメートル以上にすることも可能です。信号を調整する回数が少ないほど、機器の数が少なくて済むため省エネで経済的です。
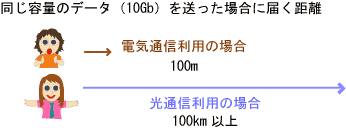
例えば、今は、海外の友達と電話で話したり、チャットで話しても国内で通話しているのと変わらないように感じますね。昔のように声が遅れたりしません。電気通信しかなかった頃は、1度に送れる距離が短く送れる情報量も少なかったので、主に電波を人工衛星で中継させて海外とやり取りをしていました。しかし、光通信の場合は、1度に送れる距離が長く、情報量も多く送れるので、光ファイバーの海底ケーブルを使うことによって、違和感なく海外とやり取りできるのです。(電波と光の速度は同じです。しかし、宇宙を経由すると経路が長くなるので信号の到着が遅くなります。海底ケーブルはずっと距離が短いので信号がより早く到着します。)
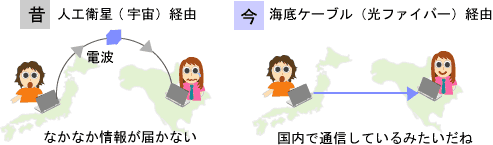
2. 1度にたくさんの情報を送れる
沢山の人が希望する情報(映画やニュースなど)を同時に受け取ることができます。電気通信は最大で1秒間に10ギガbit(0と1の信号を100億個)の伝送容量に対し、光通信は最大で1テラbit(0と1の信号を1兆個)の情報を送ることができます。
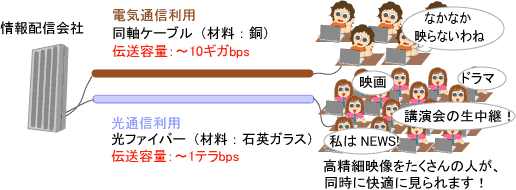
3. 通信速度が速い
電気通信の場合は、電気的ノイズによるエラーが出るため、通信速度が遅くなります。しかし、光通信の場合はノイズに影響されないので、スピードの速い信号が送れます。
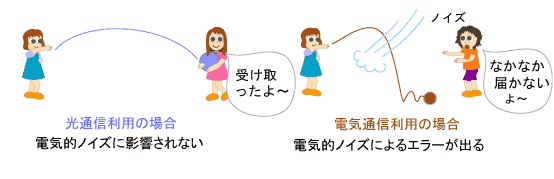
光通信ってどこで使われているんだろう
光通信は身近なところから世界へ
インターネットや携帯電話、IP電話などのネットワークを利用する仕組みは、各個人からそれぞれの地域へそして日本中へと拡がり、さらに世界中の通信網に繋がっています。 例えば、パソコンや携帯電話から発信された信号は、地域の通信業者の基地局やプロバイダー(インターネット接続会社)で集約され、そして海底ケーブルの中の光ファイバーを通して、世界へ届けられます。
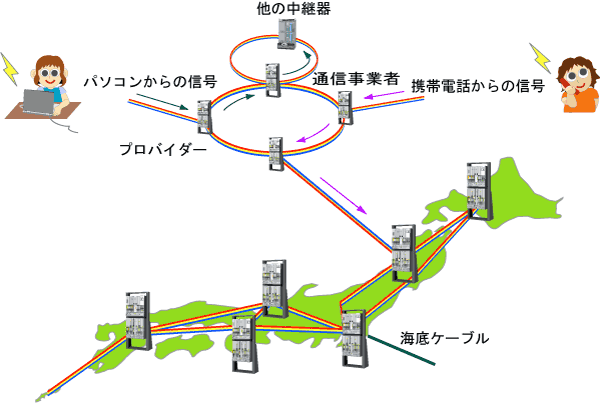
さまざまなものがネットワークにつながっている
私たちが、日々利用しているさまざまな機器がネットワークに繋がっています。そのおかげで、私たちは便利に、そして快適に過ごすことができています。
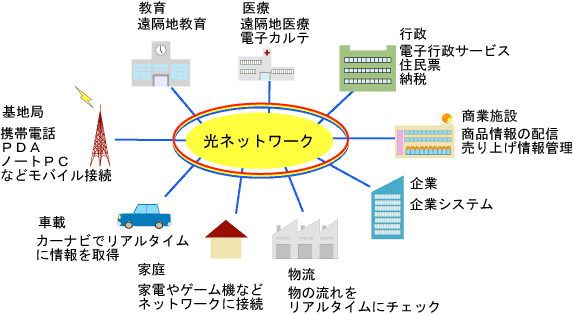
なぜこの技術が必要なのかな
1秒間の国内通信量
1秒間に812.9ギガbit(DVD容量4.7ギガByteの約21枚分)の通信量があると総務省から発表されています。これは3年前と比べて通信量が3倍になっています。私達は、日常の中で携帯電話・メール・画像配信、サイバー(仮想)商店などを情報のやり取りに利用しています。機器の性能も年々向上し、利用の仕方も変わってきています。今後も通信量は、上昇すると考えられます。この情報のやり取りに光通信技術が使われています。
- (引用元:総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課、2007年11月調べ)
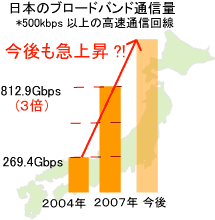
伝送量
世の中の通信量の増加に伴い、1本の光ファイバーでより多くの情報を送る技術が次々と開発されてきました。
伝送量を示す単位
bps(ビーピーエス)を使います。これはbit per second(ビットパーセカンド)の略で、1秒間に送れるビット数を表しています。例えば、1bpsという場合は、1秒間に1ビットのデータを送れることを表します。
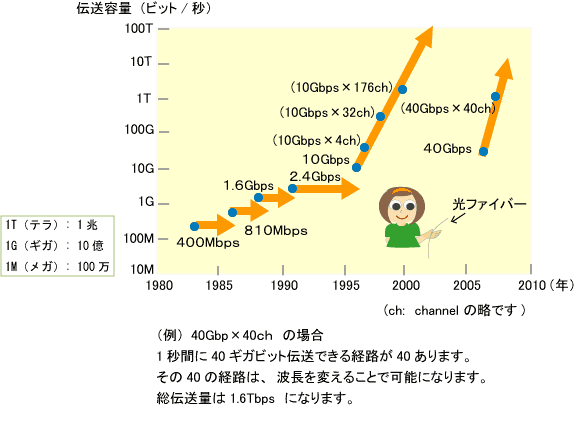
光通信で使われている装置(光伝送装置)
光伝送装置って何をしているのかな
光の通信網の要所には光伝送装置が設置されています。この装置は色々な働きをします。
- 信号を変換(送信):電気信号から光信号へ変換します。
- 信号の合流:細い幹線から広い幹線へ合流します。
- 信号を中継:離れた場所へ送るため、途中で信号を中継します。
- 信号の分岐:信号の方向転換を行います。
- 信号を分割:合流していた信号を元のように分割します。
- 信号を変換(受信):光信号から電気信号へ変換します。
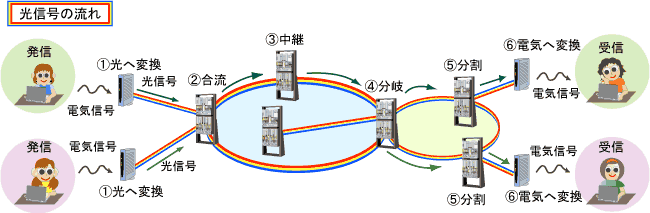
光伝送装置(例:FLASHWAVE 7500)
装置の中には、様々な部品が組み合わさっています。
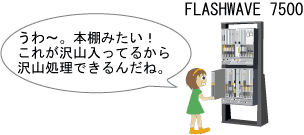
1. 変換(送信)
入ってきた電気信号を光信号に変換します。
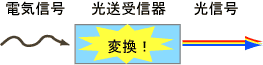
2. 合流
複数の信号を合わせて、一度に送ります。
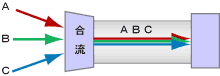
3. 中継
伝送途中に信号の波形や強さがが劣化してくるので、元の信号のようにきれいな波形に復元したり、光の強さを大きくします。
波形の劣化の状態によっては、一度電気信号に変換して電気信号の状態で、波形の間違いを訂正した後、もう一度光信号に変換して送信することがあります。
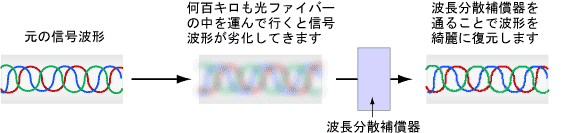
4. 分岐
光スイッチが、光信号ごとに行き先に合わせて、光信号のまま方向を切替えます。
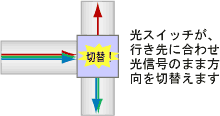
5. 分割
一つに合わせていた信号を元のように分けます。
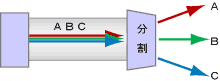
6. 変換(受信)
入ってきた光信号を電気信号変換します。
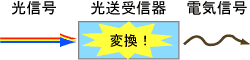
通信方式(現在と将来)
車と車線を使って通信方式を説明します。車は車線を占有できる時間(1区間)、荷物が1度に運べる情報(ビット数)、車線が光の波長ひとつであるとします。
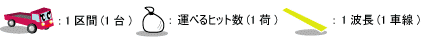
現在の通信速度: 1波長あたり10ギガbps、40ギガbps
時分割多重方式(TDM: Time Division Multiplexing)
1度に送れる情報に限りがあるため、時間で区切って送ります。例えば複数のユーザが同時に情報を発信した場合、情報を運ぶ車線は1車線しかないので、それぞれの情報の荷を乗せたトラックが1列に並んで運びます。車線が渋滞した時は、送信速度が遅くなることもあります。
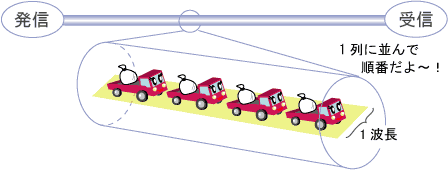
光波長多重方式 (WDM: Wavelength Division Multiplexing)
1度に送れる情報量が多く、複数のユーザの情報を波長を変えて同時に送ることができます。例えば複数のユーザが情報を同時に発信しても、車線が沢山あるので渋滞になりにくく、スムーズに荷(ビット数)を送れます。送信速度が安定しています。
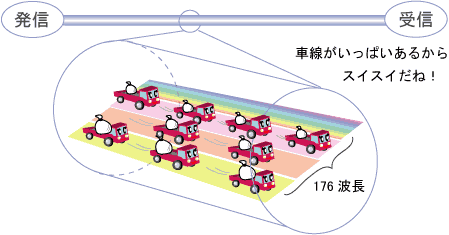
多値変調方式 (MM:Multi-level Modulation)
1波長の1区間に複数の信号を送る方式です。同じ波長の上に複数のユーザの情報を光の波形を変えて送ります。代表的な技術に、差動4値位相変調方式(DQPSK(ディーキューピーエスケー):Differential Quadrature Phase-Shift-Keying)があります。通常、トラックの荷台には1ビットを乗せて運びますが、「DQPSK」の場合、2ビットを乗せて運ぶことができます。
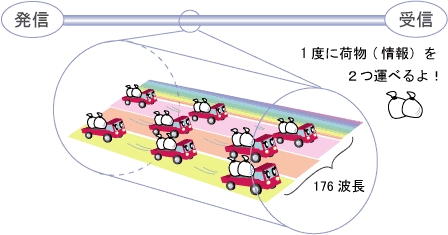
将来の通信速度:1波長あたり100ギガbps
100Gbpsは、DVD1枚を約0.4秒で伝送する速度です。(DVD容量4.7ギガByteで換算した場合)。
偏波多重方式(Polarization multiplexing)
光は振動しながら進んでいます。その振動の向きを「偏波(へんぱ)」といいます。垂直に振動しながら進む光(垂直偏波)と水平に振動しながら進む光(水平偏波)があります。偏波に乗せた情報は、混信することもなく、多くの情報を送ることができます。例えば1車線の上を2台同時に走ることができ、その2台はぶつかり合うことも無く情報を送れます。
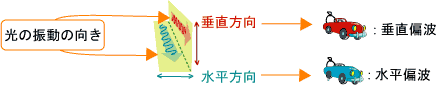
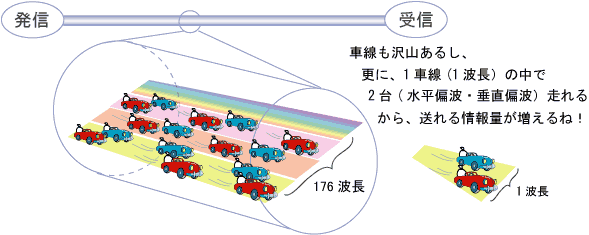
いろんなことができる光ネットワーク(事例紹介)
世界中に光ファイバーがひかれ、色々なシーンで私たちは高度なサービスを受けられるようになりつつあります。その例をご紹介します。
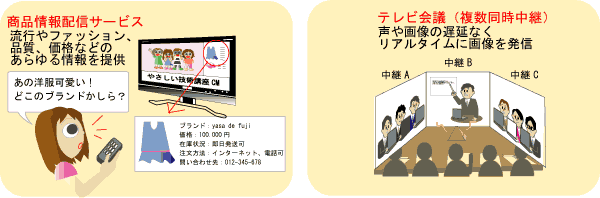
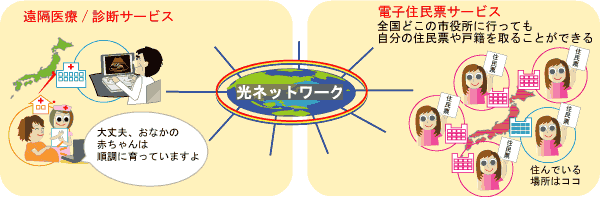
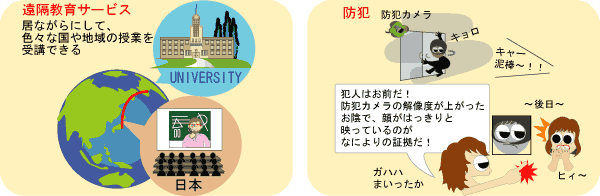
小話(空はなぜ青くて、夕焼けはなぜ赤いのかな)
空はなぜ青くて、夕焼けはなぜ赤いのかな
空がなぜ青く見えるのか、考えた事はありますか?
空が青いのにはちゃんと理由があります。光は波長によって、色が違います。(波長のお話は、この文章をクリックしてください) 太陽光は、地球の空気層(大気圏)に入ると空気中の細かいチリ(注)にぶつかり、光の向きがかわります。つまり、波長の短いもの(赤よりも青の方が波長が短い)は、それだけ細かいチリにぶつかる確率が高いので、あちらこちらに光が散らばりやすいということになります。空が青く見えるのは、波長の短い青い光が空いっぱいに散らばっているからです。
- (注) チリ:このページでは大気を構成する酸素や窒素の分子を示します。
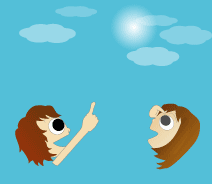
太陽光の波長
太陽の光は白っぽくみえますが、実は赤い光から青い光まで色々な色の光がまじっているのです。つまり太陽光の中でも波長が違うのです。
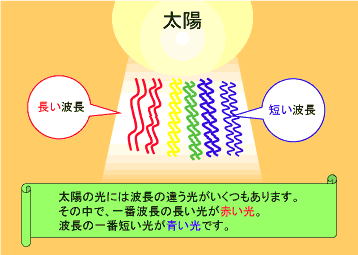
空が青く見える理由(太陽光が細かいチリにぶつかるから)
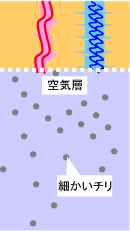
1)太陽光が空気層に突入します。空気層の中には沢山の細かいチリが浮遊しています。
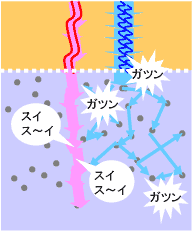
2)波長の短い青い光は細かいチリにぶつかりやすいので、光があちこちに散らばってしまいます。
一方、波長の長い赤い光は細かいチリの間をス~イスイとすり抜けます。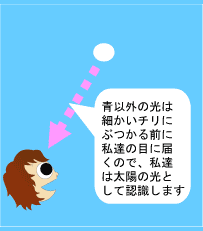
3)青い光が空の上であちこち散らばっているので、遠くから見ている私達には空が青く見えます。
夕焼けが赤いのはなぜでしょう
いままで青かった空が夕方に赤く見えるのはどうしてでしょうか。これは、太陽光の空気層を通る距離に関係があります。太陽は沈むにつれて、太陽の位置が私達の真上から横に移動します。そうすると、太陽光の空気層を通る距離は、真上に比べて横の方が距離が長い為、いままで細かいチリの間をすり抜けてきた波長の長い赤い光も、細かいチリにぶつかり散らばり始めます。青い光は波長が短い為、遠くまで光は届かず、私達には赤い光のみが散らばった空が目にうつるので、夕焼けの空が赤く見えるのです。
以上のように、夕焼けが赤く見えるのは、厚い空気の層を通っても長い波長の光は、散乱されにくくて遠くまで伝わる性質があるからです。光通信でも光ファイバーの中での散乱を少なく遠くまで伝わるように、少し波長の長い光を使っています。
予備知識(波長ってなんだろう)
波長ってなんだろう
『波長』とは、字のごとく『波の長さ』です。この『波』を持っているものの中には、音波や電波、光などがあげられます。波長は一つの波から次の波までの『一波(ひとなみ)』分の長さを指します。
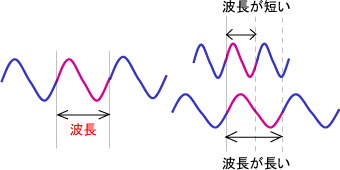
波長の違いが身近なところでわかります。例えば、色の違いや音の高低の違いは、波長の「長い」「短い」で決まります。
| 色 | 短い・・青色に近い
長い・・赤色に近い | 音 | 短い・・女性の高い音
長い・・男性の低い音 |
電磁波の仲間
電磁波は波長によって色々な名前で呼ばれています。光通信で使う電磁波の波長は1.3ミクロンや1.55ミクロンで、赤外線の一種です。
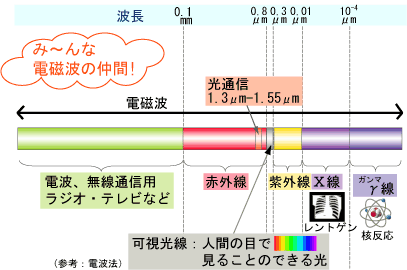
関連リンク
プレスリリース
- 超高速光スイッチによる光雑音の低減に成功 ~毎秒107ギガビットの光信号処理で実証~(2008年3月6日)
- 世界初、超小型集積光スイッチモジュールの開発に成功~8ポート入力・1ポート出力で小型化・省電力化を実現~(2008年2月26日)
- 次世代スーパーコンピュータ向け超小型光リンクモジュール技術を開発 ~業界標準製品の10分の1に小型化~(2008年2月15日)
- DQPSK方式による毎秒40ギガビットの光送受信技術の開発に成功 ~超大容量の都市間光ネットワークを実現~(2007年4月5日)
- 波長可変レーザー素子の開発に成功 ~DWDM光ネットワーク用小型光トランシーバーで動作確認~(2007年3月30日)
- 40Gbps光伝送システム用DQPSK LN変調器を販売開始 ~世界最小の低駆動電圧(4.0V)での動作を実現~(2007年3月27日)
- 高性能なG-PON光伝送が可能な小型光トランシーバの販売開始 ~広い温度範囲(-40℃~85℃)に対応した製品としては世界初~(2007年1月19日)
その他