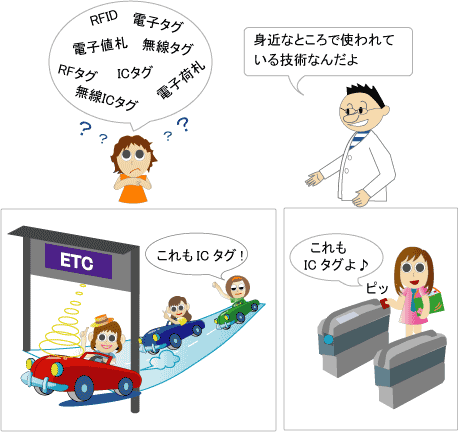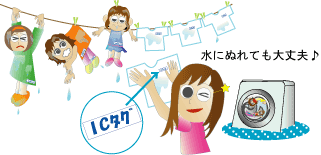ICタグシステム

ご利用にあたっての注意
この講座の内容は、2008年当時の情報 です。予告なしに更新、あるいは掲載を終了することがあります。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2008年4月1日
ICタグシステムってなんだろうし
ICタグシステムってなんだろう
ICタグを付けることにより、モノや人を電子的に識別できるようにします。ICタグに登録した情報を管理するネットワークやコンピュータを含めたシステム全体のことをICタグシステムと呼びます。
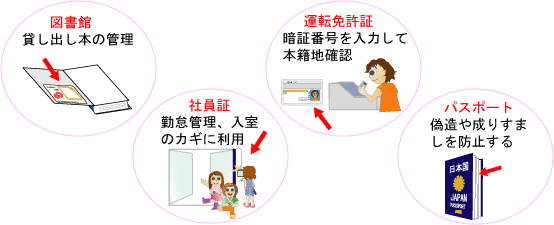
パッシブ型のICタグは、アンテナから受信した電波エネルギーを電力に変換します。その電力を使ってICタグに記録してある情報をアンテナに送ります。また、コンピュータからリーダライタ(情報を読み取ったり書き込んだりする装置)を介して、ICタグに情報を書き込むこともできます。
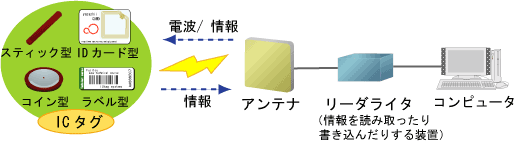
ICタグってどんなもの
情報を記録するICチップ(集積回路)と無線通信用アンテナを組合わせた小さなタグ(札)です。
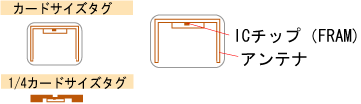
(ICタグには3種類あります)
- アクティブタグ電池が入っているので、自ら情報を発信します。
(通信距離は20メートル) - パッシブタグ電池が入っていないので、アンテナから届いた電波を電力に変えて動作します。
(通信距離は数メートル) - セミパッシブタグ電池が入っているが、自ら電波を発信しません。電池で受信回路やセンサーを補助しています。
富士通研究所で開発したICタグの6つの特長
富士通研究所で開発したICタグの6つの特長
(説明1)UHF帯は、周波数300メガヘルツから3000メガヘルツの電波のことをいいます。
(説明2) ![]() FRAMは、やさしい技術講座の中で紹介しています。ご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。(424 KB)
FRAMは、やさしい技術講座の中で紹介しています。ご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。(424 KB)
1. パッシブタグ型を採用
電池が入っていないパッシブタグを採用しています。
(アクティブタグの研究もしています)
2. UHF帯(950メガヘルツ~956メガヘルツ)の周波数を使用
アンテナからICタグまでの距離が4m位まで検出可能です。
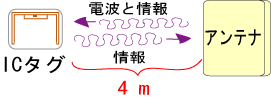
3. FRAMを使用
たくさんの情報を記憶できます。FRAMは電子データを記憶しておくメモリの一種で、その容量は64キロバイトです。
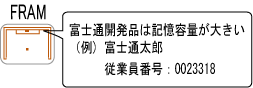
4. セキュリティ対応
メモリを小分けしてパスワードをかけることができます。
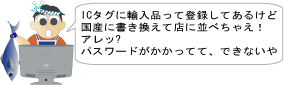
5. アンチコリジョン対応
複数のタグを同時に検出可能です。
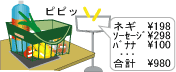
6. トレーサビリティ対応
商品の履歴をたどることができます。
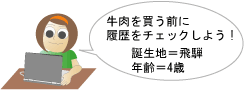
日常生活
普段の生活のなかでICタグシステムを取り入れた例を3つ紹介します。(「図書館の本の管理」と「デパートの商品管理」「盗難防止」)
図書館の本の管理
図書館では現在すでにICタグシステムが導入されているところもあります。
読取機の上に本を置いたり、かざしたりするだけで、複数ある本の情報を瞬時に読み込むことができます。そのため、本を借りる際に窓口に並ぶ手間や、本を管理する為に一冊ずつ開く手間が省け、図書館を利用する側も、運営する側も、お互いに便利になります。
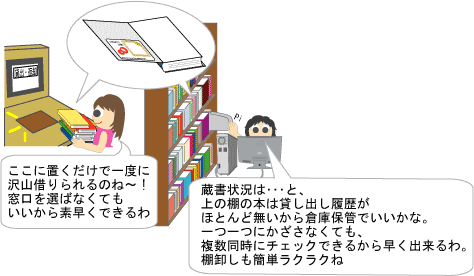
デパートの商品管理
ICタグはデパートの商品管理をするのに最適です。
商品にICタグを装着すれば、お客様の欲しい商品の在庫確認、納品時期を瞬時に把握できるため、適切な素早い対応が可能になります。
1)お客様からの要望を受け付ける
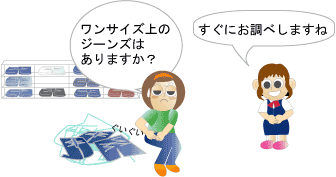
2)在庫状況の確認
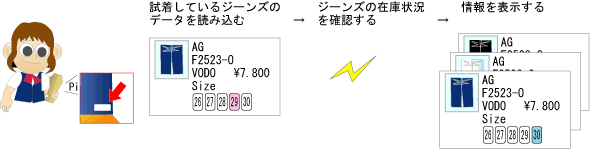
3)対応

盗難防止
高級品(高級時計、宝飾品等)の荷札(または値札)にICタグをつけて盗難を防止します。

制服や寝具の管理
リネン製品に縫い付けることのできるICタグを、富士通では「リネンタグ(補足-1)」と名づけました。制服や寝具の貸し出し、返却、クリーニング、管理までを一括して行うことができる、抜群の耐久性をもつ業界初の「UHF帯RFIDリネンタグ」の特長と利用シーンを紹介します。
( 補足-1)リネンとは、亜麻(あま)の繊維を原料とした織物のことをいいます。
「UHF帯リネンタグ」の特長
- 小さい
目立たない場所に縫い付けられます。 - 一括読み取り可能
一度に数十枚から数百枚を検品できます。(枚数は電波の環境により異なります) - 耐水性がある
水にぬれたままで読み取れます。 - 耐薬品性がある
約100回のアルカリ性薬品による洗浄にも耐えます。 - 耐圧力がある
半径1mの筒状のものに、8トンの重さをかけて脱水する業務用脱水機にも耐えます。 - 耐熱性がある
アイロンの温度(最高200度)に耐えます。

利用シーン
制服や寝具の回収、クリーニング、管理までの工程をご紹介します。
1)リネンタグが取り付けられた使用後の制服や寝具を回収します。まず、トンネルゲートを通って枚数を確認します。
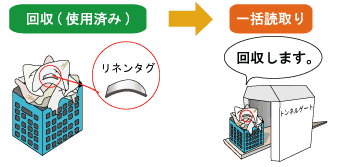
2)洗浄、漂白、殺菌、すすぎをします。終わったら、トンネルゲートを通って枚数と洗浄工程が完了したことを確認します。
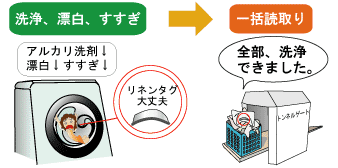
3)脱水をします。脱水は、1平方メートルあたり車一台分くらいの強い力で圧縮され、水分が取り除かれます。 終わったら、トンネルゲートを通って枚数と脱水工程が完了したことを確認します。
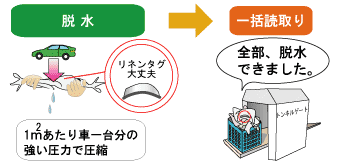
4)アイロンをかけます。アイロンは最高200度まで温度が上がります。終わったら、トンネルゲートを通って枚数とアイロン工程が完了したことを確認します。
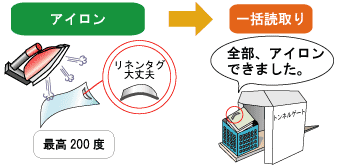
5)倉庫で管理します。リネンタグがついているので、簡単に在庫管理できます(盗難防止にもつながります)。
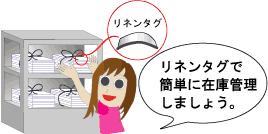
工場1
工場で使う部品の入出庫の管理の例を紹介します。
部品の入出庫管理
工場で使用する部品の伝票などに、ICタグが貼り付けられたリライタブルシートを使います。印字・消去を繰り返し500回程度可能です。ICタグの中の情報を表示、人の目でも確認でき、紙の削減にもなります。
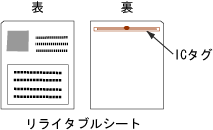
- A工場では、B工場で作る製品の部品を製造しています。B工場の製造ラインで必要な部品情報をICタグに記録した部品要求票を読取り機に入れると、ICタグの情報が直ちにネットワークを介してA工場へ送られ、次の部品要求票が自動的に発行されます。
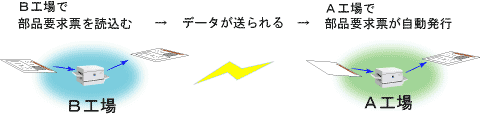
- A工場で部品要求票をもとに部品を用意し、部品要求票を箱に貼って出荷準備を行います。
ICタグのアンテナが設置されているゲートを部品要求票を貼った荷物が通ると自動的に一括読取りされ、出荷数をカウントし、出荷処理が完了します。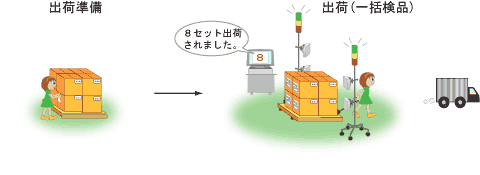
- B工場に到着した荷物は、ICタグのアンテナが設置されているゲートを通過するだけで一括読取りされ、入荷数をカウントし、入荷処理が完了します。
部品に不良がないか品質検査します。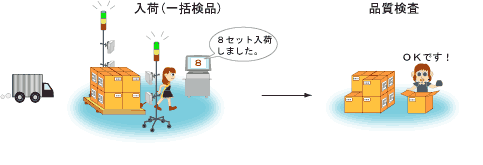
- 検査を合格した部品を必要な場所へ運び、工場内での搬送ミスや数量ミスを防ぐため、ハンディの読取り機で、入庫処理をします。
製造ラインへ部品を供給した際、箱についている部品要求票を読取り機に通し、ICタグ情報をA工場へ送ります。A工場にて受け取った情報は、自動的に部品要求票に印刷され、部品供給を依頼します。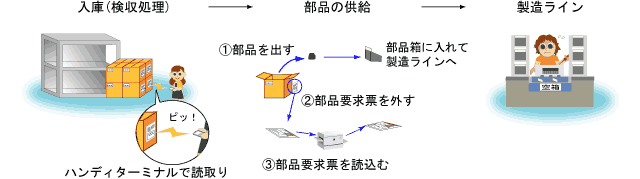
工場2
工場で使う部品を必要な時に必要な分だけ供給する「ジャストインタイム」と、ICタグを貼り付ける箇所が金属の場合に使う「金属対応ICタグ」の例です。
ジャストインタイム
製造ラインへの部品供給方法を改善できます。従来は、入庫した部品を部品棚に並べ、要求に合わせて供給を行い、製造ラインへまとめて運搬していました。
ICタグシステムの導入により、倉庫から製造ラインへジャストインタイム(必要な時に必要な分だけ)で供給することができるようになりました。これにより。無駄な在庫をなくすことができ、供給情報の入力工数も削減できます。空になった部品箱の数から、組み立てられた製品の数もリアルタイムでわかります。
部品箱にICタグをつけます。
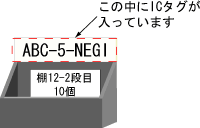
- 部品箱に指示通りに部品を入れ、倉庫から製造ラインへの移動時にICタグのアンテナが設置されているゲートを通過します。その時、自動的に部品箱のICタグを読み取り、倉庫から製造ラインへ供給された部品の情報をサーバに送ります。
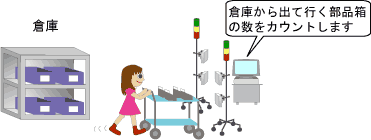
- 製造ラインの決められた場所へ部品箱を置いていき、同時に空箱を回収します。倉庫へ戻る時にICタグのアンテナが設置されているゲートをくぐります。部品箱のICタグを読み取って、倉庫から出て行った数と照合します。
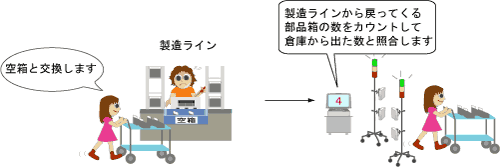
金属対応ICタグ
金属に直接ICタグを貼り付けると、金属とICタグが干渉して読み取れませんでした。
金属に貼り付けても読み取れるICタグを開発しました。例えば、ノートパソコンの本体にICタグを貼り付けて管理することも可能になります。
通常は、ICタグの発している電界を情報としてリーダアンテナが読み取ります。ICタグを金属に貼り付けると、金属が干渉して電界が弱くなり、リーダアンテナに情報を発信できなくなります。
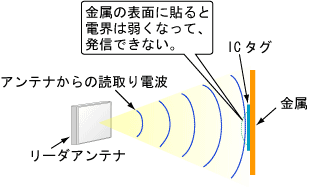
金属対応のICタグは、形を少し厚めにして、ICタグのアンテナを工夫することで、金属に貼り付けてもリーダアンテナに情報を発信することができます。
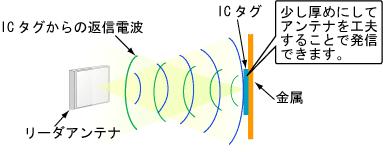
将来
「書類を積み重ねた状態での読み取り技術」と「小型・コストダウン」です。
書類を積み重ねた状態での読み取り技術
UHF帯のICタグは、アンテナとの距離が長くても情報を読み取れるのがメリットですが、逆にタグ同士が重なりあった場合、干渉しあってしまい読み取れません。
そこで、書類が積み重なった状態でも、ICタグの情報を読み取ることができれば法律事務所や保険会社など、重要書類を沢山保管しなければならない会社の棚卸や、また重要書類が無くなっていないかのチェック(セキュリティ)で活躍できます。
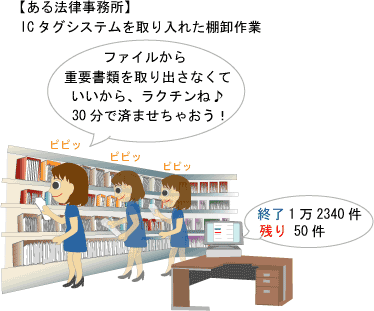
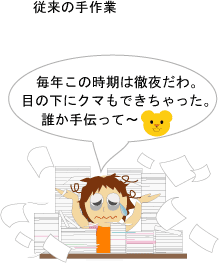
小型化・コストダウン
ICタグを更に小型化し、値段も安くなると、製造現場における部品の自動供給も可能になります。

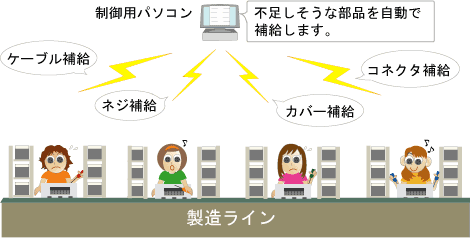
小話
ICタグ、電子タグ、RFタグ、色々聞くけど何が違うんだろう
この講座で使っているICタグは「Integrated Circuit Tag」で、日本語に直訳すると「集積回路札」となります。集積回路というのは、情報を保存したり、書き換えたりすることができる電子部品で、つまり、情報を読み書きできる札(ふだ)ということになります。情報を読み書きできる札(ふだ)は、世の中に沢山あり、まだ定着した決まった呼び方がなく、みんなが色々な言い方をしているため、いろんな単語が飛び交っているのです。例えば、電子値札、電子タグ、無線タグ、無線ICタグ、ICタグ、RFタグなど。
「電子タグ」や「無線タグ」などと聞くと、難しい感じを受けますが、例えばテレビのコマーシャルで紹介されている「おサイフケータイ」や電車の切符の代わりや買い物もできるカードと聞くと「あ、聞いたことある」または「使っている」という人も多いはずです。また、車好きの人には「ETC(高速道路に設置してある料金の自動支払いシステム)」も代表的なICタグの一つというとわかりやすいと思います。
そして、それらのタグという単語の近くで、「RFID」という言葉も聞いたことがありませんか。これは「Radio Frequency IDentification」の略で、電波(RF)を利用して(接触せずとも)個々を識別(ID)することができる「自動認識技術」の総称です。上に書いた色々な呼び方のタグは全て自動認識技術を使っているので、RFIDを利用したモノということになります。