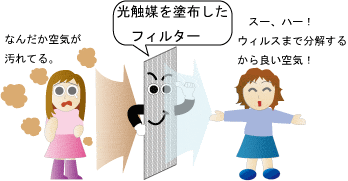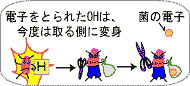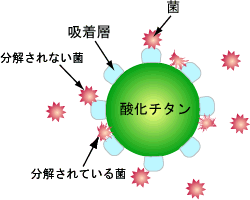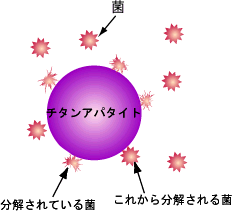光触媒技術

ご利用にあたっての注意
この講座の内容は、2009年当時の情報です。予告なしに更新、あるいは掲載を終了することがあります。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2009年1月22日
光触媒ってなんだろう
触媒ってなんだろう
化学薬品などの合成の時によく利用されます。例えば薬品AとBからDを作ろうとしています。その時に、より効率良く早く合成できるように少量のCという触媒を加えます。触媒自体は、合成するための反応を良くする働きをするだけで、合成の前と後でもCという触媒の形は変わりません。
AとBからDを作るのに20分かかります。
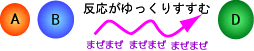
AとBからDを作るのに5分で済みます。
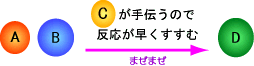
これは、触媒であるCがなくても作れますが、Cがあることによって早く作れるという効果があります。
別の場合で、触媒で反応を遅らせるということもできます。
触媒とは、そのもの自身は、反応の前後で変化しませんが、反応を促進する働きがあります。
光触媒になるとどう違うんだろう
そのもの自身が反応の前後で変化しないのは同じですが、この反応を促進する働きが光エネルギーを吸収した時だけに起こるものを光触媒と呼びます。
太陽光や蛍光灯等から発せられる紫外線を浴びるとその光エネルギーに反応して、空気中に浮遊する臭い、菌やウイルス、汚れなどの有機物を水と二酸化炭素に分解する働きをします。光エネルギーを使って環境を浄化します。
| 光触媒を使った物 | 効果 |
|---|---|
| 空気清浄機、エアコン、掃除機、食器乾燥機 | 脱臭機能:タバコの臭い成分などを分解する。
抗菌機能:ウイルス、細菌を捕まえて分解する。 |
| 照明器具 | 表面にタバコのヤニや油汚れが付着して明るさが落ちてしまうのを防ぐ。 |
| 車の排気ガス | ガスの中に含まれる窒素酸化物(NOx)を除去する。 |
| 水路や浴室のタイル | 微生物がだすヌメリや悪臭を分解する。 |
身近にあるもので昔からある光触媒反応の例
植物の葉に含まれる葉緑素による光合成が、昔からある光触媒反応です。
二酸化炭素と水だけでは、葉緑素の反応は起こりません。葉緑素が太陽光を浴びることで反応が起こり、二酸化炭素と水から、酸素とデンプンを生成します。
葉緑素自身は、反応の前後で変化していません。太陽光の光エネルギーを使って、そこにあるものを分解して、別のものに生成しなおしているだけです。
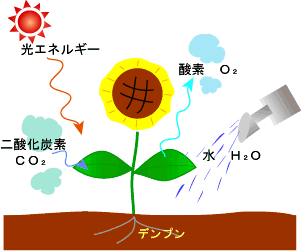
光触媒材料が汚れなどを分解する原理 -汚れや菌が分解されるサイクル-
光触媒材料の上に付着した汚れや菌が分解されるサイクル
光触媒材料の上に付着した汚れや菌が分解されるサイクルを紹介します。
- 1. 通常、空気中の水分が光触媒材料の上に薄い膜となって付いています。
- 2. そこへ汚れや菌が常に降ってきます。
- 3. 汚れや菌が付着します。
- 4. 紫外線(光)を当てます。紫外線(光)は、汚れや菌を通過して光触媒材料に吸収されます。その紫外線(光)のエネルギーによって、光触媒材料の表面の水H2OがHとOHに分解します。そのOHが汚れや菌を攻撃します。
- 5. OHに攻撃された汚れや菌は、水と二酸化炭素に変化し始めます。
- 6. 最終的に、水と二酸化炭素は蒸発して、光触媒材料の表面には何もなくなります。
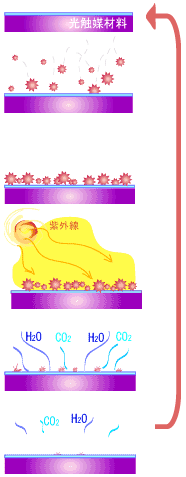
光触媒材料が汚れなどを分解する原理 -光エネルギーを吸収したときの様子-
光触媒材料が光エネルギーを吸収したときの様子をイメージ図を使って説明
光触媒材料が光エネルギーを吸収したときの様子をイメージ図を使って説明します。
登場するキャラクタ
1. 光エネルギーを吸収する前は、光触媒材料の中の原子と電子は結びついて安定している状態です。
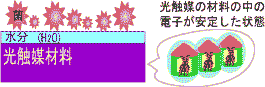
2. 光エネルギーを吸収した光触媒材料の中の電子は力が有り余って、安定した位置から飛び出し、電子と電子が抜けた孔(ホール)に別れます。
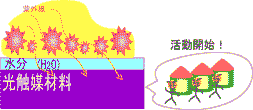
3. 飛び出した電子は空気中の酸素と結びつきます。
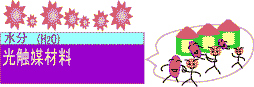
4. 残った孔(ホール)は光触媒材料の表面の水H2Oから電子を呼び込んで安定した状態に戻ります。
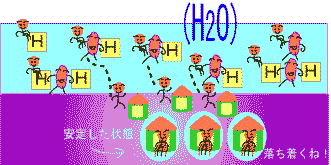
5. 逆に電子を取られた水から生成したOHは何とか電子を取得しようと、汚れや菌の中の電子を取りにいきます。汚れや菌は炭素や水素からできており、それらは電子によってお互いに結びついた状態なので、その電子を取られてしまうと、炭素や水素がバラバラになります。バラバラになった炭素や水素は空気中の酸素と結びつく(酸化する)ので、水や二酸化炭素になり、蒸発して全てなくなります。
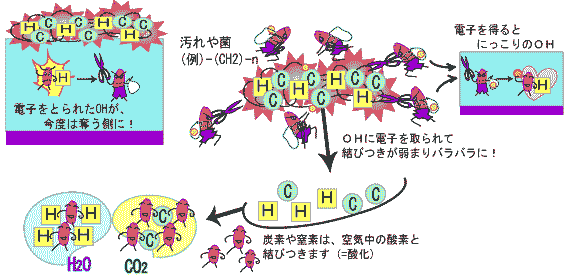
光触媒チタンアパタイトってなんだろう
チタンアパタイトってなんだろう
人間の歯や骨に含まれるカルシウムヒドロキシアパタイトを主成分とする新しい光触媒材料です。
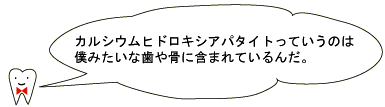
カルシウムヒドロキシアパタイト Ca10(PO4)6(OH)2 の成分にチタンを混ぜて作るとカルシウムの1つがチタンに置き換わることでチタンアパタイト TiCa9(PO4)6(OH)2 になります。このチタンアパタイトが光触媒の働きをします。
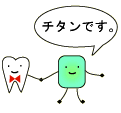
Ca10(PO4)6(OH)2

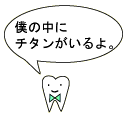
TiCa9(PO4)6(OH)2
カルシウムヒドロキシアパタイトの時に持っていた性質で物を吸着するという力があります。そこへチタンを加えたことで、紫外線が当たると菌や有機物を分解する力が加わり、今までにない吸着力を持った新しい光触媒が生まれました。
作り方
(1)チタンアパタイトの材料になる。チタン、カルシウム、リン酸を水に溶かします。
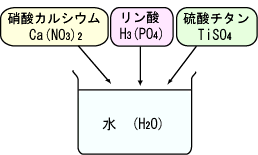
(2)水の中に入れると、それぞれに結合していた成分がバラバラになり、酸性の水溶液ができます。
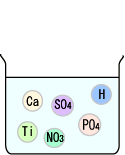
(3)ここにアンモニア水などを入れて水溶液の性質をアルカリ性にします。そうすると溶けている成分が反応し始め、安定な形になろうと結合を始めます。
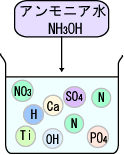
(4)結合した成分のうちチタンアパタイトは、結晶となって沈殿します。
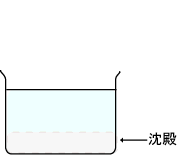
(5)この沈殿した結晶をろ過して、こし取ればチタンアパタイトを取り出せます。
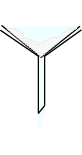
(6)チタンアパタイトは、白くて細かい粉末です。

特徴
チタンアパタイトと、酸化チタンとの比較
当社と東京大学先端科学技術研究センターで開発した新しい光触媒材料チタンアパタイトと、従来からある光触媒材料の酸化チタンとを比較してみます。
| 酸化チタンの特徴 | チタンアパタイトの特徴 |
|---|---|
吸着層に菌が大量に付着し、これ以上吸着できなくなっている。 |
|
|
|
チタンアパタイトのその他の特徴
暗所抗ウイルス性
紫外線がないと分解しませんが、吸着能力は常にあるので、光が当たっていない時でも、ウイルスを吸着し、不活性化して、動けなくさせます。その後、紫外線が当たった時にそのウイルスの死骸を分解します。
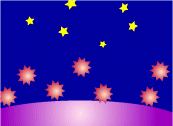
製品
実用例と将来
 現在
現在
空気清浄機の中のフィルターに使用されております。
(チタンアパタイトの粉をフィルター表面に付着させています)

その他に感染予防マスク(Fitty)やフェイスケアマスク、抗菌まな板、エアコンなどがあります。
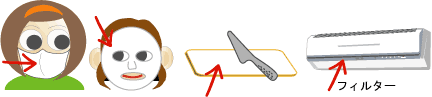
 将来
将来
携帯電話や携帯端末、パソコンのキーボードやディスプレイなどに使用予定です。

小話
研究成果を自分の鼻で実感
光触媒を研究しているグループには、しなければいけない仕事のひとつに「においをかぐ」という作業があります。光触媒材料がにおい成分を分解しているかどうかは、二酸化炭素の量を計ればわかることですが、基本は実際に人間がわかるにおいを分解していることが重要です。
そこで、グループのNさんが魚の生ぐさいにおいの分解能力を測ろうと、実験する魚(イワシだったそうです)を事務所の机の引き出しにいれておきました。(季節は夏・・・。容易に予想ができますね)
魚はすぐに腐り、においを発し始めました。
周囲の人間は、「なんかにおうな」と思っていましたが、まさか机の中に魚が入っているとは誰も想像しませんよね。(Nさん本人は別の用事で席をはずしていました)
夏だし、どこからか生ぐさいにおいが流れ込んじゃったのだろう、ぐらいの気持ちでした。そのうち、においがひどくなり、はじめは「自分かな」と思いましたが、それにしてはくさすぎます。

グループのメンバーはどうもNさんの机の中からにおうことをつきとめ、おそるおそる引きだしをひいてみるとすごいことに・・・。
フロアーの半分はすでににおいが充満していましたが、研究員は忍耐強いのか苦情はまだ出ておりませんでした。そそくさと実験室に運び、密閉できる専用のボックスにいれて、臭いをはかりはじめました。
一度、キョーレツなにおいをかいでしまったメンバーは誰もそのにおいをかぎたがりません。
しかし、そこは仕事ですから、複数名が決まった時間に臭いをかぎ、鼻がもげちゃいそうなくさいにおいに耐え、自分の開発しているものを自分自身の鼻で実感した出来事でした。
涙がにじんでいたのは、うれしかったのかくさすぎたのか。
(Nさんの机の引き出しのにおいはどうやって消し去ったのでしょうか。やはり引き出しにも光触媒の材料を敷き詰めたのでしょうか。取材に伺った時は、においませんでした。by執筆者)