Fujitsu Tech Open House 2025 Report : AIと量子コンピューティングの融合が切り拓く未来
2025年6月26日
English
AIと量子コンピューティングの融合は、私たちの未来に何をもたらすのでしょうか。富士通は、この問いに机上の空論ではなく、具体的な実装を通して向き合っています。そして、「Fujitsu Tech Open House 2025」では、富士通とパートナー企業との協業がもたらす可能性という新たな問いが浮かび上がりました。6月4日、Fujitsu Research of America, Inc.で開催されたイベントでは、最先端技術と共創が融合することで生まれる、革新的な未来の姿が示されました。
本イベントには、AI、量子コンピューティング、オープンイノベーションの未来を切り拓くという共通のビジョンを持つ、業界リーダー、スタートアップ、大学研究者など、多様な分野の専門家が集結しました。Venkatesan Guruswami教授(米カリフォルニア大学バークレー校)とのFireside ChatやTechnology Showcase、その他の講演を通じて、富士通がどのようにオープンイノベーションを推進し、社会やビジネスにおける課題解決に取り組んできたのかを紹介する機会となりました。
富士通の技術革新とビジョン

富士通は1935年に通信企業として創業して90周年を迎え、研究開発を通じて数々の技術革新を生み出してきた歴史があります。Fujitsu Research of America, Inc.のCEOであるIndradeep Ghoshは開会の挨拶で「私たちのビジョンは『信頼を軸に持続可能な世界を創造する』こと」と語り、技術開発を通じた社会貢献の姿勢を強調しました。
Fujitsu Research of America, Inc.は1993年の設立以来、30年以上にわたってシリコンバレーにおける最先端の研究を牽引してきました。世界20か所に広がる研究拠点と、1,000人を超える研究者、年間10億ドル以上の研究開発予算をもとに、AI、量子コンピューティング、コンピュータアーキテクチャ、ソーシャルデジタルツインといった領域で技術革新を推進しています。
こうした規模に加え、私たちの特長は、戦略的パートナーとの連携と共同開発を通じて、研究成果を現実の課題解決に結びつける「実装力」にあります。
パートナーとの協創が拓く新たな可能性

駒月 拓人(富士通株式会社ビジネスインキュベーション統括部長)は、「これまでにスタートアップ企業との共創実績は240件を超えています」と語り、その規模と意欲の大きさが印象的でした。
さらに、社会課題の解決に取り組むスタートアップへの「インパクト投資」を通じた共創を加速すべく、150億円(約1億ドル)の第2コーポレート・ベンチャーキャピタル・ファンドを新たに設立。これにより、富士通の投資枠は合計で250億円(約1億7200万ドル)へと拡大しました。これは単なる資金投入にとどまらず、脱炭素や循環型経済といった社会課題への本質的なアプローチを支える戦略の一環です。
また、Fujitsu Uvance Kawasaki Towerに新設された「Fujitsu Open Innovation Center」は、共創をさらに推進するための拠点として注目を集めています。この施設では、スタートアップが自由に利用できる打ち合わせスペースや共創エリアを提供し、イノベーションを阻む物理的な障壁を取り除くことで、密な連携とブレイクスルーの創出を支援しています。
AIインフラの課題に挑む「AI Computing Broker」


富士通の「イノベーションとパートナーシップの融合」を体現する取り組みの一つとして、Matthias Loipersberger(Fujitsu Research of America, Inc., Product Manager)が「AI Computing Broker」技術を紹介しました。
近年、AIインフラへの投資は急速に拡大しており、2027年には世界全体で1,000億ドルに達すると見込まれています。しかし、多くの企業においてGPUのピーク利用率は依然70%未満にとどまっており、その非効率性が課題となっています。
こうした現状に対し、「AI Computing Broker」は、GPUの利用効率を抜本的に高める技術であり、「この仕組みは、AIフレームワークの実行状況をリアルタイムで監視し、必要なときにだけGPUを割り当てるというもの」とLoipersbergerは語ります。ジョブごとにGPUリソースを動的に割り振ることで、アクティブなプログラムには常にメモリ全体へのアクセスを保証しつつ、最大限の効率を引き出します。このアプローチにより、GPUの全体的な稼働率が向上し、処理時間も大幅に短縮されます。さらに、PyTorchやTensorFlowといった既存のフレームワークにも対応しており、実際の業務環境への導入が容易である点も大きな特長です。
この技術は、現実の企業課題に応える実践的なソリューションとして、富士通の「社会実装を前提とした先端研究」の姿勢を強く印象づけるものでした。
材料開発を加速するAI活用
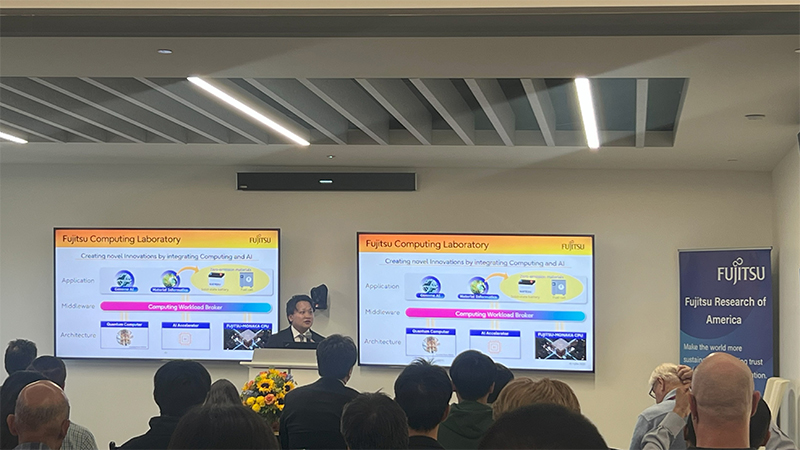
岩崎 有登(富士通株式会社コンピューティング研究所)は、AIと高性能計算の融合が材料科学に革新をもたらしている現状について紹介しました。「Neural Network Potentialsを活用することで、シミュレーションを最大で100倍から1万倍高速化することが可能」と語り、AIの活用によって製品開発サイクルを大幅に短縮できることを強調しました。
また、燃料電池向けの高分子電解質膜を題材としたケーススタディを紹介。2万個の原子を含むシステムのシミュレーションを実現した事例を通じて、こうした大規模な解析がすでに可能であることを示しました。さらに、計算リソースを拡張するだけで、より多くの有用な材料を効率的に評価できる点も、本技術の大きな魅力です。
これにより、材料探索や最適化の可能性が一気に広がり、今後のものづくりにおけるスピードと品質の両立に貢献することが期待されます。
次世代プロセッサ「FUJITSU-MONAKA」の可能性

妹尾 日出男(Fujitsu Research of America, Inc., 先端技術本部Director)は、次世代ARMベースプロセッサ「FUJITSU-MONAKA」を紹介しました。これは、高性能計算の分野で数十年にわたり積み重ねてきた技術の集大成ともいえる成果であり、スーパーコンピュータ「富岳」にも採用された技術を基盤としています。「富岳」は、2020年以降もGraph500といった主要ベンチマークで世界1位を維持しており、富士通のプロセッサ技術の優位性を物語っています。
FUJITSU-MONAKAは、こうしたHPC向け技術を、より汎用的なエンタープライズ用途に展開するために設計されており、「富岳」クラスの高性能と省電力性を、企業のデータセンターでも実現可能にします。2030年には世界のデータセンターが地球全体の電力の9%を消費すると予測される中、FUJITSU-MONAKAのようなエネルギー効率に優れた設計は、持続可能なコンピューティングインフラにとって不可欠な存在となるでしょう。
512ビットSIMD演算に対応し、HPCとAIの両方のワークロードをこなす柔軟性、高帯域のメモリ、高いスケーラビリティを誇るマルチコアアーキテクチャなど、FUJITSU-MONAKAはエンタープライズにおける計算処理のあり方を変革する可能性を秘めたプロセッサです。
量子の可能性と実装に向けた第一歩


本イベントで注目を集めたセッションの一つが、Indradeep Ghosh(Fujitsu Research of America, Inc., CEO)とVenkatesan Guruswami教授(米カリフォルニア大学バークレー校, Interim Director and Senior Scientist at Simons Institute for the Theory of Computing and Chancellor's Professor of Computer Science)によるFireside chat。富士通が取り組む「フルスタック量子戦略」―量子状態の制御からデバイス統合、ソフトウェア、アプリケーションに至るまでの包括的なアプローチについて議論しました。その中で、理化学研究所との共同開発による64量子ビットの量子コンピュータ、さらに2025年第1四半期に外部利用が可能となった256量子ビットの大型量子コンピュータなど、富士通の量子技術は世界最先端の水準にあることにも言及されました。また、富士通のダイヤモンドスピン量子技術は、モジュール型アーキテクチャを採用することで、スケーラビリティにおいて特に大きな可能性を持っており、1ケルビン以上の高温環境での動作を可能とするなど、実用性の高い構成を実現している点にも触れました。各モジュールは、ダイヤモンド内の電子スピンおよび核スピンで構成され、モジュール間はフォトニックリンク(光通信)によって接続され、これにより、拡張性と実用性を兼ね備えている今後の量子インフラの基盤となる可能性を示唆しました。
Technology Showcase:研究と現場がつながる、技術革新のいま


本イベントでは、富士通の研究所やパートナー企業との共創から生まれた先進技術を一堂に展示する「Technology Showcase」も実施。中でも注目を集めたのが、製造業向けの設計時間を「60分からわずか5分へ」と短縮できる、領域特化型の大規模言語モデル(LLM)のデモンストレーションです。高度な設計知識を誰でも扱えるようにするこの技術は、まさにAIによる現場改革の象徴といえます。
これらの展示技術は、研究成果を実社会に役立てるという富士通の姿勢を体現するものです。単なる技術的な進歩にとどまらず、それぞれが研究チームと業界パートナー、そしてスタートアップとの緊密な連携のもとで磨かれてきました。技術と実務の架け橋を担う「共創」の力が、ここには詰まっています。
未来を支える「Computing as a Service」構想
富士通のビジョンは、個々の技術開発にとどまりません。AI、高性能コンピューティング(HPC)、量子インスパイア技術、量子コンピューティングといった先端技術群を一体化させた「Computing as a Service」プラットフォームの構築を目指しています。これにより、企業は複雑な技術基盤を自前で持たずとも、最先端の計算力にアクセスできるようになります。また、各技術が連携することで、個々の性能が相乗的に引き出される点も大きな特長です。AIコンピューティングブローカーは計算資源の最適化を実現し、材料シミュレーションは新素材の探索を加速。FUJITSU-MONAKAプロセッサは省電力かつ高性能な演算環境を提供し、量子技術は従来の計算手法では解けない課題に挑みます。
さいごに:パートナーシップが生む未来のイノベーション
冒頭でも触れたように、Fujitsu Tech Open House 2025で示された最も重要な問いは、「AIと量子コンピューティングの出会いが、未来に何をもたらすのか」だけでなく、「富士通とパートナーの協業がもたらすものは何か」ということでした。その答えは、富士通だけでは成し得ないイノベーションの可能性が飛躍的に広がることにあります。
AI Computing BrokerによるGPU活用の課題解決から、次世代プロセッサFUJITSU-MONAKA、そして進化を続ける量子コンピューティングシステムまで、私たちの研究成果は着実に実績を積み重ねています。しかし、それらが真に社会や企業の課題解決に結びつくのは、パートナーシップと協創によって初めて可能となります。
今後も富士通は、オープンイノベーションや協働開発、パートナーシップを軸とした成長に注力し、複雑化する社会課題や企業課題の解決に挑み続けます。業界の先駆者、学術界の研究者、そしてイノベーションを推進するリーダーの皆様と共に、技術の可能性を探求し、新たな成長と発見への扉を開いていきたいと考えています。信頼あるイノベーションと協働を通じて、再生的かつネット・ポジティブな世界の実現を目指します。



