Fujitsu Tech Open House 2024 Report
2024年10月28日
English
今年初めて開催した当社Tech Open Houseは、AIや量子コンピューティング、オープンイノベーションの未来に向けた新たなビジョンを発信する場となった。基調講演、米国富士通研究所CEOによる講演、Fireside Chat、ライブデモを通じて、当社が技術戦略をどのように進化させ、ビジネスおよび社会の課題解決に向けてオープンイノベーションを取り入れているかを共有し、業界リーダー、スタートアップ、専門家が一堂に会して、最先端の技術や連携の可能性について議論をした。
富士通の技術戦略

2024年10月3日に開催された本イベントは、当社技術戦略本部長である岡田英人の基調講演から幕を開けた。岡田は、当社が描くAIの未来とその役割についてのビジョンを語り、我々の目標は単に特定のタスクに限定されたAIソリューションを提供するのではなく、持続可能性や社会全体の発展を促進するための広範な変革を目指すものであると強調するとともに、AIを通じて世界的な課題に取り組む姿勢は、単なるビジネス目的のイノベーションにとどまらないとも述べた。
また、本講演は「AIの民主化」への継続的な取り組みについても中心のテーマとして据えており、当社は、AIを人間の能力を引き上げ、業務効率を高め、迅速で賢明な意思決定を可能にするツールとして捉えており、大規模な組織においてもデータを管理し、規制順守を確保しながら成長を促進するための特化モデルを開発した点にも触れた。岡田は、AIを活用したコンサルティングやモダナイゼーションサービスが、この取り組みの鍵であり、当社の「Fujitsu Kozuchi」などのプラットフォームを通じて、業界のニーズに応えていることにも言及した。
特に重要なのは、従来の社内R&Dモデルを超え、スタートアップ、大学、政府など外部パートナーとのエコシステムを積極的に構築している点である旨にも触れ、このようなオープンイノベーションモデルにより、新技術の市場投入を加速し、共にソリューションを創出できるようになった点にも触れた。ジョイントベンチャーや戦略的投資、異業種間のパートナーシップを通じて、当社は迅速なイノベーションと共有の成功を促進するグローバルなエコシステムの構築に取り組んでいることを強調して本基調講演は幕を閉じた。
当社R&D戦略と取り組み
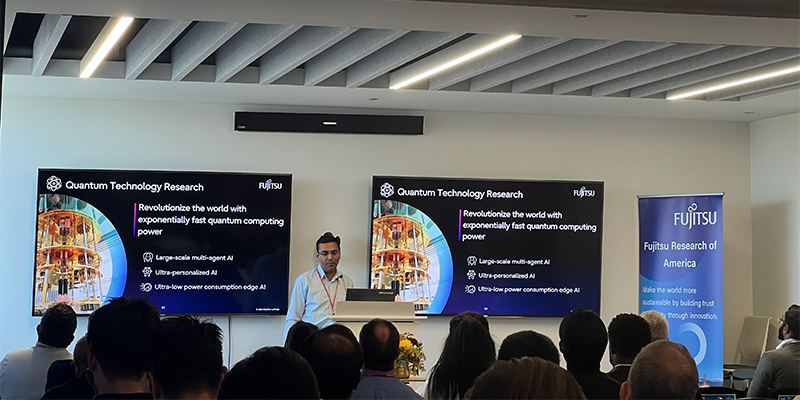
次に、米国富士通研究所のCEOであるIndradeep Ghoshが、当社のグローバルR&D戦略の進展について講演し、当社のイノベーションがどのようにビジネス変革と社会への影響に貢献しているかに焦点を当てて語った。当社の研究ネットワークは世界20か所に拡大しており、1,000人以上の研究者と年間予算10億ドルを超える規模で、AI、量子コンピューティング、セキュリティ、コンバージング技術の技術革新をリードしている点にも言及した。
またIndradeepは、当社のAI研究は、企業向けのAIモデルを活用して、ビジネス課題を解決することに重点を置いているとも述べた。例えば、「ナレッジグラフ拡張RAG」や「生成AI混合技術」「生成AI監査技術」といった主要技術を通じて、企業に大規模データの効果的な活用を提供していることを紹介し、これらの技術により、自動モデル生成やカスタマイズされたソリューションが可能となり、AI出力に対するコンプライアンスと精度を確保する監査機能も導入されており、様々な業界での応用が期待されている点も強調した。
また、AIコンピューティングブローカーの開発についても触れ、GPUの利用効率を最適化し、2030年までにデータセンターが世界の電力消費の10%を占めると予測される中、エネルギー消費の大幅な削減を目指すこの技術は、運用コストの削減と環境の持続可能性の両立を実現する点を力強く語った。
さらに、データセキュリティの分野では、当社はゼロトラストフレームワークやデジタルトラスト技術を活用し、偽情報やAI生成の誤情報の課題に対応している点に言及した。特に、金融、医療、政府といったデータの完全性が極めて重要な産業において、情報の信頼性を確保し、偽情報による脅威から守る取り組みが高く評価されている点にも触れた。
最後に、当社が進めているコンバージング技術分野での取り組みについても触れ、デジタルシミュレーションと人間の行動モデルを融合させた「ソーシャルデジタルツイン」の開発により、スマートシティやリテール領域、インフラ計画における予測モデルが実現され、複雑な社会課題の解決を支援している点にも言及し、AIの先端技術と社会科学の知見を統合することで、意思決定の改善と持続可能な成果を促進する包括的なアプローチを提供していることを説明した。
これらの当社研究領域での取り組み、オープンイノベーションへの当社の強いコミットメントを示すものであり、産業界、大学、研究機関との幅広い協力を通じて、グローバルで意義のある技術革新を推進していることを認識していただける時間となった。
当社スタートアップエンゲージモデル
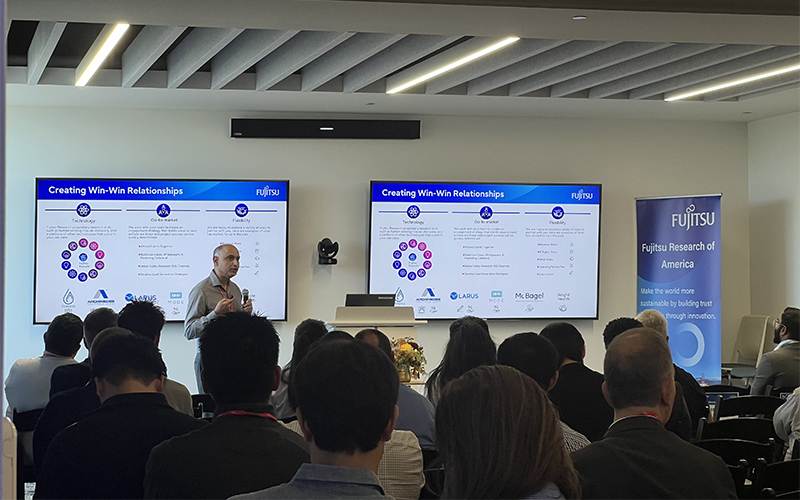
次に、米国富士通研究所のBusiness Incubation Division長であるSurya Josyulaが、スタートアップエンゲージメントモデルに関する講演を行った。Suryaは、Business Incubation部門の責任者として、戦略的投資やライセンス契約、共創を通じて、スタートアップとのWin-Winなパートナーシップをどのように構築しているかについて語り、当社のエンゲージメントモデルは、スタートアップのニーズと当社技術とのシナジーに基づき、多様な協力の形を提供していると語った。
講演の中で、Suryaは当社がこれまでに推進してきたパートナーシップ事例のなかでも、特に注目すべき例として、持続可能なアンモニア合成に焦点を当てた企業「Atmonia」とのコラボレーションについて紹介した。本コラボレーションは、当社高性能コンピューティングとAI技術を統合することで、触媒開発を最適化し、カーボンニュートラル達成に貢献している。また、医療分野での他の例として、スタートアップと協力してせん妄を検出するEEG信号分析ツールを開発し、当社の技術移転モデルがどのようにイノベーションを促進しつつ、スタートアップの成長をサポートしているかという点も述べた。
さらに、当社の富士通ベンチャーズを通じて、AI、量子コンピューティング、クリーンテック、5Gなどの分野で戦略的な投資を行い、持続可能性とイノベーションに対するビジョンに沿うスタートアップを支援している我々の姿勢にも触れ、当社の柔軟なエンゲージメントフレームワークには、収益分配やライセンス、知的財産権、株式持分といった要素が含まれており、これによりパートナーシップの拡張性と相互利益を確保している点を強調し、本講演は幕を閉じた。
スタートアッププレゼンテーション:MoBagelとArchimedes Controls
本イベントでは、2つのスタートアップより当社とのコラボレーションに関する講演があった。
MoBagel Data Ease:リアルタイムインテリジェンスへの生成的アプローチ
Data Ease:リアルタイムインテリジェンスへの生成的アプローチ

1社目は、データインテリジェンスの世界を革新しているMoBagelによるもので、彼らのプラットフォーム「DataEase」が紹介された。MoBagelのアプローチは、企業がAI駆動のハイパーオートメーションを活用して重要な運用上の課題に対処できるようにしている。MoBagelは、当社を戦略的パートナーとして、金融からサプライチェーン管理に至るまで、さまざまな業界向けにノーコードAIソリューションを導入している。「DataEase」を利用することで、「DataEase」を導入することで、利用する企業のビジネス部門はデータサイエンスの深い理解がなくてもAI/MLワークフローを展開できるため、企業は導入期間を短縮し、運用コストを削減し、需要予測の精度を向上できるメリットを語った。
Archimedes Controls : データセンターと産業用制御のためのAuto-MLによるIoTソリューション
: データセンターと産業用制御のためのAuto-MLによるIoTソリューション

2社目は、Archimedes Controlsによるもので、当社AutoMLと同社のARCOS®産業IoTプラットフォームとの統合が紹介された。このコラボレーションは、産業制御の自動化を推進しており、データセンター、環境モニタリング、農業などの分野で応用されている。リアルタイムセンサーを使用して温度、湿度、電力消費などの重要な条件を監視することで、Archimedesのソリューションは、企業がデータ駆動の意思決定を行い、予知保全を実現し、IoTとAIがどのように連携して運用効率を向上させてコストを削減できるかという点を強調した。
Fireside Chat:Henry Chesbrough教授とオープンイノベーションの未来を語る

本イベントの最後は、Zachary Rainey(米国富士通研究所Business Incubation Division, Open Innovation Manager)がMCを務め、Henry Chesbrough教授(米カリフォルニア大学バークレー校 Haas School of Business内、Garwood Center for Corporate InnovationにおけるFaculty Director・Mike and Carol Meyer 特別研究員)、岡田英人(当社技術戦略本部長)によるFireside Chatで締めくくられ、オープンイノベーションの重要性とその未来について深く掘り下げる貴重な機会となった。
オープンイノベーションの提唱者であるChesbrough教授は、分散型の知識の流れがますます重要になっていることを強調した。彼は、当社がファナックなどの企業をスピンオフしてきた歴史と、現代の業界間コラボレーションの動向を比較し、大企業がスタートアップに頼るようになっている点を挙げた。また、従来の集中型R&Dモデルからのシフトについても触れ、大企業は依然として研究分野に多くの投資を行っているが、スタートアップがR&D支出の約20%を占め、その迅速な行動力と柔軟性を活かしてオープンイノベーションを推進していることを指摘した。
また、オープンイノベーションの落とし穴についても議論が交わされ、意思決定のスピードに関する課題が焦点となった。スタートアップは迅速に方向転換できるのに対し、大企業は対応に時間がかかる傾向があることに触れ、この課題を克服するために、Chesbrough教授は高いレベルの承認を必要とせずに迅速な決定ができるよう、財務の閾値を設定することを提案した。このFireside Chatは、オープンイノベーションの可能性を再認識させ、企業間の協力による新たな価値創造の重要性を強調するものとなった。今後も当社は、スタートアップや他の企業と連携し、イノベーションの推進に努めていく。
Technology Showcase:AIの未来とスタートアップとの協力を探る


本イベントでは、当社とそのパートナーが提供する最新技術を実際に体験できるTechnology Showcaseも開催し、革新的な技術がどのように業界を変革し、企業の成長やコラボレーションを支援するかを実際に示す場となった。
- Amalgamation AI for Vision:基盤モデルを活用することでコンピュータビジョンのタスクを簡素化し、技術をよりスケーラブルかつコスト効率の良いものにする。このアプローチにより、さまざまな業界での応用が可能。
- Knowledge Graph Extended RAG:データリファレンスを拡充し、AI駆動のインサイトを向上させる方法を示した。これにより、企業はより複雑な問題をより高い精度と関連性を持って解決できるようになる。
- 当社AutoMLとMoBagelのDecanter AIの連携デモ:当社AutoMLがどのようにAIの導入を簡素化し、AIソリューションを大規模に実装しようとする企業にとって、より迅速かつコスト効率の良いものにしているかを示した。富士通とMoBagel、AIによる予測を高速化するソリューションを提供し、ビジネスプロセス変革を加速 : 富士通 (fujitsu.com)
これらのShowcaseは、私たちのFujitsu Kozuchi Platform上のAutoMLや他の当社独自技術が、様々な業界を超えた実世界のアプリケーションを推進し、よりスマートな意思決定のための高度なデータ分析を可能にしていることを参加者が実際に体験できる場となった。また、誰もが私たちの技術を直接利用できるFujitsu Research Portalは、スタートアップや外部企業との連携がどのように互恵的な成果につながるかを示す重要なプラットフォームとして紹介し、当該Portalを通して利用可能な技術や連携方法に関する展示を行った。当社とパートナー双方にとってWin-Winのシナリオを見つけることは、私たちのイノベーション戦略の中心にあり、今後もこれらの取り組みを拡大し、より良い未来のために技術革新を推進していく姿勢を直接議論する時間となった。
まとめ:オープンイノベーションの加速へ向けて共に
Fujitsu Tech Open House 2024を振り返ると、オープンイノベーションの未来に対する期待と、私たちがその実現に果たす役割への期待がますます高まっていることが改めて感じられた。AIや量子コンピューティングの進展から、スタートアップとのパートナーシップに至るまで、私たちは技術の限界を押し広げ、実世界にインパクトを与えるための取り組みを続けている。
本イベントでは、コラボレーションによるイノベーションと、迅速な製品開発サイクルへのコミットメントが強調され、当社がテクノロジーの分野だけでなく、グローバルなイノベーションエコシステムの構築においてもリーダーシップを発揮していることを示すことができた。当社は、すべてのパートナーやステークホルダーと共に歩みを進め、オープンイノベーションを通じて、研究開発から実世界への技術展開を加速させ、企業や社会にインパクトを与えるソリューションを共に創り出す姿勢を持っている。その意味で、Fujitsu Tech Open House 2024は、単なるイベントではなく、スタートアップ、学界、業界リーダーが一つになってイノベーションを実現する可能性を参加者の皆様と共に議論をする場となった。



