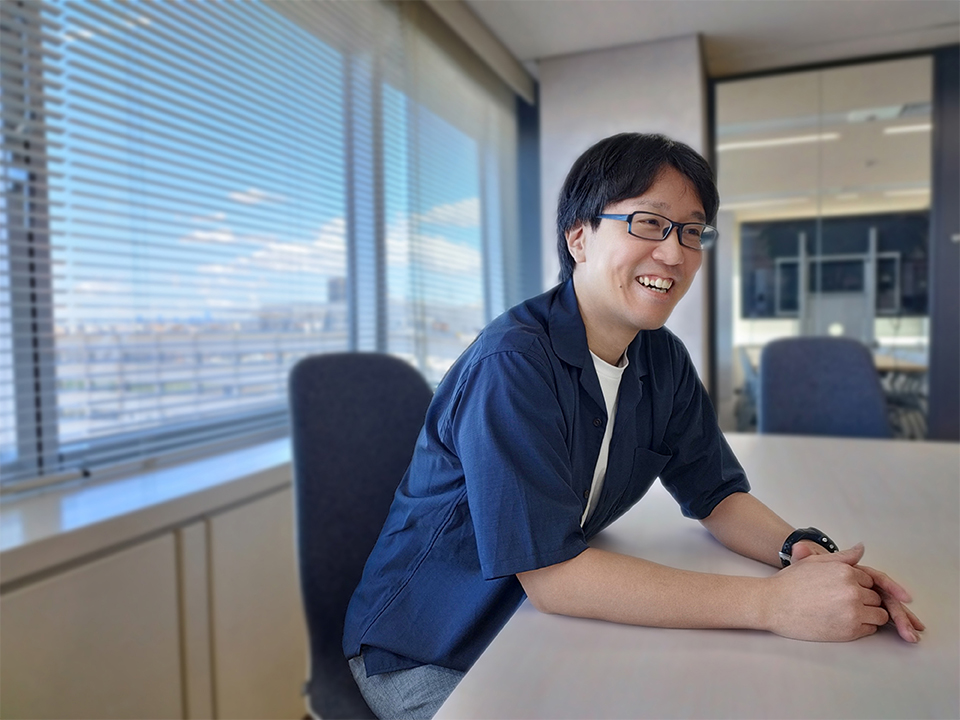大道芸ロボット。それは「廃材を利用して人を楽しませるロボットを作る」という高校の授業での課題でした。
チームでアイデアを出し合い、見ていて楽しく驚きも与えそうな皿回しロボットを作ることにしました。
皆で完成図を描き、空き缶や段ボールなどを集め、
皿を回すベルト機構を作ったり、駆動用のハンドルを取り付けたりしました。
製作が楽しく、連日遅くまで作業が続きました。
ガタンガタン。全て手作業で作り上げたロボット、最初は心もとない動きでしたが、
ハンドルを用心深く回し始めると、ロボットの手元の棒が、そして先端の皿が回転し始めました。
「やりました!」自分たちのアイデアが形になった瞬間、仲間と歓喜に沸きました。
製作したロボットは、他のチームのロボットと一緒に教室に展示し、
学校見学に来た大人や子供にも楽しんでもらいました。
こうして、人生はじめてのロボットづくりを経て、
「ものづくり」=「楽しい」という自分自身の興味に気づきました。
また、自分で作ったものを、人に見せたり使ってもらったりすることで、
「人を楽しませる」喜びが得られることも学びました。
この体験は、その後、大学ー大学院と継続してロボットの研究開発に携わるきっかけにもなり、
「自分で作ったものをもっと多くの人や世の中に役立てていきたい」という思いにもつながりました。
富士通への入社を決めたのも、ヒューマンセントリックという考えに共感し、人の「楽しい」を中心として、
人や世の中に役立つ研究開発ができると期待したからです。
入社後は、ヘルスケア領域の研究開発に携わりました。
センシングやデータ分析など新たな技術分野への学びを楽しみながら、
アイルランドやオランダなどの海外の研究機関や顧客とのプロジェクトに参画し、
グローバルな現場での課題解決に挑戦しました。
なかでも、ヘルスケア分野でAIやIoTなど最先端技術の活用が進むフィンランドに自ら赴任し、
研究開発した技術(*1)を富士通のヘルスケア向けクラウド上へ実装、
サービス化したプロジェクトでの経験は、
漠然とあった「人や世の中に役立つ」という期待を実感に変える機会を与えてくれました。
このプロジェクトでは、医療現場における理学療法士の「患者の回復状態を定量的に把握したい」
という要望に対し、患者の両足首に装着したジャイロセンサーの信号を使って
さまざまな歩き方の特徴を定量化する技術を開発しました。
病院でのリハビリの際には、理学療法士が患者の動きを観察し、患者の回復状態を把握します。
しかし、理学療法士は人数も少なく、一人で複数の患者を診る必要がありました。
また、理学療法士のスキルにはバラツキがあり、病院でのリハビリの際には、
患者の歩行動作の定量的な把握や、回復過程の記録の支援が求められていました。
開発した技術をサービス化して利用者まで届けられたのは、日本の事業部や研究所の協力のもと、
皆で一丸となってプロジェクトを進められたことが大きかったです。
当時、事業部は個人データ管理用のプラットフォームを持ち、
そこに研究所の技術を組み込むことで、サービス化を実現できました。
また、歩き方を定量化する研究所技術も、そのままでは使ってもらうことは難しく、
実際に理学療法士にテストしてもらい、
そのフィードバックからパラメータ調整や補完などの改良が繰り返され、
高精度に歩行特徴を算出する技術が完成しました。
海外に赴任した2年間の間、英国とフィンランドに滞在し、
現地開発チームとのアジャイルな技術改善や顧客先での実証、
医療機器の認証にまで携わるなど、現場ならではの様々な経験を積むことができました。
特に、現場の声を直接聞く機会にも恵まれ、
自分たちで作り上げたサービスを理学療法士が楽しそうに使っている様子を、間近でみることができました。
さらに、ある理学療法士の方から「実際の患者さんに使ってもらったところ、
自分の回復状態をデータとして見れて、泣いて喜んでいた」というエピソードを聞いた時には、
この仕事をしていて本当に良かったと思えました。
小さいながらも、「自分で作ったものが人や世の中に役立つ」という実感が得られました。
フィンランドでの生活を通じ、仕事での学びや経験に加え、色々な気づきも得られました。
最も印象的だったのは「笑顔」です。
フィンランドは幸福度世界一の国であり、その理由は、自然に近い暮らしやバランスのとれたワークライフ、
健全な社会福祉、サウナ文化など多くありますが、実感として、
都市部であっても周りの人達がいつも笑顔で、
私のような知らない外国人であっても楽しく話しかけてくれていました。
一方、フィンランドから日本に帰任して感じたのは、
スマートフォンを見ながら周りを気にせず下を向いて歩いている人や、
バスや電車、病院などで込み合いお互いに苛立つ人、SNSに没頭しすぎて疲れてしまう人など、
人や周りへの意識が低く、また笑顔も少ないということです。
理由は様々だと思いますが、その一つとして、
技術やサービスに人が”使われて”しまっているのではないかと感じています。
新しい技術やサービスを使うことで生活での利便性やコスト・効率が改善されていることは
確かだと思いますが、逆に、そういった技術やサービスを使うことにとらわれ、
人と人との繋がりが薄れ、笑顔が減っているのではないかと感じました。
本来、技術やサービスは人の生活をよりよくし、同時に、
安心感や幸福感を高めるものであるべきだと考えています。
当たり前のことですが、フィンランドでの体験から改めて気づき、
そのような人や社会の笑顔につながる技術開発を継続していきたいという思いを強めました。
現在、患者一人ひとりと医療機関や行政をつなげ、生活者が受ける
医療や健康サービスの流れ(ケアパスウェイ)を最適化する技術の研究開発に携わっています(*2)。
社会全体で、疾病予防や治療、予後ケアなどの各段階に応じて患者が受けるサービスの流れをデジタル化し、
患者自身がどのようなサービスを受けたいかなども考慮しながら、
医療・健康データと突き合わせて最適化することで、
個人の効果・体験と全体のコスト・効率を両立するケアパスウェイの確立に挑戦しています。
誰一人取り残さず、一人ひとりが先を見通せ、
安心感や幸福感をもって医療や健康など様々なサービスを利用できる世界を目指して。