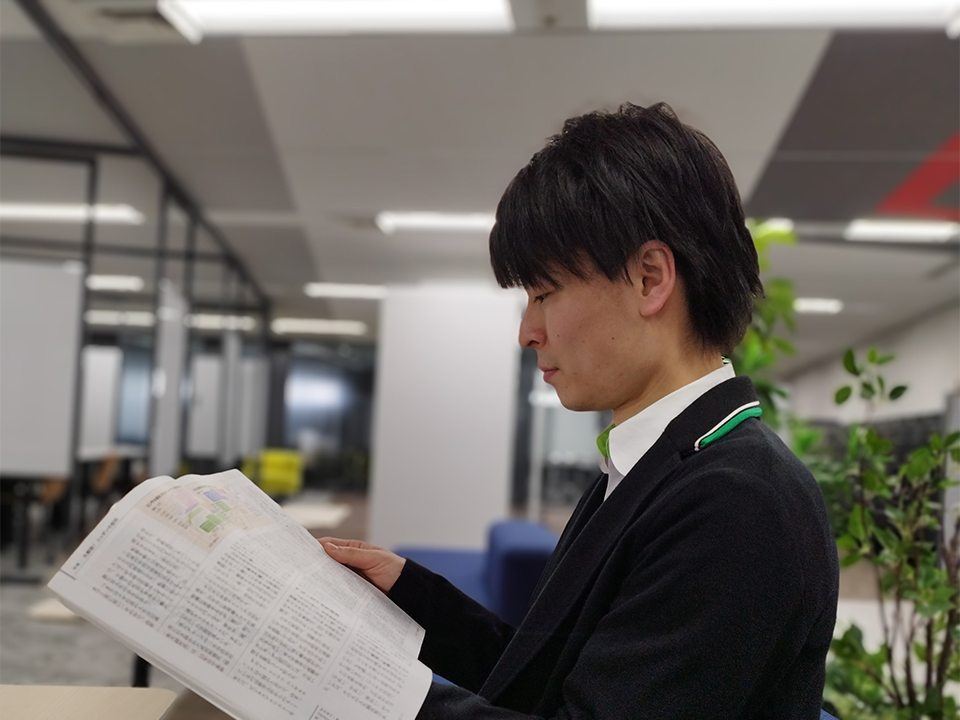私は子どもの頃から運動が得意で、友達と一緒にスポーツをすることが多かったです。
体を動かすことが好きでしたが、将来は手を動かしてモノづくりする職人になりたいと思っていました。
でも、中学の化学の授業がとても面白かったのです。
複数の化合物を組み合わせて新しい化合物を作ることが、私にとってはパズルを解くような感覚で楽しかったです。
高校に入ると、周りの人たちは携帯電話やパソコンの話題で盛り上がっていました。
当時の携帯電話は、今のスマートフォンに比べると機能が限られていましたが、着信音や待ち受け画面をカスタマイズすることができました。
私もそのカスタマイズにハマって、サウンドやデザインを色々と変更して楽しんでいました。
その後、パソコンに触れることが多くなり、パソコンの仕組みにも興味を持つようになりました。
ちょうどインターネットが普及しはじめた頃で、情報を簡単に検索できるようになり、いろいろなことを調べました。
こうした興味や経験が、大学で電子や情報の専門基礎知識を幅広く学習するきっかけとなりました。
大学院で取り組んでいた研究テーマは、音響分野の信号処理が中心でした。
具体的には、騒音を能動的に制御・低減するノイズキャンセリングと呼ばれる技術で、医療現場や工場の機器による騒音問題を解決するために役立つものです。
現場の意見や課題を聞きながら進めていく応用研究を行いました。
関係者からフィードバックをもらい技術を改良し、改良した技術を現場に適用し、最適な技術を生み出すまで改善のサイクルを繰り返しました。
私は、この進め方が好きでした。
体系的に学習した知識を応用まで落とし込み、フィードバックを繰り返して最適な技術を生み出すという、この一連の改善サイクルにより、自分が手がけた技術で世の中の課題を解決しているという実感がありました。
「世の中に存在する課題を一つでも多く解決したい」という想いが、研究へのモチベーションに繋がっていました。
ノイズキャンセリング技術の研究に熱心に取り組んで論文を書き上げ、その結果、音響技術分野でのトップジャーナルに掲載されました(*1)。
そして、自分が築き上げた専門性が誰かの生活を支える力になる仕事をしたいと考え職場を探していた頃、お客様起点の富士通に出会い、入社を決意しました。
入社後は、監視カメラの映像から人の行動を抽出する技術開発を担当しました。
それまでは、音質改善などを最新の信号処理技術の研究を行ってきましたが、画像認識分野に関する知識はほとんど持っていませんでした。
先輩たちについていくことに必死でとても苦労しました。
そこで、周囲の人々に質問をしながら日々の業務を進めることで、少しずつ基礎から学びはじめました。
業務終了後もひたすら専門書籍を読み込んで知識を深めていきました。
また、実際に手を動かしてプロジェクトを進める中で、実践的なスキルも磨くことができたと思います。
この経験により、画像認識において一定の精度を出すことができるスキルのベースラインを築くことができ、自信にも繋がりました。
ただ、新たな試練は、突如として吹き荒れる嵐のように訪れました。
次に任された業務は、ディープラーニング(DL)を活用した画像認識に関する研究でした。
画像を扱うという点では、前の業務と共通していますが、それまでに培った画像認識のスキルだけでは足りず、関係者との打ち合わせの度にDLに関する私の知識不足を思い知らされました。
このプロジェクトを機に、DLに関する知識の習得のため、一日に少なくとも論文を3本読むことを習慣にしました。
この習慣のおかげで、DLに関する知識を着実に深めることができ、この知識を活用することでプロジェクトチーム全体の成果に貢献することができたと思います。
築いてきた知識の量はもちろん、論文を読む習慣は現在でも継続し、自分の最大の財産になりました。
このような継続的な学習や研究を通して、課題を解決するためには新たな発想や着眼点を基にした技術が必要だと考えるようになりました。
既存の技術に対して、本当に今のやり方が最適なのか、もっと良いやり方はないのかといったことを考えるため、チームメンバーとの議論や論文調査などを通じて、様々な観点を取り入れる仕組みを作ろうとしています。
また、定期的に学会へ論文を投稿することも目標の一つとしています。
突き詰めて考え抜き、論文をアウトプットすることもあります。
他の研究者との交流も、新しいアイデアを得ることに繋がり、研究の改善点を発見することができるため、研究会の運営委員へ就任するなど、学会での交流は積極的に参加しています。
2020年、新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るい、医療現場は大きな負担を強いられました。
医療従事者たちは懸命に対応し、治療や診断に全力を尽くしていましたが、その中でも特に重要となったのは、新型コロナウイルス肺炎を早期発見することでした。
問診では新型コロナウイルス感染の可能性が低くPCR検査が陰性の場合でも、新型コロナウイルス肺炎の場合があります。
検査方法として胸部CT診断があるのですが、患者さん一人あたり数百枚もの胸部CT画像の目視で診断することが必要です。
そこで、医師の画像診断を支援するAI技術(*2)が注目され、その研究開発の案件が私に舞い込んできたのです。
この開発依頼は、急務であったため研究期間が数か月と短く、やり遂げられるか不安を感じました。
しかし、これまでに蓄積してきた画像とDLの知見を駆使し、医師が新型コロナウイルス肺炎の診断を効率良く行うための画像診断支援AIの技術開発に成功し、プロジェクトを成功に導くことができました。
そして自分自身としても必要な技術をつくりだすことができた達成感に満たされました。
これまで行ってきた医療現場を支援するAI技術の共同研究(*3)は、まだ発展途上の側面もありますが、確実に社会に貢献しています。
私自身は、研究人生において、世の中の問題を解決することに取り組むことを常に志し、今もその思いは変わっていません。
現在は、病気の早期発見技術の研究開発に取り組んでおり、より多くの人々が健康な日常生活を送ることができる社会を目指しています。
また、深めてきた知見や見つけてきた方法を論文や製品として形に残したいと強く思い、その目標に向けて、これからも全力で挑戦していきたいと思っています。