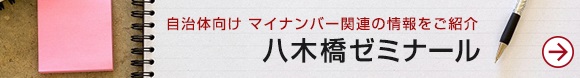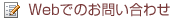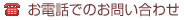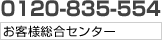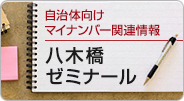- コンセプト
- 特集
- 導入事例
- 自治体におけるAI/RPAの取り組み
- マイナンバー制度への対応
- 自治体の情報セキュリティ強靱化対策2.0
- 自治体の情報セキュリティ強靱化対策1.0
- 自治体インフラ最適化
-
八木橋ゼミナール
- 第1回 「自治体の情報セキュリティ強化」
- 第2回 「自治体でのマイナンバーの利用拡大」
- 第3回 「マイナンバーカードによる自治体のサービス拡大」
- 第4回 「マイナンバー・公的個人認証サービス」
- 第5回 「マイナポータルの動向と活用」
- 第6回 「自治体のコンビニ交付サービス」
- 第7回 「マイナンバー制度の情報連携」
- 第8回 「新たな電子行政の方針」(成長戦略編)
- 第9回 「新たな電子行政の方針」(デジタルガバメント編)
- 第10回 「自治体におけるパーソナルデータ」
- 第11回 「自治体の官民データ活用」
- 第12回 「自治体におけるパーソナルデータ」(活用編)
- 第13回 「パーソナルデータをめぐる世界の動向」
- 第14回 「自治体をめぐる近未来への展望」
- 第15回 「明治150年の広域行政」
- 第16回 「在留外国人と安心・安全」
- 第17回 「新たなIT政策」
- 第18回 「在外邦人・平成最後の法改正」
- 第19回「平成最後の法改正・その後」
- 第20回「令和最初の法改正」
- 第21回「スマート自治体」
- 第22回「スマート公共サービス」
- 第23回「デジタル・ガバメント実行計画」
- 第24回「マイナンバーカードの活用(社会保障分野編)」
- 第25回「デジタル強靭化」
- ソリューション一覧
- カタログ・資料申込
- ニュース & トピックス
- イベント・セミナー
八木橋ゼミナール 第19回「平成最後の法改正・その後」
前回の「平成最後の法改正」のその後について、解説します。
今回はその前半(デジタル手続法、健康保険法等、所得税法等の改正)について。
後半(デジタル手続法の個別施策、戸籍法等の改正)は次回、解説します。
2019年6月26日掲載
法改正
第198回国会(2019年1月召集)で、マイナンバー制度やデジタル・ガバメント等にかかわる法改正(注1)が成立しました。順に、簡潔に紹介していきます。
(注1)下記の資料中6頁「マイナンバー法改正に係る検討状況について」 及び8頁「マイナンバーカードの普及策」
資料2-2-1内閣官房・内閣府「マイナンバー制度について」 内閣府 経済財政諮問会議 経済・財政一体改革推進委員会 第17回 国と地方のシステムWG![]() (2019年3月15日)
(2019年3月15日)
所得税法等の改正
平成最後の国会で、改元前に成立(平成31年法律第6号2019年3月29日公布)したのが、所得税法等の改正(国税通則法等の改正)(注2)です。
改正の要旨は、「消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うもの」(議案要旨より)です。
このなかで、マイナンバー制度の利用拡大として、以前から「証券振替業務など法律に基づき民間事業者が行う公共性の高い業務のうち利用するメリットの大きい事務へのマイナンバーの利用範囲拡大」(注3)とされていた、「社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関」(注4)がマイナンバー法の別表事務に追加されました。
(別表第一38の2 「国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務」)
この団体は、番号法第19条(特定個人情報の提供が認められる場合)第10号に記載されている「振替機関等」に該当するものです。
今回の改正により、振替機関が利用事務実施者として個人番号を取得し、この番号等を株式等の発行者や口座管理機関である金融機関等の求めにより提供するものとされました。(国税通則法第74条の13の4)
また、金融機関が施行日前(2016年1月1日前)に開設した特定口座などで、個人番号が未告知の者について、告知の期限を3年から6年に延長、また、振替機関から番号を提供受けた場合は、本人からの告知があったとみなすとされました。(番号整備法第8条、第25条関係)
今回の改正は、民間機関(株式会社)が利用事務実施者になること、限定的な範囲ですが、証券会社(口座管理機関)や信託銀行(株式等の発行者)、一般の金融機関(特定口座や国外送金等の場合)などの民間機関間で特定個人情報の提供が行われること、など、マイナンバー制度の利用拡大の一部として、紹介しておきます。
そもそも番号制度は、消費税法の改正(2012年8月公布)に伴い、「消費税率の引き上げを踏まえて、低所得者に配慮した再配分に関する総合的な施策の導入」に必要な制度として制定(2013年5月公布)されました。
その後の法改正で、消費税率10%への引き上げの延期(2015年3月公布、2016年11月公布)、軽減税率制度の導入(2016年3月公布)がなされ、今回は、2019年10月からの消費税率10%への引き上げの直前の法改正となりました。
この経過に関連して、この第198回国会(財務金融委員会)で、野田佳彦委員(第95代内閣総理大臣)と麻生太郎国務大臣(第92代内閣総理大臣)が興味深い遣り取りをしています。(注5衆議院委員会議事録参照)
自治体にとっては、消費税率引き上げにともなう対応として、2019年10月からの「プレミアム付商品券事業」(注6)の準備と対応が進められています。
これに加え、経済産業省が推進する「キャッシュレス・消費者還元事業」(中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元の支援)(注7)の「10月からの集中的な実施(9か月間)」の後、2020年度半ばからの「マイナンバーカード(マイキープラットフォーム)を活用した消費活性化」(注8)への準備が要請されています。
(注2)財務省 第198回国会における財務省関連法律 所得税法等の一部を改正する法律案![]() (2019年2月5日提出)
(2019年2月5日提出)
(注3)IT総合戦略本部 第9回マイナンバー等分科会 【資料6】マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)![]() (2015年5月20日)
(2015年5月20日)
(注4) 証券保管振替機構![]() 、略称「ほふり」、2002年に財団(1984年発足)から株式会社化
、略称「ほふり」、2002年に財団(1984年発足)から株式会社化
(注5)衆議院 財務金融委員会議事録 第198回 第2号(2019年2月19日)、第3号(2月26日)、第4号(2月27日)![]() なお、第5号(2019年3月1日)
なお、第5号(2019年3月1日)![]() で野田佳彦委員と安倍晋三内閣総理大臣(第98代)が討議しています
で野田佳彦委員と安倍晋三内閣総理大臣(第98代)が討議しています
(注6)内閣府 プレミアム付商品券事業について![]() 内閣府 「プレミアム付商品券事業の概要」
内閣府 「プレミアム付商品券事業の概要」![]()
(注7)経済産業省・一般社団法人キャッシュレス推進協議会 キャッシュレス・消費者還元事業![]()
経済産業省 平成31年度予算関連事業のPR資料 商務サービスグループ 「キャッシュレス・消費者還元事業」![]() (2019年5月10日更新)
(2019年5月10日更新)
(注8)総務省 第4回マイキープラットフォーム運用協議会総会・役員会 別紙1(議題1)![]()
総務省地域情報政策室「マイナンバーカードを活用した消費活性化の取組について(消費税率引上げに伴う対応等)」![]() (2018年12月25日)
(2018年12月25日)
健康保険法等の改正
マイナンバー関連で、次に成立(令和元年法律第9号2019年5月22日公布)したのが、健康保険法等の改正「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(注9)です。
改正の趣旨で、「保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設」が示されています。
また、「療養の給付等を受けようとする者は、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該給付等を受ける」として、「オンライン資格確認」を法定化しました。
「電子資格確認」とは、「保険者に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により、被保険者または被扶養者の資格に係る情報の照会を行い、資格の確認を受けること」としています。(健康保険法第3条13項)(注10)
これにあわせて、今回、「電子化推進」や「データ利活用」の拡張等が含まれています。
- オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
- 医療・介護分野のビッグデータの連結解析等の規定の整備
(レセプト等から収集したNDB、介護DB、DPCデータベース) - 審査支払機関の機能の強化
(支払基金でのデータ分析等業務の追加、国保連でのKDBを想定した、データ分析等業務の追加等)
などが改正されています。(注11)
なお、国会の審議により、衆議院の厚生労働委員会(2019年4月12日)で、附帯決議が付されました。
その12項目のうち、最初の2項目を紹介しておきます。(注12衆議院委員会議事録参照)
「政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一.今回の医療保険制度の運営に関する改正に続き、2025年には団塊の世代が後期高齢者に移行することなどから、少子高齢社会の進展を見据えた取組を早期に開始し、医療保険制度の健全な運営に努めること。
二.個人番号カードによるオンライン資格確認が導入されることを踏まえ、個人番号カードの更なる普及拡大に向けて、セキュリティ対策の充実など、効果的な施策を検討するとともに、関係府省が連携して取り組むこと。」
(注9)厚生労働省 第198回国会提出法律案![]() 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」![]() (2019年2月15日提出)
(2019年2月15日提出)
(注10)厚生労働省 第116回社会保障審議会医療保険部会![]() 資料3について 厚生労働省保険局 「オンライン資格確認等システムの検討状況」
資料3について 厚生労働省保険局 「オンライン資格確認等システムの検討状況」![]() (2018年12月6日)
(2018年12月6日)
(注11)厚生労働省 第117回社会保障審議会医療保険部会![]() 資料3について 厚生労働省保険局 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について」
資料3について 厚生労働省保険局 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について」![]() (2019年1月17日)
(2019年1月17日)
(注12)衆議院 厚生労働委員会議事録 第198回 第8号![]() (2019年4月12日)
(2019年4月12日)
デジタル手続法
「行政手続オンライン化法」(平成14年法律第151号)(注13)を改正、題名を変更して、「デジタル手続法」も成立(令和元年法律第16号2019年5月31日公布)しました。(注14)
法の名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」。
概要としては、「情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定める」。
目的(第1条)で、「国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現」とうたっています。
概要について、列記します
- (1)題名「行政手続オンライン化法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律)」(注13)を 「デジタル手続法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)」に改める
- (2)基本原則(情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則)を定める
(デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ) - (3)国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備
(国の行政機関等以外の行政機関等は、努力義務(第5条)) - (4)電子納付(申請等に係る手数料の納付は、情報通信技術を利用する方法ですることができる)
- (5)添付書面等の省略(他の法令において、申請等に際して添付することが規定されている書面等について、行政機関等が情報を入手し参照することができる場合には、添付することを要しない)
- (6)デジタル・デバイドの是正
- 情報通信技術の利用の能力、知識経験が十分でない者が相談、助言その他の援助を求められるようにする施策
- 情報通信技術の利用のための能力、利用の機会における格差の是正を図る施策
- (7)民間手続における情報通信技術の活用の促進
- 手続等密接関連業務を行う民間事業者は、手続を情報通信技術を利用する方法で行い、行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない
- 国は、民間取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずる
- 民間手続が情報通信技術を利用する方法で可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずる
国会の審議により、衆議院の内閣委員会(2019年4月26日)で、附帯決議が付されました。
その9項目のうち、地方自治体にかかわる3つの項目を紹介しておきます。(注15衆議院委員会議事録参照)
「政府は、本法による行政のデジタル化の推進に当たり、次の諸点について万全を期すべきである。
三.地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。
四.地方公共団体が、行政のデジタル化の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続のほか、当該地方公共団体が行う施策の実施に関する指針、基準その他これらに類するものに基づく手続についても情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための施策を講ずるに当たり、必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
六.地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。」
(注13)行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号2002年12月13日公布)総務省「電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法のポイント」![]()
(注14)内閣官房 第198回国会提出法案![]() 概要「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法)」
概要「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法)」![]() (2019年3月15日)
(2019年3月15日)
(注15)衆議院 内閣委員会議事録 第198回 第15号![]() (2019年4月26日)
(2019年4月26日)
なお、この委員会で、国会で初めての「タブレット端末を使った審議」が行われました
「国会審議にタブレット初登場 衆院内閣委」日本経済新聞![]() (2019年4月26日)
(2019年4月26日)
「国会審議にタブレット初登場 ただし1日限りですが」朝日新聞デジタル![]() (2019年5月7日)
(2019年5月7日)
デジタル手続法(個別施策)、戸籍法の改正
デジタル手続法のうち、行政のデジタル化を推進する個別施策(住⺠基本台帳法、公的個⼈認証法、マイナンバー法の改正)、戸籍法の改正(令和元年法律第17号2019年5月31日公布) については、次回に解説します。
今回紹介した範囲で、直接関係するところは、
「オンライン資格確認」での「電子資格確認」の「利用者証明用電子証明書を送信する方法」に関連し、「暗証番号PIN⼊⼒を要しない⽅式」を法定化しました。
「利用者証明検証者は、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を、当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。」(注16)
これは、総務省の研究会(注17)で「電子証明書の多様化」を検討、「PIN入力を要しない認証方式」について、「新たな電子証明書の利用方式となるため、公的個人認証法令上明確に位置づけることが必要」との報告をうけたものです。
(注16)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正
第38条の2及び3「特定利用者証明検証者」に関する事項の追加
(注17)総務省「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」において取りまとめられた中間報告の公表![]() 中間報告書の22頁(2018年5月25日)
中間報告書の22頁(2018年5月25日)
富士通の取組
デジタル社会の変革が進んでいきます。
「Human Centric Innovation: Driving a Trusted Future」
「Fujitsu Technology and Service Vision 2019」を策定![]()
デジタル時代にトラステッドなビジネスと社会を共創するアプローチを提言
(2019年4月16日 富士通株式会社PRESS RELEASE)
お客様やパートナー様と共に人を中心とするイノベーションを生み出し、誰もが安心できるトラステッドな(信頼性のある)未来を築いていきたいという思いを込め、「Human Centric Innovation: Driving a Trusted Future」をテーマとし、デジタル社会に移行する過渡期ともいえる状況の中で、ビジネスや社会における信頼の再構築の重要性や当社の考え方について提言しています。
「Fujitsu Technology and Service Vision」![]() (日本サイト)
(日本サイト)
私たちのビジョンの中心的な考えとして、ヒューマンセントリック・イノベーションというコンセプトを掲げています。これは先進技術で人をエンパワーする(力を与える)ことによって、ビジネスや社会のイノベーションを生み出す新たなアプローチです。
Fujitsu Technology and Service Vision 2019![]() (冊子PDFダウンロード)
(冊子PDFダウンロード)
ひきつづき、注視していきましょう。