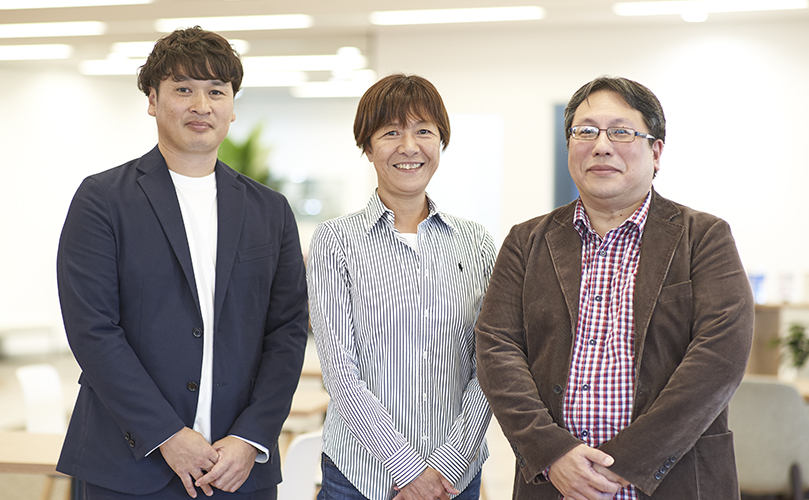【開催レポート】Fujitsu 人材育成セミナー 2024 ~人と組織の未来を共に創る。~
鼎談セッション
合同会社機械経営 代表 安野 貴博 氏(右)
株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長 佐竹 秀彦(中央)
同 ナレッジサービス事業本部 シニアディレクター 渡邉 潤(左)
記事公開日:2025年2月17日

2024年12月6日にオンライン開催され、大きな反響をいただいた「Fujitsu 人材育成セミナー 2024」。いま、デジタル技術は目まぐるしく進化し、企業規模の大小や業種・業界など、あらゆる境界を越えてその恩恵を享受できる社会が実現しようとしています。「生成AI」「ノーコード/ローコード」などを活用した市民開発が加速する現在、企業はDXとどのように向き合えば、人と組織をアップデートできるのか。今回で11回を数える本セミナーでは、様々な事例を基に企業のテクノロジー活用のあるべき姿に迫るため、2部構成でアプローチしました。
第1部・前編では、合同会社機械経営代表の安野貴博氏による基調講演「未来を創るためのテクノロジーとは~人と社会のアップデートを目指して~」の様子をお届けしました。第2部では、企業の最前線でDXおよび生成AIの導入と浸透に奮闘している株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発の大庭久和氏とカナデビア株式会社(旧・日立造船)の白川哲也氏に富士通株式会社の岡安明香を交えて、株式会社富士通ラーニングメディアの前田真太郎による進行の下、パネルディスカッションを行いました。
本稿では、第1部・後編として、安野氏を交えて行った鼎談セッションの様子をご紹介します。
第1部 鼎談セッション
合同会社機械経営 代表 安野 貴博 氏
株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長 佐竹 秀彦
同 ナレッジサービス事業本部 シニアディレクター 渡邉 潤
安野氏による基調講演の後は、株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長の佐竹秀彦と、同ナレッジサービス事業本部 シニアディレクターでDX人材育成サービスの責任者を務める渡邉 潤を交え、同事業本部の坂本美奈による進行の下、鼎談セッションが行われました。
安野氏のマニフェストと有権者の関係は「商品とお客様の関係」に近い
佐竹:安野さんに本日お話しいただいた「聴く・磨く・伝える」のサイクルは、政治だけではなく「組織開発」にも大いに有効であると感じました。弊社も組織開発事業を行っておりますが、組織開発のなかでAIなどのテクノロジーを有効に使えば、社員にとって「経営」はより身近になるはずだと考えています。それにより、一人ひとりが当事者意識をもって仕事ができるようになるのではないかとも考えますが、いかがでしょうか?

株式会社富士総合研究所、富士通株式会社などを経て2024年4月より現職。
安野氏:おっしゃるとおり、今回のフレームワークは選挙だけに使えるものではありません。従業員の声を聴き、コミュニティ全体の声を聴きながら、それを意思決定に反映させていく際には、普遍的に使える考え方だと思っています。
渡邉:仮に安野さんのマニフェストを「商品」と見立て、有権者を「商品を使うお客様」と見立てた場合、その声を集めていく様子は、まさにビジネスに活用できるものであると思いました。そのあたりには、安野さんのこれまでのビジネス経験が生きているのでしょうか?

DX人材育成サービスの責任者。富士通でのSE(システムエンジニア)経験の後、
ICTトレンド技術を中心とする研修サービスの立ち上げに携わってきた。
Salesforce認定講師として6年連続でBestInstructor賞を受賞。
安野氏:非常に生きていると思います。私が最初に起業したコールセンター等のカスタマー対応の自動化をサポートする会社では、お客様の声を聴いてその瞬間、瞬間にしっかり答えていくということも大切でしたが、それ以上に、聴かせていただいた声からどういう学びを得て、どう事業にフィードバックするのか?ということも重要でした。そういったことは、キャリアの初期からやっていたように思います。
2つめの会社ではGitHub上で社内規則や社内戦略を文書形式で共有していましたが、それもある種「磨く」のフェーズを、組織の中の小さい単位で実践する試みだったと言えるでしょう。このような各種の経験は、現在の発想の中に着実に生きていると思います。
とはいえ“GitHub”と言った瞬間に、エンジニアっぽさに苦手意識を感じる人たちは、一斉にサーッと離れていってしまうかもしれません。どうすればより多くの人が議論に参加できるのかというのは、きちんと考えるべき問題だと思っています。
社内の生成AI利用率を上げるには、企業側の覚悟も必要
佐竹:AIテクノロジーは、今や一部のエンジニアが知っていればいいという時代ではなく、全員が幅広く使っていくべき時代になっていると思いますが、安野さんはどうお考えですか?
安野氏:おっしゃるとおりであるとは思います。しかしその一方で、「果たして会社の中で生成AIを使いやすい環境が整っているか?」という問題もあるはずです。個人情報保護やセキュリティなどの関係で「使用不可」あるいは「使っても良いが、この業務では使用を禁ずる」などとされている場合も多いのではないでしょうか。さまざまな事情があるとは思いますが、企業側にも、もう少し社員に活用させるための方策はあるのではないかと考えます。

企業内でAIを使いこなすには「業務」もわかっている必要がある
佐竹:「積極的にAIを活用していかなければ」という危機意識は、多くの経営者が持っていると思います。そのなかで、今現在使っている/いないにかかわらず、企業がAI活用のレベルをさらに高めていくには何が必要だと考えますか?
安野氏:とにもかくにも人材なのですが、人材の中でも2つあると思います。まず、世の中に「このAIだけを使えばOK」という業務はほとんどないんですよね。業務を分解したうえで、この業務にはこのAIを使うなどの判断をし、作ったデータをこのシステムに入れて……というような「糊付けの部分」がたくさん発生するものです。こうした「糊付け」ができるエンジニアリングスキルを持っていて、かつ業務のこともわかっている人材の数を増やすというのがまずひとつ。
そして2つめは、「そのAIは何ができて、何ができないのか?」というのを正しく把握することです。世の中では生成AIプロダクトに関するさまざまなプロモーションが行われていますが、チャンピオンデータ(通常は出ないような、非常に良いデータ)だけをプロモーションに使っている場合も多いものです。
「ちょっと違うテーマで似たようなことをやらせてみたら全然ダメだった」ということはしばしばありますし、その逆もあります。そのため、生成AIを使いこなすには「目利き」が必要です。そして目利きができるようになるためには、これはもう使ってみるほかありません。とにかく使ってみて、それぞれの生成AIに何ができて何ができないかについて「肌感覚」を持つ人材の数を増やしていくことが重要ではないかと思います。
AI活用においてはレガシー的大企業こそ、果たせる役割は大きい
渡邉:「社内でDXを進めたい。そこでシステム部門はツールを導入し、人材育成部門はDX教育を何回も行った。だが現場にはなかなか浸透しない」というようなご相談を数多く頂戴しています。この問題についてはどう考えますか?
安野氏:それについては人間もAIも同じではないかと思っています。例えば人間の新入社員には、いきなり大事な仕事を任せるのではなく、少しずつ「これならできるかな?」という業務をしてもらい、徐々に信頼関係を作っていくはずです。そして信頼関係ができると、いろいろなことを任せられるようになっていきます。生成AIにおいても、そうした信頼関係構築のプロセスをいかに設計するかが重要になります。
例えばZ世代の社員が入社してきたとき、「Z世代はこういう特性があると言われているから、こう対応してみよう」と意識したりチューニングしたり、ということがあると思いますが、それと似たことをAIでもやってあげるといいのではないでしょうか。「AIにはこういう特性があって、こういうふうに扱うと、業務でこういう成果を出すことができる。だがこのあたりは実は苦手だから、あまり当てにしないほうがいい」などといったガイドを、会社側から使う側へ出してあげる必要があります。
ただしもう少し別のレイヤーでの課題を検討してみることも重要です。それは、そもそも社員が「価値を感じられる最低限度の精度」のものか否か、という点です。もしもそのラインを超えていない生成AIプロダクトなのであれば、いくら会社が「使え」と言ったところで社員は使いません。最低限度の精度を出せていないAIを使用すると逆に業務が遅くなり、信頼関係が崩れることもあり得ます。そこも、冷静に見ていくべきでしょう。
坂本:最後に、こちらは視聴者の方からのご質問です。安野さんが思い描く社会やGovtech(ガブテック:デジタルテクノロジーを活用して行政サービスの向上や行政課題の解決を図ること)の実現という観点から、どちらかというとレガシー色が強い大企業が果たすべき役割は何だと思われますか?
安野氏:私はテクノロジーを社会に浸透させていく上で、「大企業が果たせる役割」は非常に大きいと思っています。レガシーな大企業はチームのサイズが大きく、優れた人材も多数いることでしょう。そういった人たちが、いかに生産性高く、付加価値の高い仕事ができるかどうかで、社会全体が生み出せる富の大きさは変わってくるものです。
特にテック業界は、本当に世の中の形を変えるカギになると思います。生成AIをはじめとする新しいサービスを使って世の中を変えるには、現場を知るテック業界の人が、それらを現場のシステムに入れていく作業が必要になります。クライアントが何を求めているか、コミュニケーションを熱く取りながら理解していくプロセスも不可欠です。そうした重要な部分を担われているテック業界の皆様がいかに活躍できるかで、世の中の進化スピードは変わっていきます。ぜひ一市民としても、その活躍に大いに期待していきたいです。
登壇者プロフィール
 合同会社機械経営 代表
合同会社機械経営 代表
安野 貴博 氏
AIエンジニア、起業家、SF作家。東京大学、松尾豊研究室出身。
ボストン・コンサルティング・グループを経て、AIスタートアップ企業を二社創業。
デジタルを通じた社会システム変革に携わる。日本SF作家クラブ会員。
2024年東京都知事選に出馬、AIを活用した双方向型の選挙を実践。
 株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長
株式会社富士通ラーニングメディア 代表取締役社長
佐竹 秀彦
1995年4月 株式会社富士総合研究所入社。その後、KPMGコンサルティング、GE Japanに移り、
マーケティング、コンサルティング、人事部業務を経験。
2007年5月 富士通株式会社入社。エンジニア部門の人事担当課長として、人事業務を経験。
2015年1月 同社人事担当部長として、全社の働き方改革を推進。
2020年1月 同社人材開発統括部長として、全社のキャリアオーナーシップ推進やDX人材育成、エンゲージメント向上などを推進。2023年よりGlobal CoEの評価制度などの責任者を兼務。
2024年4月より現職。
 株式会社富士通ラーニングメディア
株式会社富士通ラーニングメディア
ナレッジサービス事業本部 シニアディレクター
渡邉 潤
DX人材育成サービスの責任者。
富士通でのSE経験を経て、クラウド、モバイル、アジャイル、AIといった時代の潮流を捉えた研修
サービスの立ち上げに携わり、Salesforce認定講師として6年連続でBest Instructor賞を受賞した実
績を持つ。
社内でもデータドリブン文化の醸成をミッションにチームでダッシュボード構築や生成AI活用推進
に挑戦中。
富士通ラーニングメディア担当者からのメッセージ
 株式会社富士通ラーニングメディア
株式会社富士通ラーニングメディア
ナレッジサービス事業本部
坂本 美奈
「反応が速い!」安野さんへご挨拶をしてすぐに、時間の流れや空気の変化を感じました。たくさんの質問をどの方向から投げかけても、説得力のある回答がテンポよく返ってくるのです。
また、よく笑ってくださるため瞬時に場が明るくなり、和やかな雰囲気でご講演がスタートし、鼎談セッションを楽しみながら進行することができました。
AIエンジニアとしての高いスキル、起業家としての洞察力、SF作家としての未来予測力に加え、素早い反応力や空気を動かす力をも兼ね備えた安野さん。安野さんの魅力に触れ、様々な学びを通じて自分自身をアップデートし続けることや、何事にもスピード感を持って対応することの大切さにも気づくことができました。今後のご活躍が益々楽しみです。
※本記事の登場人物の所属、役職はセミナー開催時のものです。
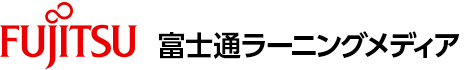

 【開催レポート】Fujitsu 人材育成セミナー 2024 基調講演 AIエンジニア 安野 貴博 氏
【開催レポート】Fujitsu 人材育成セミナー 2024 基調講演 AIエンジニア 安野 貴博 氏