お客様インタビュー
実践型DX研修で新規事業の創出に挑む
~「真面目な会社」を超えて中島董商店が目指す姿とは~
株式会社 中島董商店 経営企画部 DX推進課 担当課長 三宅淳平様(右)
株式会社nakato 業務部 業務課 課長 石井義章様(中央)
株式会社トウ・アドキユーピー 広告宣伝部 広告宣伝一課 小笠原澪様(左)
記事公開日:2025年2月19日

顧客ニーズの多様化や市場環境の急速な変化により、食品業界は今、「不確実性」が増大しています。そのためDX(デジタル・トランスフォーメーション)を通じて、変化に俊敏に対応できる企業文化と体質への変革を図ることは、創業から百余年の歴史を持つ株式会社中島董商店にとっても課題となっていました。
テクノロジーを活用して新たな価値を創出するには、業務部門とIT部門との間の垣根を取り払い、両者が一体となって「顧客起点での新しい発想に基づくアイデア創出」に取り組む必要があります。
同社では全社的なDX推進体制をつくるべく、経営層・DXリーダー層・一般社員それぞれに向けたDX教育を実施。中でもDXリーダー層向けの実践教育では、創出したアイデアの実証実験を行うなど、ビジネス化に向けた検討を進めています。
部門を越えたプロジェクト実践型教育を通じて同社は今、どのように生まれ変わりつつあるのでしょうか。DX教育の導入を推進した三宅淳平様と、DXリーダー向け研修に参加した石井義章様、小笠原澪様に伺いました。

ワインに合うおつまみシリーズの「メゾンボワール」などの開発を行っている。
自ら変化し、新しい価値を創出するためのDX推進
──研修導入前、御社が企業文化と体質の変革が必要であると判断した背景をお教えください。
三宅様:VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity曖昧性という4つの言葉の頭文字をとった造語)という言葉で表現されることも多い不確実な時代のもと、「自ら変化できる企業」に変わる必要があると考えました。
当社は、1918年の創業以来の長い歴史を持つ会社です。そして当社の社風をもしも言葉で表すとしたら、「真面目」という3文字がもっともふさわしいと思っています。もちろん「真面目であること」は良いことですが、近年は、その弊害のようなものも感じていました。

IT事業の外販営業担当を経て、現在は株式会社 中島董商店 経営企画部 DX推進課 担当課長として、
グループ全体のDX推進における中心的役割を担っている。
──「真面目であること」の弊害とは、例えばどんなものでしょうか?
三宅様:真面目とは、言葉を変えれば「慎重すぎる」ということでもあります。そのため、何か新しい施策を導入するにも検討に長い時間がかかり、施策の導入が決定された時にはすでにタイミングを逸していたというようなことも、しばしば発生しているように感じていました。
石井様:現場視点で申し上げますと、例えば受発注に関するデジタルシステムを導入したものの、「一度作ったものは長く使う」という真面目さゆえか、より効率的な新システムの利用を躊躇し、電話やメール、FAXなどを長期にわたって使用し続けているという状況でした。

中島董商店グループ各社の経理担当を経て、約10年前より主に受発注業務を担当する業務部 業務課に所属。
現在は同課課長を務めると同時に、DXリーダーにも任命されている。
小笠原様:私個人としては、当社は中小企業ゆえに経営層と社員の距離が近く、また風通しの良い社風でもあるため、さまざまなことに「スピード感をもって挑戦できる会社」だと思っております。しかし、真面目な社風だからこそ、当社の魅力である「身軽さ」や「風通しの良さ」を十分に活かしきれていないとは感じていました。

入社以来、中島董商店本社総務部にて、総務・秘書・危機管理などをはじめとする管理業務から、
サステナビリティ推進や社風改革まで幅広く担当し、DXリーダーにも任命される。
現在は株式会社トウ・アドキユーピー 広告宣伝部 広告宣伝一課に所属。
──そのためDXを推進し、業務部門とシステム部門が一体となって「新しい価値の創出」を目指したとのことですが、「新しい価値」とは、どのようなものとお考えでしょうか?
三宅様:これまではIT部門と各事業部門との間に垣根というか、分断のようなものがあり、コミュニケーションが一方通行になりがちでした。事業部門側はリクエストを伝え、IT部門側はそれにそのまま応じたシステムやアプリケーションを作る。IT部門側からの提案や双方での議論はほとんどない状況でした。つまり、事業における「課題の本質」を共に洗い出し、実効性のある解決施策を打つことはできていなかったのです。もちろんIT部門も、多忙ななか頑張ってくれていたことは事実ですが、どうしても表層的な開発のみに終始してしまっていました。
そういった状況をDXによって変革し、事業部門とIT部門が一体となってそれぞれの力を最大限発揮できたとき、自ずと新たな課題を発見し、それに対する施策が生まれるのではないか。それこそが「中島董商店ならではの新しい価値」になるのではないかと考えたのです。
徹底的なヒアリングで「課題の本質」と「想い」を抽出し、研修内容に反映
──研修実施の提案に際し、富士通ラーニングメディア(以下FLM)が御社へ行ったヒアリングと、それに基づいて提案された研修内容についての評価を教えてください。
三宅様:結論から申し上げますと、FLMさんから最終的にご提案いただいた内容と、実施された研修には大いに満足しています。ただし初回のご提案内容は、比較的オーソドックスなDX研修であり、当社がイメージしていたものとギャップがありました。といいますのも、当社はそもそも今回の研修を「単なる研修」にはとどめたくないと思っていました。より「実践的」であり「具現化できるもの」にしたいと考えていたのです。
──ギャップがあった状態から両社で協議を行い、結果としてご期待に沿える研修内容を作っていったプロセスや、その際の印象等についてお聞かせください。
三宅様:打ち合わせを繰り返すなかで、FLMさんには我々の想いや課題をしっかり汲み取っていただけました。そして想いと課題を汲み取ってくださっただけでなく、それに基づいた全体のテーマ設定やワークショップの詳細な内容など、当社がイメージしていた内容を超える提案もしていただけたのは、本当にありがたいことでした。
またメンバーへの研修を実施する前に、当社経営層にDX推進の必要性をインプットするための講義(「事例から読み解くデジタルビジネス」を中島董商店向けにカスタマイズした経営層向け集合研修半日セミナー)も行っていただきましたが、その際も「なるべく多くの事例を入れてほしい」というリクエストにしっかり応えていただけました。その後のすべてがスムーズに進んだのは、あらかじめ経営層へのインプットを効果的に実施できたからだといえるでしょう。

講師が寄り添う研修で描く「ありたい姿」
──実際の研修の内容と印象はいかがでしたか?
石井様:研修の最初の段階で、「DXに対する固定観念」を取り払ってくれたのが良かったと思っています。私自身、DXとはデジタルツールありきのもので、非常に難解かつ壮大なものであると思い込んでいたため、「自分にできるだろうか?」と心配していました。
しかし講師の方は、最初に「DXとは、ツールありきの何かではありません。まずはご自身のありたい姿、実現したいことを考えましょう。デジタルは、それを実現させるためのツールに過ぎないのです」と教えていただけました。そのため過剰に身構えることなく、研修の機会を非常に有効に使うことができたと思っています。また講師の方が本当に親身に寄り添ってくれ、かつ参加者の思考を上手に誘導していただけた点にも感心しました。
小笠原様:確かにFLM講師の方の「寄り添い力」には感服しました。講師の方は、各班のテーブルにそれぞれ20分間ほど入り、メンバーと一緒になって、課題について真剣に考えてくださいました。その姿は「講師であり、メンバーでもある」ことで安心して受講できました。
「経営層へのプレゼンテーションと事業化の決裁」までを含んだ異例のDXリーダー研修
──DX推進にあたり、DXの概要やサービス創出のプロセスは学んだものの、アイデアの事業化や業務への適用には二の足を踏んでしまうお客様も多くいらっしゃいます。今回、研修から生まれた一部の企画を実際の新規事業案として採用するに至った背景についてお教えください。
三宅様:今回の研修はそもそも「実践と具現化」に重きを置いていました。つまり座学とワークショップだけでなく、そこから生まれる「アウトプット」と「経営層へのプレゼンテーション」までを、研修の一連の流れとみなしておりました。

そのため、研修参加メンバーが経営層に新規アイデアのプレゼンテーションをする前には「これは演習ではなく『決裁する場』である。それを前提に評価していただきたい」と、あらかじめ経営層にインプットしました。
プレゼンテーションの採点基準は「提供価値(中島董商店として提供する必要性の有無)」と「市場価値」「新規性」「実現性」の4項目。役員が項目ごとに点数をつけ、プレゼンテーションの当日中に採用・不採用を検討し、結果を発表するという流れを設定しました。こういった事前準備をおこなったことで、結果的に2つの新規アイデアが採用されるに至りました。
苦労した点について申し上げますと、これは「新規事業案の採用後」のことになりますが、各DXリーダーたちも本来の業務との兼任で行っているため、新事業に関する会議開催の日程調整は非常に苦労しました。また新規事業案を具現化させる際には、企画段階では想定できていなかったさまざま「壁」が次々に出現します。それはアイデアを具現化させたいがゆえに現れる壁ですが、そこを打破するための検討には、かなりの時間を費やしました。
企業文化変革へ向かう、「最初の一歩」を踏み出せた
──研修実施後、御社の企業文化ならびに個別の業務などについて、どのような変化が発生しているでしょうか?
小笠原様:まず会社視点で申し上げますと、今回のワークショップから「ワインの縁結び」というサービスが生まれ、実装されることとなりました。こちらのサービス内容は、当社が「食品事業」「ワイン事業」「ホスピタリティ事業(小売業)」「アセット事業」および「IT事業」からなる異業種集団であるからこそ、生まれ得たものです。そういった意味で、さまざまな事業が一体となって結集できた際のパワーの大きさを実感したと同時に、「うちの会社、実は凄い!」ということに社員が気づく貴重な機会になったのではないかと思います。
個人の視点からですと、以前は時間に追われるがまま、ベターと思われる従来の方法で仕事を行っていました。しかし現在は、必要な際にはいったん手を止め、「もっと効率的なやり方はないか?」「社内での二度手間を防ぐ方策はないか?」と考え、小さなことでも関係者に共有し、「ベストなやり方」を求めることを意識できる自分に変われたと思っています。
具体例としては、例えばRPA(Robotic Process Automation)の一種であるPAD(Microsoft Power Automate Desktop)を使った開発を習得して自分や部内の業務の一部をロボット化し、「創出するための時間」を作れるようになりました。現在、その取り組みは、他の社員にも広がっています。今後はPADが中島董商店のメンバーにとって、Excelと同じぐらい「当たり前に使いこなせるツール」になることを期待しています。

石井様:正直、まだまだ「企業文化や体質が大きく変化した」という段階ではないと感じています。しかし、そんななかでも各種ツールやシステムが改善されたことで、それを利用するメンバーからは「便利になった」「時短になった」という声が上がっています。以前はITに前向きではないメンバーも多かったのですが、今では「やってみたい」という姿勢に変わってきたように思います。つまり企業文化が変わる「きっかけ」になったと考えています。
三宅様:企業文化というのは、まずは個々のマインドが変わり、それが結集することで醸成されるものだと考えています。そういった意味で「最初の一歩」は確実に踏み出すことができました。一歩ずつの歩みと検証サイクルを継続させていったときにふと振り返ると、「実は大きな変化が生まれていた」ということになるのでしょう。そうした積み重ねの中で変わっていくことこそが中島董商店という「やや真面目すぎる会社」には合っているのではないかと思います。
DXを通じて「中島董商店だからこそ創出できる価値」を届けたい
──研修を担当したFLMに対する評価をお聞かせください。
小笠原様:FLMさんは決して単なる第三者ではなく、「常に寄り添い、そして導いてくれる存在」でした。そこがユニークであり、かつ素晴らしい点であると感じています。またワークショップから生まれた「ワインの縁結び」というワイン検索サービスは、まずは当社の拠点のひとつである「仙川キユーポート」の社内売店にてトライアル実装されたのですが、トライアル中にはFLM講師の方が来てくださり、研修だけでなくその後生まれたサービスを実際に見にきて使ってくださったことを、本当に嬉しく感じました。
石井様:他社の研修と比べると非常にわかりやすい内容であったと思います。そして寄り添っていただけるだけでなく、さまざまな目線から「ヒント」も与えていただけたことで、自ら新たなアイデアを捻り出すきっかけにもなりました。短期間で経営層から事業化のGoサインが出る新事業を生み出すことができたのは、まさにこの研修があったからこそでしょう。
三宅様:研修内容を詰めていく話し合いのなかで、こちらの想いや要望を確実に汲み取っていただき、本来のコースにないカスタマイズもしていただけました。そして研修当日はイレギュラーなことも数多く発生したはずですが、それも上手にさばいていただけました。社交辞令は抜きで、本当に良い研修になったと思っています。
──最後に、今後の御社はどう変化していくことになるのでしょうか?ビジョンあるいは意気込みを教えてください。
三宅様:「自ら変化できる企業」というキーワードでDX推進を行ってまいりましたが、やっとそのスタート地点に立てたと感じています。もちろん一過性であっては意味がありませんので、「コラボレーティブ」「チャレンジ」「アジャイル」という我々が大切にしている3つの要素を大切にしながら、スピード感も兼ね備えた真面目な企業になることを、引き続き目指してまいります。そして「我々だからこそ創出できる価値」によって、社会全体に貢献していきたいと考えています。
富士通ラーニングメディア担当者からのメッセージ
 (左)ナレッジサービス事業本部 古舘 孝敏
(左)ナレッジサービス事業本部 古舘 孝敏
(右)カスタマーサクセス本部 伊藤 倫子
DX推進に向けた人材育成と企画創出、変革を支える組織風土の醸成を、実践型教育でご支援しました。
「人材育成から始めていきたい」と語られた中島董商店様ご自身も、当初は手探りでいらっしゃいました。ご担当者様と弊社の営業・講師で議論・対話の場を何度も設けて、お客様と共に教育プログラムを構築し、経営層・上長の理解を育むリテラシー教育と、DXリーダー育成と企画創出を両立した実践型教育を実施しました。
実践型教育から生まれた事業企画や業務変革案はPoC(実証実験)を経て実装され、また企画創出を全社で支える空気が醸成され始めたと聞き、とても喜ばしく思います。本教育が、中島董商店様の新たな取り組みの一助になりましたら、大変光栄です。(古舘)
中島董商店様の明確なビジョンと、それを実現しようとする揺るぎない姿勢に、いつも深く感銘を受けています。
研修を共に創り上げていく過程においては、中島董商店様のご尽力とご協力を常に感じており、心より感謝申し上げます。
これからも、中島董商店様の「新しい価値」創造への挑戦を全力でサポートしていきたいと考えています。(伊藤)
※ 本記事の登場人物の所属、役職は記事公開時のものです。
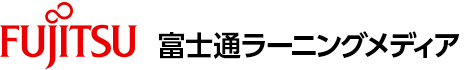


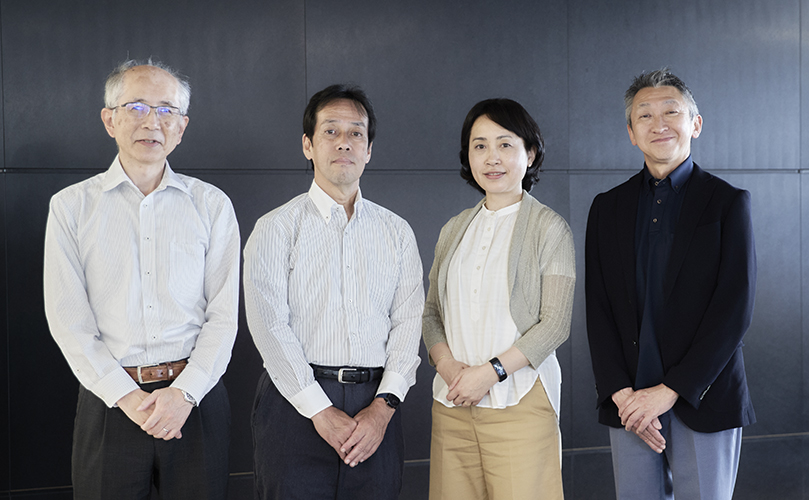 【お客様インタビュー】マツダ株式会社 様
【お客様インタビュー】マツダ株式会社 様