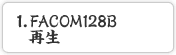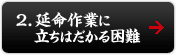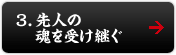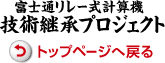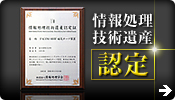- 早わかり 富士通の歴史
- 製品展示室
- 富士通アーカイブズ
- 池田記念室
-
リレー式計算機 技術継承プロジェクト
- プロジェクト仕掛け人に聞く
- コンピュータ黎明期の熱き魂を未来へ
- 技術継承プロジェクト概要
- FUJITSUサイトトップページ展示室
コンピュータ黎明期の熱き魂を未来へ 「FACOM128B 再生」
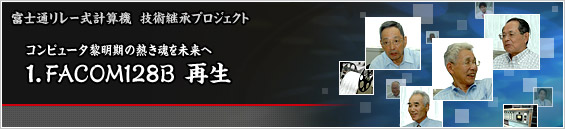
2008年夏、富士通川崎工場に8人のエンジニアたちが集まった。現存する世界最古級のリレー式計算機FACOM128B(1959年製)とFACOM138A(1960年製)を、今後少なくとも10年は動かし続けるプロジェクトの半期に一度の報告会だ。その参加メンバーは富士通を定年退職したOBの池田洋一氏、佐藤靖夫氏、竹中一生氏。この3人は、現役当時リレー式計算機を実際に保守していた数少ない経験者たち。技術の継承者側からは20~30代の児玉豊氏、濱田忠男氏、二瓶健一氏が参加している。さらにこのメンバーに加えて、プリンタなど周辺機設計を担った小平昭次氏、プリンタ製造に携わっていた伊東勝己氏のOB2名が参加。プロジェクト立ち上げの経緯と活動の詳細について語ってもらった。
OBのみなさんが再びリレー式計算機保守に携わることになった経緯をお聞かせください。

小平
1976年に沼津工場が建設された当時、工場内に何か記念になるものを作ろうという話が持ち上がったそうです。沼津工場は超大型・大型コンピュータの工場なのだから、富士通コンピュータの生みの親である池田敏雄さんの資料を集めた池田記念室を作ろう、池田さんが最初に開発したコンピュータをここに設置しようではないかということになったのです。すると、日本大学にかつて納入した1959年製のFACOM128Bが使われないまま眠っていることがわかったので、これを沼津工場へ移設することになったのです。

池田
そこで、リレー式計算機が現役だったころ、保守に係わっていた私と佐藤さん、開発課にいた竹中さんが、1976年9月に呼び出されました。私は1960年に入社して、しばらくの間リレー式計算機の保守とオペレーター業務を担当していましたが、その数年後にはトランジスタ式計算機FACOM222やFACOM230シリーズが登場し、新しい計算機の保守技術開発を担当しており、リレー式計算機とは縁が切れていました。なので、実に十数年ぶりの再会でした。
 点検するときは機械の動きと音に注意を払う
点検するときは機械の動きと音に注意を払う

佐藤
私も15年ぶりでしたから、懐かしかったですね。よく生きていたなあ、という感じでした。

池田
ところが、沼津に行ったら、ただ移設するだけでは面白くないから、動かそうという話になっていましてね、びっくりしました。

佐藤
目の前の実機を見たら、まさに瓦礫の山、ケーブルは絡まり放題でしたから。でも当時の上司から、動くようになるまでは絶対に帰ってくるな、と檄(げき)を飛ばされていたので(笑)、何が何でもやらなきゃいけない。まずは工事屋さんが配線の図面を見ながら組み立てていくのですが、その時は最低でも2~3ヶ月は掛かるだろうと思っていました。

池田
調整を始めたころは、できたばかりの沼津工場従業員寮に週3日泊り込み、3週間くらいで動かすことができました。工事図面から配線図面まで、すべての図面がしっかり残っていたからです。リレーという部品はいわば情報の橋渡しで、陸上競技のリレーと同じく情報をバトンタッチしてゆく役目があるのです。情報がどこかでちょん切れているのなら、その原因箇所を追っかけなくては分からない。それには図面が大切なのです。

小平
プリンタや紙テープ装置については、その油汚れを取るために、産湯用のブリキのたらいを買ってきて、それに石油を入れ、部品一つひとつをブラシ洗浄しました。

竹中
計算機の諸機能の一つ一つの試験と確認を繰り返し、完全に稼働するまでには約2ヶ月掛かりました。日本大学から沼津工場に移設したため、ケーブル工事が必要で、その設計から実際の作業までを工事会社に依頼しました。その工事に起因する障害原因を追究しては手直しを加えるといった作業の繰り返しでしたから、組み立て直し、動くかどうか確認したら、リレーの音がカシャ、カシャと綺麗に鳴り出したのは懐かしかったですね。いまのコンピュータはこういう音はしませんからね。
その12年後、1988年に富士通川崎工場本館が竣工したとき、技術展示室(現・富士通テクノロジーホール)の目玉展示として、沼津工場の倉庫にバラバラに分解・保管されていたFACOM138Aを甦らせる計画が持ち上がり、再び我々が動員されたのです。
 1976年に蘇ったFACOM128B。今も沼津工場で動き続ける
1976年に蘇ったFACOM128B。今も沼津工場で動き続ける「FACOM222、FACOM230シリーズ」
FACOM222は1961年に発表された富士通初のトランジスタ式計算機で、当時国産最大の汎用機。1962年に発表された小型汎用機FACOM231を核にその後、中型機FACOM230、大型機FACOM230-50が開発され、FACOM230シリーズが完成した。