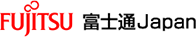2023年8月更新
ESG経営に取り組むメリットや実践のポイント、実施時の課題とは(1)

ESG投資という言葉が各所で聞かれるようになってきた現在、このESGを主軸とした経営戦略を採用するESG経営は企業として長期的な成長戦略を描く中で重要な位置づけを持っています。
サステナブル投資を普及するための国際団体であるGSIAがESG投資の7つの手法を出すなど投資の世界でも重要視されるESG経営はどのようなものなのか、注目されるに至った背景やメリットやデメリット、実践する場合の課題点などをお伝えいたします。
- 目次 -
ホワイトペーパー:ESG経営実践のための具体的手法
1. ESG経営とは
ESG は非財務の情報でありながら企業が投資する際に活用され、より良い経営をしている企業を表す指標です。

2006年に当時国連事務総長だったアナン事務総長が提唱した概念でそれぞれ環境(Environment)・社会(Society)・ガバナンス(Governance)の頭文字を取っており、それぞれ以下のような課題を解決することを求めています。
<環境(Environment)>
- 二酸化炭素(CO2 )排出量の削減 、廃水による水質汚染の改善、海洋中のマイクロプラスチックといった環境問題対策。
- 再生可能エネルギーの使用や生物多様性の確保など
<社会(Social)>
- 適正な労働条件や男女平等など職場での人権対策。
- ダイバーシティ、ワーク・ライフ・バランス、児童労働問題、地域社会への貢献など
<ガバナンス(Governance)>
- 業績悪化に直結するような不祥事の回避、リスク管理のための情報開示や法令順守。
- 資本効率に対する意識の高さなど
ESG経営とはこのESGの観点を経営戦略に盛り込み、企業の価値を高めると同時に事業継続性を高めるための経営手法となります。
2. ESG経営が注目される背景
アナン事務総長が行った提唱は金融業界に向けたPRI(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)です。
その結果として最近では機関投資家も SDGs や ESG に関する感度を上げており、特に欧州の機関投資家の要請でファンダメンタルの運用の中にESGを盛り込むケースが増えています。
国内でも金融庁が「ESG 評価・データ提供機関等に係る専門分科会報告書」において「現行で特段の規制が存在せず、当局による監督等が及ばないESG 評価・データ提供機関に関する部分について「ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範」(the Code of Conduct for ESG Evaluation and Data Providers)として市中協議を行った上で、取りまとめ・公表するべき」と提言があるなど政府としての注目度も高まっています。
参考:https://www.fsa.go.jp/singi/sustainable_finance/siryou/20220627/1.pdf
![]()
つまり市場から資金調達を行っている企業はこの方針を示すことでその調達力を向上し、企業価値を高めることができる仕組みとなっているのです。
3. SDGsとESGの違い
ESGはSDGsと共通する課題もありますが、大きな違いは概念の違いとなります。
SDGsは国連サミットによって採択された各国政府全体の目標であるのに対し、ESGは企業が経営や投資の分野において価値を高めるために取り組むべき目標です。
取り組み主体が異なっており、SDGsは国家や国際社会が主体となった全世界的な取り組みに対し、ESGはあくまでも個々の企業が取り組む活動となっています。
国際社会がSDGsの目標を達成するための活動として各企業が行うESGが存在する、といった関係性があり、ESGに取り組まない企業は長期的な成長に対する観点が弱いと判断され市場にそっぽを向かれる形となってしまいます。
4. ESG経営を実践するメリット・デメリットとは
ESG経営の実施に当たってはメリットとデメリットが存在します。
企業によって異なる部分はありますが、代表的なメリットは以下の通りです。
<投資家からの資金調達が見込めること>
投資方針としてESGが多くの機関投資家から注目されているため取り組んでいる企業がより多くの資金を調達可能になります。
GISAはESG投資の7つの手法として以下のようなリストを出しており、機関投資家はそれぞれの手法を採用し適合した企業に対して投資を行う方針を取ることになります。
- ネガティブ・スクリーニング
- ポジティブ(ベスト・イン・クラス)・スクリーニング
- 国際規範スクリーニング
- ESGインテグレーション
- サステナビリティ・テーマ投資
- インパクト・コミュニティ投資
- エンゲージメント・議決権行使
<リスク対応力が高くなり経営が安定する>
災害やパンデミック、近年のウクライナ危機など様々な要因で市場環境が激変する中ESG経営を行うことで想定外のリスクに対する対応力が高まり事業継続の安定性が出てきます。
<環境及び社会に対する責任を果たすことにより中長期的な自社のブランディングに寄与する>
SDGsの概念が一般常識として浸透している中、企業の取り組みとして共通項が高いESG経営を行うことはブランディングの観点でも意義があり、採用活動や市場での営業活動においてもプラスに影響します。
社員の定着はすなわち企業としてのスキルの蓄積、ノウハウの伝達にプラスに働くため大きな強みとなります。
反対に想定されるデメリットは以下の通りです。
<直接的なコストの増加>
福利厚生の拡充、テレワーク体制の構築、環境に優しい資材の利用などESG経営を実践するにあたってコストが増加することが想定されます。
許容できる範囲を財務上どこに設定するかを検討のうえ適切なラインを算出する必要があります。
<管理コストなどの間接的なコスト増>
管理体制が変わることによる管理コスト増やCO2排出量データのとりまとめコスト、またIRのための資料作成コストなど管理面でのコスト増も想定されます。
ソリューションの導入などによる間接コスト抑制もスコープに入れて検討を行うのが最善と言えます。
<短期的な業績への影響>
部門によっては今までと大きく工程が変わる可能性もあるため効率が一時的に下がってしまう可能性があり、経営層としてそのリスクと対応を検討したうえで実施しなければ短期的には業績が悪化してしまう可能性が発生します。
株主への説明責任が発生するためその背景を納得してもらうためのコストは無視できない影響を及ぼします。
それまでの事業活動において取り組んでこなかったESGという概念を新たに取り入れる場合は長期的な活動であることを念頭に財務計画や業績見込みなどについて整理したうえで投資家に対して「なぜ今ESGに取り組むのか」「なぜESG経営を行うことで長期的な成長が見込めるのか」について明確な説明を行い既存株主に納得してもらう必要があります。
● ホワイトペーパー:ESG経営実践のための具体的手法
「環境・CSR ・ SDGs 等のデータを一元管理したい」「データの自動集計をしたい」「法律の報告や調査機関などへの情報開示を支援してほしい」といった要望に応える方法をまとめたホワイトペーパーをご用意いたしました。
Eco Trackがお客様に選ばれている理由についても詳細に記載しております。
ESG経営の検討を進める企業の皆様にぜひ一度ご覧いただき、どのようにして効率的なESGデータ収集を行っていくべきか把握していただければと思います。
ホワイトペーパー:ESG経営実践のための具体的手法
富士通Japan株式会社
【事業内容】
自治体、医療・教育機関、および民需分野の準大手、中堅・中小企業向けのソリューション・SI、パッケージの開発から運用までの一貫したサービス提供。AIやクラウドサービス、ローカル5Gなどを活用したDXビジネスの推進。

おすすめコンテンツ
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)