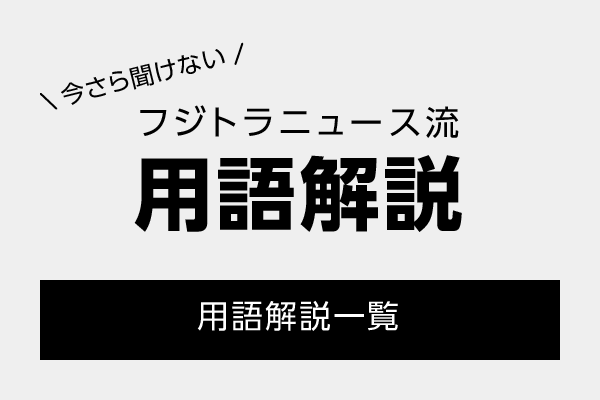流通サプライチェーンは、私たちの生活に欠かすことができない大切な社会インフラです。
一方で、そのプロセスにおいてさまざまなロスが発生しています。段ボールの汚れや傷に伴う返品もその一つで、実はこれが社会的ロスを発生させる深刻な社会問題につながっていることをご存じでしょうか?
この社会課題を解決すべく、富士通とサントリーは共同で、業界全体を巻き込みながら梱包段ボールの汚破損判定基準の標準化に取り組んでいます。
前編では、サントリー食品インターナショナル(株)生産・SCM本部SCM部 課長の玉井 浩氏とサントリーホールディングス(株)サプライチェーン本部 物流部 部長の中村 繁氏、そして、富士通(株)CPG事業部でビジネスプロデューサーとして本プロジェクトをリードする金澤 駿にプロジェクトの概要についてお話を伺います。
- 目次
段ボール汚破損による返品が引き起こす3つの社会ロスとは?
――まず初めに、一般消費者からは意識されにくい梱包段ボールの汚破損問題ですが、これはどのような社会ロスを生み出しているのでしょうか?
玉井氏: 私の仕事はサプライチェーンのマネジメントで、営業部門と物流部門の橋渡しをしながら、さまざまな課題解決にあたっています。その中の1つが、工場出荷時、倉庫保管時、配送時など、製品流通の各段階で発生する梱包段ボールの汚破損に起因する問題です。
梱包段ボールには中の製品を保護する役割があり、本来は、流通段階で多少の汚れや傷がついてしまっても、中身の製品に影響がない限り製品の販売は許容されるべきだと考えています。ところが、配送事業者(メーカー側)が、中身の製品にまったく問題が無いと判断しても、段ボールの少しの汚れや傷が原因で、お届け先からメーカー側に返品されてしまうケースが少なくありません。
「食品ロス」というと、食べ残しを思い浮かべる方も多いと思いますが、実はこういった返品もその原因の一つとなっています。返品された製品自体に問題がないことが確認できたとしても、梱包し直して再出荷した際には、すでに製造日の新しい製品が先に納品先に届いていることになります。これは「ロット逆転」といって、在庫管理上、結果的に古い製品を破棄するケースに繋がるのです。
また、返品になると現場担当者間でのやり取りや手続き等が必要になり、ドライバーの待機時間が増える「輸送ロス」、梱包のやり直しにより現場の労働負担が増える「作業ロス」も引き起ります。

――なぜ本来ならば持ち戻り・返品(や廃棄)をしなくても良いものまで処理が必要となってしまっているのでしょうか?
玉井氏: 問題は、流通サプライチェーンの複雑さと、現場における汚破損判定基準の曖昧さです。目視による梱包段ボールの汚破損の判断基準は、「飲料配送研究会」(※1)という団体より提唱されていますが、得意先の現場担当者や業務委託する物流会社まで浸透されていないことが実態です。
倉庫内の個々の担当者の出荷可否判断にバラつきがあるのに加え、荷崩れや破損が生じた際の廃棄基準は現場担当者間で判断されます。そのため、配送事業者と受け取り手(お届け先)の間で、一方の納得が得られず、結果的に返品となるケースもあります。
- ※1飲料配送研究会とは農林水産省、経済産業省、国土交通省及び国税庁、中小企業庁は飲料配送の関係者(メーカー、卸売業、小売業)や法律の専門家等を構成員として飲料配送に係る商品の毀損範囲の決定や毀損した商品の廃棄の費用負担などについて議論を行っている研究会。
流通業界全体を巻き込んだ段ボール汚破損判定基準の標準化に挑戦
――こうしたロスは、ビジネスにどのような影響を与えているのでしょうか?
玉井氏: 2019年の持ち戻り・返品数量実績と判断ミス率から一連のロスの最大モデルを計算すると年間約1100万円のロスが試算されました。比率的には、作業ロスが約2割、製品廃棄ロスが約7割、物流ロスが約1割というところです。
このような状況に対して、どこまでの汚破損なら許容できるかを標準化できれば、無駄が省かれてコストダウンにもつながります。
ただ、サントリーの中だけで判断基準の標準化がされただけでは、社会的な影響は限定的です。
この問題は、社会全体のサステナビリティの実現へとつながるため、賛同して頂ける企業をできる限り増やして、業界全体で判断基準の標準化に取り組む必要があります。
同じ問題を抱える企業同士が力を合わせて判断基準を見直していくことで、流通業界全体として社会ロスを減らしていけると考えています。
そのために、社会課題の解決を目指す富士通様は最適なパートナーでした。
金澤: 私たち富士通としても、この段ボール汚破損における返品課題・製品ロスがサントリー様一社の悩みではなく、流通サプライチェーン全体で解決すべき問題であると捉えておりました。そのために、食品・飲料メーカーの業界垣根を越えて、卸売業や小売業までを巻き込んだ判断基準の標準化への取り組みをサントリー様と共同で開始しました。

現場の声を活かしたAIによる実証実験で、誰もが納得する判定基準を目指す
――具体的には、判定基準の標準化に向けてどのような取り組みを行っているのでしょうか?
中村氏: 私は、サントリーグループの物流部で製品物流における安全と品質の責任者を務めています。まずは現場の実態を把握するため、サントリーロジスティクス(株)三郷倉庫にて実証実験を始めました。
実際に出荷可否の判断を行うのは現場の人たちなので、彼らの声を聞くことが重要です。
具体的には、試作されたAIツールで汚破損のある段ボールの写真を撮り、サンプルを数多く集めます。それらを現場の担当者と1枚ずつ確認し、判定結果をフィードバックすることで精度を高めていきました。

玉井氏: 特に、湿度が高い時期に段ボールの側面が膨れ上がる胴膨れや、ペットボトルの重みによる表面の変形などは判定が難しいです。AIツールを使った汚破損判定が納得できるレベルにあるかどうか、現場の意見が重要な判断材料となりました。
私たちが目指しているのは、ある意味で判定基準の標準化なのですが、同時に誰もが納得できなければ意味がありません。双方を実現する上でも現場のノウハウが活かされています。
――今もAIの精度向上や業界への働きかけを続けられているとのことですが、現時点までの実証実験による成果はいかがでしょうか?
玉井氏: 20年から2年間で飲料配送研究会の基準に合わせて基準外製品を出荷しない活動を物流部門、営業部門でそれぞれ行ってきました。物流部門は中村のグループが中心となり全国各地の物流協力会社様と日々の対策活動を図ってきました。営業部門ではお得意先である卸売業、小売業に対して基準内製品の荷受け商談を行った結果、持ち戻りや返品は20分の1に減少しました。
物流業界の人材不足が常態化していく中、倉庫では外国人の雇用も進んでいます。文化が異なる方々に判断基準の写真や絵だけで汚破損基準を理解させるのは困難です。また、新任者への教育の手間も課題となっています。今後はソリューション開発の途中段階ではありますが、AI技術を活用する事で標準化や簡素化に有効活用できると期待しています。
中村氏: 中身の製品に問題ないものを持ち戻るのは、まさに判断基準の曖昧さを起因とした無駄であったと感じております。この問題が解決されるだけでも十分に意義があると考えていますが、結果的にトラブルも減り、これまで矢面に立たされていた配送ドライバーも含め、誰もが気持ちよく働けるよう労働環境が変化することも期待しています。
金澤: 汚破損した段ボールの画像データや出荷可否に関する業務記録などをデータとして蓄積できることで、具体的な返品率やこれまで把握しきれずにいた現場の問題が見える化された点も本プロジェクトを通して気づけたポイントだと考えています。

――業界全体に対する今後の展開構想については、どのように考えられていますか?
玉井氏: 業界への展開構想としては、大きく分けて以下の5つの段階で考えています。
1)プロトタイプによるPoC
2)サントリー内での実証実験
3)他メーカーの参画
4)業界垣根を超えた卸売業・小売業の参画
5)官公庁、業界団体への協力・支援要請
現在は、共同実証実験の中に競合メーカーと大手小売業様を加えた3.5段階で、業界巻き込み活動に注力し、本取組を拡げているところです。
4)業界の垣根を超えた卸売業・小売業の参画については、流通各社様に本取組の紹介や、今後の参入可能性についてのディスカッションを行なってきました。その結果、多くの賛同意見が得られ、社内外の両方で、判断基準を標準化しようという流れが強化されたと感じています。標準化の意義を説明する際にも実証実験による実例を見せることができ、説得力が増しました。
金澤: 「サプライチェーンイノベーション大賞2020」(※2)において、優秀賞をサントリー様が受賞頂いたことで、社会からの共感・賛同をいただけている取り組みであること、官公庁や業界からの取組み認知にもつながっていると考えています。
玉井氏: ありがたいことに、大手流通業者にも関心を寄せられていますが、これは、働きやすく生産性の高い物流を目指す「ホワイト物流」の動きとも関係するものです。これからは限られた労働力をうまく使って、効率よくビジネスを回していくことが求められます。
物流の現場では特に配送ドライバーの高齢化が進み、平成30年12月には有効求人倍率が3.03倍になるなど、深刻な人材不足に陥りました。また、運送・物流業界における時間外労働時間の上限が年960時間に制限されることで生じる「2024年問題」もあり、会社にとっては売上・利益の減少、従業員にとっては収入の減少、荷主にとっては運賃の上昇などの懸念が出ています。そのため、現場での待機時間を減らす、検品時の無駄をなくす、外国人労働者に対する検品基準を明確にし、研修の効率化を図るなどの対応が迫られています。
こうした問題にも、本取り組みが貢献できると考えています。
- ※2「サプライチェーンイノベーション大賞」とは、サプライチェーン全体の最適化に向け、製・配・販各層の協力の下、優れた取り組みを行い、業界を牽引した企業に対して、製・配・販連携協議会がその功績を表彰するもの。

SDGs達成の鍵を握る業界と消費者の意識改革
――このプロジェクトは、SDGsとのつながりも強く感じられますが、特にどのようなゴールの達成に貢献していると思われますか?
玉井氏: まず、12項の「つくる責任、つかう責任」に当てはまります。私たちは、つくる責任の一環として梱包段ボールを流通に利用しているので、これに起因する社会ロスを削減できれば、社会貢献につながります。加えて、特に輸送ロスの削減は無駄なエネルギー消費の抑制になりますから、13項の「気候変動に具体的な対策を」にも該当するでしょう。
これら2つの項目がメインですが、少し拡大して考えると、食品ロスを減らすことは2項の「飢餓をゼロに」、気持ちよく働けることは8項の「働きがいも経済成長も」、現場の情報とAIの組み合わせで新たな価値を作り出すことは9項の「産業と技術革新の基盤を作ろう」につながります。そして、将来的に検品の無人化や自動化が実現すると従業員の生活環境の改善にもなって11項の「住み続けられるまちづくりを」に通じ、富士通様や業界各社と協力して問題解決に取り組むことが17項の「パートナーシップで目標を達成しよう」に相当するといえるでしょう。
まだ先は長いですが、こうしたSDGsやDXの観点から、問題意識と改革に向けた機運が、点から線、線から面へと広がっていく可能性を感じています。
――最後に、改めて今回のプロジェクトに対する思いや、その先にある理想の社会についてお話しください。
玉井氏: これまでも営業スタッフの9割に対して、飲料配送研究会の判定基準や汚破損が起こるメカニズムなどに関する勉強会などを行なってきました。サントリーグループには創業以来の「やってみなはれ」の精神がありますが、来年には、今回の新しいAIツールの有効性やDXに基づく物流のあり方についても営業スタッフに学んでもらい、「この会社にはいつでもだれでも社会を変えていける環境がある」ことを理解してもらおうと思っています。そして、アジャイル型の取り組みによって、富士通様と一緒に社会改革の可能性を広げていくことが目標です。
中村氏: 2019年から苦労を重ねて、このソリューションを倉庫のスタッフと共に改善してきたわけですが、最終的にはお客さまの理解も得て、トータルで良い状態にもっていくことを目指します。そして、無駄な作業を出来る限り削減して、誰もが価値を感じられる職場で働けるようになることが理想です。
日本には、品物に「のし」を添えたり、美しい「風呂敷」で包むといった包装文化がありますが、そうした文化的背景から、梱包の外箱にも美しさや完璧さが求められてしまうのかもしれません。一方で、輸入製品の段ボールの場合には、現場でもある程度の汚破損が許容される傾向が見られ、国内外のスタンダードが異なっています。美的感覚と社会課題解決のバランスをとることが大切ですので、今回のプロジェクトがそうした意識改革を促すことに期待したいですね。
玉井氏: 人々の意識の変化とともに基準自体も変わっていくので、それにAIが追従できる仕組みを、現場や業界各社の皆氏と一緒に作っていきたいです。
金澤: サントリー様の協力を得て、AIによる汚破損判定の仕組みが一定の評価を得るところまで仕上がってきましたので、このまま取り組みを継続して、最終的には業界標準にまで持っていくことを目指します。あくまでも、1社のみのメリットや利益を追求するものではなく、業界全体として社会課題の解決とSDGsに貢献するための仕組みであることに本取組の意義と価値があると考えています。
サントリー様の改革への思いをしっかりと受け止めながら、このプロジェクトを通じて社会課題の解決に貢献していきたいと思います。

後編では、流通業界全体を巻き込んだ社会課題解決を目指す前例のない仕組みがどのようにして生まれたのか、その開発秘話をお届けします。
(後編に続く)
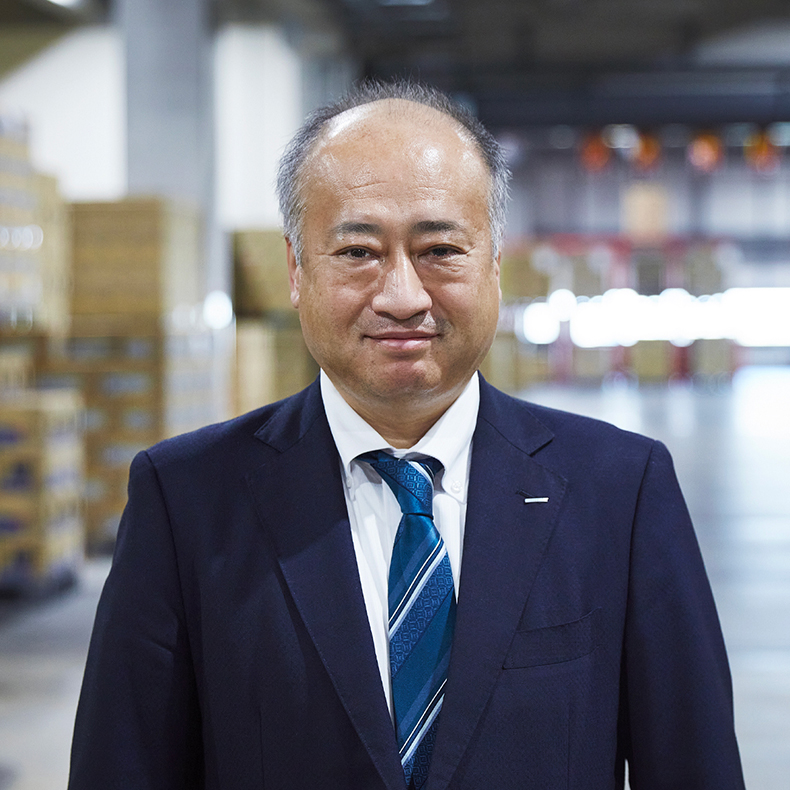 玉井 浩 氏
玉井 浩 氏サントリー食品インターナショナル株式会社
生産・SCM本部SCM部 課長
 中村 繁 氏
中村 繁 氏サントリーホールディングス株式会社
サプライチェーン本部 物流部 部長
 金澤 駿
金澤 駿富士通株式会社
CPG事業部 ビジネスプロデューサー