導入事例 岡山中央総合情報公社様
オンラインサービスの全面Webシステム化
~Interstage for GSによる行財政運営の効率化とサービスの均一化~
[2004年12月10日 掲載]
 岡山中央総合情報公社様は、昭和40年代より、岡山県北部の自治体様を対象とした情報処理や設備の共同運営を実施するという、当時では非常に珍しいアウトソーシングビジネスを展開され、全国的にもモデルとして高い評価を受けておられます。
岡山中央総合情報公社様は、昭和40年代より、岡山県北部の自治体様を対象とした情報処理や設備の共同運営を実施するという、当時では非常に珍しいアウトソーシングビジネスを展開され、全国的にもモデルとして高い評価を受けておられます。 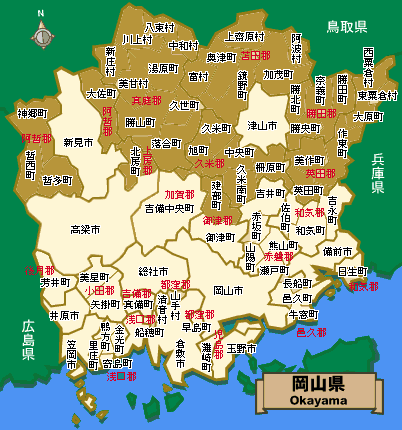 小規模市町村も参画できる共同利用の仕組みは、参画団体のそれぞれの良さを吸収し、積み重ねながら、時代に合わせて柔軟に形を変えてきました。
小規模市町村も参画できる共同利用の仕組みは、参画団体のそれぞれの良さを吸収し、積み重ねながら、時代に合わせて柔軟に形を変えてきました。
現在(2004年10月)では岡山県の38市町村、鳥取県2町村、島根県4町村の共同処理運営を行っています。自治体規模としては人口23万人相当になります。
日経パソコン(2004年8月30日号)のe-都市ランキング2004では他の町村と比較して高い評価となっています。
ここでは、情報公社様のオンラインサービスの全面Webシステム化の取り組みについてご紹介します。
導入の背景
着眼点と設立のタイミング
 岡山県北部の市町村におけるコンピュータの共同利用のあゆみは、昭和43年までさかのぼります。津山市内の会計事務所に導入された1台のコンピュータを見て、これからの時代は手計算ではなくコンピュータの時代になるであろうと考えたのが最初の着眼点でした。
岡山県北部の市町村におけるコンピュータの共同利用のあゆみは、昭和43年までさかのぼります。津山市内の会計事務所に導入された1台のコンピュータを見て、これからの時代は手計算ではなくコンピュータの時代になるであろうと考えたのが最初の着眼点でした。
その当時、津山市と周辺の14町村が広域圏制度の第1号に指定されたのを受けて、その核として行政の情報化とその共同利用という大きな目標を掲げました。道路整備ができていない時代であり、他の多くの広域圏では道路整備に力を注いだのに対し、行政の効率化・事務処理の統合化=住民サービスの向上に目を向けました。税計算等を手処理で行っていた頃に共同利用組織を構築することで、各町村は安価でかつ高度に標準化された行政基盤を整備することができました。
今振り返ると、当情報公社設立の発想は、かなり先見的であったと思っております。
導入の経緯
導入システムのアウトソーシング
 コンピュータの共同利用はエリアをカバーして行う消防組織に似ています。
コンピュータの共同利用はエリアをカバーして行う消防組織に似ています。
人口の少ない市町村が単独で高額なコンピュータを購入して管理運営していくことは困難です。ならば民間に委託するという方法もあります。しかし、行政に関してはそうもいかないので、各市町村の行政の専門委員を情報公社に集約し、制度の開発や、行政の電算化を行いました。特徴的なのは、行政の事務を中心に行政の専門家が実務をやっているということです。35年も前からアウトソーシングを先行して行ったことになります。
システム化の要件
2002年11月、加盟市町村からの要望を受け、情報公社はオンラインサービスをWebシステムへ全面移行する方針を打ち出しました。
システムの概要
既存資産の継承
2003年に稼働したIAサーバによるシステム構築の経験を元に、あえてメインフレームを活用するミドルウェア "Interstage for GS" を選択しました。
Web化システムの検討では、これまでメインフレーム上で培ってきたCOBOLアプリケーションを活用して、効率よくWebに移行できるかが最大の課題となりました。IAサーバによるシステムの構築時には、パッケージソフトを使用して効率化を図ったのですが、情報公社から見るとブラックボックスの点が多くて、万が一の時に対応が困難になるのではないかと不安に思っています。その点、メインフレームのCOBOLアプリケーションであれば、情報公社で迅速な対応が可能です。
また、メインフレームでは、同一業務のエミュレータ版とWeb版が共存できます。情報公社では、各町村ごとのパソコンのリースアップタイミング等も考慮して、サービスを提供する必要があります。情報公社の都合で、勝手に一括して新しい方式に切り替えることはできません。この点、メインフレームであれば、運用だけで簡単に切り替えていくことができます。
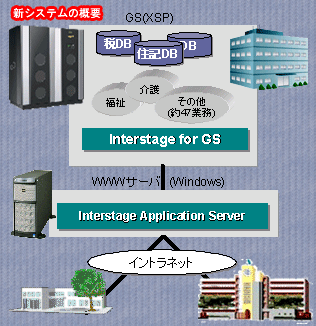
INTERSTAGE for GSを選択した理由
メインフレーム継続活用の指標~4つの観点~
信頼性
 自治体の一部の部門で使う業務であれば、サーバでよいでしょうが、多くの市町村で使用している基幹系業務を止めるわけにはいきません。2003年に稼働したIAサーバの住記システムでは、信頼性を最優先に考え、待機サーバ等を配置し、万全の体制をとる必要がありました。サーバの信頼性が上がってきたとはいえ、複数のサーバが必要です。その点、メインフレームは1台で十分な信頼性が確保でき、しかも実績もあります。この点を高く評価しました。
自治体の一部の部門で使う業務であれば、サーバでよいでしょうが、多くの市町村で使用している基幹系業務を止めるわけにはいきません。2003年に稼働したIAサーバの住記システムでは、信頼性を最優先に考え、待機サーバ等を配置し、万全の体制をとる必要がありました。サーバの信頼性が上がってきたとはいえ、複数のサーバが必要です。その点、メインフレームは1台で十分な信頼性が確保でき、しかも実績もあります。この点を高く評価しました。
価格
メインフレームはサーバシステムと比較し、維持管理を含めたトータルコストが安価であると判断しました。
メインフレームはそれ一つで考えると、サーバよりも価格が高いように思えます。しかし、サーバシステムの場合、信頼性を確保するためにサーバを何台も導入する必要があります。実際、住記システムでは待機サーバや開発系サーバを含め、6台の構成となっています。昨今の技術の流れが変わっていくことや、市販のソフト製品の互換性の乏しさを考えると、その6台が数年後のリプレース時にそのまま使えるのか、保証がありません。その点、メインフレームは、富士通で互換を保証しています。万が一、非互換があっても富士通が対応してくれます。
つまり、この先数年後を考えても今の投資は無駄にならず、総合的に"安い"と判断しました。
運用
日々のバックアップの運用方法が、従来と変わらないことを評価しました。
サーバシステムのバックアップのためには新しいハード構成や機材が必要となる上、運用が煩雑となります。当然、サーバが増えると、サーバごとの運用が必要となります。
保守性
V/LアップやPTFアップでも、富士通で情報提供してもらえる点を評価しました。一般の市販ソフトではサービスパックが提供されますが、その内容から情報公社のシステムに適用すべきかどうかが判りません。その点、メインフレームは富士通から情報提供があり、安心して適用することができます。
これらの点から、我々は本来の業務システムそのものの開発や法改正対応等の維持管理に専念できることも大きなメリットと考えます。
メインフレームの資産を継承しつつWeb化を実現できる製品は幾つかありましたが、今後の電子自治体への展開等も見据えて、拡張性が高い "Interstage for GS" を選択しました。
新システム構築
 Web化にあたっては、従来と同じエミュレータ画面の操作性を保つことを優先しました。Java Appletですと従来の画面と同じにできますし、操作ボタン(PFキー)等も作れます。マウスに不慣れな方が選択ミスをすることも十分に考えられますので、PFキーのサポートは必須でした。
Web化にあたっては、従来と同じエミュレータ画面の操作性を保つことを優先しました。Java Appletですと従来の画面と同じにできますし、操作ボタン(PFキー)等も作れます。マウスに不慣れな方が選択ミスをすることも十分に考えられますので、PFキーのサポートは必須でした。
当初、情報公社ではJava Appletの知識がなく、Web化に対する不安がありました。そこで、誰でも作業を行えるように、富士通SEがCORBA通信を意識させない共通基盤や既存の画面(MEDやPSAM)と同様の動きをする共通部品を標準的に用意しました。これにより、Interstage Apworks(Java統合開発ツール)のプロパティを設定するだけでJava Appletが作成できるようになり、作業者はJava Appletを意識せずに、画面を作成することができました。
Interstage for GSでは、情報公社のCOBOLのノウハウを継承し、既存のCOBOLアプリケーションを流用してJava Appletと通信することができました。システム改修は、既存のCOBOLアプリケーションをメッセージファイルから表示ファイル化する必要がありましたが、画面操作、DB構成は極力変更しない方針で行いました。
システム構築で苦労した点
外字の対応に一番苦労しましたが、富士通SEの協力を得て、すべての外字の入力表示および帳票の出力が実現できました。
公共ネットワーク網の拡充で住民サービスの向上
今回構築したシステムは、岡山県が整備した岡山情報ハイウェイを利用することで、システム全体としての運用・サポートなどにかかるコストの削減が図れました。
また、新しく構築したシステムを利用された方からは、新たに教育を受ける必要もなく今までと変わらず使いこなせると、好評を得ています。
将来の展望
現在も進行している市町村合併に伴うシステムの統合では、情報公社も他業者との競合が発生します。競合しても選ばれるためには、今後も利用者主体の共同利用というスタンスで、費用対効果を重視し、より低コストで安定したシステムを提供することがミッションのひとつであると考えています。新しいものへの取り組みには決断が必要です。長年蓄えてきたノウハウやスキルで新しい技術に対応する力、新しいシステムを読みきる力を兼ね備え、地域住民サービスの向上を図っていこうと思っております。
【会社概要】
社団法人 岡山中央総合情報公社
- 所在地: 岡山県久米郡中央町
- 理事長: 辻 騏一郎(落合町長)
- 会員: 40公共団体(市町村)、2公共的法人(2004年9月1日現在)
- 事業概要: 岡山県北部市町村が情報処理を有効活用するために共同設立した、県知事認可の公益法人(社団法人)
- ホームページ: http://www.jkousya.or.jp/

本コンテンツについて
- 製品名など固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- その他、ここに記載されている製品名等には必ずしも商標表示(TM,(R))を付加していません。
なお、情報公社様のイメージデータについては、情報公社様よりデータを提供していただき掲載しています。許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを禁じます。