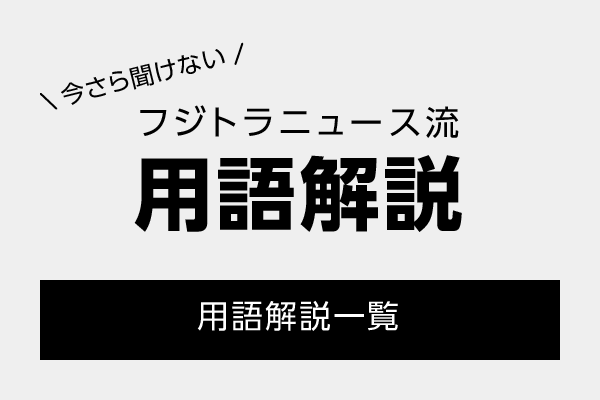富士通は、神山まるごと高専の取り組みに賛同し、スカラーシップパートナー(奨学金基金の拠出・寄附者)11社の1社として活動しています。「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指す同校とのコラボレーション活動について、私たちが学生らとともに、どのようにして「コトを起こす第一歩」を踏み出し始めているかについて前後編でご紹介します。後編は、コトを起こす実践事例として、現在取り組みを始めている神山町での地域課題解決についてお届けします。
- 目次
「全体のかけ算」による地域課題解決を目指す神山町
神山まるごと高専と富士通は、神山町とともにコトを起こす取り組みを始めています。本取り組みにおける【ゴールとなるコト】は、未来の町づくりにおいて地域交通を起点とした様々な地域課題が解決された姿です。
後編記事は、本取り組みの参加者6名(神山町総務課 杼谷 学氏、神山まるごと高専の学生の名和 真結美さん、付 媛媛さん、富士通Mobility事業本部の石川 勇樹、福井 伸彦、増野 晶子)へのインタビュー内容を元にお届けします。
 神山町、神山まるごと高専、富士通の関係者での会合の様子
神山町、神山まるごと高専、富士通の関係者での会合の様子
まずは、神山町総務課の杼谷氏に神山町の地域課題への取り組みについてお話頂きました。
 神山町総務課
神山町総務課
杼谷氏
神山町の人口は、現在5千人を切っています。人口減少は住民の暮らしに大きな影響を与えていますので、将来世代へ町をつなぐために地方創生の流れに神山町としても本腰を入れています。
元々、NPO団体など民間の動きは活発で、チャレンジできる土壌が整っていましたが、2023年4月の神山まるごと高専の開校は想像を超える出来事でした。せっかく若い力や英知が結集しているので、地域や高専と共に可能性が広げられる取り組みを一緒にできたらと思っていました。なので今回の共同での取り組みには期待を寄せています。
神山町としては、地域交通を起点として、経済循環、高齢者の安心な生活、地域外との関係性など分野横断的で、相乗効果の得られる「全体のかけ算」となるような課題解決方法が重要だと考えています。
神山町の町営バスは1970年代には、年間利用者が6万人に達していました。2023年4月からは、変わり行く町に合わせ、町営バスに代わって「まちのクルマLet’s」が運行を始めています。神山町の住民がアプリなどを通じて、神山町内のタクシー会社3社の利用ができる新たな公共交通サービスです。町の助成金によって、利用者は隣町の役場まで約20kmの移動でも約800円(個人負担15%)で移動できます。
国交省は「交通のリ・デザイン」と「地域の社会的課題解決」を一体的に推進することを掲げています。「全体のかけ算」という目指す姿とは共通する点があり、杼谷氏も「神山町だけではなく、全国の自治体へも貢献できるような取り組みにできると良いなぁ」と、考えているそうです。そして、これからの将来世代に向け「神山町」×「神山まるごと高専」×「富士通」での本取り組みの今後の展開に期待されています。
コトを起こすには、MaaSアイディア「ライドシェア」「貨客混載」だけでは足りない!
モビリティ(移動)を車等のモノの観点ではなく、サービスの観点から考えるMaaS(Mobility as a Service)の取り組みは、持続可能な都市交通の実現や自動運転の推進等の様々な文脈から世界規模で進んでいます。海外にいくとUber社の提供する一般ドライバーの提供するライドサービスをタクシー代わりに利用する人も多いかもしれません。こういったサービスでは、スマートフォンのアプリなどから乗客とドライバーをマッチングさせたり、貨物荷主とトラック運転手をマッチングさせたりといったサービスを、ユーザは手軽に利用することができます。
「ライドシェア(相乗り、配車)」サービスや、「貨客混載(ユーザと貨物を一緒に運ぶ)」サービスは、1台の車が最適なCO2排出量で移動することを可能にします。そのため、MaaS先進各国では、地球環境の持続可能性という文脈で必要性を議論されることも多いのですが、日本でのライドシェアは法律で規制されていました。
しかし、昨今、タクシードライバー不足の課題などに対応し、国内でも一部解禁の動きがあります。今後も、こういった柔軟なモビリティサービスが広がっていくと予想されています。
 リモート会議を活用した、神山まるごと高専×富士通のアイディエーションの様子
リモート会議を活用した、神山まるごと高専×富士通のアイディエーションの様子
神山まるごと高専の学生と、富士通Mobility事業本部との取り組みの始まりは、2023年春のアイディアワークショップでした。彼らは、神山町の未来の町づくりの中で交通がどうあると嬉しいかについて考え、サービスデザインの様々な手法同様、ユーザへ“共感”するフェーズから始めました。富士通Mobility事業本部のメンバーに、神山町住民の方々へ行ったヒアリングの背景、得られた気付きなどについて伺いました。
 富士通Mobility事業本部
富士通Mobility事業本部
石川(上段)、
福井(中段)、
増野(下段)
関係者にとってサービス全体がどのような形であると嬉しいか、将来の姿を明確にしていく為に現在地点を知ることから始めました。一つはデータ分析、一つはヒアリングです。
データ分析では、富士通研究所メンバーとも連携しながら進めました。ヒアリングでは、神山まるごと高専の学生とともに、住民とタクシー会社の方へインタビューを行いました。
この2つを通じて、神山町の新たな公共交通サービスLet’sは、多くの住民から利用されていること、将来にわたっての継続が望まれていることが分かりました。しかしながら、現在の仕組みは町の負担が85%とかなり大きい為、持続可能な仕組みとは言いにくい状況です。
また、住民の方へ直接お話を伺いながら実感したのですが、机上で解決策を考えて、Let’sを良くする仕組みを提供するといっても受け入れられないだろうな、と感じています。
一歩進んで、関係者を巻き込んで議論していくことが大事だと感じています。
住民とつながっていく神山まるごと高専生「神山町の未来の為に、私たちは何ができるか?」
2023年に一期生として入学したばかりで、早速、実際のコト起こしに取り組み始めている神山まるごと高専の学生、名和さんと、付さん。今回の取り組みで行ったユーザヒアリングでは様々な学びがあったようです。具体的には、学生である自分たちと事業者との考え方の違い、ステークホルダー間でバランスをとることの難しさ等を痛感したそうです。本記事の前編で教えて頂いたお二人のパーパスと本活動との関係について、お聞きしました。
 神山まるごと高専
神山まるごと高専
付さん
神山町の皆さんは、まさに私のパーパスの「相手を信じて信頼を」すること、そのものを体現しているように感じています。神山町の住民の方は、普段から神山まるごと高専の学生にとても親切にして下さいます。ヒアリングした際、住民の方と直接お話する良い機会なので、何故なのかを尋ねたら「歓迎したいんだよ」と教えてくれました。私も、この相手を信頼する姿勢で、皆さんとの良い関係を築けるよう、自分をプッシュしていきたいと思っています。
 神山まるごと高専
神山まるごと高専
名和さん
神山町×神山まるごと高専×富士通のコラボレーションでは、一人ひとりが内面に持っている美学を持ち寄って、互いにとって良い関係を創っていきたいと思っています。
タクシー会社へのヒアリングでは、神山町の住民の方と直接お話できました。神山まるごと高専生は、住民1年目の新参者ですが、本当に助けてもらっています。実際に対面でヒアリングできたことで、神山町やその方々の為に不利益にならないよう、何ができるかをより強く考えるようになりました。サービスをずっと続くものにしたいと思っています。
全国の未来の町づくりへも「横展開できる仕組みづくり」へ
本取り組みは、デザイン思考等のサービスデザインプロセスでいう、“共感”フェーズが終わった段階です。次の段階では、実際に社会へ実装するサイクルを素早く1周まわすことを計画しています。
現在、神山まるごと高専の学生と富士通Mobility事業本部は、他の事業者ら、活動に賛同して下さる方と共にサービスプロトタイプを使って、仮説検証を進めていくことの検討を始めています。神山町と共にサービスを作り、さらに次の段階では、他の自治体の課題解決に向けたサービスとしても横展開を図っていきたいと考えています。
ここまで、神山まるごと高専と富士通のコラボ活動について、コトを起こす実践事例として、現在取り組みを始めている、神山町での地域課題解決についてお届けしました。2024年4月に、新入生がコラボ活動へ参加しました。X(Twitter)やnoteでも、定期的に様々な取り組みをご紹介しています。是非ご覧ください。
関連リンク
- [プレスリリース] デジタルツイン上に人の行動を高精度に再現する技術を開発し、英国ワイト島にてシェアードeスクーターの運用改善に向けた実証実験を開始
- [ソリューションサイト] オンデマンド交通サービス
- [記事] コトを起こす第一歩:一人ひとりの自律的挑戦を支える原動力としてのパーパス
- [記事] ともにイノベーションを!神山まるごと高専×富士通のコラボがスタート-前編-
- [記事] ともにイノベーションを!神山まるごと高専×富士通のコラボがスタート-後編-
- [外部サイト] 公共交通がもたらす 豊かなコミュニケーション 「まちのクルマ」プロジェクト
- [X] 神山まるごと高専x富士通コラボ
- [note] 神山まるごと高専x富士通コラボ