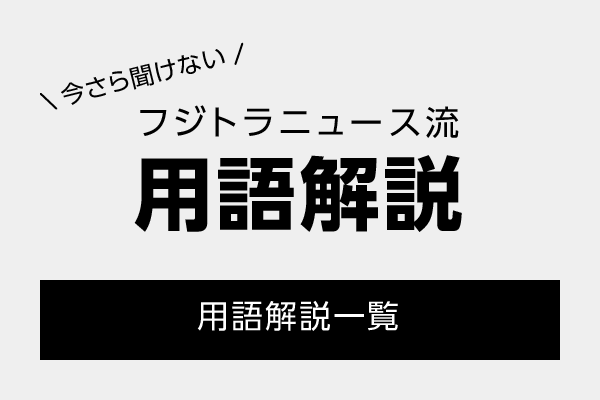ビジネス環境が目まぐるしく変化する中、富士通は経験や勘ではない、データに基づいた経営判断やスピーディーな意思決定を実現させる「データドリブン」を自社で推進するとともに、お客様企業のデータドリブン経営を支援しています。
データドリブン経営を実践する上で欠かせないのは、データサイエンティストの存在。しかし、DXやAI活用の需要の高まりに伴い、多くの企業でデジタル人材が不足しています。このような状況下において、富士通は2022年にビジネスの現場でデータサイエンティストを育成する「データサイエンス部」を開校。20〜30名の大学生がデータサイエンス部のハッカソンに参加し、自身が選んだテーマにチャレンジしています。ビジネスの現場で活躍する“真のデータサイエンティスト”に求められるものとは?データサイエンス部の取り組みを担当するDIGITAL SHIFTS DIS事業部グループ長の土井 悠哉と、学生サポートを務めたパブリック&ヘルスケア事業本部の中川 玄、今年のハッカソン優勝者である安田 花純さんに話を聞きました。
※写真左上:EVP CDXO(兼)CIO 福田さん 右上:ハッカソン優勝者 安田さん
左下: パブリック&ヘルスケア事業本部 中川さん 右下:DIGITAL SHIFTS DIS事業部グループ長 土井さん
広い視野でデータを活用し社会課題に挑む
――データサイエンス部を開校したきっかけを教えてください。
土井: データを使って自社の変革に取り組むにも、お客様企業の変革を支援するにも、主役となるのはデータドリブンの考え方が身についているエンジニアです。実際のプロジェクトでも特に若い世代の活躍が目覚ましい。そこで、業務で使っているプラットフォームを学生が使ったら、どんな化学反応が起きるだろうかと考えたことがきっかけとなりました。
 富士通株式会社 DIGITAL SHIFTS DIS事業部 Sグループ長 土井 悠哉
富士通株式会社 DIGITAL SHIFTS DIS事業部 Sグループ長 土井 悠哉
――最近では、大学などでDX人材育成を加速する動きも見られますが、データサイエンス部だからこそできることはありますか。
土井: AIの作成やデータの分析ができる人材は少なくありません。ただ、ビジネスの現場でデータを使った業務変革まで提案できる人材は不足しています。学生は主に、収集・整形されたデータを使ってモデルを組むことを学んでいます。しかし、ビジネスの現場では、モデルを組む以前に、バラバラなシステムからデータを集めて使える形に処理するといったデータの前処理が業務の多くを占めています。プロセスの一部を担うのではなく、データの収集・整形からビジネス価値の設計・提供まで全体を担えるデータサイエンティストを育成したいと考えています。
「データサイエンス部でモデルを組む」と言うと、日々の業務改善といった目先のことに向いてしまいがちです。それも業務を「自分ごと」として捉えているという点ではよいのですが、広範囲に目を向け、データ活用によって社会課題や経営課題を解決できることを目指していきたいと考えています。
――SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)企業になるためには、なぜデータドリブン経営が不可欠なのでしょうか?
土井: 従来は、強いリーダーシップを持つ経営者が勘や経験に基づいて単独で経営判断を行ってきたように思います。しかし、デジタル化の急速な進歩により情報量が膨大に増え、それぞれの情報が複雑に絡み合っているため、従来のような経験だけで判断できる次元を超えるようになりました。これからはデータに基づいて仮説を立て、実行し、検証するサイクルを高速で回す必要があります。データで捉えておかないと仮説が正しかったかどうかも検証できません。サステナブルな成長にはデータドリブン経営が不可欠なのです。
――ハッカソンを通じて学生にどのような変化が見られましたか。
土井: 最初のオリエンテーションで、「自分で選んだテーマは、社会課題の解決につながっているか、広い視野で考えよう」と言うと、それが彼らにとっては大きな試練となるようです。しかし、社員とコミュニケーションを取り、やるべきことが見えてくると、素晴らしい成果をだせるようになりました。学生にとって、実際にビジネス価値につなげるにはどうすればよいのかということを理解してもらえるプログラムになっていると思います。
現場との対話が実践型の育成につながる
――中川さんは、学生の取り組みをどのように支援したのですか。
中川: データマイニングには、使用できる有益な情報の入手が重要です。学生がテーマに対して主体的に取り組む中で、私は誰にどのような内容を質問したらよいかを少しアドバイスしました。たとえば、災害における生活・医療物資備蓄と供給をテーマに取り組んでいるチームがありましたので、東日本大震災の際に災害対策本部で活動した経験をお持ちの方を紹介し、一緒に現場でどのような課題が起きるのかをヒアリングしました。学生の取り組みの主旨が明確でしたので、サポートしやすかったですね。
 富士通株式会社 パブリック&ヘルスケア事業本部 中川 玄
富士通株式会社 パブリック&ヘルスケア事業本部 中川 玄
――ハッカソンを振り返って、データサイエンティストの育成をどのように考えていますか。
中川: 社会課題に対してデータを収集し、可視化して価値を提供することの重要性を私自身が再認識したとともに、それを実現できる人材が必要だと改めて感じました。データサイエンス部でのハッカソンを通じて、この社会課題はこうすれば解決するのではないかという仮説を立て現場の方々と対話することで、「実践型の育成」ができると感じています。
2023年の優勝者が学び得たビジネスの視点
データサイエンス部のハッカソンでは、最後に参加者がそれぞれのテーマ成果を発表します。今年、優勝者に選ばれた九州工業大学大学院1年生の安田 花純さんにハッカソンで学んだことを語っていただきました。
――ハッカソンに参加しようと思った動機をお聞かせください。
安田: 私の将来の夢はデータサイエンティストになることです。その夢を実現するためには、実務経験を積むことが近道だと考えて、富士通のハッカソンに参加しました。
 九州工業大学大学院1年生 安田 花純さん
九州工業大学大学院1年生 安田 花純さん
私は大学でAI技術を活用して新しい創薬のアプローチを考える研究をしています。その中でヘルスケア領域に興味があり、「医薬品の在庫最適化」をテーマに応募しました。その後、サポートしてくださる富士通の社員の方から、もっと広い観点で社会課題と組み合わせてブラッシュアップするようにアドバイスいただき、防災を起点としたテーマでの設計に至りました。
――テーマに取り組むにあたり、苦労したことや工夫したことはありますか。
安田: テーマを具体化していくことが難しかったです。「防災」と言っても、誰をターゲットに、どのような仮説を立てられるのかなど、考えるべきことがたくさんあります。それらを曖昧にしたまま進めてしまうと、途中で目的を見失い迷ってしまいます。そのようなことが無いよう、とにかく「具体化する」ことを意識して進めました。
例えば、防災対策を担う自治体との連携を考えるにあたっても、それが市町村の方なのか、都道府県の方なのかによって扱う領域が異なり、利用者の観点で細部を見る必要があることに気づかされ、非常に勉強になりました。
約一ヶ月半という短い期間でしたが、「社会に貢献できる成果に結びつけたい」という一心で、実サービスとしても提供できるものを作りたいという気持ちで取り組んできました。その結果優勝という形で評価され、自分が信じて取り組んできたことは間違っていなかったのだなと実感しました。
――富士通の社員と一緒に取り組んで感じた印象を教えてください。
安田: 私たちを学生として扱うのではなく、社員と同等に接してくださったことが印象的でした。現場でも社員の方々が、社員と同じ目線でアドバイスしてくださったお陰で、実際の業務に対する理解が深まりましたし、本気で向き合ってくださっている気持ちが感じられ嬉しかったです。手法を知っていること以上に、データを使ってどのような価値を提供できるかが重要であるという視点を持てたことが、私にとって大きな学びとなりました。
人材育成を通じてデータドリブン経営を加速
学生が取り上げた社会的なテーマを、その最前線で活躍している社員が加わることでさらに掘り下げ、ビジネスの実現性へと導き出されていくことに新鮮な気づきがありました。参加された学生はもとより一緒に取り組む社員にとっても刺激的であり貴重な体験となりました。
ビジネスの現場で活躍するデータサイエンティストが育成されることで、データドリブン経営が進み、さまざまな社会課題の解決につながることが期待されます。
今後も富士通は自社がデータドリブン経営を進めていくとともに、お客様企業のデータドリブンの取り組みを支援し、サステナブルな社会作りに貢献してまいります。