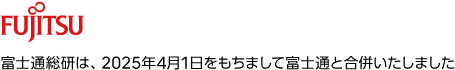「中山間地域等における在宅医療・介護連携に関する調査研究事業」(老人保健健康増進等事業)の実施について
全国に先駆けて高齢化が進行する中山間地域等において、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるための地域包括ケアシステムの構築を進める時、在宅医療・在宅介護の資源の少なさ、担い手の減少という課題に直面します。一方、在宅医療・介護連携推進における医療と介護の専門職連携は、今後爆発的に高齢者の増加がみられる都市部等では適応しやすいものの、地域に医療・介護に係る資源が少ない中山間地域等が多い地方では適応しづらい一面もあります。
在宅医療・介護が密接な連携のもと提供されることは、在宅で療養生活を送る高齢者にとって、在宅生活の限界点を上げるために必須のものです。一方で、在宅生活の限界点をあげるためには、医療と介護の確保のみならず高齢者の日常生活を支えるための支援があることが重要です。さらに、中山間地域等のように医療と介護の資源が少ないだけではなく、独居等高齢者のみ世帯が多い地域では、医療と介護が連携して提供できる工夫に加え、地域の中に高齢者の日常生活を支えるための支援や重度化防止に向けた支援が地域の中で連続して整っていることが大事です。
あらためて中山間地域等をみてみると、医療・介護に係る資源は限られてはいるものの、それらも地域を支える一つの資源として日常生活を支える支援や地域づくりの活動と柔軟につながり、結果として在宅医療・介護連携を効果的に推進し、高齢者の在宅療養の限界点を上げるような先駆的取組も行われています。また、人口減少・少子高齢化・少資源の地域は、近い将来における日本の多くの地域の姿でもあり、そこで在宅医療、介護の専門職や地域の関係者、住民、自治体が連携している状態は地域包括ケアシステムの姿でもあります。
本調査研究では、中国5県における中山間地域等を調査研究の主対象とし、行政、医療・介護関係者、在宅医療・介護連携推進事業以外の地域支援事業の関係者、住民等も含むまちづくり活動の関係者等が、医療・介護の資源の少なさを補完するような取り組みを実施し、地域の課題を克服していったプロセスを把握し、その解決過程をまとめ、考察することで、現在の中山間地域等、そしてこれからの全国の在宅医療・介護連携の推進に寄与することを目的に実施いたしました。
報告書
 中山間地域等における在宅医療・介護連携に関する調査研究事業報告書(PDF) (18.9 MB)
中山間地域等における在宅医療・介護連携に関する調査研究事業報告書(PDF) (18.9 MB)
報告会
主催 富士通総研 協力 厚生労働省 中国四国厚生局
令和5年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
「中山間地域等における在宅医療・介護連携に関する調査研究事業 報告会」
~少子高齢化・人口減少・少資源のまちから在宅医療・介護連携推進の可能性を考える
中山間地域は、少子高齢化・人口減少が進み、医療や介護等の社会資源も少なく、将来の日本の縮図・課題先進地域として取り上げられることが多々あります。
しかし、「少ない」からこそ互いの知恵と力を活かしてやらねばならないこと、「少ない」中でもできることもあります。市町が連携し圏域全体で強い医療・介護の体制をつくる、在宅医療・介護の専門職連携を超えた連携による住み続けられる地域づくりで在宅生活の限界点を上げる、年齢を重ねて変化する高齢者を医療・介護の専門職をはじめとする含む地域の関係者が一丸となって包括的に支える・・これらは「在宅医療と介護の連携」があるからこそ成立する地域包括ケアシステムの姿でもあります。
本報告会では、本調査研究の中で確認された内容の報告とその実施プロセスに着目した取組事例のご紹介、シンポジウムを通じて、これからの在宅医療・介護連携における可能性を考えます。
 パンフレットはこちら (0.6 MB)
パンフレットはこちら (0.6 MB)
開催概要等
| 日時 | 2024年3月11日(月)13時00分~16時00分 |
| 開催方法 | オンライン開催(zoomウェビナー) |
| 対象者 |
|
| 締切日 | |
| 留意事項 |
|
御申込はこちらから
|
プログラム
報告会(2024年3月11日月曜日)
| 項目 | 登壇者 | 内容等 | 資料 |
| Ⅰ.事業報告 | 中山間地域等における在宅医療、介護連携に関する調査研究の報告
株式会社富士通総研 (調査研究事務局) |
| |
| Ⅱ.事例報告 | 事例報告①
広域・複数市町で取り組む在宅医療・介護連携 鳥取市福祉部次長(兼)長寿社会課長 橋本 渉 |
| |
| 事例報告②
複合的な支援を行う拠点を中心とした医療、介護、生活を支える活動について -事例から得たヒントを他の地区で展開するには- 廿日市市在宅医療・介護連携相談支援室 保健師 阿部 朱美 特定非営利活動法人ほっと吉和 理事長 益本 住夫 |
| ||
| 事例報告③
住民、専門職、町でわが町の医療・介護・福祉・保健の連携システムをつくる 社会福祉法人奈義町社会福祉協議会 生活支援コーディネーター植月 尚子 |
| ||
| Ⅲ.シンポジウム | 少子高齢化・人口減少・少資源のまちから在宅医療・介護連携の可能性を考える
【コーディネーター】 公立大学法人埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 研究開発センター教授 川越 雅弘 ※本調査検討委員会委員長 【パネリスト】 鳥取市福祉部次長(兼)長寿社会課長 橋本 渉 廿日市市在宅医療・介護連携相談支援室 保健師 阿部 朱美 特定非営利活動法人ほっと吉和 理事長 益本 住夫 社会福祉法人奈義町社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 植月 尚子 ※事例発表者 |
お問い合わせ先
株式会社 富士通総研 行政経営グループ 担当:名取・藤原・金
 Email:fri-regionalpolicy@cs.jp.fujitsu.com
Email:fri-regionalpolicy@cs.jp.fujitsu.com
電話:03-6424-6752(直通) Fax:03-3730-6800