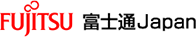2023年04月03日 更新
ユーザーとベンダーの協力を深めるためのHL7 FHIR第04回 長期展望:「検証された医療プログラム」に貢献する社会モデルへの変革
ここまで、FHIRというコンセプトに関する技術的説明と、ユーザーとベンダーの協力のあり方の変化の可能性について私なりの視点をご紹介してきました。これは、(1)単純な参照、(2)単純な連絡業務、(3)複数システム間の機能連動の実施方法と関連しています。
最終章:FHIRが名実ともに「標準」となるとき、医療情報システムの連携の中に「医療アルゴリズム」の流通が起きる、という将来像について
医学会は様々な医学研究を通じ、「ガイドライン」という形で、特定の疾患や病態に対する診断方法、着眼点、治療の流れを示したフローを提供しています。ガイドライン自体は当然ながら「文書:ある文字」ですが、人間である医療者によって理解され、場面に応じて安全かつ有効に実施される時、ガイドラインは「プログラム」になります。では、これと同じように、あるガイドラインが「コード:ある文字」として提供され、これがある病院の計算機やロボットによって理解され、場面に応じて安全かつ有効に実施される時、コードは「プログラム」になることも、特に不思議はないはずですが、いかがでしょうか。そして、このような「計算機が医療ワークフローの実施を積極的に支援する」機能を、「1つの施設の枠を超えて提供し、共有する」ことこそが、FHIRの利活用の最終形によって描かれる社会モデルであろう、と私は考えます。HL7 FHIRが「API(Application Program Interface:他のプログラムから呼び出し可能なプログラム実行機能)の変革」と呼ばれる所以です。FHIRは、これまでのように「施設間でデータを交換する規約」だけでなく、「施設間でプログラムを交換する規約」になりうる、ということです。
さて、このような社会モデルに至るには、私たちにはどのようなハードルが待ち構えているでしょうか?医療機関の活動には、診療科の名前や保険収載、検査などのように、方法・手技が統一されているものと、病院食の提供や4444コールの連絡順序、同意文書のスキャン担当など、その運用の細部まで厳密に指定されていないものに分けられます。病院情報システムは、この「統一されている箇所」と、「統一されていない箇所」の両方に関わっていますが、医療者が「統一の有無」について実施の際に意識することは殆どありません。幸い、クリニカルパス学会、クリティカルパス学会のように「患者の治療状況と状態遷移に応じてすべきことをフローにする」「パス」の手法は広く浸透し、推測では6割を超える医療機関がパス運用を診療に取り入れているとの報告があります。現在は、前述のように、パスを解釈するのは医療者であり、パスの分岐の要因となる状態把握(体温測定や血算など)はともに医療者が行うことになっています。さて、ここで、状態把握を自動センサーや患者自身が実施する体温計などで半自動化、全自動化された場合、またパス自身の解釈支援が現在よりも複雑になった場合、人力だけでなく、計算機の演算能力によりこれが支援されるのが望ましい、と考えるようになるでしょう。
このような取り組みはAMED事業に2018-2020年度で採択された「e-Path Project」によって実証が進められました。このe-Path Projectで明らかになった課題こそ、本稿で取り扱う内容です。それは「患者状態の類推を計算機が行い、疾患の把握や副作用の早期発見などを計算機によって精度良く推測したり、推奨される方法を提案することで、より安全で質の高い医療を提供する、というものです。この概念に、パスの見直しによって得られる有効性の検証と改善のサイクルが伴うことで、「LHS (Learning Health System)」 と呼ばれる、「施設内での持続的な医療能力の向上」が機能することが強く期待されます。このLHSの最初の段階では、改善サイクルは個々の施設で開始されます。
ここまで書き進めれば、読者諸賢からは「全国で試行された改善サイクルのベストプラクティスを自院でも速やかに使いたい」との要望が上がってくることも十分推測されるのではないかと思います。さて、この目的を達するために、前段で述べたFHIR標準化を役立てることは可能でしょうかーこれが、FHIR標準化を院内で進める「長期的なモチベーション」になることを強く期待しています。
東京大学名誉教授・畑村洋太郎教授が創設した「失敗学会」という活動団体があります。失敗は決して単に忌避するものではなく、丹念に分析し、失敗のプロセス構造を明らかにすることこそ、その失敗を貴重な社会財に昇華できる、という趣旨が込められていると感じます。医療情報の分野では、全国に普及し、厚労省標準に認定されたSS-MIX2は「成功した標準形式」のひとつですが、電子カルテと部門ベンダーの間でHL7 v2フォーマットの日常プロセスで十分に普及したとは言い難いのではないかと思われます。またオブジェクト指向モデル(正確にはUML:Unified Modelling Language)で医療プロセスの論理構造をモデル化したHL7 v3は、世界的にも一部の国でのみ実用化するに留まりました。私の推測ですが、この「オブジェクト指向の行き詰まり」は、必ずしも医療ITに限った話ではなく、全IT領域に生じた課題でありました。この行き詰まりが顕在化してきたのが2000年前後で、これを乗り越えるための「Web2.0」が市場で歩みを始めたのが2010年頃ではないかと思われます。Webサービスは医療ITと比べ、ユーザー数の桁違いの多さが特徴で、特に「使いやすさ」「レスポンス」「セキュリティ」について洗練が進んだのではないかと感じます。
一方、医療ITのように過去データの確実な引き継ぎを必要とし、計算機連携が必須の機器を抱える製造業においては、医療IT業界と同じように「相対的な新陳代謝の遅れ」が指摘されています。さらに、医療IT領域は製造業よりもライフサイクルの長い情報資産を取り扱います。
したがって私たちは、ソフトウェア開発においてはWebサービス技術を模範とすることが可能ですが、既存データの引き継ぎ等においては「業界最難関」の領域を扱っているのではないか、と個人的には考えています。ピーター・ドラッカーは2002年のハーバード・ビジネス・レビュー誌に「病院は世界で最も複雑なシステムである」との言葉を残しています。こうした要素を総合して眺めますと、医療現場にITを導入するということは、「本来、人的、資金、期間を含め、莫大なコストを要求する領域である」という認識が共有されるようになるのではないかと思います。それでもなお、オブジェクト指向開発のパラダイムから抜け出すための努力を含めて、「必ずしも資金が目的達成のために活用されてきたとは言えない」ということも敢えて指摘しておきたいと思います。そして、だからこそ、「医療施設が個別に開発する」時代から、「小さな機能であっても、医療に有益であれば、それが全国、全世界で流通するようになる」仕組みを伴った時代への変化こそが、医療ITの将来を明るくする道標となるのだろう、と私は考えています。
ユーザーができること
群大病院では電子カルテからの処方、検査を中心とするFHIR化を行い、電子処方箋フォーマットへの対応を行います。併せて、調剤支援システムをFHIR化することで、配薬確認や入院時持参薬確認の省力化モジュールを提供して総務省5G実証事業に活用しています。少し高度な作業になりますが、ベンダーさんに「情報サーバ間、特に電子カルテと部門サーバ間で通信できる情報の充実と規格化を要望する」発注を含めていくことが重要になります。ここで「情報の充実」は、「情報連携」という表現で通用しているかもしれません。多くのサイトでは、電子カルテベンダーが提供するソケット接続を用いて部門システムと接続されていると思われます。医療情報では通信の信頼性が大変重要ですので、広域的なサービスを提供するために、電子カルテベンダーがソケット接続モジュールの動作信頼性を高めてきました。一方、なぜベンダーにおいて通信の規格化が速やかに広まらなかったかを振り返ると、「医療上、何の改善も視認できない通信モジュールの規格化」に対して、「不要な費用」に割り付けられてきた過去があるのではないかと感じています。実際、群大病院でもHL7 v2やSS-MIX、FHIRの導入において、「なぜ接続費用がこんなにかかるのですか?」と質問されました。内容を十分知らない事務さんからすると、「経費を不当に高く見積もってキックバックさせるつもりでは?」とさえ疑われたかもしれません(勿論そのようなことはありません)。ここで、FHIRの導入には「まず、データの可視化が医療ワークフローで役立つ箇所を見つけましょう」と紹介したことを思い出して欲しいのです。「現場で、この箇所でのデータ可視化は、現場に役立つのだ」という価値を担保するのは、ベンダーの仕事ではなく、医療機関側の責任範疇です。最初はスモールスタートが重要です。継続的な取り組みにより、ある程度の情報システムがFHIRで通信するようになると、医療における利活用の幅が急速に広がってきます。医療情報をあずかる読者諸賢は、それぞれの現場においてFHIRのよき導入における先導者となることが求められています。
ベンダーができること
私は富士通Japanをはじめとする医療情報ベンダーさんが、市場という流動的で不安定な足場にありながら「超長期にサービスを提供する」医療情報ベンダーとして社会的役割を果たしてこられたことに心から敬意を表し、また感謝します。私の出自は大型高エネルギー加速器の設計と実証実験で、そこでは加速器は30-40年のライフサイクルを通じて継続的改造を可能とするような「先見の明」ある設計が為されているのを目の当たりにしました。「優れたデザインと巧みな実装」は、システム全体の全期間にわたり決定的な影響を与えます。Mike Gancarz著「UNIXという考え方」には、「早くPhase-3へ向かえ」というくだりがあります。Phase-3とは、立ち上げの難しさ、運用継続して初めてわかることの両方を踏まえた上で、「新たに作り直す」という段階です。医療情報の中の標準化としてもv2→v3→FHIRと、FHIRは"Phase-3"の要件を満たしているように感じます。計算機アーキテクチャとしても、「シーケンス型」→「オブジェクト指向」→「Web型」と、やはりPhase-3の要件にあるように思えるのです。この「好機」にベンダーとしてできることは、(きっと開発部では日々検討が進んでいるものと期待していますが)"Phase-3にふさわしいグランドデザインと巧みな実装"を達成することに尽きます。また、ユーザー会の更なる活動促進を通じ、病院側への医療CIO/CISO職の創設を医療情報学会等と協力して推進することも肝要です。そして、ユーザーの「接続仕様の変更」の足並みを揃えてもらい、来たる医療モデルの変革を実現するために、次期更新において大胆なFHIR接続変更を唱導することさえも射程圏内にできるでしょう。
おわりに
”Chance”は常に両義的です。それは危機でもあり、可能性でもあります。本稿は「門外漢」である私に”Chance”として依頼されました。このような挑戦の機会をいただきましたユーザー会会長の岸真司先生に心から感謝申し上げます。私は、この「門外漢」の立場にしかできないこととは何かを考えた後、これまで、敢えて語るには緊張が走るかもしれないと案じながらも、「ユーザーの本音」「ベンダーの本音」に迫ろうとする"Chance"として、医療情報におけるFHIRの議論に一石を投じようと決め、構成を定めました。それなりに言葉を選びながら綴ってきたつもりですが、読み辛い所も多々あったかと思います。筆者の浅学故にて、何卒ご容赦ください。それでもなお、来る労働者人口の急激な減少や社会構造の変化に立ち向かうためには、まるで神輿のように、全国津々浦々の医療機関が、一斉同時に標準化の声を上げることでのみ開く可能性が確かにあることを伝え、その"Chance"に皆さんが自ら賭けてアクションを起こしていただくことがどうしても必要です。幸いなことに、電子カルテフォーラム「利用の達人」(注1)ユーザーは全国津々浦々で活躍されています。ユーザー・ベンダー双方の立場の理解が、より建設的な医療情報の発展に繋がりますことを心からお祈り申し上げます。末筆が纏まりませんので、近頃手にした本の句を紹介します。雑文にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
「万物をひとしい目で眺め、万物の内に一つの「我」を見ることを学びなさい」 シュリーマッド・バーガヴァタ、オルダス・ハクスレー、永遠の哲学、平河出版社、p151
「恵みは人格的な仕方で自ら身を向けてくださる出来事(Ereignis)であって、譲渡された物的な状態(Zustand)ではない、と」 カール・バルト 吉永正義訳 教会教義学 神の言葉 I 新教出版社、p81
注1 電子カルテフォーラム「利用の達人」
https://www.r-tatsujin.com/![]()
著者プロフィール
群馬大学医学部附属病院
システム総合センター副センター長・准教授
鳥飼 幸太(とりかい こうた)氏
【略歴】
1979年福岡県生まれ。2006年九州大学大学院工学府エネルギー量子工学専攻博士課程修了(工学博士)。医学物理士。2002年高エネルギー加速器研究機構特別共同利用研究員、2006年量子科学技術研究開発機構博士研究員、2008年群馬大学重粒子線医学研究センターを経て現在に至る。2011年-2016年特命病院長補佐(通信・エネルギー)。
受賞歴に、平成20年度全国発明表彰 21 世紀発明賞(皇室表彰)(2008年6月)「誘導加速シンクロトロン方式を用いた全種イオン加速器の発明」(2009年4月)、自動認識システム大賞(2012年8月)など。日本Mテクノロジー学会理事、一般社団法人医療サイバーセキュリティ協議会常任理事、日本医療情報学会会員、日本加速器学会会員。

-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)