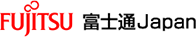2023年03月03日 更新
ユーザーとベンダーの協力を深めるためのHL7 FHIR第02回 「院内Web化」のためのITインフラ整備
第1回では、FHIRの導入について私案を紹介しました。データ参照を中心とするサービスから始めることで、ユーザーは必要な利用シーンでの診療情報を増加できます。特に、これまではデスクやラウンド用カートでしか参照できなかった患者情報が、ベッドサイドを含む任意のシーンで、スマートフォンなどを通じて個々に確認できることの利点が生じますので、活用シーンを見つけることは比較的容易だと思われます。また情報参照の使い勝手に繋がる見た目についても、Web技術のひとつであるHTML5をベースにすれば、試行錯誤する負担も少なくなります。では、この参照利用によって作り出された「ユーザーの時間」を再投資する先としては、何が適切でしょうか?個人的には、創出された時間を「ITインフラ整備」に充てることが望ましいと考えます。本コラムの第2回では、ITインフラ整備に着手する理由について考えてみたいと思います。
ここでお伝えするITインフラとは、特に「サーバの情報処理性能」、「有線/無線ネットワーク通信速度」、「有線/無線ネットワークトポロジー」、「端末のデータ処理性能」、「端末所在やIPアドレスのリスト」などを指します。これらを「整備する」とは、
1: 現在のシステム状況と性能を正確に把握すること
2: より性能が引き出せるように設定を見直し、段階化すること
3: 更なる性能向上のために機器の入れ替えやネットワークトポロジーの再設計と実装を行うこと
の3つを併せ持った表現だと捉えていただくと実情に沿うかと思います。本回ではこの3点を基本軸として解説していきます。
1: 現在のシステム状況と性能を正確に把握する
マーク・ローエンタール著「インテリジェンス」p97には、「完全に把握していないシステムに適切な任務を付与するのは困難である」という一節があります。ユーザーの皆さんは、電子カルテアプリケーションを使いながら、「困ったこと」はありますでしょうか。群大病院で最も問い合わせが増えるのは「アプリケーションのレスポンスが下がった時」です。私は、「医療DX」と呼ばれる活動の、最も効果的な手段は「システムレスポンスの向上」だと考えています。それは、医療においては、常に診療が継続している高度急性期病院において、現場のワークフローを変えることは「言うほど簡単ではない」からです。医療の多くの場面は複数の部署のスタッフの協力により成り立っていますから、医療DXの実現には、より効率的なワークフローの立案だけでなく、関係する部署との調整も欠かせません。そして何より、これらの議論をするだけの「時間的余裕」が現場から引き出せない、という状況も多いのではないでしょうか。
システムレスポンスの向上というのは、料理に例えて言うなら、「シチューを作るのに、ホワイトソースを手作りせず、ハインツの缶を買ってくる」ようなものです。出来上がるものがシチューであることには変わりありませんが、ハインツ缶はちょっと高価でしょう。しかし、「作るための時間」を比較すると、手作りソースだけで30分以上かかるのに対し、ハインツなら缶を開ける1ー2分で済んでしまうでしょう。「医療DX」の代理表現を「時間創出」と捉えるならば、ハインツ缶の導入は立派な「時間創出」をもたらします。ワークフローの変化を伴う大きな医療DXを行うためには、まずスタッフの「時間創出」に直結する一手が求められます。
それでは、今の病院情報システムにおいて、「どの箇所に手を入れれば、レスポンスの向上に直結する」成果が得られるでしょうか。この問いに答えるためには、「現在のシステム状況と性能を正確に把握する」ことが不可欠です。把握によってはじめて、システムレスポンスに直結する「ボトルネック」を見つけ出すことが可能になります。群大病院が最初に目を付けたのは、大掛かりな改造ではなく、「電子カルテの日本語入力に医療辞書変換を追加する」ことでした。医療職は他の職種に比べて、スタッフが入力する情報が多く、しかも迅速な同期が必要だという特徴があります。変換がスムーズであるだけで、操作時間を短縮でき、ユーザーの時間創出に繋がりました。こうした理解をもとに改造提案したのは、電子カルテのデータベースを保存しているストレージでした。本院では2015年にストレージメディアをハードディスク(HDD)からソリッドステートディスク(SSD)に交換しました。これは「データベースプログラムは、多数の細かなデータをランダムにアクセスすることで、集計や抽出を行っている」という動作に対する理解に基づいています。また「回転する部品が少ない方が、稼働信頼性が高い」というSSDの特性にも注目しました。しばしば「ゼロスピンドル」と呼ばれる、冷却ファンやDVD-ROMなどの、モーターで動作する部品を用いない機器は、工場のラインなど、稼働停止をできる限り避けたい箇所で活躍しています。ハードウェアの性能は、正しい指標を参照すればカタログでの検討でおよその結果を予想できるところも利点です。ユーザーの皆さんのサイトでは、どのようなハードウェアが使われているでしょうか?ボトルネックはどの要素にあるでしょうか?こういった点について、ユーザーからベンダーに相談をする、ということも有用なコミュニケーションだと考えます。さらに、昨今医療界で脅威となっているサイバー攻撃に対する対策の「最初」が、「資産(=セキュリティの専門用語であり、人的スキルや施設能力なども重要資産として計上されるもの)のリストアップ」であることに注目する必要があります。「汝自身を知れ」は、常に有効であるようです。
2: より性能が引き出せるように設定を見直し、段階化する
さて、システムの概要やボトルネックについての推測が得られたら、いきなり装置を買うのではなく、「手戻りの少ない改造計画」を考えましょう。システムは1日では悪くなりませんが、1日で良くなるものでもありません。確かにボトルネックの改善は劇的な時間創出をもたらしますが、それを維持するのが大変困難であったり、他の改善を行うための障壁になっては自縄自縛になりかねません。システム概要に基づき、「長期的に、維持可能な改善計画」を立てたいものです。また、現行のシステム性能を引き出せて、費用対効果が高いような「巧みな一手」が見つけられるかは、ひとえにユーザーとベンダーのコミュニケーションの内容にかかっています。一例としては、ネットワークの配線を切り替えたり、あるネットワークの経路を一本だけ光ファイバー化するなど、「ちょい足し」で効果が得られることもあるでしょう。或いは、端末の配置を変える、ディスプレイを大型にして、表示する情報量を増やすことでユーザーの操作量を減らすなど、電子カルテの根幹に着手しなくても時間創出に繋がる施策があります。このように着手効果が「ユーザーのユーザー」である医療スタッフで実感しやすくなると、今後必要な長期的改善に対する賛同を得られやすくなるのではないかと思います。長期的ゴールは「デジタル機器の導入それ自体」ではなく「アナログな人間の働き方の変化」であることを常に意識したいものです。
3: 機器の入れ替えやネットワークトポロジーの再設計と実装を行う
長期計画がおよそイメージできるようになったら、部科長や経営層へのインプットや交渉を始める段階です。ここで医療情報のオーナーである「利用の達人ユーザー」は、自らの考えを何もかも言語化しないと実行できないのでは、と思い悩む必要はありません。しかし、前項の調査や検討により、「このポイントに着手すれば、このくらいの時間創出が見込める」という端的で確実そうなイメージを持てるようにしましょう。さて、「頭出し」と呼ばれる作業は、簡単なラフスケッチやA4の1枚ものの概要で構いませんので、できるだけ早期に行うとよいかと思います。一度で受諾されなくても、必要性が以前からあったことを議事録などに遡って示せます。「以前にもご相談しましたが...」という枕詞はなかなか効果的です。これも「時間を味方につける」一つの方法です。前項の簡単な着手で少し時間ができたところで、大きな機器の入れ替えやネットワークトポロジーの再設計を計画することになります。ユーザーが機器のすべてを把握しているわけではありませんから、保守ベンダー、ネットワークベンダー含めて相談することになります。場合によっては心あるシステム関連会社にシステムデザインの設計費を合理的な価格で依頼することもあるでしょうし、もし新棟建設や病院移転が計画されているのでしたら、病院システムに詳しいコンサルティング会社を探し始めることもあるでしょう。
群大病院では、システム更新に合わせて、前述した電子カルテストレージの全SSD化と、1300本の光ファイバー網の敷設、1800台のシングルチャネルWi-Fi設置、1200台の低遅延シンクライアント端末設置を計画しました。経営層の説得には、「フェルミ推定(注1)」を応用した概算が有効です。仮に医療スタッフが電子カルテを操作する中で、1日5分の時間短縮(患者一覧の表示のように、30秒待つ時間を3秒に短縮して、それを10回操作するだけですから、現実的な見積です)がもたらされれば、スタッフが2000人とすると、創出される時間は人件費で年1億円以上になります。ここでは「経営層からみた支出額」が1億円という額面で、一見少なそうに見えますが、採用公募、面接、登用と配置、訓練、コミュニケーションを身につけるまでの手間を考えますと、実際にはその何倍ものコストを内包していることが理解されるかと思います。加えて、診察中に患者と医師がともに操作待ちを行っているシーンも多数ありますから、これは患者さんの待ち時間も同時に削減できていることになります。
このように「見えないコスト」を積算して可視化すれば、目の前にあるストレージの変更に1億円かかるとしても、「1年で回収できる」と主張できるでしょう。群大病院における2015年の更新の際には、目につきやすい電子カルテ本体のソフトウェア改造は軽微でしたが、医療スタッフからの反応の変化として、「感謝のお電話の増加」ではなく「苦情問い合わせ件数の大幅な減少」をもたらしました。こうして医療情報部にも「電話削減での時間創出」が生まれることで、より長期の計画を立てる機会や問い合わせ対応サービスの向上に繋がってきたと感じています。そしてなにより、ユーザーにはこの表現の方がより直截的に感じられることと思いますが、「苦情を聞くストレスの減少」は、目に見えませんが大変大きな現場改善になります。
ユーザーが必要なこと
以上より、ユーザーは「比較的容易に着手出来て、時間創出を実感できる」箇所を探してみましょう。時間創出は、電子カルテの仕組みが革新的に変更されなければ達成されないものではありません。しかしながら、ポイントを押さえた小さな改善では時間創出に限界があります。次回以降に詳説しますが、こうした「システムレスポンスの向上」は、Web/FHIR化に欠かせない要件です。
ベンダーが必要なこと
全体的なシステムインフラや情報ネットワークの整備の必要性を感じていらっしゃるベンダーエンジニアさんも多いかと思います。たとえば、このコラムを紹介しながら、ユーザーと対話を始めるきっかけにするのもよいでしょう。ここで対話のポイントをひとつだけ挙げたいと思います。ベンダーのエンジニアさんは確かに「必要なこと」を提案してくれているのですが、それが「なぜ必要なのか」について、「ベンダーが考える必要性」とともに、「ユーザーが考える必要性」の観点から照会を試みる努力が必要です。ネットワークトポロジー整理、ネットワーク強化には、しばしば「病院内のステークホルダー(実施の決定権を持つ方)が分からない」という状況もあるかと思います。このような場合に、時にはユーザーの代わりに経営層に説得を試みる要請があるかもしれません。技術的側面からの誠実な回答だけでなく、ユーザーに時間が創出されることの意義について切実な関心をもつことで、たとえ直近の受注に繋がらなくても、ユーザーからの共感を得やすくなり、運用をより円滑に行えるようになるのではないかと思います。将来的にスクリプトベースのサービス提供に不可欠な性能アップ、サイバーセキュリティ強化などについても、しばしばユーザーとの交渉が難しいこともあるかと思います。医療は「成功した先例」が大きな実施の推進力になりますので、他のサイトで時間創出に成功した事例をマーケティング部門と協力して探して紹介する、という広報活動も有効でしょう。
注1 フェルミ推定
実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算すること
著者プロフィール
群馬大学医学部附属病院
システム総合センター副センター長・准教授
鳥飼 幸太(とりかい こうた)氏
【略歴】
1979年福岡県生まれ。2006年九州大学大学院工学府エネルギー量子工学専攻博士課程修了(工学博士)。医学物理士。2002年高エネルギー加速器研究機構特別共同利用研究員、2006年量子科学技術研究開発機構博士研究員、2008年群馬大学重粒子線医学研究センターを経て現在に至る。2011年-2016年特命病院長補佐(通信・エネルギー)。
受賞歴に、平成20年度全国発明表彰 21 世紀発明賞(皇室表彰)(2008年6月)「誘導加速シンクロトロン方式を用いた全種イオン加速器の発明」(2009年4月)、自動認識システム大賞(2012年8月)など。日本Mテクノロジー学会理事、一般社団法人医療サイバーセキュリティ協議会常任理事、日本医療情報学会会員、日本加速器学会会員。

-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)