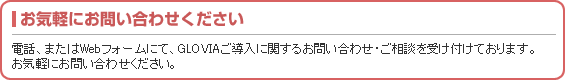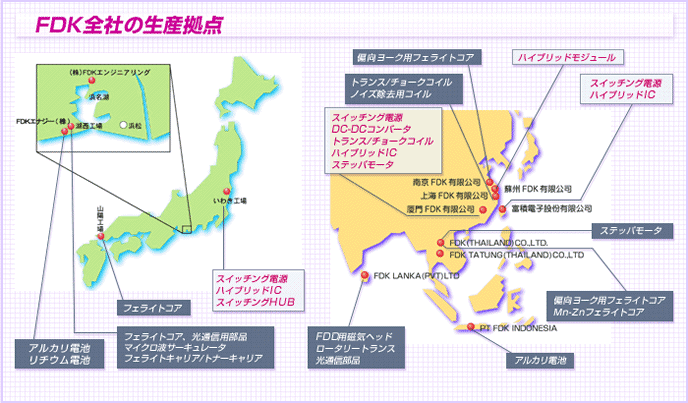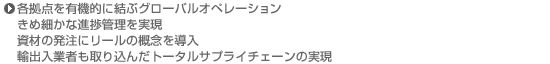FDK株式会社様
グローバルに生産統合を実現
~glovia.comによるグローバルビジネスモデル導入事例 ~ 1
このページの情報は、2002年に掲載されたものです。
最新情報は、GLOVIAトップページよりご覧ください。

グローバル化を背景に、生産管理のあり方が大きく変わろうとしている。従来は、計画・調達・購買・生産・販売のオペレーションが国内だけに閉じられていた。だが、今求められているのは海外拠点も含めた、有機的に連携したグローバルビジネスモデルである。この必要性にいち早く着目し、システム化したのがFDKいわき工場を中心とするハイブリッドモジュール部門だ。glovia.comをベースに、中国の厦門(アモイ)と蘇州(そしゅう)および台湾の生産拠点を接続。さらに、輸出入業者も含めたバリューチェーン全体を対象にしたシステムを構築し、大きな成功を収めている。
[ 2002年9月3日掲載 ]
| 創立 | 1950年(昭和25年) |
|---|---|
| 本社 | 〒105-8677 東京都港区新橋5-36-11(浜ゴムビル) |
| いわき工場 | 〒972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜の前1 |
| 資本金 | 132億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木惟司 氏 |
| 売上高 | 連結 862億円
(2002年4月~2003年3月) |
| 単独 629億円
(2002年4月~2003年3月) |
|
| 従業員数 | 約 1,465名
[FDKグループ約 11,100名] (2003年3月31日現在) |
| 事業内容 | 各種電子部品、デバイス等の製造・販売。主な製品は、ハイブリッドモジュール、スイッチング電源、コンバータ、テレビ・ディスプレー用フェライトコア、光通信用部品、電源・ノイズ防止関連用フェライトコア、コイルデバイス、アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム電池、ステッパモータ。 |
| URL | FDK株式会社 |
 |
|


FDK株式会社
経営企画統括部 情報システム部
ソリューションビジネスグループ 幹部社員
グロービアサポート担当
須藤 浩次 氏
FDKいわき工場(以下、いわき工場)は、各種電子部品やデバイスの製造を手がけるFDK株式会社のハイブリッドモジュール部門の国内生産拠点である。ハイブリッドモジュール部門では、PDP(プラズマディスプレイパネル)の制御基板や、LCD(液晶ディスプレイ)の制御モジュール、さらにVCO高周波モジュールなどを生産している。
同工場を中心としたハイブリッドモジュール部門は、早くから海外へ進出しており、中国福建省の厦門と江蘇省の蘇州および台湾に生産拠点を置くことで、グローバルな生産体制を展開している。
従来、同工場は、他の製造業と同様短納期と低価格を要求されていた。とくに、電子部品は技術革新が激しく、製品のライフサイクルも短い。多品種小ロット化と、高品質化の要求も高い。加えて、海外とのコスト競争が激しいのも、業界の大きな特長だろう。
「企業の生き残りをかけて、ビジネス全般を見直すことにし、工場内に業務改革プロジェクトを発足させました。国際会計基準による会計のオープン化も求められていたこともあり、いっさい業務を見直すことにしました」と、FDK株式会社 経営企画統括部 情報システム部 ソリューションビジネスグループ 幹部社員[グロービアサポート担当] 須藤 浩次 氏は語る。
プロジェクトチームが活動を開始したのは1999年4月。半年におよぶ富士通総研からの業務分析とコンサルティングを受けて、改革骨子を作成。その改革の中核となったのが、生産部門へのERPの導入であった。
同年10月には、ERP導入のためのプロジェクトが立ち上がり、システム構築に着手。プロジェクト名は「WING」。そこには、大空へ飛翔するという、改革成功への祈りが込められていた。ERPには、富士通glovia.comを採用し、2000年10月には試運転を開始。既存システムとの整合性を確認しつつ、翌2001年4月に本格的に稼働を開始している。その後、半年間ほど運用状況を確認し、8月に海外3拠点への導入を開始する。中国の蘇州工場の立ち上げが2001年4月であり、このタイミングに合わせて同年5月に3拠点同時に運用を開始した。9ヵ月間という、極めて短期間での海外展開を達成している。
以下、「グローバルオペレーション」「きめ細かな進捗管理」「リール概念の導入」「トータルなサプライチェーン」の4点にフォーカスして、いわき工場で構築した新システムを紹介したい。
いわき工場におけるERP導入で、最大の特長となるのが、生産、販売、在庫管理における一連のオペレーションの自動化である。
いわき工場での拠点間取引は、単純ではない。いわき工場からある海外拠点へ生産を発注すると、次のような流れになる。
- 海外工場へ発注する。
- 海外工場では資材が工場内在庫にあるかを確認し、あればそれで生産計画を立案し生産する。
- 在庫がない場合は、いわき工場に資材の発注指示を出す。
- それを受けて、いわき工場は業者に対して海外工場へ届けるよう指示を出す。
- これら資材が届いてから海外工場では生産を開始する。
だが海外工場に、受注や発注、生産計画を立案できる人材を配置することは困難である。そこで、上記工程2から4までは、glovia.comにより自動処理できるようにすることで正確な生産計画や在庫管理、さらに省力化により人員の効果的な配置が可能となった。