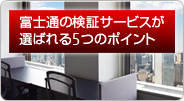Japan Storage Vision 2012レポート
~2月8日(水)東京コンファレンスセンター・品川 開催 ~

Japan Storage Vision 2012では、「ストレージインフラの新しい選択基準を探る」をテーマに、ITインフラの変革、信頼性や安全性への訴求、ビッグデータ時代の到来などがストレージ投資にどのような影響を与えるか、講演とパネルディスカッションが行われた。
IDCの調査・分析によると、以前は同程度に推移していたIT投資とストレージ投資の前年比成長率は、2011年以降にはストレージ投資がIT投資を上回ると予測される。このようなストレージ投資パターンの変化は、「ITインフラの変革」「信頼性・安全性」「データの多様化とビッグデータ」といった潮流によりストレージインフラの構造変革が進みつつあることを示唆している。
今回は、ストレージ投資に影響するこれらの潮流の背景を交えながら、お客様の関心度が高い「災害対策」「クラウド・仮想化」「ビッグデータ」をキーワードにストレージソリューションを提案した、富士通の熊沢の講演についてレポートする。
ICTシステムの変革を支援する富士通のストレージソリューション
災害対策のストレージソリューション

富士通株式会社 ストレージシステム事業本部
ストレージ企画統括部 統括部長 熊沢忠志
IDCによると事業継続 / 災害対策投資のピークは2007~2008年前半であった。2011年の大震災をきっかけに、2012年以降は事業継続 / 災害対策がストレージ投資の重要課題になると思われるが、その内容には変化が見られる。
以前は、事業継続 / 災害対策向けに高価なストレージを利用するハイエンドソリューションが主流であった。大震災以降は、クラウドやデータセンターサービスの利用など、多様な選択肢から自社のIT予算に適応したソリューションを選択する傾向が見られる。また、大震災に起因する電力不足問題から、省電力、遠距離間のバックアップが重視され、クラウドや仮想化などのITインフラの再構築と同一のフレームワーク内で事業継続 / 災害対策が捉えられるものと予測される。
熊沢は、事業継続で重要なことはデータを守ることであると説明する。企業データを格納するストレージが破損するとデータは失われる。そのため、事業継続を考えた災害対策ソリューションでは、ストレージ内の保有データをいかに守るかを最優先に考えることになる。
災害対策ソリューションでは、RLO(Recovery Level Objective)、RPO(Recovery Point Objective)、RTO(Recovery Time Objective)の「3つのR」を検討することが重要である。RLOは災害発生後、業務範囲やサービスをどのレベルで運用継続させるのか、RPOは災害発生前のどの時点までデータを復旧させるのか、RTOは災害発生後、業務の重要順に、いつまでにシステムを復旧させるのかを示す指標である。例えば、災害発生後なるべく早く、被災時直前のデータでシステムを復旧したい場合には、リモートミラーリングなどのコストのかかるソリューションが必要になる。データのSLA(Service Level Agreement)に応じてRLO、RPO、RTOを検討し、適用する対策を決定しなければならない。
ストレージの災害対策ソリューション
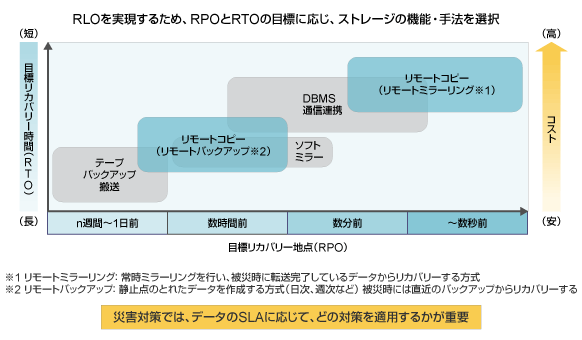
さらに、富士通では、データのSLAとコストのバランスに応じて、ETERNUSのディスクアレイ、テープ、デデュープアプライアンス、ソフトウェアを利用したレベル0~レベル5の災害対策ソリューションを提供していること、およびその具体的な内容を紹介した。
事業継続・災害対策実現のレベル
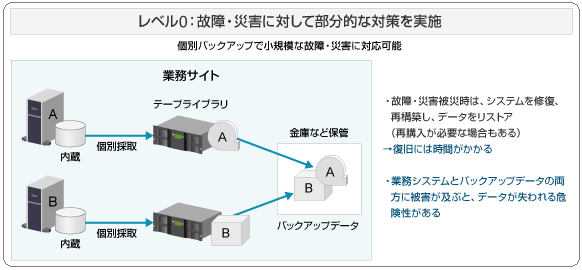
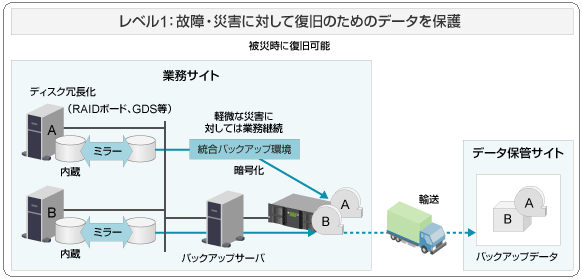
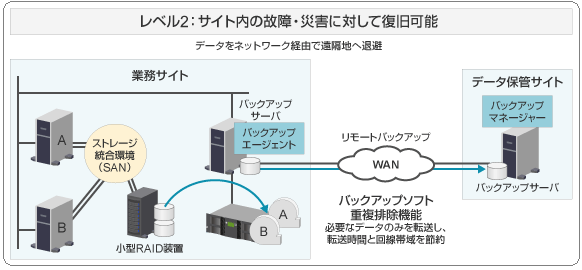
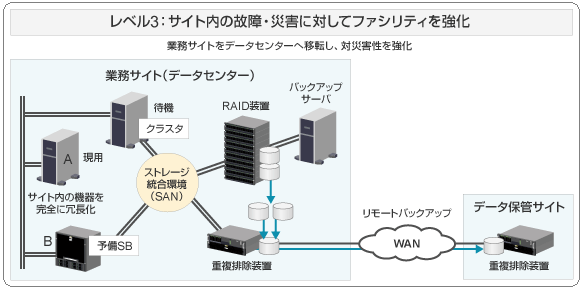
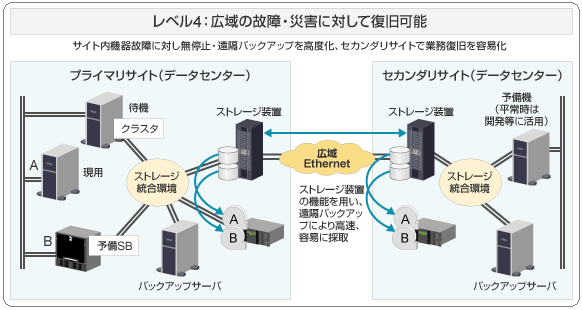
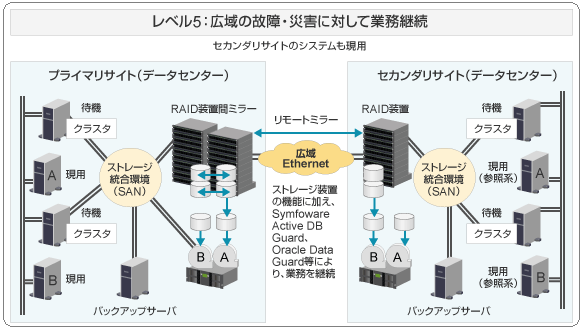
クラウド・仮想化に最適なストレージソリューション
近年、コスト削減のためにITインフラの再構築に着手する企業が増えている。その手法として、サーバ仮想化、クラウドの利用や構築が進んでいるが、ITインフラ全体を最適化して利用効率を向上するには、次にストレージインフラを見直し、ストレージ管理の課題を解決することが求められる。
IDCの調査では、サーバ仮想化環境でのストレージ管理課題の解決策として、「シン・プロビジョニング」「リモートレプリケーション」「スケールアウト型ストレージ」「デデュプリケーション(重複排除)」などの新技術の導入が進んでいることを示している。また、いち早く導入した企業では、「シン・プロビジョニング」「デデュプリケーション(重複排除)」「外部ストレージ仮想化」「階層型ストレージ」に対し、9割以上が「期待どおり」または「期待を上回る」と評価している。
富士通では、社内クラウドセンターでの実践や豊富なクラウド商談・構築事例からパブリッククラウドやプライベートクラウドの幅広いクラウドソリューションを提供していることを説明。さらに、クラウド、仮想化、サーバ、ネットワーク、ストレージを最適なハードウェアとクラウド支援ソフトウェアとともに統合したパッケージ「Cloud Ready Blocks(クラウドレディーブロックス)」も紹介した。また、運用性、拡張性(仮想化)、セキュリティやパフォーマンスを向上する具体的なストレージソリューションを提案した。
※ストレージソリューションの提案内容は講演資料(次のPDF)をご一読ください。
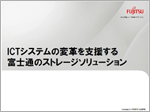 |
| クラウド向けストレージソリューションの例 | |
|---|---|
| 運用性 |
|
| 拡張性(仮想化) |
|
| セキュリティ、
パフォーマンス |
|
クラウド向けストレージソリューション(運用性向上)の例
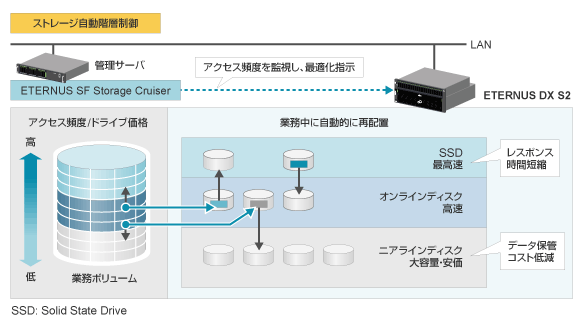
ビッグデータ活用のためのストレージソリューション
IDCは、ビッグデータテクノロジを「収集・発見・解析プロセスを高速に実行することで、大規模(Volume)かつ多様な(Variety)データから重要な価値や意味(Value)を低コストで引き出す(Velocity)新世代の技術アーキテクチャ」と定義している。また、データの多様化がさらに加速し、2015年には国内ディスクストレージ容量の53.5%を非構造化データが占め、産業分野ごとに多様なビッグデータが生み出されていくと予測している。
熊沢は、ビッグデータ時代に向けてストレージの変革が必要であり、ビッグデータのビジネス分析処理にHadoop(大規模データを効率的に分散処理・管理するためのソフトウェア基盤)やHANA(High- Performance Analytic Appliance)などが必須になることを示した。また、富士通はNTTデータとともに、ETERNUSへのアクセス方法を拡張してHadoopやPOSIX(Portable Operating System Interface for UNIX)対応のストレージシステムを共同開発したことを説明した。
Hadoop以外の外部システムからデータにアクセスできるため、データ入出力時間の短縮やデータの統合管理が可能であるほか、ETERNUSベースのバックアップや運用管理を利用できる。
データが多様化、大規模化するビッグデータ時代では、データの特性により最適なストレージアーキテクチャが異なる。さらに、データセントリック(データ中心)な業務が増え、データが最適なストレージに格納されるとその近くにプロセスを移動してデータ処理を実行するようになると説明。階層制御によりメモリやストレージ上の最適な位置に配置し、VM(仮想マシン)移動技術によりアプリケーションを最適な実行環境へ移動するモデルを示した。
ビッグデータ時代のデータ処理の例
(ストレージ内のデータの近くでプロセスを実行)
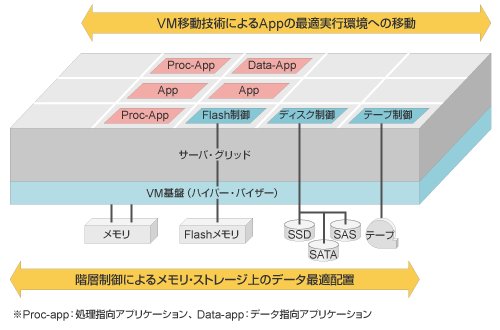
富士通は、このように災害対策、クラウド・仮想化、ビッグデータ活用に最適なストレージソリューションを提供してお客様を支援すると同時に、ICTの利活用によって人がより豊かに安心して暮らせるヒューマンセントリックな社会の実現に向けて、引き続き取り組む。
掲載日:2012年3月15日