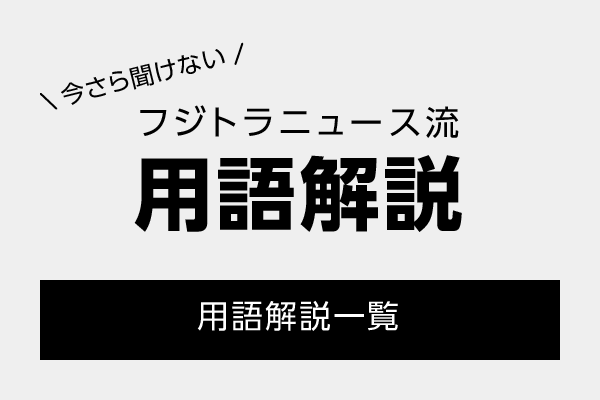DXのカギを握る、データ利活用。大陽日酸株式会社は、データドリブンな企業文化の醸成を目指しています。
企業全体でデータ利活用に取り組むには「ビジネス力とデータ分析力を、両利きで推進できる人財」が必要だと考えた大陽日酸は、富士通および富士通ラーニングメディア(以下、FLM)と共に「データ利活用スキルアップ研修」を設計、実施。単なるスキル習得だけでなく、業務課題の解決に直結するデータ利活用の実践を経て、受講者の行動変容まで目指すこの取り組みについて、大陽日酸と富士通・FLMの担当者に話を聞きます。
- 目次
大陽日酸が目指す、「ビジネス力とデータ分析力を、両利きで推進できる人財」の育成
大陽日酸は、酸素・窒素・アルゴンなど産業ガスを製造・販売する企業です。1910年に創業した日本酸素と、同じく1910年代に起源を持つ大陽東洋酸素が2004年に合併し、大陽日酸が誕生しました。2020年には持株会社制に移行し、グローバルに事業を展開する日本酸素ホールディングスの日本事業会社として、産業ガスの国内シェアNo.1を誇っています。「進取と共創。ガスで未来を拓く。」という理念のもと、人と社会と地球の心地よい未来の実現を目指して日々努力されています。

2022年4月、大陽日酸では、経営企画・ICTユニットの傘下で「DXセンター」が発足しました。デジタル技術を活用することにより、大陽日酸グループの企業風土・企業文化の変革に取り組まれています。
DX推進に向けた取り組みや、人財育成について、DXセンターの赤井 康昭 氏、松島 洋輔 氏、峯 竜二 氏、佐藤 優成 氏に話を聞きました。
――大陽日酸全社でのDX実現に向けて、DXセンターが今感じておられる課題と、どのように解決しようとされているのかお聞かせください。
赤井 氏:DXの実現には、全社的な活動への発展が不可欠です。DXセンターのメンバーはデータ活用やデジタル化技術に長けていますが、各部門・各分野のビジネス上の課題を隅々まで熟知しているわけではありません。そのため、各部門・各分野のビジネス人財をDX人財に育てることで、全社的なDX推進活動や業務課題解決の原動力になってもらおうと考えました。
松島 氏:現場には、様々なデータが存在します。大きな成果を出すには、DXセンターだけでなく、多くの社員を巻き込み、企業全体でデータ利活用に取り組む必要があります。データ活用を「個人戦」から「団体戦」に引き上げなければ、会社全体の進化にはつながりません。
――こうした課題を踏まえ、DXセンターが目指すDX人財として、どのような人財像を描かれたのでしょうか。
赤井 氏:「ビジネス力とデータ分析力を、両利きで推進できる人財」。つまり、データやツール、AIという武器・道具を用いてビジネス上の課題を解決でき、発想の転換ができる人財の育成を目指しています。各部門・各分野の業務に精通した人財にデータ分析力が備わることで、現場の社員自ら社内に眠るデータを分析・活用し、そこから得たノウハウと気づきをもとに課題解決に向けた業務変革の起点となってもらいます。

大陽日酸株式会社 経営企画・ICTユニット
DXセンター 所長 赤井 康昭 氏

DXセンター デジタルビジネス推進部長 松島 洋輔 氏
――新たに教育プランや研修プログラムを検討する中で、重視されたポイントを教えてください。
峯 氏:プランニングにはFLMもコンサルタントとして参加し、1年ほどかけて徹底的に議論しました。その中で、データ活用で成果を上げるには単なるスキルの習得だけでなく、周囲を巻き込みながら主体的に課題解決へ取り組むマインドセットが重要だという結論に至りました。
赤井 氏:重視したポイントは、ツールの活用に留まらず、受講者が抱えるビジネス上の課題を題材とした点です。課題の仮説、データ加工や分析のノウハウを実践形式で学ぶことができれば、受講者は研修から気づきとインサイトを得て課題解決に向かえます。このように、受講者の行動変容を促すことに重きを置きました。
富士通とFLMは、当社の要望に真摯に向き合い、研修プログラムを具体化してくれました。
研修のテーマは、受講者自らが抱える業務課題。伴走支援で一人ひとりに向き合う
2024年度、DXセンターは、富士通およびFLMと共に「データ利活用スキルアップ研修」を実施しました。営業、物流、研究、技術など、様々な立場から参加を希望する10名の社員が受講。受講者が抱える業務課題をデータ利活用によって解決すべく取り組みました。
約4か月(15週)にわたる研修は、大きく分けて2つのフェーズで構成されています。
まず、インプットフェーズでは、受講前の事前ワークから始まり、入門、課題探索、2度のハンズオンを通じてデータ分析の基礎を習得。データ分析に馴染みのない受講者にも理解しやすいよう、事前のアンケートや課題を通して現状を把握し、必要に応じて個別にサポートすることで、安心して学習に取り組めるよう設計しました。
次のプランニング~アナリティクスフェーズでは、メンタリング形式で現状の課題や悩みに対する相談やアドバイスを実施。受講者の現状を把握した上で、それぞれの業務課題の解決に向けて、都度軌道修正やフォローアップを行いました。研修全体の3分の1を伴走支援(OJT支援)に充て、受講者の方々をサポートしながら実践を通してスキルを身につけていただくことを目指しました。
受講者が取り組んだテーマは真に業務に役立つものなのか、途中上長へのヒアリングも実施しながら、ファイナルプレゼンテーションを行うまでを研修プログラムとして実施しました。
セールスとして大陽日酸を担当する富士通 長島 彩 と、研修を通じて企業の課題解決を支援するFLM 前田 真太郎、生方 史郎が、今回の研修を振り返ります。
――「データ利活用スキルアップ研修」のポイントを教えてください。
前田:DXセンターの皆様と理想的な研修のかたちを議論する中で、特に私が共感したのは、「受講者の行動変容につながらなければ意味がない」という考え方です。これを起点に、受講者自身が抱える業務課題をテーマに解決へ取り組む研修プログラムを組み立てました。
今回の研修プログラムでは、実際の業務データを使い、受講者が自らの手でデータ分析の設計からアウトプットまで行うことを重視しました。
赤井 氏:これまで富士通とFLMが提供する研修プログラムに、実際の業務課題の解決まで行うカリキュラムはなかったと聞いています。ニーズに合わせて新たなカリキュラムを考えていただいた対応力とノウハウの豊富さには驚きました。
生方:FLMには、教育のナレッジやノウハウは豊富にありますが、OJT支援は提供していませんでした。一方、OJT支援に取り組まなければ本当の人財育成は成し得ないと私は考えており、Ridgelinezに出向しコンサルタントとして現場経験を積んだ後、FLMに戻って真っ先に取り組んだのがOJT支援プログラムの開発でした。社内でプログラムの準備を進めていたタイミングで今回の研修の話を受け、熱い想いを持って取り組ませていただきました。

株式会社富士通ラーニングメディア
ナレッジサービス事業本部
マネージャー 前田 真太郎

株式会社富士通ラーニングメディア
ナレッジサービス事業本部 生方 史郎
――富士通が、デジタル技術の導入のみならず、人財育成に取り組む意義はなんでしょうか。
前田:富士通は、テクノロジーを強みとする企業ですが、その普及を実現する上で欠かせない要素のひとつが人財育成です。
国内の労働人口減少に伴い、生産性向上は喫緊の課題となっています。生産性を向上させるには「人」と「テクノロジー」の両面からのアプローチが重要です。人の成長を促すアプローチと、テクノロジーを活用してオペレーションを効率化し、よりクリエイティブな仕事にシフトするアプローチ、その両方が求められています。富士通と、富士通グループで人財育成を担うFLMは、これらの両面からお客様を支援できる体制を整えています。
長島:富士通も今、自身を変革する全社DXプロジェクトに取り組んでいます。お客様や社会のDXを支える企業となるために、私たち自身が変わり続けなければいけないという強い思いで取り組んでいますが、それがどれほどノウハウとして身についているかは未知数です。ただ、富士通の一員として、この変革の波を肌で感じているのは確かです。日々試行錯誤しながら、私たちの業務や提供価値をどのように進化させていくべきか模索しています。この経験によってお客様の変革に貢献できることがあるはずだと信じ、今回のような取り組みを行っています。
 富士通株式会社 グローバルカスタマーサクセスビジネスグループ CustomerEngaging事業本部 長島 彩
富士通株式会社 グローバルカスタマーサクセスビジネスグループ CustomerEngaging事業本部 長島 彩
実務に直結する「データ利活用スキルアップ研修」から得た、3つの成果
――「データ利活用スキルアップ研修」で得られた成果を教えてください。
佐藤 氏:大きく分けて3つあると考えています。
まず1つ目は、自社のデータを使った実践的なプロジェクトを経験できた点です。研修では、実際の業務データを使い、テーマの設定からデータ収集、分析、そして評価まで、一連のプロセスを経験できました。
2つ目は、実務に直結するデータ分析スキルを身につけることができた点です。受講者はデータサイエンスの基礎から実務への応用までを学び、データ加工や様々な分析手法を習得しました。すぐに現場で使えるスキルを身につけることができたのは、大きな成果だと感じています。
そして3つ目は、ビジネスにおける改善提案の能力が向上した点です。研修を通して、業務上の課題を整理し、可視化、定義し、改善策を提案するスキルを磨くことができました。その結果、受講者はデータに基づいた、より効果的な改善提案ができるようになったと考えています。

DXセンター デジタルビジネス推進部
プロジェクト企画課長 峯 竜二 氏

DXセンター デジタルビジネス推進部 佐藤 優成 氏
峯 氏:多忙な業務の合間を縫って研修に取り組んだ受講者は、データ分析のノウハウを習得し、それぞれの課題に対して分析を行い、解決に向けて行うべき施策までは見えてきたという段階です。今後の課題は、受講者が研修で得た知識やスキルを継続的に活用し、実装につなげていくことです。受講者の上長からも「研修で発表された内容を実装したい」という声が多数寄せられており、実現までDXセンターにて伴走支援を行います。
生方:DXセンターの皆様と、思いをひとつにチームとして協働できたことが、最大の価値を生み出したと考えています。私たちにはデータ分析やDXの知見はありますが、大陽日酸様独自の業務に関する知識は不足しているため、できるアドバイスにも限りがあります。DXセンターの皆様に知見や事例を共有いただきながら、共にフィードバックを行えたことが、受講者にとって非常に有益な学びの場となりました。富士通だけでは、このような手厚いフォローは難しかったでしょう。
――「データ利活用スキルアップ研修」実施後の反響について、受講者や周りの方からお聞きになったことがありましたら教えてください。
峯 氏:受講者からは「自身の課題だけでなく他の受講者の課題にも触れることができ、視野が広がった」「当初は分析が行き詰まることもあったが、様々なアプローチ方法の提案を受けて、やりたかったことが形にできた」など、多くの好評を得ることができました。
また「この研修で学んだ考え方やノウハウが、業務の改善に向けた気づきに繋がると感じており、他の業務にも活用していきたい」とのコメントもあり、DXセンターとしても大きな励みとなりました。
松島 氏:ファイナルプレゼンテーションには、受講者の上長やDXセンターのメンバーなど関係者40名が出席し、オンラインでも約100名の社員が参加しました。参加者から「よくここまでやり遂げた」「質の高い発表だった」といった声が聞かれました。中には研修に興味を持った経営層も参加しており「とても良かった、楽しく聞いていた」との感想を得ることができました。
ここがスタート地点。2030年、データを当たり前に活用する組織を目指して
――今後の展望についてお聞かせください。
赤井 氏:「第1回 データ利活用スキルアップ研修」は終了しましたが、私たちにとってはここがスタート地点です。DXセンターは、今回の研修で取り組んだ各テーマの実現化に向けて、受講者一人ひとりに寄り添い、しっかりと管理し、伴走してまいります。
大陽日酸のありたい姿は、データドリブンな企業文化を醸成し、データを最大限に活用した柔軟かつ機動力の高い企業体です。5年後である2030年には、100人のデータ利活用人財の育成を目指します。その100人が変革の起点となり、売上向上、収益力強化、業務効率化などを率先して実現してくれることに期待します。
今がまさに、時代の転換点だと感じています。かつてWordやExcelが特別なツールだったように、機械学習や生成AIといった新たな技術を用いることが当たり前の世の中になるでしょう。5年後、10年後、取り残されないために、私たちは今、変わらなければなりません。
――富士通とFLMは、人財育成プログラムの先に、どのような未来を実現したいですか。
前田:DXと言うと壮大な話に捉えがちですが、まずは現場の課題を一つひとつ知っていくことから始まると考えています。デジタル技術は富士通の強みですが、あくまで課題解決のための手段です。だからこそ、お客様それぞれが抱える課題を深く理解し、その解像度を上げていくことに精進します。
現代社会は、リスキリングや生涯教育といった課題に直面しています。富士通グループでは、人財育成を担う企業として、FLMがその一翼を担っています。人財育成を通じて、学習機会の提供やデジタル技術への接点を創出することで、お客様に寄り添い、課題解決を支援したいと考えています。
生方:イノベーションは、技術だけでは起こりません。技術と、それを使いこなす人財、この両輪が揃って初めて実現すると、私は考えます。
AIなどの進化によって、ビジネスパーソンに求められる役割も変化していくでしょう。これまで人が行っていた雑務はAIに代替されていく一方で、AIを活用し、イノベーションを起こしていくための新たなスキルセットが求められます。このように、人の役割は変化しても、人財育成の重要性は変わりません。時代の変化に合った人財育成プログラムを提供できるよう、私たちも努力を続けてまいります。
長島:私たちが目指すのは、パーパスとして掲げている「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」です。お客様それぞれの強みをデジタル技術というツールでさらに強化し、最大限に発揮できるよう支援する。お客様の成長こそが持続可能な社会の実現につながると、私は考えます。
お客様のあらゆる課題の解決へ共に取り組み、共に成長し、信頼されるパートナーであり続けたいと思っています。
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。