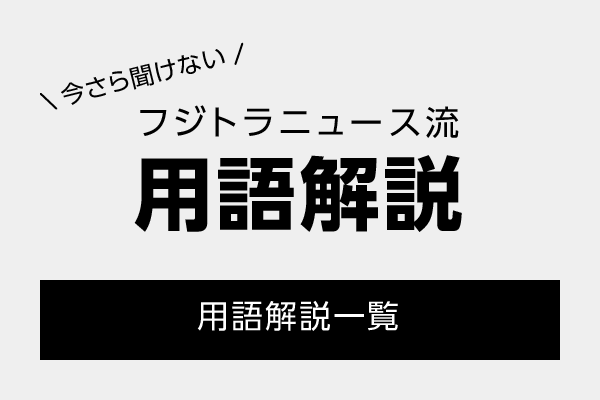近年、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼確保につなげるEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング:証拠に基づく政策立案)が推進されています。教育分野においても、教育に関するデータや研究成果のさらなる蓄積・活用が進められており、その一つとして、国立教育政策研究所と富士通、富士通Japanは、教育データの集約を目的とした「公教育データ・プラットフォーム」を構築・提供しています。教育分野においては、これまでデータによる現状把握やそれを踏まえた効果検証が不十分ではない状況にありましたが、本プラットフォームにて、教育分野の調査データや研究成果・事例等を集約することで、教育課題の発見やエビデンスに基づいた政策立案、より効率的な教育実践を支援しています。本プラットフォームを公開するに至った背景や今後の展望等について、関係者へのインタビューを通してご紹介します。
「公教育データ・プラットフォーム」とは
――国立教育政策研究所の業務概要をお聞かせください。
大野 氏:本研究所は、教育政策に関する唯一の総合的な国立の研究機関として、初等中等教育から高等教育、生涯学習など、教育行政全般にわたって、将来の政策形成のための先行的調査や既存の施策の検証など、教育改革の裏付けとなる基礎的な調査研究を進めています。また、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)等、国際的な共同研究に我が国の代表として参画するほか、児童生徒の学力や学習状況の全国的な把握、教育委員会や学校と連携した調査研究、教育課程や生徒指導・進路指導に関する情報提供など、幅広く活動しています。
――貴研究所が提供されている公教育データ・プラットフォームとは、どのようなプラットフォームでしょうか。
大野 氏:本プラットフォームは、文部科学省や国立教育政策研究所等が実施した教育分野の自治体・学校等の状況に関する調査データや研究成果、取組事例を集約したプラットフォームです。教育分野におけるデータによる現状の把握やそれらを踏まえた政策・実践の改善、新たな知見の創出につながる研究の活性化などを目的としています。
 国立教育政策研究所 教育データサイエンスセンター長 大野 彰子氏
国立教育政策研究所 教育データサイエンスセンター長 大野 彰子氏
――公教育データ・プラットフォームの公開に至った背景をお聞かせください。
大野 氏:教育分野は、政策立案や実施にあたり、データによる現状把握やそれらを踏まえた効果検証が十分ではない分野でした。しかし、文部科学省におけるGIGAスクール構想の進展により、児童・生徒へ1人1台端末を整備し、活用されるようになったことで、データが蓄積され、そのデータを利活用しようという機運が高まりました。その中で、様々な教育データの分析結果を効果的に政策や学校での実践に反映できるような環境整備が必要となりました。
また、令和3年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」や同年の「教育再生実行会議 第十二次提言」においても、教育データの収集・分析や大学・研究機関等へのデータの貸与を行う公的な教育データ・プラットフォームの必要性が提言されたことを踏まえ、構築・公開に至りました。
プラットフォーム構築に向けた取り組み
――公教育データ・プラットフォームの構築に至るまでに、どのようなアプローチを進めてきましたか。
松本:文部科学省が教育DXに注力されることを想定し、文部科学省の各セクションへ仮説提案等を進めていました。その中で、国立教育政策研究所内にデータサイエンスセンターが新設されたことをきっかけに、同研究所と教育データの利活用について議論を重ね、本プラットフォームの立ち上げへと繋がりました。
――構築にあたり、工夫したポイントをお聞かせください。
阿部:本プラットフォームの要件として、教育データを一元管理できること、また公開データとして広く一般に提供することが求められていました。これらの要件を実現するために、管理システムとして高い汎用性と拡張性を備え、デジタル庁等の多数実績を有するデータポータルプラットフォーム「CKAN」と、図書館等の学術分野で豊富な実績を有する富士通提供の学術情報ポータル「Ufinity」を採用し、ユーザビリティとセキュリティ、安定稼働を確保したシステム構築を実現しました。
また、公教育データ・プラットフォームにデータを登録するにあたっては、データの整理・構造化にも注力しました。メタデータとして登録する項目の形式については、これまで利用されてきたレイアウトを活用し、データファイルに関しては、国立教育政策研究所で管理しているフォルダの構成を最大限活用することで、効率的にデータ整備を行うとともに、データの標準化とアクセスビリティを確保しました。
 富士通Japan株式会社 Public&Education事業本部 教育サービス事業部 阿部 美優
富士通Japan株式会社 Public&Education事業本部 教育サービス事業部 阿部 美優
教育データへのワンストップアクセスを実現
――公教育データ・プラットフォームを公開後、どのような成果がありましたか。
大野 氏:国が公表している教育分野の調査データにワンストップでアクセスできる点がとても良い等のご意見をいただいています。また、グラフ作成機能追加のご要望も寄せられており、現在、アクセス数の多い一部データについて、自治体と全国の値との比較や推移をグラフで作成できる機能の構築・改修を進めています。さらに今後は、具体的な調査名がわからなくても曖昧なキーワードで検索できるようにするなど、より多くのユーザーに利用してもらえるプラットフォームを目指して、継続的な機能改善を図りたいと考えています。
阿部:公開から約2年となりますが、国立教育政策研究所によるシンポジウム等でのご紹介により、アクセス数が着実に増加しています。また、本プラットフォームのトップ画面に表示されるダウンロード数の多いデータセットも日々変化しており、教育分野のトレンドの変化が感じられるプラットフォームになっているのではと思われます。
2025年度は、アクセス解析に関する提案も検討しており、よりユーザーのニーズに最適化されたプラットフォームを目指していきたいです。
教育データの利活用促進に向けた課題
――本プラットフォームのさらなる発展に向け、今後克服すべき課題や取り組みについてお聞かせください。
山下 氏:今後のさらなる発展に向けて、さらに多くのユーザーに利用いただくためには、データカタログや研究成果、事例を充実させることが重要だと考えます。更新頻度を上げて最新データを提供することで、まずはデータの充実化を図っていきたいです。
また、本プラットフォームを訪れた方が調査結果等の教育データをもとに、全国の状況を把握した上で各自治体や学校の状況を分析し、具体的な政策立案に繋げていただきたいと考えています。そのため、現在、グラフ作成機能の構築・改修や曖昧検索機能の追加検討を進めています。これらの機能により、データの利活用が促進され、より効果的な政策立案に貢献できることを期待しています。
 国立教育政策研究所 教育データサイエンスセンター データ基盤課課長補佐 山下 智子氏
国立教育政策研究所 教育データサイエンスセンター データ基盤課課長補佐 山下 智子氏
――富士通からの支援として、どのようなことを考えていますか?
大塚:教育データの利活用促進に向け、最新の技術を活用した支援を提供していきたいと考えています。Microsoft Power BIを活用したグラフ作成機能に加え、AIを活用した類似情報の提案機能(類似度検索機能)の構築・改修も進めていますが、これらを実装することで教育データへの関心を高め、利活用いただくきっかとなることを期待しています。
しかし、本プラットフォームのさらなる発展のためには、データ収集や分析、利活用の意義を明確にすることも重要であると考えています。そこで、2024年秋に国立教育政策研究所の皆様や自治体の先生方、教育委員会の方々とともにワークショップを開催しました。そこで質の高い教育データの収集方法や教育の質をどう高めていくか等について議論し、本プラットフォームの意義を再確認させていただきました。
教育関係者のニーズを的確に捉え、富士通の技術とノウハウを活かして、引き続き本プラットフォームの発展に貢献していきたいと考えています。
 富士通株式会社 パブリック事業本部 官庁第二事業部 大塚 美穂
富士通株式会社 パブリック事業本部 官庁第二事業部 大塚 美穂
プラットフォームの未来像
――今後の展望をお聞かせください。
大野 氏:教育データの利活用を推進するために、文部科学省や国立教育政策研究所が持っている様々な教育データを繋ぎ合わせ、全国の教育状況を俯瞰的に把握できるように整備するとともに、グラフ作成機能により教育現場における成果や課題を可視化し、本プラットフォームを通して確認できることを提示していく必要があると考えています。また、各自治体や学校で蓄積されている様々な学習データをどのように連携して活用できるかということも考えていきたいです。さらに、近い将来はAI技術を活用すれば、蓄積されたデータから分析結果を示すような機能も提供できるのではと思っていますので、技術的な観点から助言をいただきながら本プラットフォームの充実を図りたいです。
教職員の働き方改革や教育の都市・地方間格差、いじめ・不登校対策等、教育における様々な課題がありますが、本プラットフォームを訪れた方が、解決策を模索する中で少しでも多くの知見を得られるよう、引き続きデータの質・量の充実と機能改善を図っていきたいと思います。
松本:国や自治体の教育DX推進における課題や解決策を検討する公教育データ・プラットフォームの利活用に関するワークショップを国立教育政策研究所と引き続き進めています。ワークショップで得られた知見をもとに、同研究所や自治体との連携を深め、具体的な施策に繋げていくとともに、現在直面している教育格差の問題や教職員不足、高等教育以降の国際的な学力低下といった課題解決にも寄与していきたいです。
 富士通株式会社 パブリック事業本部 官庁第二事業部 事業部長 松本 晃典
富士通株式会社 パブリック事業本部 官庁第二事業部 事業部長 松本 晃典
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。