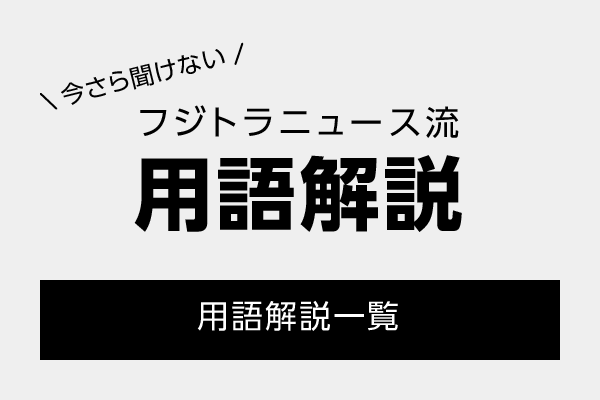不確実性が高まり未来の予測が難しいとされている今、企業には生き残りをかけた変革が求められています。富士通ではお客様のSXパートナーとして、お客様のビジネスの成功と社会課題の解決に貢献するため、2019年より今もなお自社の変革を続けています。今回はその取り組みの1つであるマーケティング変革におけるコーポレートサイトの刷新について、富士通グループにおけるお客様とのデジタル接点を司る、富士通グローバルマーケティング本部 デジタルエクスペリエンス推進室長の二木 隆司(ふたき たかし、以下、二木)に、変革の概要や、そこにかける思いについて聞きました。
今なぜ企業にマーケティング変革が求められているのか
――未来の予測が難しい時代と言われています。企業はこの時代をどのように捉えるべきでしょうか?
二木:誤解を恐れずに言うならば、未来を「予測」することをあきらめるべきだと思います(笑)。 有名な言葉に「未来を予測する最良の方法は、未来を創ることだ (The best way to predict your future is to create it.)」というものがあります。この先どうなるのかを予言するかのように予測することに力を割くより、どんな未来であるべきかという目標を立て、それに向けてアクションを起こす方がはるかに確実で建設的です。
地政学的なことはともかく、環境問題の解決やデジタル社会の発展、そして人々のウェルビーイングの向上については様々なビジネスを通じてあるべき未来を創ることは可能です。従来、これらの課題はまだ起きていない「リスク」止まりだったかもしませんが、今や見なかったフリが出来ない、そこにある危機です。両方の意味で企業にとって持続可能な社会を実現するためのSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)への取り組みは、もはや逃れられない必然と言えるでしょう。
富士通も今、従来のIT企業からお客様のSXパートナーになるための変革を推進し、ネットポジティブ※1と呼ばれる未来の状態を実現出来るよう全社を挙げて取り組んでいます。サステナビリティをCSR(企業の社会的責任)として、ビジネスとどう「バランスを取るか」という二律背反的な視点で取り組む企業は多いですが、当社のようにサステナビリティの実現そのものをビジネスの中核に据えているところは企業の中でもユニークな存在ではないでしょうか。富士通はFujitsu Uvanceを通じて、人々が豊かに安心して暮らせる持続可能な社会、そのような未来を目指しています。
-
※1:ネットポジティブとは、財務的なリターンの最大化に加え、地球環境問題の解決やデジタル社会の発展、そして人々のウェルビーイングの向上に取り組み、テクノロジーとイノベーションによって社会全体へのインパクトをプラスにすること。
――そのような時代、企業の中でのマーケティングにも変化はあったのでしょうか?
二木:もちろんです。先程の通り未来を予言のようには予測出来ないとすれば、お客様自身が認識されていないニーズをも先取りして、過去にとらわれない方法・手法で新しいマーケット、つまり「未来」を創っていく重要度が益々高まっています。
また同時に、正しく目標に向かえているか、乖離があるとすればどれだけなのか、それらの把握とキャッチアップに求められる速さ、広さ、深さが飛躍的に高まっています。
従来、富士通をはじめとする日本発の企業、特にB2B企業の多くは、マーケティングの面では大きく二つのモデルに注力してきた傾向があります。一つは、企業が作りたい商品、提供したいサービスをプロモーションするマーケティング。もう一つは、営業担当者がお客様に張り付き、要望されるものをテイラーメイドでご提供し、結果的に企業イメージの向上だけを担うことになるマーケティング。どちらもマーケティングというより、その中の一部である「広告宣伝」と言った方が良いかも知れません。しかし、お客様のビジネスの在り方が多様化する中で、お客様のニーズを忘れた前者は当然打率が低く、またマーケットニーズ全体を捉えた未来を創れない後者はビジネスがグロース(成長)せず、自ずとそのようなアプローチには限界がきています。企業には、社会のマクロな動きとそれにつながるお客様ニーズを俯瞰的かつ機動的に捉え、部門横断的な立場で未来を見据えた戦略を練るマーケティングが求められており、その期待される役割はますます重要になっていると思います。
 富士通株式会社 グローバルマーケティング本部 デジタルエクスペリエンス推進室
富士通株式会社 グローバルマーケティング本部 デジタルエクスペリエンス推進室室長 二木 隆司
富士通が考える、マーケティングのありたい姿
――それでは、富士通が考えるマーケティングのあり方について教えてください
二木:富士通ではお客様のSXパートナーとしての貢献に向けて、次の3つの観点でマーケティングが重要な役割を担っていると考えています。
まず、何度かお話ししている「未来」を指し示すことです。ただ、この「未来」は従来の延長線上から考えた未来ではありません。延長線では、馬車の未来を自動車では無く、速い馬車、と予測してしまうような過ちを犯してしまうかも知れません。お客様自身が気づいていないものも含めどのような課題があり、何が求められるのか、それに対し富士通はどのような価値を提供できるのか、マーケットを俯瞰した視点で明らかにします。自社ビジネスの目線でもっとストレートに言い換えれば、「誰に、何を、どう売っていくべきか」を徹底的に考え直すことです。このように設定した未来に向かって逆算で組み立てることで、ビジネスを大きくグロースさせることができます。
次に、お客様に、SXパートナーとしての新しい富士通の提言、提供できる価値を分かりやすく示して共感していただくことです。どんなに良い考えを持っていたとしても、それを頭の中にしまっておいては実現しませんし、ビジネスにもつながりません。その考えを共有し、共感して、一緒に実現いただける相手や仲間を増やす必要があります。特に社会レベルの課題には1社の取り組みではなく、様々な企業が連携し、エコシステムを形成して取り組む必要があります。その際重要なのは、方針や提供できることを単純に知っていただくのではなく、その軸となる考えに「まさにその通りだ」と感じていただくことです。どんな信念で何を目指し、世の中にどんなインパクトをもたらそうとしているのか、そこに共感できる部分があれば、未来に向かって同じ舟に乗って頂く強い動機になります。
最後は、データドリブンです。BP(ビジネスプロデューサー、営業職)がお客様の課題やニーズを「点」で深く捉えているケースが多いのに対し、マーケティング部門はお客様との様々なデジタル接点から得た膨大なデータやマーケティングデータを通してお客様を総合的に理解し、市場全体を俯瞰的に「面」で理解できる立場にあります。
個々のお客様を誰より理解している「点」と、それには敵わないがマーケットを「面」で捉える視点の両方が組み合わさることで、富士通全体でお客様をより良く理解することに繋がります。また、客観的なデータを根拠としますので、経験や勘といった個人の考えやスキルに依存しすぎず、意思決定の精度と再現性を高めることに繋がります。
また究極的にはデータを根拠にした次の打ち手もリアルタイムに打てるのが、データドリブンなデジタルマーケティングの強みだと考えています。
富士通が実践する、コーポレートサイト改革とは
――このたび富士通は「Webトランスフォーメーションプロジェクト(以下、Webトラ)」を立ち上げました。進める上での方針や、重視されてきたことを教えてください。
二木:私たちは、お客様との関わり方、我々のマインドセット(基本的な物事の考え方、思考パターン)の双方で、まだまだ発展・変革の途上にあります。そこでそれぞれに3つの原則を設定し、「3x3の原則」としています。
お客様との関わり方における1つ目は、先ほどもご紹介した「Resonate(共感を呼ぶ)」です。富士通が言いたいことを発信するのではなく、「まさにその通りだ」と思っていただける、お客様が知りたいと思う、価値あることを発信します。次に「Consistent(一貫している)」です。富士通は幅広い領域においてグローバル(世界100か国以上)にビジネス展開していますが、関係する全ての部門を束ねて一貫したメッセージを発信する必要があります。最後に「Dynamic(躍動的である)」です。同じ情報でも、受け手がつまらないと思う構成や表現では目的を十分に果たせません。仕様書のようなコンテンツを見て共感いただける方は少ないはずですので。
つぎにマインドセットの面ですが、1つ目は「Goal-Oriented(ゴールから考える)」です。当たり前のことですが、Webを刷新すること自体が目的化しないよう、企業のパーパスや、会社が示す方向性、ビジネス目標に向けて立案・実行します。そして「Data-Driven(データに基づく)」です。デザインが伴うものは、ややもすると感性に依存しがちですが、我々が手がけているのはアートではありません。個人や立場に左右される主観ではなく、客観的なデータを根拠にした施策を展開していきます。最後は「Collaborative(協働的である)」です。幸か不幸か富士通ほどの規模になると、部門間がそれほど連携しなくとも何とかなってしまうところがあります。いわゆるサイロですね。そこをいかに擦り合わせて結果を最大化できるかを重要視しています。

――Webトラでは2023年6月を皮切りに、コーポレートサイトをリニューアルし始めています。その改革の概要と、現在までに得られた効果について教えてください。
二木:Webトラは富士通の進めるマーケティング変革の一部ですが、それでもWebサイト全体を刷新する非常に大規模なプロジェクトです。変革の対象が広範に渡るため、綿密な計画と丁寧な社内コミュニケーションを行いながら、2025年度までの一旦の完了を目途に段階的に進めていく予定です。段階に応じて注力するポイントと達成すべき成果・効果は変化していきますが、現在の主な改革ポイントとこれまでに得られた効果は以下の3点です。
SXパートナーとして一貫したメッセージのグローバル展開
従来の機能・性能を軸としたコンテンツから、弊社の各領域の第一人者による論考、調査レポート、事例を中心に、SXパートナーとして社会とお客様の課題に対する洞察と、それらを踏まえた提供価値を提示するコンテンツへと大幅に転換しました。またこれらの統一されたメッセージを、世界各地域の特性や状況を踏まえながらグローバルに発信できるよう基盤を整え、改革を進めています。
情報発信体制の変革と発信力の強化
従来の富士通は、各事業部がそれぞれにマーケティング機能を持っており、Webコンテンツを事業部ごとに独自に作成していました。その結果、各部門のWebサイトが十分な連携や統一性なく同じ屋根の下に寄せ集まっている、という様相を呈していました。
そこでマーケティング機能を集約すると同時に、各部門との連携を緊密にする推進体制に変革しました。その結果、各部門のコンテンツはマーケティング部門主導の下、全社戦略およびブランディングとの一貫性を高め、かつ関連する他コンテンツやSNSをはじめとする他のお客様接点との連携を計画的に最大化することで、発信力を大幅に高めています。
例えば先般公開した富士通 統合レポート2023では、Webに訪れていただく方の数が同期間で前年比の約2倍、レポートをダウンロードいただいた回数が1.6倍となりました。
お客様接点のUXおよびオペレーションの改善
Webコンテンツのデザインやサイト構成をお客様に分かりやすいかたちに改善するとともに、そこに至る制作プロセスを標準化および一元化しました。担当者や担当部署に依存しない適切な品質管理を可能にすることで、WebサイトのUX(User Experience, お客様体験)を向上させることに成功、一定以上の関心を持って閲覧したお客様の割合を示す指標を33%改善させました。
また同時に、Time to Market※2を縮めるための対応を進めてきました。具体的には、再利用可能なコンポーネント(Webページの部品)でページ制作工数や制作者のトレーニング時間も短縮し、大規模なWebサイトのリニューアルは通常約1年要するところ、6ケ月で第一段階の刷新に漕ぎつけました。
-
※2:Time to Market:ここでは、Webサイト、ページの構想から実際にリリースするまでの時間
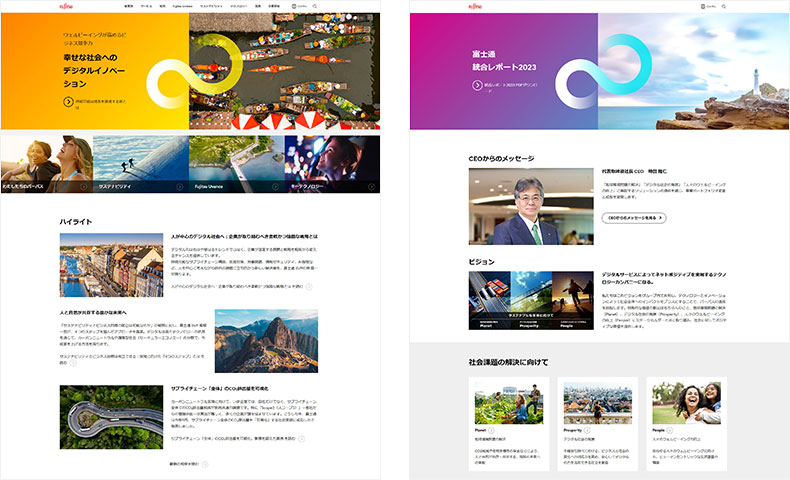 リニューアルした富士通コーポレートサイトの一部
リニューアルした富士通コーポレートサイトの一部
これらを実現するにあたり、Webの基盤としてグローバルに実績のあるSitecore社※3のSitecore CMSを導入しました。
Webトラでの改革はまだ道半ばですが、Sitecore社にはこれまでの実績を高く評価いただき、富士通はこのたび、2023年度APJ地域(APACおよび日本)におけるSitecore Experience Awardsを受賞しました。この賞は、革新的なインパクトのある方法で組織を変革したユーザ企業を表彰いただくものです。その中で、私たちのリーダーであるCMOの山本がマーケティング部門を代表して「Best Leadership in an Experience Transformation」を受賞しました。これは、Webトラの組織を超えた変革におけるマーケティング部門のリーダーシップを高く評価いただいたものです。この受賞を励みに、私たちもより一層、改革を進めていきたいと思います。
-
※3:Sitecore社:Webサイトおよびコンテンツを管理するプラットフォームを提供する企業
これからのマーケティングで目指すこと
――では最後に、これからの展望について教えてください
二木:やはり、マーケティングでグロース(成長)を牽引する役割を果たしていきたいですね。富士通がグロースするということは単純に売上や利益が拡大するという事象を超えて、あるべき未来に向かってあるべきビジネスを展開することでお客様のSXを推進し、そこにつながる社会課題を解決することにつながります。大袈裟かもしれませんが、広告宣伝に留まらない本来のマーケティングがよく機能している企業が増えることで、より良い社会の実現を後押しするエンジンを増やすことができると考えています。
そして個人的には、「富士通があんなマーケティングの変革をできるのだったら、ウチでもできるんじゃないか?むしろウチならもっとできるんじゃないか?」と多くの企業に思っていただけるようなモデルになれるとうれしいですね。
とはいえ、ありたい姿としてお話しした、未来を指し示す、共感を得る、データドリブンの三点は、まだ始まったばかりです。たゆまないマーケティング変革による富士通のグロースを通じ、お客様のSXパートナーとして、お客様のビジネスの成功と社会課題の解決に貢献していきます。

富士通株式会社
グローバルマーケティング本部 デジタルエクスペリエンス推進室
室長
二木 隆司
2020年富士通入社後、コーポレートブランド変革、Fujitsu Uvanceの立ち上げ等を経て2023年5月より現職。デジタルエクスペリエンス推進室長として、お客様とのデジタル接点を通じたDX/SXパートナーとしての認知、信頼、共感の獲得と、新たなビジネス機会の創出を推進。
富士通入社以前は外資系ITベンダーにて長くB2B マーケティングを経験。
![]() Takashi Futaki | LinkedIn
Takashi Futaki | LinkedIn