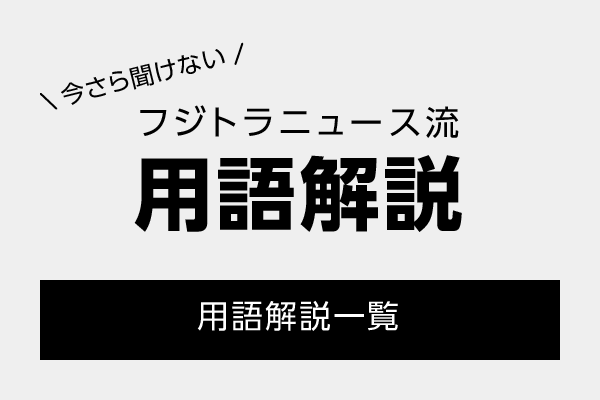あらゆる人のライフエクスペリエンスを最大化し、個人の可能性を拡張し続けられる「Healthy Living」な世界の実現を目指す富士通。その具体的な取り組みのひとつが、富士通の革新的なテクノロジーを応用した創薬プロジェクトです。現在は、共同出資した合弁会社を通じて新型コロナウイルス治療薬の開発にも取り組んでいます。
テクノロジーによって中分子創薬にどんな変革が起きるのか?このプロジェクトに邁進する人の想いとは?今回は、プロジェクトマネジメントに携わる、デジタルラボ事業部の岸 雅人さんに、取り組みの内容や社会貢献への想いを聞きました。
- 目次
中分子創薬のトップランナーとの共創
――まず、ペプチドリーム社との共同研究で、創薬プロジェクトが立ち上がった背景を教えてください。
岸さん: ペプチドリーム社は、中分子創薬の分野のトップランナーで、創薬プロジェクトをたくさん抱えていらっしゃいます。富士通はかねてより「誰も取り残さない健康長寿の社会の実現」に向けて、テクノロジーの活用を推進してきました。テクノロジーを社会貢献に役立てたいという想いを持つ私たちが、ペプチドリーム社のビジョンに共鳴し、2019年9月から共同研究をスタートさせるに至りました。
――ペプチドリーム社と取り組んでいる中分子創薬とはどういうものなのでしょうか?
岸さん: 薬は分子量の違いによって「低分子」「中分子」「抗体医薬」等に分類されます。これまで多くの薬は低分子でした。多くの低分子薬が今までに実現されてきている一方で、その開発は飽和しつつあります。そこで注目されているのが、中分子創薬です。ターゲットとなる体内のタンパク質に確実に作用して副作用が少ないなど様々なメリットがあると期待されています。
中分子創薬によりこれまでの薬で治療が難しかった病気も治せるようになるかもしれませんし、より副作用の少ない薬を創ることも可能になるかもしれません。例えば、ある癌に効く成分が見つかったとして、低分子の薬にすることが出来なくても、中分子創薬なら実現できる可能性があるのです。

テクノロジーにより創薬プロセスの変革に取り組む
――ペプチドリーム社との取り組みについて具体的に教えていただけますか?
岸さん: デジタルアニーラを活用した候補化合物の安定構造探索を行っています。
薬の候補となる化合物を実際に薬にしていくためには、重要な性質を維持したまま構造を変化させる「化合物最適化」と呼ばれるプロセスがあります。化合物の形は病気への効き方に影響する重要な要素なのですが、候補化合物が立体的にどのような形を取るのかは周囲の環境の影響も受けるので実際に作ってみないと分からない部分があります。これをコンピュータ上の計算で予測をするのが、安定構造探索です。
ペプチドリーム社では、中分子医薬品の候補化合物の開発を数多く進めてきましたが、中分子というのは低分子に比べて分子量が多いので、コンピュータ上での計算が飛躍的に困難になります。
例えばアミノ酸3個で構成される低分子の化合物であれば取りうる配列は4,200通り、これなら一般的なコンピュータでも計算可能です。しかし、アミノ酸15個の中分子の化合物の場合、配列は1,600京通りにのぼり、計算すべき組合せの数が桁違いです。従来のコンピュータでは、中分子の候補化合物の安定構造を求めることは難しく、実験を繰り返し行わなければなりません。そのため数か月から年単位の時間を要します。
そこで私たちは、この絞り込みをスピードアップするテクノロジーとして、デジタルアニーラの活用を提案しています。数か月から年単位で時間を要するのが課題でしたが、ペプチドリーム社との共同研究の結果、候補化合物の安定構造探索を約12時間という短時間で高精度に実施することに成功しました。これは、組合せ最適化問題に特化したデジタルアニーラという次世代コンピューティング技術によって実現されたことです。高速に適切な化合物を見つけることができれば、中分子医薬品を誕生させるまでのタイムスパンを短くできます。
――中分子創薬の鍵となる化合物最適化のスピードアップに、富士通の技術が貢献しているということですね。
岸さん: そうですね。これまでの創薬のアプローチでは、化合物最適化の際に研究者の方が頭の中で仮説を立てて化合物を設計し、それを合成して、その結果を受けてまた合成して……というプロセスを繰り返していました。デジタルアニーラがそのプロセスの一部を代替できれば、候補化合物最適化の期間を短縮し、新薬開発の可能性をさらに高めることが期待できます。
また、創薬プロセス全体を考えると、テクノロジーが活用できる領域は安定構造探索だけではありません。現在はペプチドリーム社との協業の取り組みを通じて、デジタルアニーラ以外にもスーパーコンピュータやAIの技術も活用した創薬プロセス全体の変革を目指しています。

コロナ禍の世界を救う。
共創で新薬の開発を
――現在、新型コロナウイルス感染症の新薬開発も手掛けているそうですね。
岸さん: はい、2020年11月にペプチドリーム社と富士通を含む5社で、新型コロナウイルス感染症の治療薬開発を目的とした合弁会社「ペプチエイド株式会社」を設立しました。治療薬開発は社会的ミッションでもありますから、富士通としても業界の垣根を越えて、この社会課題に力を尽くしたいと考え、新会社設立にいたりました。
ワクチン接種も進んでいますが、感染後の疾患を適切にコントロールする治療薬の存在は不可欠です。中分子創薬分野のリーディングカンパニーであるペプチドリーム社が持つ専門的な知見・ノウハウと、富士通が持つテクノロジーの融合により、早期の治療薬開発を目指しています。一刻も早く世界中の人の健康と安心につながる薬をお届けしたいですね。

ビジネスを深く知り、
社会貢献の想い強まる
――岸さんご自身の社会課題解決に懸ける想いについて伺えますか?
岸さん: 学生時代に遡りますが、カンボジアの孤児院の支援を行うNGOに所属してボランティア活動をしていたんです。就職のときも、社会にインパクトを与えることができる仕事をしたいと考えて富士通に入社。当時、社会の仕組みを構築する仕事に携わることで、社会的に弱い立場にある人たちに対してアプローチができればいいなという想いを持っていました。そう考えると、当時の想いはいまの仕事につながっているかもしれません。
入社後は、スーパーコンピュータの営業という責任ある仕事を任され、社会貢献への想いは、いつしかビジネスのスキルを磨くことに移行。大学院に2年間通い、ビジネスについて専門的に学びました。
この経験を通じて、企業活動も本質的には社会の課題解決であって、ビジネスの世界でも最終的にはどのような世界を実現したいのかという「想い」が重要になるものなのだということを改めて学びました。
営業として日々向き合っていた目の前の商談や売上を、社会を良くするということと切り離して考えてしまっていた時期もあったのですが、ビジネスについて深く学んだことが、一周回って社会課題を解決したいという想いに立ち戻るきっかけになったんです。
パーパスでつながる仲間。
心をひとつに挑戦へ
――現在、どのようなお仕事をされているのでしょうか?
岸さん: 大学院卒業後、新しいことへのチャレンジと社会課題の解決にダイレクトにつながる仕事ができるのではと思い、現在所属するデジタルラボ事業部に異動しました。
現在は、主にペプチドリーム社との協業のプロジェクトに携わっています。私は技術者ではないので、ビジネスサイドから専門性を持つメンバーたちに力を発揮してもらえるようにプロジェクトをマネジメントしています。

――岸さんが仕事で大切にしていることは、何ですか?
岸さん: 自分の考えを臆さずに発言することですね。それから、相手を理解することに一生懸命でいること。現在、SEやデザイナーなど、さまざまな立場の人と協業しているのですが、相手が何を考え、何を実現しようとしているのかを知ろうとする姿勢は大切にしています。
社内だけでなく社外の方とも基本的には同じ様に考えています。ペプチエイド社の設立の際、契約内容などについてペプチドリーム社とも厳しい交渉が必要な場面がありました。私たちの考え方をしっかりお伝えした上で、「コロナを治せる薬を創りたい」という大きな共通の想いの下で合意点を見出すことにより、困難を乗り越えることができたと思っています。
いま、富士通は「Healthy Living」をKey Focus Areaのひとつに掲げ、あらゆる人の可能性を拡張し続けられる世界の実現を目指しています。
今後も様々な困難にぶつかることもあると思いますが、同じ目標に向けて想いを熱くする仲間と共に、誰もがイキイキと活躍できる社会を実現していきたいです。
Fujitsu Uvance
当社は、2020年度に定めたパーパスをもとに、世界をより持続可能にするため、社会のあるべき姿を起点としたビジネスに取り組みます。
このたび、2030年の社会を想定し、社会課題を起点に選定した7つのKey Focus Areas(重点注力分野)を、新たな事業ブランド「Fujitsu Uvance」のもとで展開していきます。
 岸 雅人(きし・まさと)
岸 雅人(きし・まさと)
1988年神奈川県生まれ。富士通入社後、スーパーコンピュータの営業に従事。2020年より新設されたデジタルラボ事業部へ異動。
営業時代は、当時国内最大(世界5位)のスーパーコンピュータシステムを始めとした複数の大規模プロジェクトを担当した。異動後はライフサイエンス領域での新たなビジネス創出を目指し、ペプチエイド社設立やペプチドリーム社との協業プロジェクトなどのパートナリングを含むビジネス企画業務に携わっている。