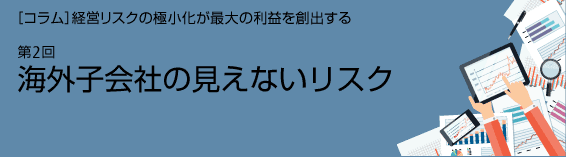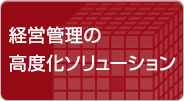FUJITSU Enterprise Application GLOVIA
【コラム】経営リスクの極小化が最大の利益を創出する
第2回 海外子会社の見えないリスク
予見力を上げるうえでの大きな障壁は、海外子会社の実態把握です。
海外子会社の実態が上手く掴めない一番大きな原因は言葉の問題です。次が特殊である日本的経営の雇用形態と業務慣行の長所短所への理解不足です。
言葉と理解不足の問題を乗り超える解決策は、数字で会話する体制を作ることです。数字のデジタル情報を駆使すれば、遠隔地の業務実態も可視化が可能です。
海外拠点の増加
海外の日系企業の海外拠点は、平成18年に約35千ケ所だったのが、平成27年には約71千ケ所と2倍になり、海外子会社数も飛躍的に増えています。海外子会社の日本人駐在員は26万人以上で、うちアジアが6割となりました。(注1)
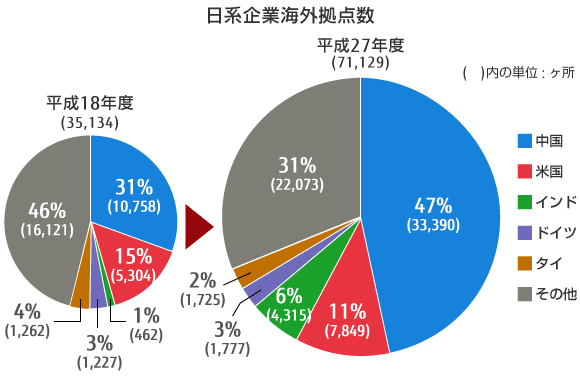
海外事業のウエイトが大きくなり、連結決算書の作成はもとより、課題となっている「海外事業損益の製品別把握」や「連結原価の横串し捕捉」が難しいことが問題となっています。
海外の現場で何が起きているのかが見えず、海外経営リスクの把握が難しい時代となりました。
とりわけ多くの製造業の会社は、海外業績の把握と分析や予測、事業実態の監視監督と可視化に苦慮している様子がみてとれます。
いわく、人材不足(人がいない)、資金不足(お金がない)、知見不足(ノウハウがない)、時間不足(暇がない)などです。業種や業態に関係なく、余程の大手以外は共通の悩みをお持ちのようです。
現地の状況が見えない
みなさんの会社でも、「製造制作現場の実態が見えない」「利益が減った理由が不明」「かなりの損失が出たが原因解明ができていない」「報告された決算書の翌月、翌期の事後修正が多い」「予実の差異説明が不十分(現地の説明を聞いても事情がよく飲み込めない)」「業績見通しや予測のはずれが大きすぎる」などのご不満を現地に対してお持ちではないでしょうか。
現地の不満
一方、現地サイドでは、「本社、国内本部の様々なところから資料作成指示が来て対応しきれない」「現地の実情を説明してもなかなか納得してもらえない」「管理スタッフが不足しているが逆に人を減らせと言われている」「有能なローカルスタッフに急に辞められた」「予算もないのにシステム化、合理化を考えろと言われる」「本社本部の人事異動で海外経営方針がころころ変わる」などの不満があるようです。
現地の事情や感覚が伝わらない
これは、単に情報の伝達不足や共有不足、といえばその通りですが、現地の仕事の仕方や人の使い方、商習慣や法的慣行、生活環境などを理解せず、日本国内と同様のイメージで現地の業務や生活を想像している本社、国内サイドの方に問題がありそうです。現地サイドからはブーイングの沸き起こる「本社見解」もあります。(注2)
丸呑み丸投げも困る
逆に、現地のことは分からないから、口はださない、一切お任せで、何でも現地要求を丸呑み、仕事は丸投げということもよく起こりがちです。
現地に関心をもってよく見守ることを諦めて「経営リスク」を見ざる聞かざる言わざるの本社は、必ずどこかで痛いしっぺ返しを受けることになると思います。
海外拠点で実際に起きた弊害
こんなことが実際にありました。
事例1:分かったつもり弊害
現地子会社の取締役会に出席した現地語のわからない本社役員が、現地駐在員の耳打ち通訳で会議の内容を理解したつもりになったが、席上何の発言もできず、現地役員から「注意不要人物」と侮られ、後日、知らないうちに粉飾決算の共犯者にされた。
事例2:丸呑み弊害
現地語を理解しない出向社長が、現地ローカルの経理課長の求めに応じて、毎月の支払い許諾をしていた高額支出の中味が、その経理課長個人の車のローン代だったことが、現地の日本人公認会計士の監査で初めて明らかにされた。
事例3:情報見逃し弊害
現地でおきた納品検査不合格品の処置につき、本社本部からの指示に時間が掛かり製品在庫が放置された結果、現地担当者のミスでいつの間にか製品が廃棄されてしまい、莫大な損失が生じた。
事例4:トリック弊害
巧妙な誤魔化しを織り込んだ日本本社あての予算書のトリックを日本の事業本部が見抜けず、不必要な増資要請を認めてしまい、現地の野放図な資金流出に手を貸してしまった。
事例5:粉飾誘導弊害
海外子会社の経営者に業績見通しで予算利益が確保できないなら、インセンティブ(ボーナス)の支払いは出来ないと発破をかけたところ、粉飾決算を誘導する羽目になった。本人はボーナスを手にするとさっさと辞めて逃げてしまった。
以上の事例のような弊害(ダメージ)を含めて、子会社経営が上手くいかないのは、主に「言葉」「雇用形態」「仕事の仕方」「子会社の作り方」が原因として考えられます。
言葉の違いの問題
言葉の問題が非常に大きいことは、一般論としてはお判りと思いますが、現地でローカルスタッフを管理業務で使う場合は、特に大きな障壁となります。世界観、人生観、生活感覚、タブーの違い、などにもつながってきます。
外国語副作用
単に言葉がよく伝わらないことの他に、認知心理学でいうところの「外国語副作用」が悪さをすることが多いのです。
「日本語が十分でない外国人」と話をしていると、「この人、あんまり頭がよくないのかな」と思ってしまうことはありませんか。
言葉が十分に伝わらないときは、お互いに相手を知能的に低くみてしまいがちです。
これが、相互不信を醸成します。同じ日本人同士でもおきることが「外国語副作用」で増幅するリスクは軽視できないと思います。
通訳を使えば伝わると思うのは早計
通訳にもいろいろあって、経験上、安い通訳はレベルが低く誤訳されるリスクが大きいです。また料金が高くても、専門用語や業界用語に疎い通訳は避けたほうがよい。
日常会話がこなせても、少し込み入った話で、契約や人事評価に関わる会話は、面倒でも、「上質な翻訳者」を使うことをお奨めします。少しでも違和感があれば、念押しする、復誦してもらう、メモをとるなどの手間が必要と思います。
いらぬ誤解、曲解、早とちりが、先にいっての大きなトラブルのもとになることは少なくありません。
言葉による理解には限界がある
外国語副作用をわきまえて、時に応じて上質な翻訳者を用意しても、現地ローカルスタッフと確かな意思疎通を図れるようになるには、時間を要しますし、言葉だけで伝えることには一定の限界があります。双方の能力の問題もあります。
雇用形態と業務慣行
雇用形態と業務慣行は日米間における経営基盤の違いが以下図の通りにあります。
(日本基準とグローバル基準と呼ばれるものとの違いです。)
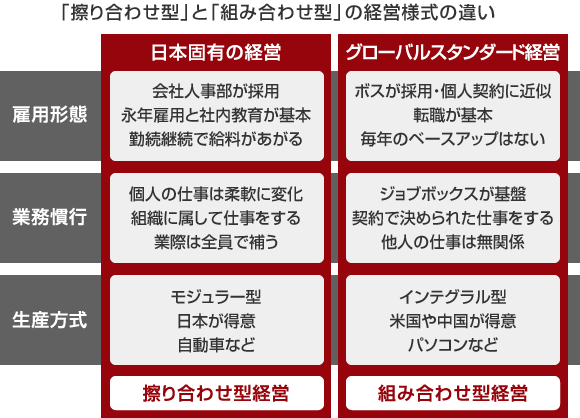 【雇用形態と業務慣行における日米の違い】
【雇用形態と業務慣行における日米の違い】
これは、東大ものつくり経営研究センター長の藤本隆宏教授が、「技術・生産管理」「設計論」の視点で主唱されている「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」の違いと深い関係があります。
トヨタ生産方式の自動車の「擦り合わせ(インテグラル)型」の製品とパソコンのような
「組み合わせ(モジュラー)型」の製品の生産方法が異なるのは、事実と思います。
◇この生産方式・製造方法の違いと軌を一にして、「組み合わせ型のジョブ・ボックスありきの雇用形態と業務慣行」は、「擦り合わせ型の永年雇用前提のマニュアルレスの雇用形態と業務慣行」は、大いに異なるのです。優劣を言っているのではありません。
文化や歴史を含めた大きな社会基盤と人口構成が違うのです。(注3)
人の使い方と雇い方の問題
第2の問題は、人の使い方、雇い方の違いの問題です。(雇用条件、労働条件、人事評価基準、ハラスメント感覚など)
日本的な雇用形態の特殊性
あまり認識されていないのですが、日本的な雇用形態は非常に特殊です。肯定的な意味も否定的な意味もありますが、高度工業社会を営む人口の多い国で、日本のような雇用形態をとっている国は他にはまずないと思います。
北米での駐在業務や中国での長期滞在監査業務、また欧州やアジアでの子会社調査と経営指導などを通じて、「日本的な雇用形態=経営が如何に現地の経営と異なっているか、またそのことを双方が如何に理解していないか、」ということに一種の驚きをもってみてきました。
人を雇うのは人
米国では、新卒を会社が雇ってから、新人教育を施して配属先を人事部が決めることはありません。最初から入社希望者は職種(ポスト)を決めて応募してきます。そのポストに任用するかしないかはそのポストのボスが決めるのであって、人事部が決めるわけではありません。応募者は詳細な「業務記述書/業務規程書(ジョブ・ディスクリプションjob description)」に従って、採用されたら、ボスと「雇用契約」を結びます。
日本では「ジョブ・ディスクリプション」ありきで雇用されることは以前は全くなかったし、個人と個人の雇用契約書に基づく採用・就業の概念はありませんでした。
詳細な業務規程の慣行を前提として転職ありきの「グローバル社会」では、日本最大の自動車メーカーの社長が「終身雇用を守る」と発言しただけで、会社の格付けが下がるような不思議なことが、起きるのです。
ここに、日本の製造業の強さの秘密と、海外では通用しない日本的経営の弱さが潜んでいると思います。
業務慣行、仕事の仕方の違いの問題
第3が、仕事の仕方、業務慣行の違いの問題です。(商習慣、社会慣行、社会規範、法令感覚など)
何故、日系企業の海外経営がそれほど上手くいかないのか。
勿論、上手くいっている会社も多くありますし、海外子会社の立ち位置がいろいろあるので、一概にこうだとは言えませんが、大きな原因は、雇用形態の違いに基づく業務慣行の違いが正しく認識されていないために、子会社経営のやり方が的はずれになりやすいことだと思います。
グローバル経営というもの
これらの雇用形態や業務慣行の差異は、繰り返しますが、優劣の比ではありません。とりわけ「人種のるつぼ」である米国では、社内の従業員であっても何処の誰かは関係ありません。何時入ってきて何時辞めるかもわかりませんし、宗教・民族・母国語・学歴・教養などが千差万別です。
だから、厳格な業務記述書なり仕事マニュアルを、文書で明示して、「これこれをこうやれ」「指示されないことはするな」と細かく規定した「ジョブ・ボックス」のなかで強制しないと、仕事が回らないのです。(注4)
子会社の作り方の問題
第4が、子会社の作り方の問題です。
直系子会社の場合
自前で一から立ち上げた「社内会社」形態で事業を開始する「直系子会社」の場合は、如何に現地化するかというテーマを別にすれば、それほど大きな課題は生じないでしょう。
そのかわり立上げには時間が掛かります。
これとは異なり、いわば「居抜き」で買収した子会社の場合の経営は非常に難しくなります。「直系で手作り」の子会社と違って、「速戦力になりうる手軽さ」が当初は期待できるでしょうから、一概に否定すべき選択肢ではありません。
買収した会社の経営陣や経営の仕組みが上等ならば、「居抜き買収会社」でも上手くいく「僥倖」に巡り合えないとは言いませんが、まず「宝くじ級」でしょう。(注5)
リスク回避に向けて
日本のガラパゴス化現象
日本人同士のコミュニケーション力は、とても深くて広くて強く濃密です。
ツーと言えばカー、阿吽の呼吸、以心伝心、問わず語り、等々が自然の、伝達方法として、良し悪しは別として認められています。
これが、日本のガラパゴス化の源で、長所もあれば欠点短所もあります。
短所のひとつが、日本人感覚で、海外現地ビジネスを取り仕切るのはまず無理だという点です。中国も東南アジアも、基本的には米国流の「ジョブ・ボックス方式」でないと、人を動かせません。
小売業やサービス業の世界では、日本式「おもてなし」接客サービスを定着させ、成功している企業がありますが、とても長い時間をかけて仕上げてきた経緯があります。
性善説について
日本人は「性善説」でものごとを考えたがる傾向があります。これは、日本人の良質な徳性であると同時に、海外では命とりになりかねません。海外では、脇の甘さをみせれば、「お人善し」で「騙しやすい金持ち」と見下されることになりかねないのです。平和ボケと言われようと日本は特殊であっても居心地はとても良いのです。ただし、日本人の好きな「性善説」に拠り所を求めて海外ビジネスをしてはいけません。海外では「性悪説」から出発しないと、不適切な結末を迎える公算が大きいと思うべきです。
解決策はあるのか
かなりネガティブな評論をしてきました。
では、救いの道はないのかです。
あります。
まず、言葉の障壁を低くするための若干の工夫です。
- 関係者間で簡易な「業務用語辞書」を共同で作ること
(現地語:英語:日本語の用語翻訳書で、作成過程で相互理解が進みます) - 予算決算値は、常にエクセルシートのフォーマット化されたマトリックス表でやり取りすること(数字で会話する癖をつけること)をお奨めします。
数字で会話すると、お互いの勘違いや早とちりを減らして、嘘や怠慢、不真面目さ、だらしなさが浮き彫りになり、「いい加減な言い訳」は許さないことになります。
何よりも記録が残ります。
次に、双方の理解不足の解決策ですが、それほどお金を掛けなくても、時間を掛けなくても、海外事業の実態を可視化し、現場を管理監督する方途があります。
ただし、少しの手間と決意と忍耐は必要です。
その要点は、
<1>数字で会話する仕組みを作ること、数字で監視できる制度を取り入れることです。
- 数字で会話する体制を作ることが最もコストの掛からない解決策です。
<2>デジタル情報を駆使することです。
- デジタル情報を駆使すれば遠隔地の業務実態も可視化が可能です。
話だけでは、実現のハードルは高いと感じられると思います。
実践的なやり方、アプローチの仕方がありますので、最終回、「原価の話」のなかで、その一端をご紹介したいと思います。
注1:
- 昨年10月の外務省調査によると、日本企業の海外駐在員は26万7千人になり、12年前(2003年)に比べて1.5倍に増えたとのことです。その62%はアジア駐在で、北米は21%、欧州が10%で、女性も3万3千人(2003年は1万8千人)に増えました。
【出典:日本経済新聞 2016年7月18日、9面特集記事】 - 海外在留邦人は、永住者を含めて約126万人ですが、帰国予定のある長期滞在者は約84万人、このうち民間企業の駐在員本人の数が約26万人(出典:外務省領事局政策課年報・平成26年度版)です。
注2:
だいぶ以前のことですが、米国の西海岸に駐在している家族が車を2台持っていると聞いて「贅沢だ」といった本社役員がいました。日本の都市部と違い、公共交通機関のない生活を想像できない方の不用意な発言でした。
生活事情もさることながら、職場事情も経験者でないとなかなか理解してもらえません。短期出張で現場視察をして分かったつもりになられることが現地サイドからは迷惑と映ることもあるようです。
注3:
人口構成とマイルドにいいましたが、実際は人種構成です。
母国語、民族、宗教、生活習慣、教養などは、「差別」ではなくはっきりと差異があることを見落とすわけにはいきません。実業の世界ではそこは冷静に見極めて対処しなければなりません。
注4:
永年雇用・終身雇用が暗黙の大前提となっていて、周りの仕事仲間は氏素性から趣味や家族環境までわかっている人間関係の仕事基盤とは全く異なります(最近は少し事情が変わりつつあります。)加えて、日本はどこへ行っても日本語が完璧に通じます。このことを当たり前と思っているのは、日本人の幸せです。
私の駐在していた米国カルフォルニア州は、南部にいけば英語は通じない、スペイン語しか通じない地域が過半です。
英語はしゃべれるが、書けない人、書けるが文法が滅茶苦茶な人が少なからずいます。日本語の世界では想像できない言語環境です。
随分、レベルの低い階層としか付き合ってこなかったのか、と感じられるかもしれません。米国社会の実相は、テレビや映画などからは伝わって来ないようです。
注5:
海外で買収した子会社の経営陣、特にCFO(財務最高責任者)やCEO(最高経営責任者)をそのまま引き継ぐことは止めたほうがいいと思います。
彼らのことを相当に理解したつもりになっても、経営に関する考え方が基本的に異なるためのトラブルが、外国人トップをリクルートする「経営のグローバル化」事例で多々生じています。
そもそも誰が雇っているのか、誰への報告義務があるのか、何をすると首になるのか、などを契約文書で明文化しておくやり方に日本人は慣れていません。